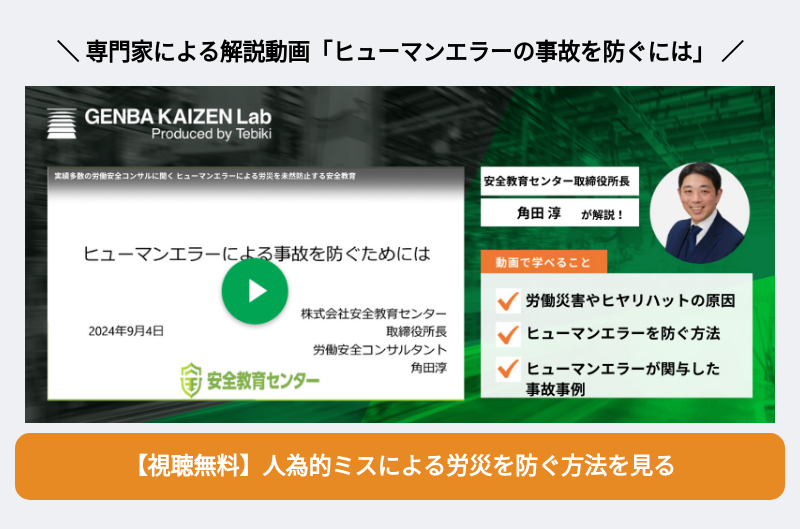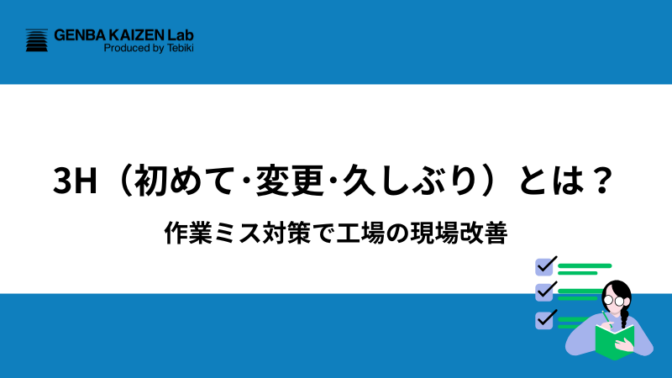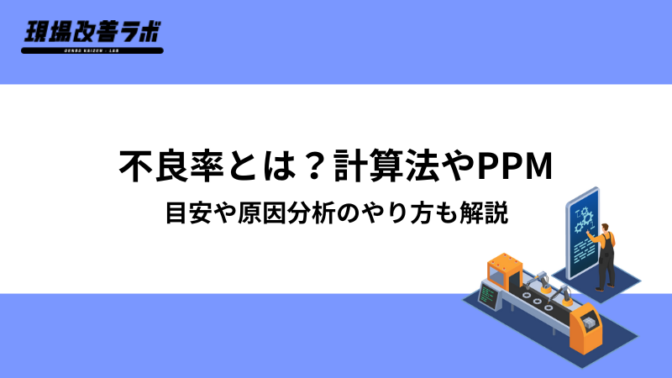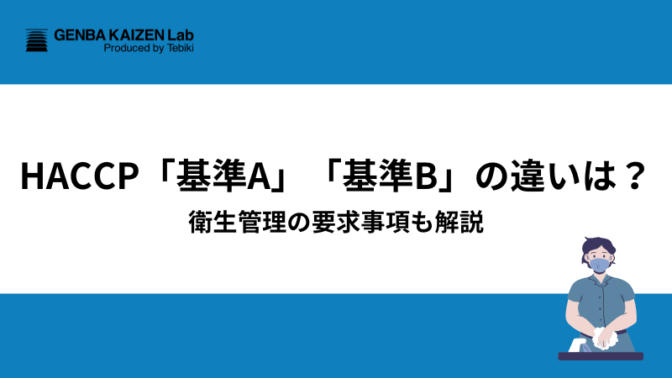かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
労働災害は、従業員の心身の健康を害するだけでなく、企業の信頼・生産性低下にもつながる深刻な問題です。この記事では、職場で実践できる「労働災害対策」を解説します。基本的な対策から応用的な対策までご紹介しますので、安全な職場環境整備のためにお役立てください。
労災の対策は以下の資料で網羅しており、本記事で紹介する内容は以下資料から抜粋してお届けしています。労災の根本を解消する網羅的な対策を知りたい方は、以下の資料を先んじてご覧いただければと思います。
▼製造業の労災対策を網羅的に知りたい方▼
製造業での労災ゼロを達成する従業員の安全意識を向上させる安全教育
▼ヒューマンエラーや作業ミスの対策を重点的に知りたい方▼
・繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網
・ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育
労働災害の発生原因
労働災害を防ぐには、労働災害が発生するメカニズムを知ると良いでしょう。ここでは、労働災害が発生しうる以下の4つの原因について詳しく解説します。
- 人間的要因
- 設備的要因
- 作業的要因
- 管理的要因
人間的要因
人間的要因とは、労働者の心理状態、身体状態、行動特性などを指します。具体的には以下のようなものが挙げられます。
| 具体的な例 | |
|---|---|
| 不安全な行動 | ・作業手順を省略したり、安全規則を守らなかったりする ・作業前の点検や、危険箇所の確認を怠る |
| 心理的要因 | ・ストレスや疲労によって注意力が散漫になる ・納期やノルマに追われ、安全確認を怠ってしまう ・経験や慣れから、危険に対する意識が薄れる |
| 身体的要因 | ・発熱や体調不良により、判断力や集中力が低下する ・身体機能の低下により、作業中の動作が困難になる |
| 知識・スキル不足 | ・危険に対する知識や、安全な作業方法に関する知識が不足している ・異常発生時の対応方法を知らない |
これら「人間的要因」の中でも、特に「不安全な行動」が多くの事故の直接的な引き金となります。
この「繰り返される不安全行動」を、行動科学の観点から根本的に防止する方法を、以下の資料で解説します。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
「人の問題」を「仕組み」で解決する
これらの人間的要因は、決して従業員個人の資質や意識だけの問題ではありません。こうした要因が背景となって引き起こされる人的なミス(いわゆるヒューマンエラー)は、「気をつけてください」「よく確認しましょう」といった表面的な注意喚起や精神論に頼るだけでは、根本的になくすことは不可能です。
重要なのは、誰が作業しても、いつでも安全な結果が再現される「教育の仕組み」を現場に構築することです。その仕組みの核となるのが「作業の標準化」です。
しかし、多くの現場では文字ばかりで分厚い作業手順書が形骸化し、結局は個人の経験やカン・コツに頼った作業が行われているのが実情ではないでしょうか。この「作業のバラつき」こそが、人的ミスが生まれる最大の温床なのです。
▼関連資料▼
・製造業での労災ゼロを達成する従業員の安全意識を向上させる安全教育
・繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網
「一目でわかる」が標準化を浸透させる鍵
安全な作業手順を全従業員にムラなく浸透させるには、形骸化した手順書ではなく「一目見るだけで、正しい動きと危険箇所が直感的にわかるマニュアル」が必要です。
こうした背景もあり、工場や製造業といった多くの現場で「動画マニュアル」が導入されているのです。 例えば、以下の動画は実際の現場で作成された動画マニュアルですが、言語や経験の差に関わらず、誰もが安全な作業を正確に理解できるようになっています。
▼ドリルで穴のバリをとる動画マニュアル▼
作成元:児玉化学工業株式会
動画マニュアルは、実際の作業映像に「見るべきポイント」や「やってはいけないこと」を視覚的に示せるため、従来の紙マニュアルでは伝えきれなかった「カン・コツ」や「暗黙知」までも簡単に共有できます。
このような「見てわかる」仕組み作りこそが、人的要因による労働災害を防ぎ、安全意識が高い現場を実現する第一歩です。詳しくは、動画マニュアルによる教育の進め方や企業事例についてまとめられた資料をご覧ください(下のリンクをクリック)。
>>【資料を無料で読む】“安全意識が高い製造現場”がやっている安全教育
設備的要因
機械設備の不具合や不適切な操作によって、労働災害が発生する可能性もあります。
特に、古い機械や保守が適切に行われていない機械は、突然故障や異常動作を起こす恐れが考えられます。定期的な点検やメンテナンスを行い、故障や不具合を見過ごさないようにしましょう。
現場改善ラボでは、設備トラブルを未然に防ぐ方法などを解説したガイドブックもご用意しています。DXを活用した設備h全への具体的な取り組み方法なども解説しているので、適切な保全活動ができていない方は参考にしてください。
>>【資料を無料で読む】設備トラブルを解消する設備保全のDX手法
作業的要因
作業方法や作業手順、作業内容などが原因で労働災害が発生することもあります。例えば、以下のような行動や状況が労働災害発生の引き金となりえるでしょう。
- 身体に負担のかかる姿勢での作業を長時間続ける
- 作業手順が確立されていないがゆえの、危険な方法で作業
- 作業時間が短く、急いで作業を行わざるを得ない
- 作業手順が曖昧で、人によって作業方法が異なる
こうした作業的要因による労働災害を防ぐためには、業務の標準化が重要です。しかし、標準化の進め方は決して簡単ではなく、推進方法や勘所は現場によって様々なのが実状です。そこで、トヨタ自動車株式会社が実践している標準化の進め方やポイントを参考にしながら、標準化を推進するための方法を探るのが1つの手です。そのための資料を用意しているので、あわせて参考にしてみてください。
>>トヨタ流に学ぶ 作業標準の見直しで実現する製造現場の生産性向上を見てみる
管理的要因
管理的要因は、組織や管理体制、運営方法など、安全に関する管理上の要因を指しています。
管理が不十分で正しい作業手順や安全対策が確立されていない場合、労働災害のリスクが高まります。他にも、十分な教育が行われていないことや従業員の健康が配慮されていないことも管理的要因に含まれます。
次章からは、『労働災害を防止する対策』として8つの手法をご紹介します。今日から実践できる内容も含まれていますので、しっかりチェックしていきましょう!
労働災害を防止する8つの対策
労働災害を防止する代表的な対策は以下の8つです。ここからは、それぞれの対策方法について詳しく解説していきますので、気になる対策法を以下からクリックしてご覧ください。
- 安全意識向上のための安全教育を実施
- リスクアセスメントで「現場の危険」を洗い出す
- KYT(危険予知訓練)で危険感受性を高める
- 5Sで作業環境の整備・危険要因の排除を行う
- 高リスク作業に備える特別教育の実施
- ヒヤリハットを記録して共有する
- 機械設備の点検で未然防止型メンテナンス
- フェイルセーフで設計から事故を防ぐ
安全意識向上のための安全教育を実施
安全教育とは、「安全衛生に関する知識や技術を労働者に伝えるための取り組み」です。労働災害を防ぐために、新入社員からベテラン社員まで、すべての従業員を対象に行う必要があります。特に、雇入れ時や作業内容変更時には、対応する作業特有のリスクや安全対策に関する知識を伝えましょう。
安全意識を効果的に向上させるために、動画やイラストなどの視覚資料を活用したり、理解度テストを実施したりするのがおすすめです。安全教育は一度きりではなく、継続的に実施して従業員の安全意識を常に高く保つことが大切です。
関連資料:製造業での労災ゼロを達成する従業員の安全意識を向上させる安全教育
とはいえ、読者の皆様は安全教育の重要性をそもそも十分に理解されているかと思います。突き詰めると、「安全教育は毎年実施している。しかし、ヒヤリハットや労災は一向に減らない…」 多くの現場管理者が、このようなジレンマを抱えているのではないでしょうか。その根本原因は、安全教育の「形骸化」にあります。以下のような、ありがちな失敗パターンに陥っている場合、表面的な安全教育にとどまっている可能性が高いです。
ヒューマンエラーによる労災を未然に防ぐための、本当の安全教育を以下の資料で解説します。
>>ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育を見てみる
| 失敗パターン | 詳細 |
|---|---|
| マンネリ化 | 毎年同じDVDを視聴し、代わり映えのしない資料を読むだけで、従業員が「またこの話か」と飽きてしまっている。 |
| 他人事感 | 教科書に出てくるような一般的な事故事例ばかりで、自分たちの現場に潜むリアルな危険として捉えられていない。 |
| 精神論への偏り | 「気をつけよう」「安全第一に」といった言葉を繰り返すだけで、具体的に「何を」「どうすべきか」が伝わっていない。 |
こうした形骸化した教育では、従業員の心に響かず、行動変容には繋がりません。効果的な安全教育とは、「他人事」を「自分事」に変えるための工夫を凝らしたものです。本質的な安全教育を実施するための原則を以下にまとめましたので、ひとつひとつチェックしてみてください。
原則1. 教材は「自社のヒヤリハット」が最強
他社の重大災害事例よりも、昨日隣のラインで起きた「ヒヤリハット」の方が、従業員にとっては遥かにリアルな教材です。実際に提出されたヒヤリハット報告書をもとに、「なぜ起きたのか?」「自分ならどう防ぐか?」をグループで議論しましょう。身近な事例を自分事として考えることで、危険の意識が飛躍的に高まります。
例えば物流業のASKUL LOGIST株式会社は、ヒヤリハット事例を動画で従業員に共有する時間を定期的に設けています。
安全教育を徹底するという観点では、ヒヤリハット事例の共有やKYTを行うなどがあります。ヒヤリハット事例の共有では、直近の拠点で起こった事故事例を動画マニュアルで共有すると禁止動作の確認や、感染病などその時々で挙げられるトピックスをと注意喚起を促しています。
以下の動画では、同社の動画マニュアル導入に関するインタビュー動画です。動画マニュアルの活用イメージや効果がより知れると思います。
▼同社の動画マニュアル導入の背景や効果▼
※同社が安全教育に活用している動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」の機能詳細や活用事例は、以下の資料でご覧いただけます。
原則2. 「なぜ」を伝え、納得感を醸成する
「この作業では手袋をしましょう」と指示するだけでなく、「なぜなら、過去にこの作業で指を挟む事故が起きたからです」という理由や背景をセットで伝えます。ルールの1つひとつに先人たちの痛みを伴う教訓が込められていると理解すれば、従業員はルールを「やらされ仕事」ではなく、「自分を守るための知恵」として能動的に遵守するようになります。
原則3. 「見てわかる」教育で、行動を変える
正しい作業手順と、ヒヤリハットに繋がった誤った手順を、動画や映像で見せるのが現場教育では主流になりつつあります。紙のマニュアルでは伝わりにくいスピード感や目線の動き、危険なポイントを視覚的に示すことで、言語や経験の差を超えて誰もが「正しい行動」を直感的に理解できます。
多くの企業が取り組む、動画マニュアルを活用した安全教育の具体的なノウハウや対策事例を、以下の資料で詳しく解説しています。現場の安全レベルを一段階引き上げるためのヒントとしてご活用ください。
>>>「安全意識が高い製造現場はやっている! 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例」を見てみる
リスクアセスメントで「現場の危険」を洗い出す
リスクアセスメントとは、現場に存在する危険性や有害性を調査し、低減または除去するための一連の手法を指します。労働災害を防ぐためには、このリスクアセスメントの実施が欠かせません。
具体的なリスクアセスメントの進め方は、以下の通りです。
- 労災につながる危険源の特定
- 特定した危険源の評価と分析
- 分析結果から対応優先度の決定
- 優先度の高い危険源から対応を実施
リスクアセスメントは労働災害を未然に防ぐうえで欠かせない取り組みですが、「リスクアセスメントの正しい進め方がわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
現場改善ラボでは元労基署署長によるリスクアセスメントのわかりやすい進め方を動画で無料公開。
>>【動画を無料で見る】現場のキケンを見極める「リスクアセスメント」とは?
KYT(危険予知訓練)で危険感受性を高める
KYT(危険予知訓練)とは、職場の労働災害を予防するためにメンバー全員の危険意識を高め、職場の危険源を対策・低減するトレーニングのことです。製造現場や建築現場など危険が伴う作業現場でヒヤリハットや労働災害を予防するための取り組みとして、全国的に普及しています。
製造現場の労働災害は、予期せぬ事故やミスにより突如として発生します。そのため、KYTによって事前にリスクを予知し、対策を講じられるようにしましょう。
KYTは形骸化しやすく、表面的に実施しても安全意識の向上にはつながりません。現場の安全に直結する本質的なKYTは「動画」が有効で、多くの現場で導入が進んでいます。詳しくは「労災ゼロ!形骸化したKYTから脱却する動画KYTとは」をご覧ください。
>>「労災ゼロ!形骸化したKYTから脱却する動画KYTとは」を見てみる
5Sで作業環境の整備・危険要因の排除を行う
5Sとは、整理、整頓、清掃、清潔、躾(しつけ)の5つの項目から成り立つ活動です。5Sを徹底することで、安全で効率的な作業環境を実現し、労働災害を未然に防ぐことにつながるでしょう。さらに清潔な職場は、心理的なストレス軽減にもつながることから、労働災害防止に有効であると考えられます。
5Sの実践的な方法や事例を知りたい方は、以下から5Sコンサルタントによる解説動画をご覧ください。5Sは、労災防止だけではなく、生産性の向上にも寄与する取り組みです。現場改善の1つとして事業所全体で取り組みましょう。
>>>セミナー動画「生産性を高める5S活動 正しい運用に欠かせない「重要なS」とは」を視聴する
高リスク作業に備える特別教育の実施
特別教育は、特定の危険有害業務に就業する前に必要となる知識を作業者へ周知させるための教育として位置づけられ、労働安全衛生法が実施を義務付けている取り組みです。
労働安全衛生法で定められている「危険または有害な業務」は、労働安全衛生規則第36条「特別教育を必要とする業務」で規定されています。
▼危険または有害な業務一例▼
- 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
- アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等
- 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転
- 小型ボイラーの取扱いの業務
参照元:中央労働災害防止協会「免許・技能講習等が必要な業務について」
上記の例のように重大な労働災害のリスクがある業務を行う際は、十分な教育が必要です。特別教育を受けさせないまま危険有害業務に従事させると、事業者が法的に罰せられるリスクがあるだけでなく、労働者の命に関わる重大な事故が発生する可能性が高まるため注意が必要です。
特別教育の必要性や実施する内容、具体的なやり方は以下の記事で詳しく解説しています。
ヒヤリハットを記録して共有する
ヒヤリハットとは、事故に至らなかったが危険を感じた出来事のことです。少しの違いで事故になり得た場面を「無事でよかった…」で終わらせず、内容を記録して共有することが現場全体の安全対策につながります。
実際に起きた出来事と対策例を全社的に共有することで、ヒヤリハットに直面していない従業員も類似する場面で『危なそう』と予測できます。よくある工場のヒヤリハット事例を共有する形でも効果的です。
労災の主な要因の1つである「ヒューマンエラー」は、単なる注意喚起や直接指導ではゼロにできません。ヒューマンエラーが根本的に生じない「仕組み作り」が重要ですが、その本質的な安全教育について解説された資料「ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育」もあわせて参考にすると、安全対策の具体的なヒントが得られるはずです。
>>「ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育」を見てみる
機械設備の点検で未然防止型メンテナンス
機械設備の不具合や故障は、労働災害の大きな原因の1つです。機械設備の点検を定期的に実施し、故障を未然に防ぐことで、労働災害のリスクを減らせます。点検方法としては、以下が一般的です。
- 種類や使用頻度に応じて、点検頻度や点検項目を定めた定期点検計画を作成
- 作業前や作業中に、目視や簡単な動作確認を行う日常点検を実施
計画に基づき、専門的な知識や技術を持った担当者が、機械設備の詳細な点検を行う定期点検も重要です。
一つひとつは短時間でも、積み重なると大きな生産ロスにつながる「チョコ停」。多くの現場で重要課題とされながらも、なかなか対策が進まないのが実情です。
このチョコ停の改善手段として「帳票のデジタル化」をはじめとするペーパーレスでの設備保全が推奨されています。その理由や具体的な進め方については、以下の資料を参考にしてみてください。
>>「チョコ停ゼロ・安定稼働へ-ペーパーレスでの設備保全の第一歩」を見てみる
フェイルセーフで設計から事故を防ぐ
フェイルセーフとは、何らかの故障が発生してもシステムが正常に機能しつづけ、安全に停止できるように設計された機能や仕組みのことを指します。システムの故障が人々の命や製品の品質に影響を及ぼす可能性があるため、フェイルセーフは重要な仕組みです。
また、似た言葉としてフールプルーフがあります。フールプルーフとは人間の操作ミスを防ぐための機能のことを指します。フールプルーフは誤った操作が行われた場合でも、システムが正しく動作するようにすることを目的としています。
次章からは、企業による労働災害の防止対策事例をご紹介します。業務効率や品質向上にもつながる対策を実施している企業の事例ですので、安全対策という側面以外からも参考にしていただけるでしょう。
企業による労働災害の防止対策事例
ここからは労働災害が多い「製造業」や「物流業」でどのような労働災害対策が行われているか、実際の企業事例をもとにチェックしていきましょう。
▼製造業の労災対策を網羅的に知りたい方▼
製造業での労災ゼロを達成する従業員の安全意識を向上させる安全教育
▼ヒューマンエラーや作業ミスの対策を重点的に知りたい方▼
・繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網
・ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育
児玉化学工業株式会社
児玉化学工業は、産業機器の製造などを行う化学メーカーです。現場には、ほぼ日本語がわからない外国人スタッフも多く、文書ベースのマニュアルでは「理解されない」という問題を抱えており、安全靴を履く理由すら知らない人がいるという状況でした。
そこで、理解度向上のために既存の紙マニュアルを動画化しようと、我々が展開するかんたんに動画マニュアルが作成できる「tebiki現場教育」を導入。導入後に強く感じていただけたのは「作るのはかんたんで、学ぶ側にもわかりやすい」ということ。さらに、動画マニュアルの導入によって、「ルールや手順を守るようになる、守らせるようになる」という体制が確立したそうです。
▼同社の動画マニュアル導入の背景や効果▼
児玉化学工業株式会社の事例を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:製造業の動画マニュアル導入事例 | 工場の作業手順や異常処置、安全指導を動画で作成。手順書作成の工数は紙の1/3に。自動翻訳で外国人教育にも活用。
ASKUL LOGIST株式会社
ASKUL LOGIST株式会社は、EC専門の総合物流企業として全国15拠点展開しています。長期的な労働人口問題対策として外国籍スタッフを雇用していますが、言語や文化の違いにより、安全教育を行っても伝わらないという問題を抱えていました。
外国籍スタッフのほかにも、障がい者の方の採用も推進している同社。多様な人材を抱える現場において、誰もが理解しやすい教育の方法を模索する中、「動画化した方がわかりやすい」と考え、tebiki現場教育を導入することになりました。
▼同社の動画マニュアル導入の背景や効果▼
安全教育の徹底のために、直近起こった事故事例を動画マニュアルで共有。動画により、現場のリアルな臨場感をつくれて「何が原因」で「どこに注意が必要」かが伝わりやすくなりました。実際に「動画の方が画像で説明するよりも解りやすい」という声も挙がっているそうです。
安全をすべてに優先させることを行動指針としているASKUL LOGISTの事例を詳しく読みたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:従業員数3,500名超・全国14拠点で動画マニュアルtebikiを活用
株式会社メトロール
マザーマシンの高精度タッチセンサの製造で、世界トップシェアを誇る株式会社メトロールでは、新人スタッフ向けの安全衛生教育に動画マニュアルを活用し、安全意識の定着と新人教育の効率化に取り組んでいます。
製造現場で使用するアルコールによって、労働災害が発生しないように薬品の扱い方を未経験のスタッフでも理解できるように、分かりやすい教育講座を整備しているそう。
このような動画マニュアルの整備によって、トレーナーが繰り返し教える時間の削減にもつながり、導入前に1時間近く割いていた教育工数が半分以下の時間まで減っています。
株式会社メトロールの事例を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:世界で200社以上の装置メーカーに採用されているセンサの製造工程でtebikiを活用し、新人教育と多能工化を推進
労働災害を防止するためのQ&A
労働災害の防止には職場の危険を見つけ出し、安全活動への全員参加が重要です。安全で安心な職場作りは、サービス品質向上にもつながります。
労働災害を減らすために労働者ができることは?
労働災害を減らすため、労働者は安全意識の向上と積極的な安全活動の参加が求められます。具体的には職場の危険箇所の特定と報告、安全な作業方法の学習と実践、そして、日常的な安全チェックの実施が挙げられます。
たとえば、転倒や滑り事故を防ぐためには、床の清掃や整理整頓を心がけ、障害物の撤去を行うことが重要です。また、重い物の持ち運びでは正しい姿勢と方法を学び、無理な力仕事を避けることが肝心です。さらに脚立や台車の安全な使用方法を習得し、墜落や転落事故のリスクを低減させることも労働者ができる安全対策です。
労働災害を防止するためのポイントは?
労働災害防止の施策は、職場全体の安全文化の定着にあります。安全活動に対する経営層からの強力なサポートとリーダーシップや従業員の安全に対する意識向上、そして継続的な教育と訓練が不可欠です。
安全推進者の配置による安全活動の組織化と職場環境、そして作業方法の改善が基本です。5S活動(整理、整頓、清掃、清潔、躾)による職場の物理的環境の改善、KY活動(危険予知)による危険箇所の特定と対策の実施、そして、安全教育・研修を通じて正しい作業手順や危険予知の方法を従業員に伝えることが重要です。
また、安全活動の成果を定期的に評価し改善策を講じることで、職場の安全性はさらに向上します。労働災害防止には全員が安全に対して責任を持ち、積極的に活動に参加することが重要です。
労働災害の防止に関連する法律は?
労働災害の防止に関連する代表的な法律として、労働基準法・労働安全衛生法・労働契約法などが挙げられます。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 労働基準法 | 労働基準法は、正規・非正規を問わず賃金を受け取るすべての人々を「労働者」と定義し、すべての労働者に適用される労働条件の最低基準を定めることで労働者の権利を保護する法律です。 |
| 労働安全衛生法 | 労働安全衛生法は労働基準法から派生した法律で、職場の安全と労働者の健康を守るための具体的な措置を定めています。労働安全衛生法の目的は労働災害を防止し、職場における安全と健康を確保することです。 |
| 労働契約法 | 労働契約法は雇用契約に関する基本事項を定めるもので、従業員と事業者間のトラブルを防ぐことを目的としています。労働契約法の遵守は、企業が日頃から従業員の安全を確保しているかどうかの指針であるといえます。 |
種類別!労働災害対策取り組み具体例
厚生労働省「令和4年 労働災害発生状況」によると、最も多い労働災害は転倒で35,295人と全体の約27%を占めています。そして動作の反動や無理な動作、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれと続きます。
ここで、労働災害防止の取り組みとして以下3つの具体例を紹介します。
- 転倒災害防止対策
- フォークリフト災害防止対策
- はさまれ・巻き込まれ災害防止対策
発生が多い労働災害について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
関連記事:製造業に多い労働災害ランキング!死亡事故事例や対策方法を解説
転倒災害防止対策
転倒災害は製造業における労働災害の中でも最も多い事故とされ、対策への優先度も高いです。職場での転倒災害を効果的に防止するための具体的な対策として、以下の3つが挙げられます。
| 対策 | 詳細 |
|---|---|
| 階段の安全対策の徹底 | 階段を使用する際には右側通行を徹底し、手すりを使用します。 万が一足を滑らせた場合の被害軽減にもつながるでしょう。 |
| 滑り止め材の使用 | 作業エリアや階段の踏み面に滑り止め材を塗布することで、足元の安定性を高め、転倒事故を防ぎます。特に、湿気の高い環境や油分が存在する場所では、滑り止め材の使用の効果は絶大です。 |
| 床面の整備と清掃の徹底 | つまずきや滑りの原因を取り除けます。清潔で整理された作業環境は、 転倒災害のリスクを大幅に低減できます。 |
フォークリフト災害防止対策
フォークリフトは製造業や物流業で広く使用されていますが、操作ミスや安全管理の不備により事故が発生することがあります。以下の対策は、フォークリフトによる災害を防ぐための効果的な方法です。
| 対策 | 詳細 |
|---|---|
| 運転者の資格と訓練 | フォークリフトの運転者は適切な資格を持ち、定期的な訓練を受けることが必要です。結果、運転技術の向上と安全意識の向上が図られます。 |
| 作業エリアの整理整頓 | フォークリフトの運行エリアを明確にし、障害物を除去することで事故のリスクを低減します。また、歩行者とフォークリフトの運行エリアを分離することも重要です。 |
| 定期的な点検と メンテナンス | フォークリフトを定期的に点検して必要なメンテナンスを行うことで、機械的な故障による事故を防ぎます。 |
はさまれ・巻き込まれ災害防止対策
労働災害の中でも、はさまれや巻き込まれによる事故は死亡事故など深刻な結果を招くことがあります。はさまれ・巻き込まれ災害を防ぐためには、以下のような対策が効果的です。
| 対策 | 詳細 |
|---|---|
| 保護装置の徹底的な利用 | 保護装置の適切な使用と管理は、事故を防ぐ上で重要な対策です。保護装置の定期的な点検とメンテナンスを行い、常に最適な状態に保つことが必要です。 |
| 安全教育と意識の向上 | 特に新規採用者や未経験者に対しては、機械の正しい操作方法だけでなく、緊急時の対応策についても教育することが必要です。作業中の注意点や安全対策を可視化するために、警告標識や指示板を設置することも効果的でしょう。 |
| 安全な作業環境の整備 | 作業環境を整理整頓し機械の周囲に十分な作業スペースを確保することで、はさまれや巻き込まれのリスクを低減します。また、機械の設計段階から安全性を考慮し、操作者が危険な部分に近づきにくい構造にすることも重要です。 |
安全教育を実施しても、業務の慣れによって安全意識が薄れ、業務中の注意を怠ることで労働災害発生のリスクが高まります。現場改善ラボでは労働安全コンサルタントによる「現場で実践できる安全意識を形骸化させない安全教育の進め方」について解説した動画を以下にご用意しておりますので、是非ご参考ください。
まとめ
この記事では、労働災害を未然に防ぎ、安全な職場環境を実現するために、今日から実践できる8つの対策を詳しく解説しました。
労働災害対策は、1度実施して終わりではなく、継続的に見直し、改善していく必要があります。労働災害は未然に防げるものですので、従業員の安全を守り、より働きやすい職場環境を実現するために、この記事で紹介した対策を参考に安全活動に取り組みましょう。
厚生労働省の『労働災害原因要素の分析』によれば、労働災害の原因のうち8割がヒューマンエラーであると示されています。そのため現場改善ラボでは、ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育の解説動画を無料公開中。繰り返し発生するヒヤリハットをなくしたい方は、ぜひ以下の画像より動画をご覧ください。