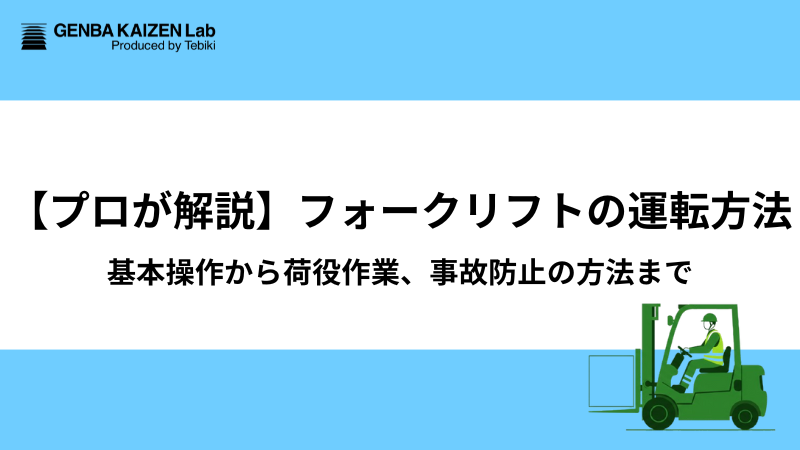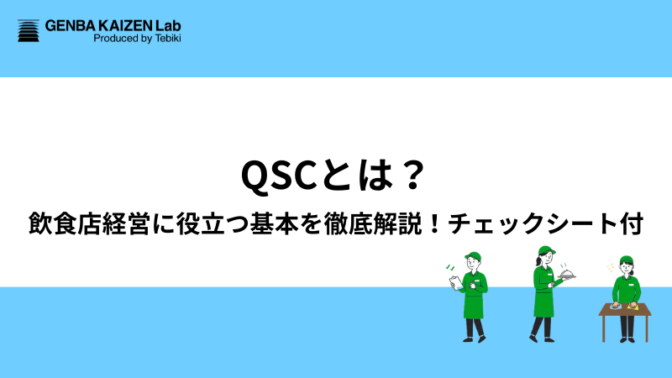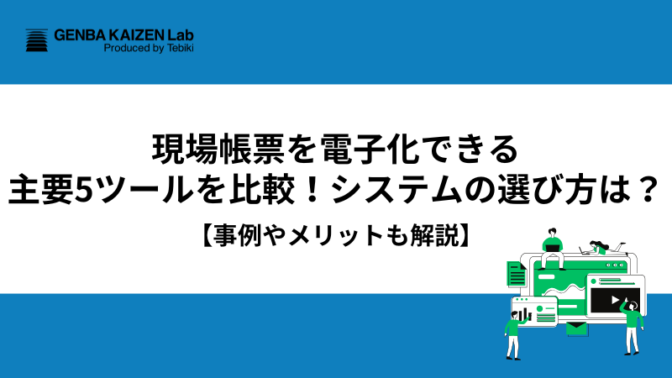物流現場で役立つかんたん動画マニュアル「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
- 「フォークリフトはどうやって運転するのだろうか?」
- 「現場の事故をなくしたい」
これから資格取得を目指す方や運転にブランクがある方、あるいは企業の安全衛生担当者の方の中には、このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
本記事では18年間フォークリフト作業に従事したプロの視点から、基本的な運転方法を徹底解説。さらに、フォークリフト事故を撲滅するための効果的な方法もご紹介します。是非最後までご覧いただき、安心・安全な作業の実現にお役立てください。
なお物流現場では、フォークリフトによる事故の未然防止策として「動画マニュアル」の導入が増えています。正しい操作手順だけでなく、何をどうやったら危険やヒヤリハットにつながるのかも可視化(危険の見える化)するため、安全意識や危険意識が浸透する教育アプローチとして有効とされています。
動画マニュアルによるフォークリフト安全対策の具体的な効果や企業事例は、資料「動画マニュアルを活用したフォークリフトの安全教育・対策事例」で解説しているので、併せてご参照ください。
>>「動画マニュアルを活用したフォークリフトの安全教育・対策事例」を見てみる
目次
確認しておきたいフォークリフトの基本情報
まずは基本情報を押さえておきましょう。安全な作業の第一歩として、以下の3点について解説します。
- 必要な資格は「運転技能講習」と「特別教育」
- 主要なタイプは「カウンターバランス式」と「リーチ式」
- 主な変速機仕様は「トルコン車(オートマ)」と「クラッチ車」
フォークリフトの基本操作マニュアルについてすぐ確認したい方は、以下の関連記事もご覧ください。
関連記事:フォークリフト基本操作マニュアル!作業手順書の例も紹介
必要な資格は「運転技能講習」と「特別教育」
フォークリフトの運転に必要な資格は、事業所で扱う車両の最大荷重によって以下の2種類に分かれます。
| 最大荷重の区分 | 必要な資格(運転業務) | 根拠法令など |
|---|---|---|
| 1トン以上 | フォークリフト運転技能講習の修了者 | 労働安全衛生法施行令第20条第11号、安衛法第61条 |
| 1トン未満 | フォークリフト運転特別教育の修了者 | 労働安全衛生規則第36条第5号、安衛法第59条 |
公道を走行する場合には、別途「大型特殊免許」や「小型特殊免許」などが必要になる点に注意しましょう。フォークリフトの資格について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
関連記事:【フォークリフトの特別教育】社内実施の方法・技能講習との違い
主要なタイプは「カウンターバランス式」と「リーチ式」
次に、フォークリフトの主な種類をご紹介します。倉庫などで使用されるのは、主に「カウンターバランス式」と「リーチ式」の2つです。
| 項目 | カウンターバランス式 | リーチ式 |
|---|---|---|
| 市場シェア/販売傾向 | 全体的な販売台数が多い。汎用性が高く幅広い現場で導入されている | Eコマースの増加等による倉庫の集約化・高層化に伴い、屋内作業での需要が非常に高まっている |
| 操向/小回り | 後輪で操舵。回転半径が大きく、小回りは苦手 | 駆動輪が約90度回転し、その場での旋回も可能。小回りが非常に得意 |
| 運転姿勢/操作方法 | 座って運転。足元のペダルとハンドルで操作するため、自動車の運転感覚に近い | 立って運転。手元のレバーで前後進や速度を調整するため、独特の操作に慣れが必要 |
| 安定性/構造 | 車体後方の重り(ウェイト)でバランスを取るため、安定性が高い | マストが前後に動き、重心が高めなため、安定性はやや劣る |
【ワンポイントアドバイス】
リーチ式は、軽くレバーを倒しただけで鋭く進む感覚やマストを押し出す独特の動作があり、カウンターバランス式の経験者でも最初は戸惑うことが多いです。慣れれば非常に効率的ですが、焦らず慎重に操作感覚を掴むことが大切です。
主な変速機仕様は「トルコン車(オートマ)」と「クラッチ車」
カウンターバランス式のエンジン車には、自動車と同様にオートマ(AT)とマニュアル(MT)にあたる変速方式があります。クラッチの無いタイプは「トルコン式」、有るタイプは「クラッチ式」と呼ばれます。
なお、リーチ式やバッテリー式のフォークリフトは基本的にオートマ仕様で、操作方法はトルコン式とほぼ同様です。
| 項目 | トルコン車(オートマ) | クラッチ車 |
|---|---|---|
| 市場シェア/販売傾向 | こちらが圧倒的に主流。特に大型車はほぼこちら | 新規での導入は減少傾向 |
| ギアチェンジの方法 | 前後進レバーを切り替えるだけ | クラッチペダルを踏み込んでニュートラルにし、前後進レバーを切り替える |
| 長所 | ・操作が簡単で運転が楽 ・エンストしない ・右手を操作レバーに集中できる | ・車両価格が比較的安い ・ダイレクトな操作感がある ・繊細な速度調整(微速走行)が可能 |
| 短所 | ・クリープ現象による意図しない動きに注意が必要 ・メンテナンスコストが比較的高め | ・必要な操作が多く、初心者は慣れが必要 ・頻繁なクラッチ操作で足が疲れやすい ・クラッチ板の摩耗・交換が定期的に必要 |
【ワンポイントアドバイス】
操作が簡単なトルコン車が主流ですが、クラッチ車は繊細な速度調整が可能なため、傾斜地での作業など特定の場面で根強い人気があります。しかし、一般的な倉庫作業ではその利点を活かす場面が少なく、操作の負担も考慮してトルコン車が選ばれることがほとんどです。
ここまで、フォークリフトの基本情報について解説しました。「そもそも、なぜフォークリフト事故が発生するのか?」その原因から詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
関連記事:フォークリフトの物損事故が発生する原因と対策!参考になる企業事例も紹介
フォークリフトの運転方法マニュアル①【乗車・走行編】
ここからは、実際の運転方法について具体的に解説します。まずは安全な作業の基本となる、乗車から走行までの手順と注意点を見ていきましょう。
フォークリフトの運転方法をわかりやすく伝えるマニュアルの作成方法や実際のマニュアルについて確認したい方は、以下のリンクをクリックし別紙のガイドブックをご覧ください。
>>【すぐに使える4種類のサンプル付き】 物流・倉庫作業のマニュアル作成ガイドブックをみる
車両トラブルを防止する始業前点検の方法
毎日の始業前点検は、労働安全衛生規則 第151条の25によって義務付けられています。車両の異常を早期に発見し、作業中の事故を防ぐために必ず実施してください。
【ワンポイントアドバイス】
筆者は、始業前点検でタイヤのボルトの緩みに気づき、締め直してから作業に取り掛かった経験があります。もし点検せずにそのまま作業を続けていたら、タイヤ逸脱の大事故につながっていたかもしれません。
具体的な点検方法については以下の記事で詳しく解説していますので、是非参考にしてください。
▼関連記事
・フォークリフト点検は義務?点検の種類や項目、やり方について
・フォークリフトのオイル交換時期とは?やり方や怠るリスク
運転席への正しい乗り方/降り方
乗降時の転倒・転落事故を防ぐため、陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)が定める正しい手順をタイプ別にご紹介します。
カウンターバランス式
- 運転席『左横』に進み、両足を揃えて立つ
- 左手はヘッドガードの柱(握手)をにぎり、右手は座席の背もたれをにぎる
- 左足をステップ上に乗せて乗車する
- 着席後の座席を調整する
- 後写鏡の写影を調整する
- シートベルトを着用する
- 各種レバーが中立位置にあるかを確認する
- 駐車ブレーキがかかっているかを確認する
- エンジンキーを始動スイッチに差込む
- ブレーキペダルを踏込む
- エンジンキーを「START」位置まで回してエンジンを稼動させる
リーチ式
- 左手で車体を、右手は立ち席の背当てを摑み右足から(次に左足を乗せ)乗車する
- キースイッチをONにして電圧その他各計器の作動を確認する
【ワンポイントアドバイス】
特にカウンターバランス式は、座席までに段差があるので足を踏み外すリスクが高まります。「慌てていて足を踏み外し、スネを強打する」などは、よくあるヒヤリハットです。どんな状況でも、正しい手順で乗降することが重要です。
前進/後進走行時の操作手順
安全に乗車して準備が整ったら、いよいよ走行です。こちらも陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)が定める手順に沿って解説します。
カウンターバランス式
- フォークをリフトする(地上5~10cm)
- マストを後方一杯にティルトする
- 前方及び側面の左右の安全を確認する
- 前後進レバーを前進(後進)に入れ、駐車ブレーキを外す
- 静かに発進する
カウンターバランス式のバック走行時は死角が多く、特に注意が必要です。後方確認の重要性については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:フォークリフトバック走行時の後方確認の重要性と安全対策
リーチ式
- リフトレバーを手前に倒しフォークを上昇する(地上から 5~10㎝まで)
- ティルトレバーを手前に倒しフォークを後傾する(3度以上)
- フォークリフトの周囲の安全を確認する
- 左足でブレーキペダルを踏んでブレーキを解除する
- 走行レバーを前方(後方)に倒しゆっくり発進する
前進/後進走行時の注意点
最後に、カウンターバランス式とリーチ式に共通する走行時の注意点を解説します。これらは現場での経験に基づいた重要なポイントであり、意識することで事故のリスクを大幅に減らすことができます。
| 注意点 | 詳細 | ポイント |
|---|---|---|
| 「急」のつく操作はしない | 急発進、急加速、急ブレーキ | 新積荷の荷崩れ防止につながる |
| 制限速度を守る | 8〜10km/hに設定されているところが多い | ・物理的な安全はもちろん、心の焦りの防止にもつながる ・機種によってはディスプレイで上限速度の設定が可能 ・速度超過を警告灯で知らせる装置あり |
| 交差点では一旦停止 | ラックや荷物の間から走行レーンに出る際、必ず一旦停止 | 「絶対に誰か来ている」という気持ちを持つ |
フォークリフトの運転方法マニュアル②【荷役作業編】
次に、フォークリフトの荷役作業について、その手順と注意点を以下の4つのポイントで解説します。
>>フォークリフトの運転方法をわかりやすく伝える「マニュアルの作り方・サンプル」はこちらをクリック!
各操作レバー/ペダルの役割と機能
カウンターバランス式とリーチ式は同じフォークリフトですが、操作レバーやペダルの仕様が大きく異なります。それぞれの役割を正確に理解しましょう。
▼カウンターバランス式フォークリフト▼
| レバー名称 | 役割 | 備考 |
|---|---|---|
| リフトレバー | フォークを上昇/下降させる | ・上昇:レバーを手前へ引く ・下降:レバーを奥へ倒す |
| ティルトレバー | マストを起こす/倒す | ・起こす:レバーを手前へ引く ・倒す:レバーを奥へ倒す |
| 前後進レバー | 前後進を切り替える(真ん中は中立) | ・トルコン車:ハンドル横 ・クラッチ車:フロア足元横 |
| 高低速レバー | ギアを切り替える(真ん中は中立) | ・クラッチ車のみ ・フロア足元横 |
| 駐車ブレーキレバー | 駐車ブレーキをかける/解除する | |
| アクセルペダル | 加速する | |
| ブレーキペダル | 減速/停止する | |
| クラッチペダル | 動力を遮断/繋ぐ | クラッチ車のみ |
| インチングペダル | ・動力を遮断/繋ぐ ・減速/停止 | トルコン車のみ |
▼リーチフォークリフト▼
| レバー名称 | 役割 | 備考 |
|---|---|---|
| リフトレバー | フォークを上昇/下降させる | ・上昇:レバーを手前へ引く ・下降:レバーを奥へ倒す |
| ティルトレバー | マストを起こす/倒す | ・起こす:レバーを手前へ引く ・倒す:レバーを奥へ倒す |
| リーチレバー | マストを押し出す/引き入れる | ・押し出す:レバーを奥へ倒す ・引き入れる:レバーを手前へ引く |
| アクセルレバー | 前進/後進の動作をする | ・前進:レバーを奥へ倒す ・後進:レバーを手前へ倒す ・真ん中は中立 |
| ブレーキペダル | ブレーキを作動/解除する | ・作動:足を離す ・解除:踏み込む |
【ワンポイントアドバイス】
トルコン車にある「インチングペダル」は、フォークリフト特有の便利な機能です。このペダルを使うと、アクセルを踏んでマストの昇降速度を上げながら、車体をゆっくり動かしたり停止させたりといった微調整が可能になります。使いこなせば、荷役作業の効率と精度が格段に向上します。
荷の積み取り手順
積み取り作業(荷物をフォークで取る作業)について、厚生労働省「フォークリフト」が示す正しい手順をご紹介します。
- 積み取りする荷の手前で減速する
- 荷の前に近づいて、一旦停止する
- 積付けしてある荷の荷崩れ、その他の危険がないかを確認する
- マストを垂直にし、フォークを水平にしてパレット又はスキッドの高さまで上昇(リフト)させる
- フォークの差込みの位置をよく確認し、フォークリフトを静かに前進させてフォークを差し込む。リーチ形では、マストを静かに伸ばして差し込む
- 差し込んだらフォークを少し (5 ~ 10cm) 上昇(リフト)させてから、フォークリフトを後進させ、パレット又はスキッドを 10 ~ 20cm ほど手前に引き出し、一旦降ろす
- さらにもう一度、フォークを根もとまで深く差し込み、荷をフォークの垂直前面又はバックレストに軽く接触させて、上昇(リフト)させる
- 上昇(リフト)させたら、荷を安全に降ろせる位置まで静かに後退する。リーチ形では、後進させるより先にマストを引っ込め、次に後進させ、パレット又はスキッドを安全に降ろせる位置にあるかを確認する
- 地上から 5 ~ 10cm の高さまで降ろし、マストを十分に後傾(ティルト)させ、フォークが床上より約15 ~ 20cm の位置の姿勢で目的の場所に移動する。リーチ形では、フォークをリーチレッグ上面から5cm 程度まで降ろし、次に十分に後傾(ティルト)し、目的の場所に移動する
取り降ろしの手順
取り降ろし(荷物を所定の場所へ降ろす作業)について、厚生労働省「フォークリフト」が示す手順に沿って解説します。
- 取り降ろしする場所の手前にきたら、速度を落とす
- 取り降ろしする場所に近づいたときは、一旦停止する
- 取り降ろし場所に荷崩れ、荷の破損などの危険がないかを確認する
- マストを垂直にし、フォークを水平にして、取りおろしの位置よりやや高めの位置まで上昇(リフト)させる
- 取りおろしの位置をよく確認してから、静かに前進して予定の位置に降ろす。リーチ形では、マストを静かに伸ばし予定の位置に降ろす。この場合、フォークリフトの前進は行わない
- 静かに後進してフォークを10~20m ほど引き抜き、再び上昇(リフト)させて安全かつ正しい取りおろしの位置まで前進して降ろす。リーチ形ではマストを静かに引っ込め、フォークを 10~20cm 引き抜き、再び上昇(リフト)させて、 安全かつ正しい取りおろしの位置まで伸ばして降ろす。この場合、フォークリフトの後進、前進は行わない
- 取りおろした荷が安定したら、後進してフォークを降ろし、マストを十分に後傾(ティルト)し、フォークが床上約 15~20cm の位置の姿勢で走行に移る。リーチ形では、フォークをリーチレッグ上面から出ない程度まで降ろし、次に十分に後傾(ティルト)し、走行に移る
荷役作業時の注意点
荷役作業は、わずかな不注意が重大な事故に直結するため、特に慎重な操作が求められます。注意すべき点は多岐にわたりますが、欠けていれば事故につながりかねません。
具体的には以下に挙げる点に注意し、安全な作業を心がけましょう。
関連記事:荷役作業の安全対策10選!事故や労働災害を防止するポイント
| 注意点 | 詳細 | ポイント |
|---|---|---|
| 「だろう」で判断しない | 「大丈夫だろう」「いけるだろう」と、死角の状況を憶測で決めつけない | ・確実に安全を確保した場合のみ、次の動作に移る ・不安があれば目視確認をする |
合図者をつける | 8〜10km/hに設定されているところが死角を補い、危険があれば知らせてもらう | ・荷物の状態や周囲の安全を確認してもらう ・危険な作業にも関わらず誰もいなければ、作業を中止する |
後方確認を徹底する | 荷物に集中すると後方確認がおろそかになりがち | ・荷役作業と走行を分けて考える ・指差呼称を行う |
【ワンポイントアドバイス】
フォークリフト事故の多くは荷役中に起こり、その根本原因には「焦り」が潜んでいます。私自身の経験でも、ヒヤリハットのほとんどは「急がなければ」という気持ちからくる判断ミスが引き金でした。
例えば、不安定な荷物を見て「大丈夫だろう」と確認を省いて荷崩れを起こすのは典型的な例です。冷静であれば、一度降りて荷物を直すという正しい判断ができたはずです。
「焦って事故を起こす方が、結果的に何倍も時間がかかる」ということを肝に銘じ、常に落ち着いてそれぞれの動作を確実に行うことが、安全への一番の近道です。このような安全意識の醸成に役立つフォークリフトの安全教育・対策事例もご用意しておりますので、本記事と併せてご覧ください。
>>フォークリフトの安全運転に役立つ「フォークリフトの安全教育・対策事例」をみる
フォークリフトの事故を削減し、生産性・作業効率を上げる方法
一般社団法人日本産業車両協会がまとめた資料によると、フォークリフトによる労働災害の発生件数は、残念ながら減少傾向にあるとはいえません。事故を減らし労働災害や物損事故を予防するには、現場の実態に即した継続的な取り組みが不可欠です。
ここでは、その具体的な方法として以下4つのポイントを解説します。
- 作業手順書を作成し基本操作を標準化する
- 操作が上手い人を参考に個々がスキルアップする
- KY活動(危険予知活動)を実施し従業員の安全意識の向上を図る
- 安全教育に動画を活用する
>>フォークリフトのゼロ災を達成する近道!「フォークリフトの安全教育・対策事例」はこちらをクリック!
作業手順書を作成し基本操作を標準化する
作業の標準化とは「誰が、いつ、どの作業を行っても一定の品質や効率で業務を遂行できるように、最適な手順やルールを定めて統一すること」を指します。これは現場作業の事故防止に効果的であり、作業者ごとの判断のばらつきをなくし、不安全行動や思い込みによるミスを防ぎます。
標準化されたルールに基づくことで作業環境が安定し、誰が行っても同じ安全レベルを確保できるようになります。また教育や引き継ぎも容易になり、新人でも安全に作業できるため、事故削減と生産性向上の両立につながります。
重要なのは、標準化を「浸透」させることです。ルールを作るだけでなく作業標準書やマニュアルのような分かりやすい形で共有し、教育や訓練を通じて定着させる必要があります。紙マニュアルだけでなく動画や図解を活用すれば理解度が高まり、現場の声を取り入れて改善すれば、安全と効率を兼ね備えた仕組みを維持できます。
フォークリフトの運転方法をわかりやすく示し、標準化を推し進める「マニュアルの作り方やサンプルマニュアル」について知りたい方は、以下のリンクからマニュアル集をご覧ください。
>>【すぐに使える4種類のサンプル付き】 フォークリフトのマニュアル作成ガイドブックをみる
操作が上手い人を参考に個々がスキルアップする
作業の標準化を土台としたうえで、個々のスキルアップを目指すことも重要です。職場にいる運転が上手い人の技術を観察し参考にすることが、現場全体のレベルを底上げする近道となるでしょう。
フォークリフト運転が上手い人の特徴や上達のコツについては、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
関連記事:【経験者が解説】フォークリフト運転上達のコツ!上手い人の特徴とは?
KY活動(危険予知活動)を実施し従業員の安全意識の向上を図る
フォークリフトを実際に運転する前に、「KY活動」を実施するのも効果的な手段の1つです。KY活動とは作業に潜む危険を事前に予測し、予防措置を講じることで労働災害を未然に防ぐ活動を指します。事故防止のために、現場での積極的な実施がおすすめです。
日々の活動を通じて危険への感受性を高め、安全意識を熟成させることは結果的に事故の未然防止に繋がります。具体的なKY活動の例や形骸化しにくいKY活動の進め方については、以下のリンクから別紙の資料をご覧ください。
>>「やって終わり」で形骸化させないKY活動/KYTの進め方・好事例をみる
安全教育に動画を活用する
ここまでに挙げた「標準化」「スキルアップ」「安全意識向上」をより効果的に進める手段として、安全教育における動画の活用をおすすめします。
例としてKYT(危険予知訓練)の教材を動画に置き換えたり、安全ルールの周知に活用したりと、その用途はさまざまです。
では、なぜ動画の活用が有効なのでしょうか。次の章で詳しく解説します。
フォークリフトの事故防止には「動画による教育」が有効!
先述したようなフォークリフトの事故を防止し、安全で生産性の高い現場を実現する手段として「動画」の活用が注目されています。
ここではなぜ動画の活用が事故防止に有効なのか、具体的な3つの理由を掘り下げて解説します。
- 安全教育に作業風景を使用すれば状況を鮮明にイメージできる
- 上手い人のテクニックを動画で共有すれば効率的に学習できる
- 動画マニュアルなら基本操作の標準化を実現しやすい
安全教育に作業風景を使用すれば状況を鮮明にイメージできる
KYT(危険予知訓練)などの安全教育では、作業に潜む危険な状況を参加者に伝える場面がよくあります。しかしイラストシートや口頭での説明だけでは、危険な状況を具体的にイメージしきれないことも少なくありません。
その点、動画であれば実際の作業風景を用いて危険なポイントを視覚的に伝えられるため、誰もが状況をリアルに理解し、危険感受性を高めることができます。
例として、「フォークリフトのNG運転例」を動画でマニュアル化したものをお見せします。
※「tebiki現場教育」で作成しています
動画であれば「どのような動作が危険なのか?」を見たままに伝えられるため、従業員の安全意識や業務理解がより深まります。
本サンプル動画の作成に使用されたかんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」なら、現場の担当者がスマートフォンで撮影するだけで、誰でもかんたんに動画教材を作成・編集できるため、手間なく実践的で効果的なKY活動が可能です。
>>動画マニュアルを活用したフォークリフトの安全教育・対策事例をもっとみる
上手い人のテクニックを動画で共有すれば効率的に学習できる
熟練者の「カン・コツ」といった言語化しにくいノウハウも、映像なら直感的に伝えることが可能です。さらにスマートフォンでいつでもどこでも視聴が可能なため、時間や場所の制約を受けずに繰り返し学習でき、全員を現場に集めてOJTを実施するよりもはるかに効率的な教育を実現できます。
例として、以下の記事では、フォークリフト運転上達のコツや上手い人の特徴を紹介しています。
関連記事:【経験者が解説】フォークリフト運転上達のコツ!上手い人の特徴とは?
動画マニュアルなら基本操作の標準化を実現しやすい
乗車方法や始業前点検といった基本操作は、全従業員が同じ手順を遵守できるよう標準化することが不可欠です。その周知徹底にも、動画は大きな力を発揮します。
例として、物流企業の「株式会社近鉄コスモス」ではフォークリフトの安全ルールを動画マニュアルで共有し、教育の標準化に役立てています。
▼始業前点検の手順や方法を動画マニュアル化した事例▼
※「tebiki現場教育」で作成しています
テキストや口頭での説明と異なり見る人によって解釈のブレが生じにくいため、教育内容のばらつきを防ぎ、作業品質の標準化を実現します。
動画マニュアルの有効性やさらなる活用事例については、以下の資料でも詳しく解説しています。
>>教育のばらつき/教育負担の削減が見込める”動画マニュアル”の有効性&活用事例をもっとみる
ここまで、動画の活用がフォークリフトの運転方法の標準化や安全教育に役立つ理由や、実際のマニュアル例についてお見せしました。
次章では、現場の負担を減らしながら動画マニュアルが簡単に作成できるおすすめのツールについてご紹介します。
撮影・編集・共有がかんたんにできる!おすすめは動画マニュアル「tebiki現場教育」
「tebiki現場教育」は、誰でもスマホで撮影するだけで動画マニュアルが作成できるツールです。
難しそうに見える動画マニュアルを映像編集の知識がなくても直感的に作成・編集できるため、多くの現場で高く評価されています。実際に、マニュアル作成にかかる時間を約75%削減した事例もあるほどです。
tebiki現場教育の主な機能とメリットは次の通りです。
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| 自動文字起こし機能 | …動画内の音声を自動で文字起こし 動画内で話している音声を自動で文字起こしし、字幕として表示できます。誤字や言い回しの細かい修正を行うだけで、字幕付きマニュアルが完成します。 |
| キーワード検索機能 | …見たいマニュアルがすぐ見つかる 大量の紙マニュアルや手順書を探す手間がなくなり、知りたい作業をその場ですぐ確認できます。 |
| コース機能 | …部門別にノウハウを整理整頓 フォークリフトの特別教育コースや基本的な運転の習得コースなど、ノウハウごとに動画マニュアルをまとめられます。コース機能のページを共有するだけで、該当業務のノウハウを学べます。 |
| スキル管理機能 | …人材スキルを可視化できる 従業員ごとの「できること・できないこと」を可視化。業務の最適な割り振りが可能になり、誰にどの教育が必要かも一目で把握できます。 |
「tebiki現場教育」について詳しく知りたい方は、下のリンクをクリックしサービス資料をご覧ください。
>>物流現場の安全教育・標準化に役立つ動画マニュアル「tebiki現場教育」の詳細をみる
物流現場の安全教育に動画を活用した企業事例
動画で全拠点の安全品質意識の向上と業務ノウハウの可視化を達成!
まず、社員・パートナー社員・派遣社員を含め約300名が在籍する物流企業である、株式会社ロジパルエクスプレスの事例をご紹介します。
| 課題 | tebiki現場教育導入の効果 |
|---|---|
| ・拠点ごとにマニュアルやルールが異なり、作業品質がばらつく ・紙マニュアルは検索性が低く、現場で活用されにくい ・「胸の高さまで積載」といった曖昧な表現で、安全ルールが人によって異なる解釈に | ・動画による統一マニュアルで理解度が高まり、事故防止や品質向上に直結 ・検索性やアクセス性が向上し、必要な時にすぐ確認できる環境を実現 ・教育コスト削減と業務効率化に貢献、トラックドライバーのスキマ時間学習にも活用 |
従来は拠点ごとに紙マニュアルを作成していたため手順やルールが統一されず、業務品質のばらつきや曖昧な表現による事故リスク、情報検索の手間、ベテラン社員のノウハウ属人化といった課題を抱えていました。
解決のため動画マニュアル(tebiki現場教育)に切り替えたことで、安全・品質教育を全拠点で統一できたほか理解度や検索性が向上し、必要な時に現場ですぐ確認できるようになりました。承認に1か月近くかかっていたマニュアル作成工数も短縮され、教育コストや業務負荷が削減。さらに、トラックドライバーが隙間時間で学習するなど倉庫外でも活用が広がっています。
現場からは「フォークリフトの危険予知トレーニングを動画配信することで全員が同じ基準で学べるようになった」「受け手の解釈の差がなくなり教育が平準化された」と高く評価されており、事故防止と品質向上の両面で成果を上げています。
>>同社が活用した動画マニュアル「tebiki現場教育」の機能詳細や事例をもっと見たい方はこちらをクリック!
フォークリフトの運転方法や安全教育に動画を活用し教育工数を削減!
続いて、港湾運送事業や倉庫業などを展開する総合物流企業である株式会社フジトランスコーポレーションの事例をご紹介します。
| 課題 | tebiki現場教育導入の効果 |
|---|---|
| ・従業員の入れ替わりが多く、教育や引き継ぎの負荷が大きい ・口頭や紙マニュアルでの教育に依存し、解釈の差や品質のばらつきが発生 ・外国人労働者への教育で翻訳や指導に工数がかかる | ・動画で手順を統一することで教育の均一化を実現し、工数を削減 ・動画により誰でも同じ基準で学べ、作業品質の安定化につながった ・多言語自動翻訳機能で正確な教育を効率的に展開できるようになった |
従来は口頭や紙マニュアルでの教育に頼っていたため教育者ごとに伝え方が異なり、受け手の理解度に差が出ることが大きな課題でした。さらに外国人労働者への教育では翻訳や説明に時間を要し、現場や管理部門の負担となっていました。
解決のために動画マニュアル(tebiki現場教育)を導入した結果、作業手順を誰でも同じ基準で学べるようになり、教育の質が均一化。多言語自動翻訳により外国人労働者にも正確に教育を展開でき、問い合わせ対応も効率化されました。その結果、教育工数や対応時間が大幅に削減され、全社的な業務効率化と安全水準の底上げにつながっています。
現場からは「動画で共有することで解釈の差がなくなり、教育の質が平準化された」「繰り返し学習できるため安全教育が定着した」「問い合わせ対応時間が月10時間から3時間に減った」との声が上がっています。
>>同社が活用した動画マニュアル「tebiki現場教育」の機能詳細や事例をもっと見たい方はこちらをクリック!
まとめ
本記事ではフォークリフトの基本情報から具体的な運転方法、そして事故を未然に防ぐためのポイントまでを網羅的に解説しました。
フォークリフト作業における安全は、個々のオペレーターが正しい運転方法を理解し、日々実践し続けることで確保されます。こうした地道な取り組みが悲しい事故を未然に防ぎ、ひいては働きやすい労働環境の改善にもつながるのです。
安全で生産性の高い職場を実現するためには、以下のような継続的な取り組みが重要となります。
- 操作が上手い人を参考に個々がスキルアップする
- KY活動を実施し従業員の安全意識の向上を図る
- 作業手順書を作成し基本操作を標準化する
- 安全教育に動画を活用する
中でも、これらの取り組みを効率的かつ効果的に進めるうえで、動画の活用は有効な手段です。特に動画マニュアル「tebiki現場教育」は、現場の担当者がスマートフォンで撮影するだけで、誰でもかんたんに分かりやすい教育動画を作成・共有できるツールです。熟練者の技術伝承から安全ルールの標準化まで、フォークリフト教育が抱える多くの課題解決に貢献します。
フォークリフトの安全教育や操作手順の標準化に関心をお持ちの方は、是非以下の画像からサービス資料をダウンロードし、詳細をご確認ください。
引用元/参照元
・e-Gov法律検索「労働安全衛生規則 第151条の25」
・陸上貨物運送事業労働災害防止協会「運転試験操作手順」
・厚生労働省「フォークリフト」
・一般社団法人日本産業車両協会「フォークリフトに起因する労働災害の発生状況」