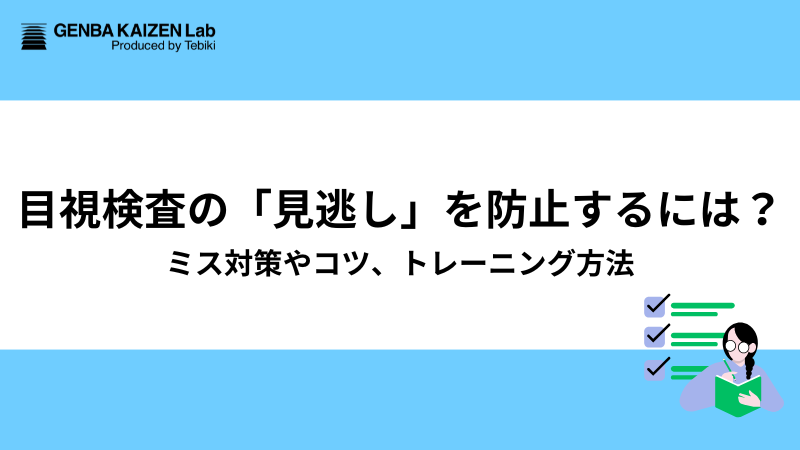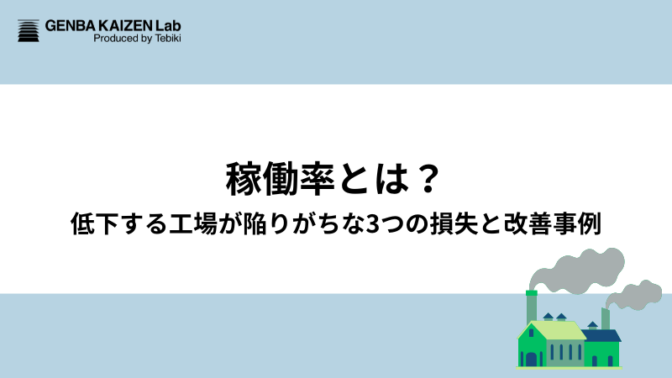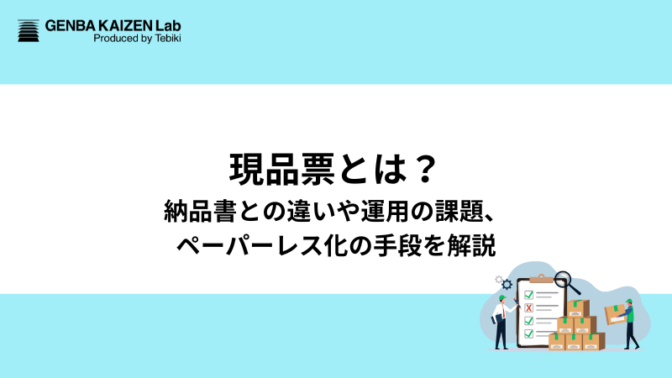かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
目視検査とは、人間が肉眼で製品の傷や不具合をチェックする検査方法です。製品を出荷する前の最終検査として重要なプロセスであり、品質を担保するために多くの企業が導入しています。しかし「もっと効率よく目視検査を行いたい」「見逃しが多く、精度が低いので改善したい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では目視検査の課題対策や検査の質を高める方法を紹介します。品質を向上させたい方は最後までご覧ください。
目次
目視検査の限界を克服し、不良品流出を防ぐ改善策については上記のハンドブックでも詳しくご紹介しています。実践的な品質不良の改善方法を知りたい方は併せてご覧ください。
目視検査とは?
目視検査とは、人の目で製品や部品の外観をチェックし、不良や欠陥を見つける検査方法です。まずは目視検査におけるチェック項目と、検査の種類をご紹介します。
目視検査では何をチェックする?作業内容を紹介
検査員が直接目で見て、製品に異常がないかどうかを確認する目視検査では、形状や構造、表面、仕上がりなどを重点的に確認しています。
▼目視検査の確認項目例▼
| チェック内容 | 検査例 | |
|---|---|---|
| 形状や構造 | 設計通りの形状になっているか、構造上の問題がないかを確認 | 自動車のブレーキシステムの形状が適切か確認し、不良があれば事故防止のために修正 |
| 表面 | 傷やへこみがないかを確認 | 家電製品や自動車のボディに傷やへこみがないかをチェックし、外観品質を維持 |
| 仕上がり | 塗装や組み立てなどの最終チェック | 家電製品の塗装ムラや異音の有無を確認し、顧客満足度を向上させる |
不良品検知の具体的なコツや改善方法については、以下の関連記事もご覧ください。
関連記事:不良品検知とは?検知の方法と導入の課題、解決方法を解説!
目視検査の種類
目視検査には以下のような種類があります。表形式でわかりやすく解説します。
- インライン検査:製造ライン中で行う検査
- オフライン検査:製品ラインとは別で行う検査
- 全数検査:全ての製品に対して行う検査
- 抜取検査:ランダムに行われる検査
その他の検査種類や、目視検査に代表される品質検査の質向上に必要な対策については、以下の記事でわかりやすくまとめています。
関連記事:製造業の品質検査に潜む課題と改善策!検査員スキル向上事例も解説
| 特徴 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| インライン 検査 | 製造ライン上で次工程に進む前に検査を行う | ・リアルタイムで不良を検出できる ・早期に不具合を発見し対策できるため納期短縮につながる ・製造プロセス全体の品質を向上できる | ・製造ライン上で行える検査には限界がある ・検査精度が作業者のスキルに依存する ・検査によるラインの遅延リスクがある |
| オフライン 検査 | 製造ラインから製品を取り出し、専用エリアで実施 | ・生産ラインに左右されずに検査を実施できる ・製品をじっくり確認できるため詳細な検査が可能 ・製造ラインへの影響が少ない | ・検査に時間とコストがかかる ・製造の後段階で実施するため不良品の流出リスクがある |
| 全数 検査 | すべての製品を対象に実施 | ・不良品の流出リスクが低い ・全数を検査するため信頼性が高い | ・すべての製品を検査するため生産効率が低下しやすい ・検査を行うために多くの検査員が必要 |
| 抜取 検査 | 一部の製品をランダムに抽出して実施 | ・全数検査と比べて検査にかかる時間とコストを大幅に抑えられる ・検査環境や検査基準を調整しやすい | ・全数検査と比べ不良品を見逃すリスクが高い ・全体の品質を推測するには統計の知識が必要 |
目視検査のメリット/デメリット
目視検査を実施する利点と問題点は、以下の通りです。
メリット
目視検査を実施するメリットは、以下の2点です。
さまざまな検査に柔軟に対応できる
目視検査は機械やシステムを導入する必要がないため、さまざまな検査に柔軟に対応できます。たとえば、検査項目や検査する部品が変更したとしても、すぐに対応することが可能です。
比較的安価なコストで導入できる
目視検査は比較的安価なコストで導入できます。高価な機械や専門的な検査装置が必要ないため、最小限の初期投資と運用コストで検査を行いたい方におすすめの検査方法です。
デメリット
目視検査には、以下のようなデメリットもあります。
検査員の育成がきつい
目視検査は検査員の育成が大変というデメリットがあります。検査員には、微細な不良品を見分ける鋭い観察力と検査基準に基づいた正確な判断能力が求められます。そのため、検査員を育成するには長期間の実践練習を行うことが不可欠です。
精度が作業員に左右されやすい
目視検査には精度のばらつきが生じやすく、特に検査員によって視力や疲労・度合い・判断基準に違いがあるため、一貫した精度を保つのが難しい場合があります。そのため、検査基準を厳格に定め、検査員同士で情報共有を行うことが重要です。
検査に時間がかかる
目視検査は他の検査と比べて検査時間が長くなりがちです。検査員が製品を1箇所ずつ入念に確認する必要があるため、検査結果が出るまで時間がかかります。そのため、不良品が見つかった際に製造ラインを迅速に停止させるのが難しい可能性があります。
目視検査の見逃し原因や課題
目視検査は製造現場において広く採用されている品質管理手法ですが、不良品の見逃しというリスクが常につきまといます。検査の精度が低下すると、不良品が市場に流出し、クレームやリコールにつながる可能性があります。その原因として、主に以下のような課題が挙げられます。
ヒューマンエラー
目視検査は人の感覚や判断に依存するため、必然的にヒューマンエラーが発生します。特に検査対象が多岐にわたる場合や微細な欠陥を見極めなければならない場合、ミスのリスクが高まります。
また、人間の記憶には限界があり、一度に多くの情報を処理しようとすると、誤認識や判断ミスが生じやすくなります。さらに作業に慣れてくると「この程度なら問題ないだろう」という思い込みが生まれ、検査精度が低下することもあります。
ヒューマンエラーが発生する原因や再発防止の方法についてすぐに知りたい方は、以下のハンドブックをご確認ください。
>>製造業におけるヒューマンエラーの未然防止と具体的な対策方法を見てみる
検査員の疲労や注意の散漫
目視検査は長時間にわたることが多く、集中力を維持し続けるのは困難です。特に連続した作業では視覚的な疲労が蓄積し、細かい異常を見逃しやすくなります。
また、単調な作業の繰り返しによって注意力が散漫になり、作業に対する意識が低下することも少なくありません。このような状態では、一瞬の判断ミスが見逃しにつながりやすくなります。
検査環境の不備
検査環境の不整備も目視検査の精度を左右する重要な要素です。検査環境が整っていないと、検査員の作業効率や集中力に悪影響を及ぼします。たとえば、照明が不十分で明るさが足りない環境ではわずかな傷やへこみを発見できず、不良品を見逃す可能性が高まります。
さらに、作業スペースが狭い、整理整頓がされていないといった環境要因も検査の効率や精度を低下させる原因となります。例えば、検査台が狭く製品を適切な角度で観察できない場合、本来見えるはずの欠陥が死角に入り、見逃してしまうことがあります。
検査基準の曖昧さ・暗黙知
目視検査の精度を保つには明確な検査基準が必要ですが、実際には基準が曖昧なまま運用されているケースも多く見られます。例えば、「軽微なキズ」「許容範囲内の色むら」といった表現は、検査員によって解釈が異なる可能性があります。
基準が明確でない場合、検査の合否判断にばらつきが生じ一貫性のある品質管理が難しくなります。また、熟練者がカンコツなど経験則に頼って検査を行っている場合、新人が基準を理解しにくく、判断ミスを引き起こす要因になります。特に、「経験を積めば自然と分かる」といった暗黙知が多い場合、新人が適切な判断をするのは難しくなります。
「熟練工のノウハウを伝承させたいが、上手く伝わらない…」とお悩みの方は、本記事のほか以下の資料もご覧ください。
>>“伝わらない・属人化している”カンコツ作業の伝え方は?(無料DL)
作業員のスキルのばらつき
検査員のスキルに差があると、不良の見逃し率にも違いが生じます。熟練者は経験をもとに異常を素早く見つけられますが、新人は判断基準が曖昧で、迷いや誤判断が起こりやすくなります。
また、検査員ごとに重視するポイントが異なると、同じ製品を検査しても結果にばらつきが生じます。特に検査機会が少ない作業員は経験を積みにくくスキル向上が遅れるため、検査精度が安定しにくくなります。こうしたスキルのばらつきは検査結果の一貫性を損ない、品質の安定を妨げる要因となります。
スキルのばらつきを解消する上で、動画マニュアルの活用が有効視されています。動画という共通の教材を使うことで教育内容を統一し標準化することや、繰り返し視聴することで迅速な教育訓練が可能です。
動画マニュアルの有効性について詳しく知りたい方は、以下のリンクをクリックしマンガ形式の資料をご覧ください。
>>動画マニュアルで標準化を促進できる!活用方法や効果について知る
目視検査の見逃しを解消しスピードを上げる3つの対策
目視検査の課題を解決し、見逃し解消やスピードの向上を目指したい方は以下のような対策がおすすめです。
- 作業環境を整備する
- 周辺視目視検査法を導入する
- 標準作業を定めて順守させる
作業環境を整備する
良好な作業環境を整えることで、検査員の集中力と作業効率が向上し、目視検査の精度を高められます。たとえば、検査スペースが暗いと手元がよく見えないため、製品不良を見逃してしまいます。そのため、照明の光度・温湿度・騒音レベルなどを管理して、検査員が快適に目視検査を実施できる環境を整えるようにしましょう。
ここで、作業場や動きの導線にムダがないか?ということを洗い出すこともおすすめです。検査台の高さや配置、工具や検査対象の置き場所を最適化し、ムダな移動や姿勢の変化を減らすことで、検査の効率と精度を向上させることができます。
作業場のムダを可視化し対策するには、5S活動を実施しましょう。進め方や具体例などを詳しくまとめた解説動画もありますので、以下のリンクをクリックし是非ご参照ください。
>>現場のムダを排除し、生産性を高める5S活動の具体的な方法をみる(視聴無料)
周辺視目視検査法を導入する
周辺視目視検査法とは製品の一部ではなく全体を周辺視野を使って見ることが特徴で、中心視野よりも周辺視野の方が動きをとらえやすいという人間の目の特性を利用した検査方法です。
周辺視目視検査法の具体的な進め方として、品質を満たした良品のイメージを事前に確認したうえで製品全体を目視し、良品かどうかを視線を動かさずに次々と確認するということが挙げられます。
この検査方法を活用することで目の疲れを軽減しつつ、見逃しやミスのリスクを減らすことが期待できます。
標準作業を定めて順守させる
標準作業が曖昧だと検査員ごとに判断基準が異なり、不良の見逃しや合否判定のばらつきが発生しやすくなります。特に、新人と熟練者のスキルの差が大きい場合、経験に依存した検査では一貫性を保つのが難しくなります。
標準作業を定める際には、不良の判定基準や検査の手順を詳細にマニュアル化し、すべての検査員が同じ基準で作業できるようにすることが重要です。例えば、「傷の深さが0.5mm以上なら不良とする」といった具体的な基準を設けることで、個人の主観に頼らない判断が可能になります。
「手順書はあるものの、読まれず形骸化してしまう…」という現場には共通点があります。標準作業を現場に浸透させるコツをまとめた以下の資料をもとに、自社の手順書を見直してみるのも良いでしょう。
>>「手順が守られる」作業手順書を整備するポイントについて知る
目視検査の課題対策には「教育と記録の改善」が欠かせない
目視検査の課題対策として、自動化や機械化の導入を考える方も多いのではないでしょうか?しかし、以下の理由から完全な自動化は難しいといえるでしょう。
- 柔軟な判断が求められる工程や最終チェックでは人の判断が不可欠
- コスト面や設置環境の制約により、導入が現実的ではない場合がある
- 検査を自動化しても、検査結果の記録や確認には人の介在が必要
つまり、どれだけ自動化が進んでも人の手が完全に介在しない状況は現実的ではなく、むしろ人によるチェックと正しい記録には、検査員への適切な教育と記録業務の改善が品質維持の鍵となります。
本章では、具体的な改善方法について解説します。
教育によるトレーニングでばらつきを排除
目視検査の精度向上には、検査員の教育とトレーニングが欠かせません。定期的にスキルチェックを行うことで検査のばらつきを防ぎ、検査員の判断精度を向上させることが可能です。
例えば、良品と不良品の判断基準や製品ごとのチェックポイントを明確にしておくことで、個々の検査員が一貫した判断を下せるようになります。
このとき、マニュアルや手順書の「動画化」が注目されています。
▼目視検査の手順を動画化したマニュアルの例▼
※「tebiki現場教育」で作成
このように動画化することで、検査員は視覚的に実際の作業を確認しながら学べるため、テキストだけでは理解しにくい部分も直感的に把握できるようになります。特に、目視検査では細かな違いを判断する必要があるため、実際の検査シーンを動画で再現し、具体的な判断方法や注意点を示すことが効果的です。
動画マニュアルの有効性について詳しく知りたい方は、以下のリンクをクリックしマンガ形式の資料をご覧ください。
記録のデジタル化で負担軽減
目視検査を効率化するには、デジタル化による記録の改善も有効です。
多くの製造現場では検査結果を紙の検査成績書などといった帳票に記録していますが、毎回作業を中断して記録する場合は用紙の配布・収集を行う手間がかかり作業効率が落ちるという課題があります。また、製造ラインの不具合で不良品が急増した際に、紙の帳票ではすぐ確認できないという問題もあります。
そのため、目視検査自体のやり方を改善することも大切ですが、記録方法を改善する方が低コストで効率を高められるといえるでしょう。
記録や帳票のデジタル化にご興味がある方は、導入の流れや費用対効果なども確認できる以下のハンドブックをご覧ください。
目視検査のトラブルを解決する2つのツール
先述した「教育・記録のカイゼン」が実現する、2つのツールについてご紹介します。
動画マニュアル「tebiki現場教育」
tebiki現場教育 は、現場での作業手順や検査のポイントをスマートフォンで撮影し、簡単に編集・共有できるクラウド型動画教育システムです。
動画による学習は、視覚と聴覚を活用することで紙やテキストのマニュアルに比べ直感的に理解しやすく、未経験者でも短期間で習得できます。また、手順の標準化や検査基準の統一が可能になり、検査品質の均一化も期待できます。
さらに、自動字幕機能や多言語対応により、多国籍なスタッフが在籍する現場でもスムーズな教育が可能です。教育の進捗をデータとして可視化できるため、個々のスキル向上の管理も容易になります。他にも、tebiki現場教育には以下の魅力的な機能も備わっています。
| テスト機能 | オリジナルテストを作成してユーザーの理解度を確認 |
| レポート機能 | 従業員1人ひとりのアクセス履歴と習熟度進捗を可視化 |
| タスク機能 | 完了予定日を指定しタスクを課す |
| コース機能 | 作成したマニュアルをまとめて教科書を作成 |
| スキル機能 | 個々の従業員の習熟度を可視化し、育成計画に活用 |
tebiki現場教育の具体的な機能や活用事例については、以下のリンクから確認いただけますので併せてご覧ください。
>>tebiki現場教育の機能詳細や事例、サポート体制をみる
デジタル帳票「tebiki現場分析」
tebiki現場分析は、現場帳簿をデジタル化し、帳簿の作成・記録・管理、さらに分析まで簡単に行えるツールです。日々の記録がクラウド化されることで、場所を問わずデータにアクセスできるようになり、現場状況の確認にかかる手間を軽減します。
特に注目すべきは、記録が正常値から外れた場合に異常値として自動検出する機能です。異常値は強調表示されるだけでなく承認者へアラートメールが送信されるため、迅速な問題対処が可能です。
さらに、tebiki現場分析は以下のような充実した機能も搭載されています。
| データ分析機能 | 記録した数値を自動でグラフ化 |
| 画像記録機能 | 画像をアップロードして記録できる機能 |
| 定時記録機能 | 数時間おきに実施する記録の効率化をサポート |
tebiki現場分析の充実したサポート体制も魅力のひとつです。詳しい情報をご希望の方は、是非以下のリンクから資料をダウンロードしてご確認ください。
>>tebiki現場分析の機能詳細や費用対効果、導入までの流れをみる
まとめ
目視検査は製品の品質管理において重要な役割を担っていますが、その精度や効率に課題が存在します。本記事では、目視検査の主な問題点や課題を明らかにし、これらを克服するための実践的な対策を紹介しました。
目視検査の課題解決には、特に「教育と記録の改善」が重要です。本記事でご紹介した動画マニュアル「tebiki現場教育」 とデジタル帳票「tebiki現場分析」を使えば、検査手順を視覚的に示し作業者の教育を支援することや、検査結果がリアルタイムで記録・可視化し問題発見を迅速に行うことが期待できます。これらのツールを導入することで検査精度の向上と作業者の負担軽減を実現でき、持続的な品質改善が可能となります。
ツールの詳細は以下の資料に記載されていますので、興味がある方はぜひご覧ください。