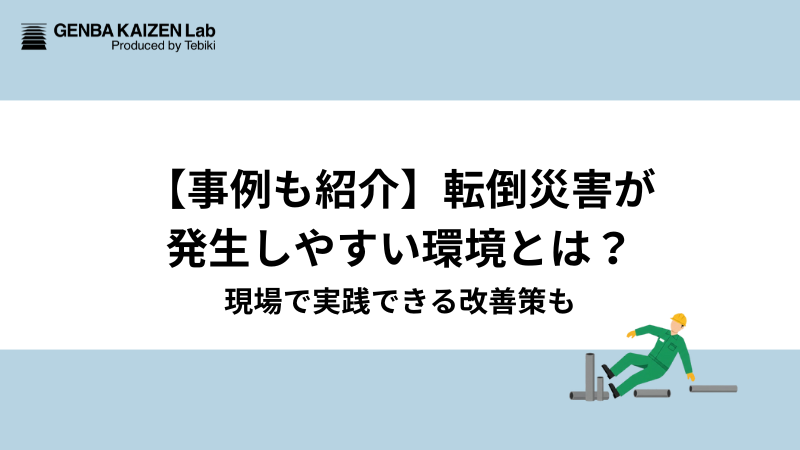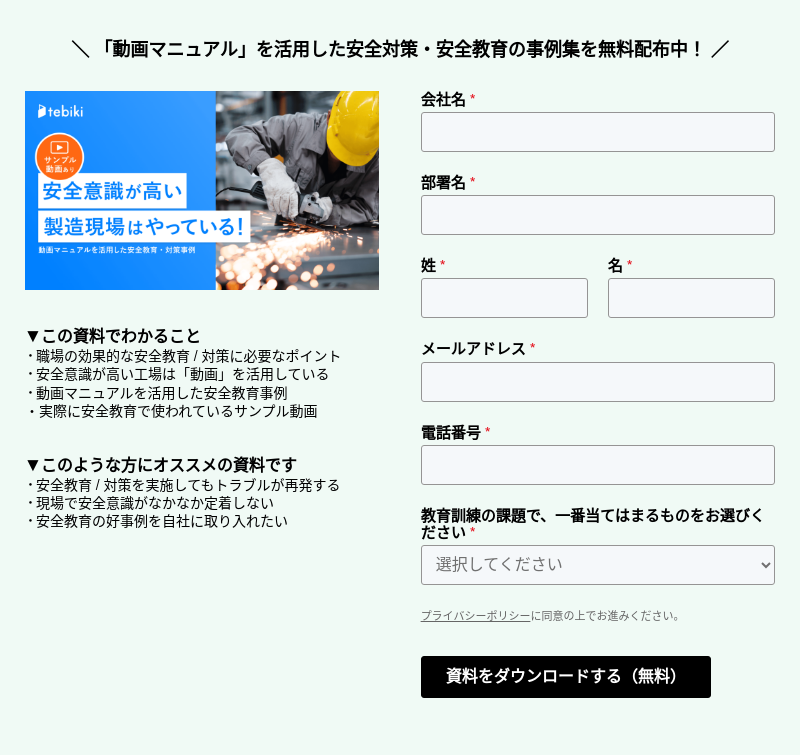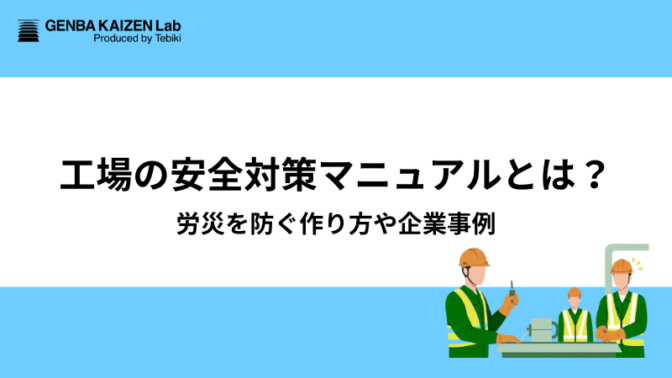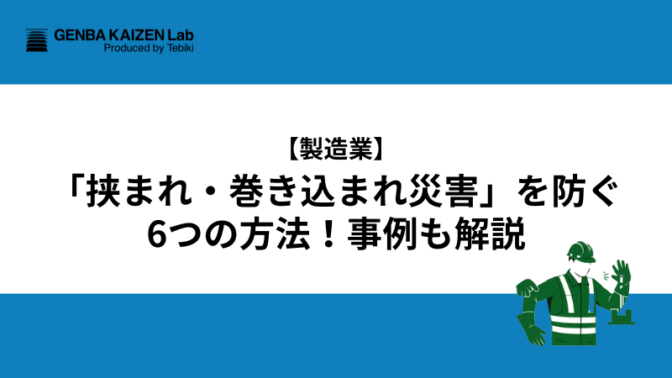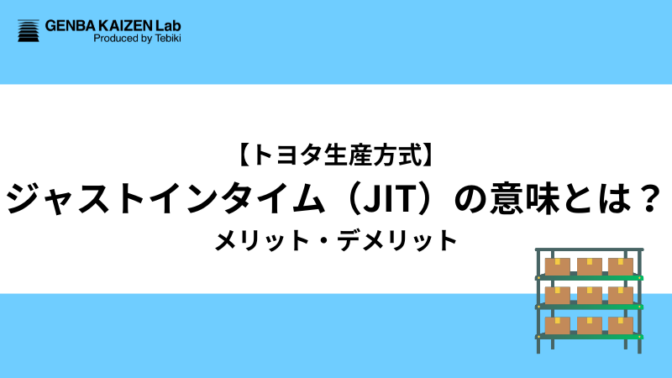かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
製造業の現場では、日々の作業に潜む危険が数多く存在します。その中でも、転倒災害は労働災害の中でも発生件数が多く、深刻な問題です。
本記事では、製造業における転倒災害の定義や発生状況、具体的な原因と対策について詳しく解説します。さらに、転倒災害を防止するための現場改善策や、安全教育に役立つ動画マニュアルの活用事例もご紹介します。
目次
製造業での転倒災害とは?
厚生労働省の「事故の型分類表」によると、転倒とは、「人がほぼ同一平面上でころぶ場合をいい、つまずきまたはすべりにより倒れた場合をいう。車両系機械などとともに転倒した場合を含む。交通事故は除く。感電して倒れた場合には感電に分類する。」と定義されています。
転倒災害とは、この定義に基づき、工場や作業現場で発生する労働災害の一種です。転倒災害が発生すると、作業員は怪我を負うだけでなく、最悪の場合、死亡事故につながる可能性も否定できません。また、企業にとっても、損害賠償金の支払いが発生したり生産ラインが停止したりするなど、大きな損失につながる可能性があります。
製造業における転倒災害について、以下の2つに分けて詳しく解説します。
- 製造業における転倒災害の発生率の発生率と統計データ
- 転倒災害のリスク
製造業における転倒災害の発生率と統計データ
厚生労働省の労働災害発生状況によると、令和4年度には約3万5千件、令和5年度には約3万6千件の転倒事故が発生しています。
製造業における死傷災害の内訳を見ると、令和2年では転倒災害が最も多く、令和3年では「挟まれ・巻き込まれ災害」に次いで2番目に多い状況です。これらのデータからも、転倒災害が製造業において頻繁に発生していることがわかります。
関連記事:【製造業の労働災害】事例や対策例、多い月などランキングを解説
転倒災害のリスク
転倒災害は、労働者と企業双方にとって、様々なリスクをもたらします。
| 労働者のリスク | ・怪我 ・労災による休業 ・離職 |
| 企業のリスク | ・生産ラインの停止や納期遅延 ・企業の信頼低下(安全意識の低い企業として評価される) ・労働基準監督署の指導や監査の強化 |
このように、労働者・企業ともにリスクのある転倒災害を防ぐ必要があります。どのような現場で転倒災害が発生しやすいのか、次章を見ていきましょう。
転倒災害が発生しやすい製造現場の例
製造現場では、以下のような状況で転倒災害が発生しやすいため注意が必要です。
- 滑り
- つまずき
- 踏み外し
「滑り」による転倒の原因と具体例
製造現場では、床面の状態、液体の飛散、作業靴の問題など、様々な要因が複合的に絡み合い、滑りによる転倒が発生します。特に、水や油で濡れた床、切削油が飛び散る金属加工工場、薬品がこぼれやすい化学工場などは、滑りやすく非常に危険です。
| 滑りの原因 | ・床面の状態 ・液体の飛散 ・作業靴の問題 |
| 滑りやすい環境 | ・食品工場 ・金属加工 ・化学工場など |
「つまずき」による転倒の原因と具体例
つまずきによる転倒は、工具や資材の散乱、コードやホース類の放置、予期せぬ段差などが主な原因です。狭い作業スペースや暗い場所では、足元が見えにくく、つまずきに気づきにくいため、注意が必要です。
| つまずきの原因 | ・工具や資材の散乱 ・コード・ホース ・段差 |
| つまずきやすい状況 | ・狭い作業スペース ・暗い場所での作業 |
「踏み外し」による転倒の原因と具体例
高所作業、階段や段差の昇降、不安定な足場など、足を踏み外しやすい状況は様々です。特にフォークリフト周辺や段差のある通路は、踏み外しによる転倒が起こりやすい危険な場所です。
| 踏み外しの原因 | ・高所作業 ・階段・段差 ・足場の不安定さ |
| 踏み外しやすい場所 | ・フォークリフト周辺 ・段差のある通路 |
実際に発生した転倒災害(ヒヤリハット)の事例
実際に発生した転倒災害の事例を状況別に表にまとめました。製造業の事例については、現場改善ラボの会員231名を対象にしたアンケート調査から引用しております。
| 転倒の種類 | 業種 | 事例 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 滑り | 介護施設 | 介護施設の浴槽内で清掃中に滑って転倒しそうになった | 清掃中のため、石けん水で滑りやすくなっていた |
| 製造業 | 作業場内で移動する際、床面が濡れていて足を滑らせ転倒しそうになった | 作業環境や設備に問題があった | |
| つまづき | 製造業 | 作業場を移動する際、置いてはいけない私物や荷物があり、足を引っ掛けて転倒しそうになった | 作業環境や設備に問題があった |
| 小売業 | 積み込み作業中、足元の空のパン箱(番重)に気づかず、つまずき転倒しそうになった | 番重は幅が広いため、足元が見えにくかった | |
| 踏み外し | 製造業 | 床面にある凹みに、手押し台車のキャスターが引っ掛かり、転倒しそうになった | 作業環境や設備に問題があった情報共有やコミュニケーションが不足していた |
| 建設業 | 仮通路でつまずいて転倒しそうになった | 仮通路に段差があった |
製造業以外の業種でも転倒災害は発生します。原因を考え対策を行うことが大切です。製造業以外の事例については、厚生労働省「職場の安全サイト」より引用しております。
関連記事:工場のヒヤリハット事例21件を解説!事故対策につなげる方法もご紹介
転倒災害がなくならない原因
転倒災害は、様々な対策が講じられているにもかかわらず、依然として製造現場で発生し続けています。
ここでは転倒災害がなくならない主な原因について、以下の3つに分けて具体的に解説します。
作業環境が改善されていない
転倒災害の大きな原因の一つとして、作業環境が十分に改善されていないことが挙げられます。
製造現場には、床が濡れていたり、油で汚れていたりする場所、物が散乱していたり、段差があったりする場所など、転倒のリスクが高い場所が多く存在しています。これらの場所が改善されない限り、転倒災害は繰り返されてしまいます。
さらに5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)が徹底されていない場合、作業環境は乱雑になり、転倒のリスクが高まります。例えば、工具や部品が所定の位置に戻されていなかったり、床が清掃されていなかったりすることがつまずきや滑りの原因です。
作業員の安全意識が低い
作業員の安全意識の低さも、転倒災害がなくならない原因の一つです。
長年同じ作業を行っている作業員の中には、「自分は慣れているから大丈夫」という意識を持つ人がいます。しかし、慣れた作業でも、不注意や油断によって転倒災害が発生する可能性があります。
ヒヤリハットが発生しても、その情報が共有されず、対策が講じられない状況も問題です。ヒヤリハットを教訓として生かす仕組みがなければ、同じような状況で転倒災害が発生する可能性があります。
教育・管理体制に不足がある
教育・管理体制の不足も、転倒災害を減らすことができない原因の一つです。
作業員に対する安全教育が十分に実施されていない場合、作業員は転倒災害のリスクや予防策について十分に理解していない可能性があります。他にも、ヒヤリハットの共有が十分でなかったり、ルールや手順を形式的に伝えるだけで、現場で実際にどう行動すべきかが腑に落ちていない場合もあります。
その結果、作業標準や安全手順が現場で形骸化し、指示された通りの動作が守られないまま作業が進められてしまうことがあります。つまり、作業順守が教育で徹底できておらず、「知っているが守られていない」状態が常態化してしまっているのです。
このような原因を解消するためには、作業環境の改善、作業員の安全意識の向上、教育・管理体制の強化など、多角的な対策が必要です。次章で詳しく解説します。
製造現場でできる!転倒災害を防ぐ3つの改善策
製造現場における転倒災害は、適切な対策を講じることで大幅に減少させることが可能です。ここでは、具体的な改善策を3つのポイントに絞って解説します。
- 作業環境は5S活動で改善する
- 従業員の安全意識を強化する
- 教育体制を整備する
作業環境は5S活動で改善する
まず、作業環境の改善は転倒災害防止の基本です。5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)を徹底することで、床面の整理整頓や清掃が行き届き、転倒のリスクを大幅に減らすことができます。
さらに、KY(危険予知)活動も重要です。作業前に潜在的な危険を予測し、対策を講じることで事故を未然に防ぎます。ヒヤリハット事例を記録・共有することも、同様に効果的です。過去の事例を分析し、改善策を講じることで、将来の事故を防止します。
5S活動やKY活動の具体的な進め方や現場に定着させるコツについて、専門家が解説した動画もございます。「中途半端な実践」で終わらせないための秘訣が満載ですので、是非ご覧ください。
>>現場に5S活動を定着させる「正しいS」とは?(視聴無料)
>>元労基署長が解説!事故を未然防止するKY活動の進め方とは?(視聴無料)
従業員の安全意識を強化する
次に、従業員の安全意識を高めることが重要です。定期的な安全教育を実施し、従業員一人ひとりが安全に対する意識を持つようにします。また、毎日の健康チェックやツールボックスミーティングを実施することで、日々の体調管理や安全確認を徹底します。
これらの取り組みは、従業員の安全意識を高め、転倒災害を未然に防ぐために欠かせません。
従業員の安全意識が継続する教育方法について、労働安全コンサルタントが直々に解説した動画を見て学びたい方は、以下の画像をクリックしてください。
教育体制を整備する
最後に、効果的な教育体制の構築も重要です。現場での作業順守を徹底するためには、実効性のある教育体制の整備が欠かせません。
特に新入社員や外国人作業員など現場経験が浅い層には、転倒災害のリスクや具体的な予防行動を「理解し、実行できる」レベルまで落とし込んだ教育が必要です。単なるルールの伝達にとどまらず、実際の作業手順に即した体験型の教育や、ヒヤリハット事例をもとにした振り返りの場を設けることで、行動変容につなげていきます。
加えて、チェックリストや安全確認フローを活用し、管理側も日常的に指導とフィードバックを繰り返すことで、作業標準の形骸化を防ぎ、安全意識の定着を図ります。
このように改善策を総合的に実施することで、製造現場における転倒災害を大幅に減少させることが可能です。次章では、これら3つの改善策に役立つ「動画マニュアル」の有効性について解説します。
転倒災害の防止に動画マニュアルが注目されている!
近年、製造現場における転倒災害や労働災害の防止策として、動画マニュアルが注目を集めています。動画マニュアルは従来の紙のマニュアルや口頭での指導に比べて、より効果的に安全意識を高め、教育体制を効率化できる有効な対策です。
動画マニュアルが注目されている理由を、以下の3つに分けてご紹介します。
継続的な5S活動が行える
5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)は、転倒災害防止の基本ですが、その効果を維持するためには継続的な教育が欠かせません。動画マニュアルであれば、作業員はそれぞれのタイミングで繰り返し確認できるため、5Sの重要性を常に意識し、実践することができます。
5S活動は一度行えば終わりではなく、日々の積み重ねが重要です。動画を活用することで、常に新鮮な気持ちで安全に取り組むことが可能になります。
動画で「キケン」が伝わることで安全意識が高まる
転倒災害の危険性をリアルに伝えるためには、文字や静止画だけでなく、実際に事故が起きそうな場所や危険な作業風景を動画で見ることが効果的です。動画であれば、必要な時に何度でも確認できるため、作業員の安全意識を飛躍的に高められます。
▼動画でキケンをわかりやすく伝えている例▼
※「tebiki」で制作
また、動画は視覚的に動きを伝えられるため、言葉だけでは伝わりにくいニュアンスや危険な状況も、より正確に理解できます。作業員は「自分ごと」として危険を認識することが可能です。さらに、動画マニュアルは作業員の自主学習が可能なため、教育コストの削減にも貢献します。
動画で効率的な教育体制を整備できる
動画マニュアルは、新入社員や外国人作業員など、様々な背景を持つ作業員に対する教育にも効果的です。各工場や作業現場ごとに特化したマニュアルを作成し、動画で共有することで、効率的かつ均一な教育体制を構築できます。
また、ヒヤリハット事例や実際の転倒事例を動画で共有することで、事故の再発防止にもつながります。問題発生時に、動画を通して迅速かつ正確に情報を共有できる仕組みは、安全管理体制を強化する上で有効です。
このように動画マニュアルは、転倒災害防止のための強力なツールです。継続的な5S活動の推進、作業員の安全意識向上、効率的な教育体制の構築など、様々な面で効果を発揮します。
動画マニュアルの有効性や活用のイメージについてより知りたい方は、以下のリンクから資料をご覧ください。マンガ形式でわかりやすく解説しています。
>>日々の業務で動画マニュアルを活用することによる効果はどのくらい?
次章では、複雑そうに見える動画マニュアルが簡単に作成できる、現場に特化した動画マニュアル「tebiki」についてご紹介します。
安全対策に使える「動画マニュアルtebiki」の活用事例
ここでは、安全対策に有効な動画マニュアルがかんたんに作れる「tebiki」の特徴や実際の活用事例について、以下の具体的な事例を交えてご紹介します。
- 動画マニュアルをかんたんに作るなら「tebiki」
- 事故防止月間にあわせて安全動画を配信
- 動画で現場ルールが外国人労働者にもわかりやすく伝わる
動画マニュアルをかんたんに作るなら「tebiki」
動画マニュアルのメリットは理解しているものの、「動画作成のスキルがある従業員がいないから…」と諦めていませんか?そんな時に役立つのが、簡単に動画マニュアルが作成できる「tebiki」です。
tebikiは「かんたんさ」に特化したツールで、シンプルな操作で直感的に動画を作成できます。専門的な技術や編集スキルがなくても使える設計のため、初めての方でも安心です。
さらに、効率的な教育を実現するため、以下の機能も搭載されています。
- 動画の字幕などの自動翻訳
- オフライン再生
- 文書作成機能
- 動画の音声を認識して字幕の自動生成
- タスク機能により自主学習を促す
- レポート機能
- テスト機能
「tebiki」には役立つ機能がまだまだ搭載されています。詳しくは、以下のサービスご紹介資料をぜひご覧ください。
活用事例①:事故防止月間にあわせて安全動画を配信
動画マニュアルtebikiは安全品質の教材や、各拠点の倉庫内作業やトラックドライバーの業務といった現場の作業マニュアルとして活用できます。
例として、親会社である株式会社バンダイロジパルの物流部門を担う株式会社ロジパルエクスプレスでは、拠点ごとにマニュアルやルールが統一されておらず、同一の業務を行っていても業務品質や作業手順にバラツキが出てしまうことが課題でした。
そこでtebikiを導入し、事故防止強化月間にあわせて、フォークリフトの危険予知トレーニングや商品の取り扱いルールを動画教材として作成し、各拠点の従業員がtebikiで視聴・学習する取り組みを行いました。
結果として、動画を通して具体的な事例や注意点を共有することで従業員の安全意識を高め、事故防止に繋げることに成功しています。また、動画であれば、場所や時間を問わず視聴できるため、効率的な安全教育が実現しました。
| tebiki導入前の課題 | tebiki導入の効果 |
|---|---|
| ・拠点ごとにマニュアルやルールにばらつきがある ・安全品質を高めて事故やヒヤリハットを削減したい ・紙マニュアルの工数を削減したい | ・全拠点でルールやマニュアルを統一できる環境が整った ・業務上の危険や業務解像度が伝わりやすくなり、安全品質意識が向上 ・マニュアルを申請してから確認と承認までの時間が短縮 |
tebiki導入時の様子や導入後の効果については、以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:動画で全拠点の安全品質意識の向上と業務ノウハウの可視化を達成
活用事例②:動画で現場ルールを外国人労働者にもわかりやすく伝える
動画マニュアルtebikiは、字幕翻訳機能がある動画マニュアルです。翻訳機能の活用により、現場の標準化や安全性を担保した例をご紹介します。
⽇世株式会社はコーン・ミックス・フリーザーを含めた全ての関連商品を供給できる日本で唯⼀のソフトクリーム総合メーカーです。外国人労働者も増える中で文章のマニュアルに課題を感じていました。
同社では、紙ベースの日本語マニュアルでは伝わりにくい部分や、人によって教え方やニュアンスが異なることによるトラブルやヒヤリハットが発生していました。
そこで「tebiki」の字幕翻訳機能を活用し多言語に対応した動画マニュアルを作成したところ、外国人労働者にも現場ルールが正確に伝わるようになり、標準化が進んでいます。
| tebiki導入前の課題 | tebiki導入の効果 |
|---|---|
| ・外国人労働者の増加 ・非効率な新人研修 ・製造現場での専門的な技術伝承 | ・外国人労働者のスキルアップ ・新人研修の講義時間を1/10に削減 ・製造現場での作業標準化 |
tebiki導入時の様子や導入後の効果については、以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:新人研修の手間が1/10に!自動字幕翻訳で、外国⼈スタッフの理解度テスト正答率が100%になりました
これらの事例からわかるように、「動画マニュアルtebiki」は、安全教育の効果を高め、効率的な安全対策を実現するための強力なツールとなります。
まとめ|転倒災害を防ぐために動画で現場の安全対策を強化しよう
製造業における転倒災害は、労働災害の中でも特に発生件数が多く、深刻な問題です。しかし、リスクを正しく理解し、適切な対策を講じることで、その発生を大幅に減らせます。
本記事では、転倒災害の定義や発生状況、具体的な原因と対策について詳しく解説しました。また、転倒災害を防止するための現場改善策や、安全教育に役立つ動画マニュアルの活用事例もご紹介しました。
これらの情報を参考に、各企業において転倒災害のリスクを正しく理解し、原因を把握した上で、適切な現場改善と教育を行うことが重要です。そして、動画マニュアル「tebiki」を活用することで、効率的な安全教育を実現し、転倒災害のない安全な職場環境を目指しましょう。
転倒災害のリスクを正しく理解し、安全な職場環境を実現するために、ぜひ本記事をお役立てください。