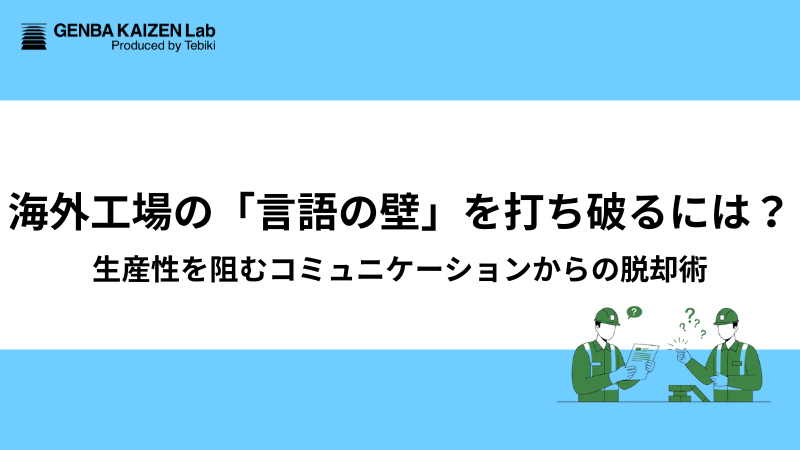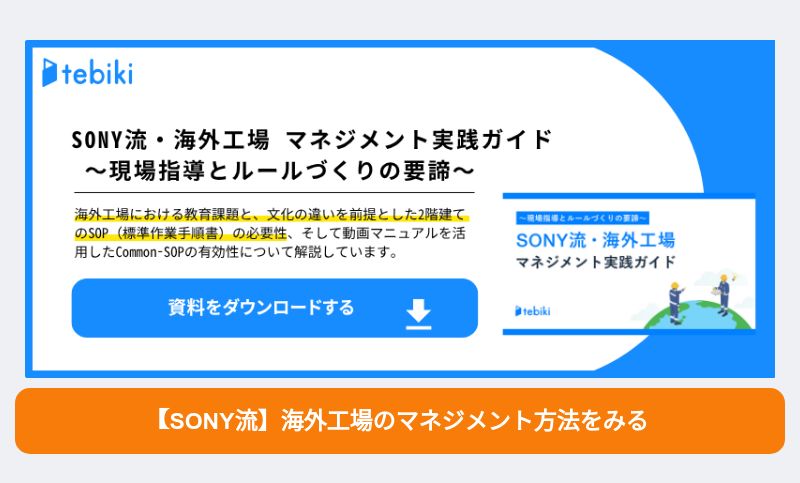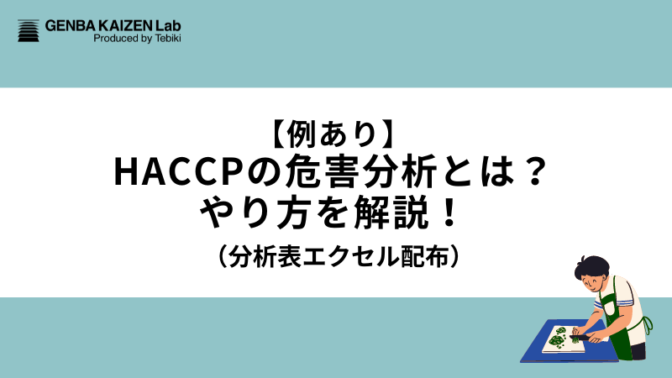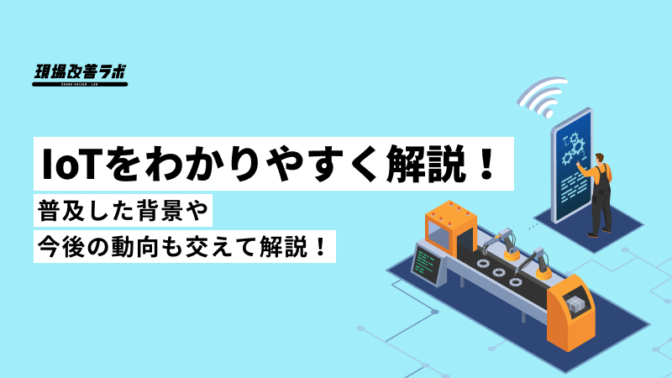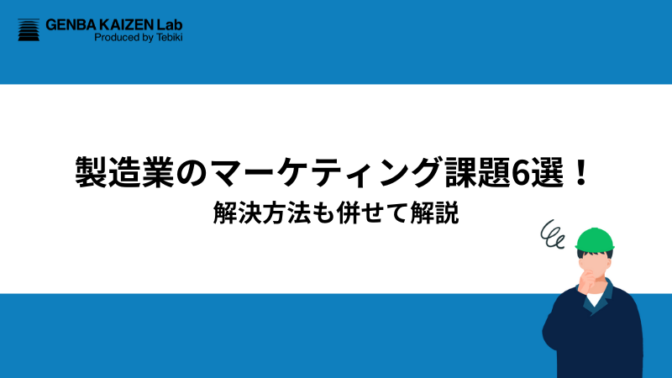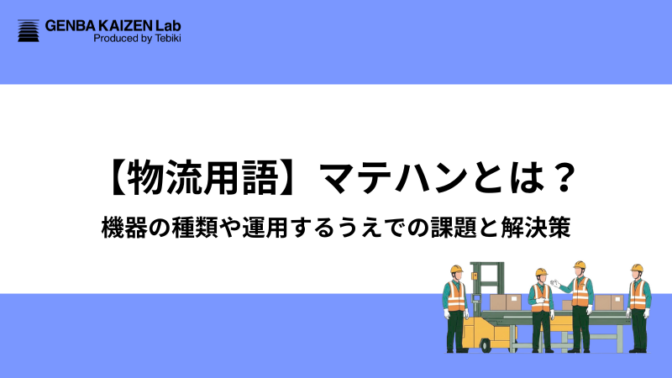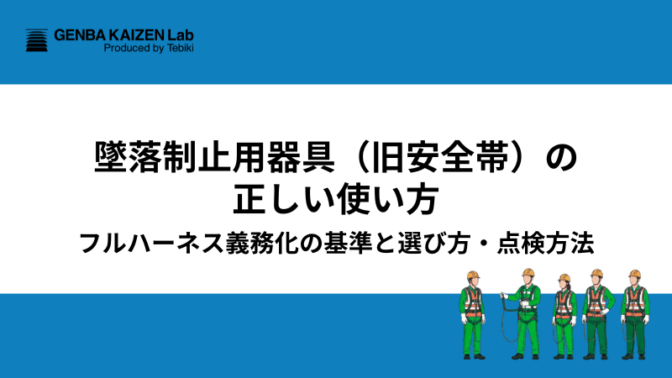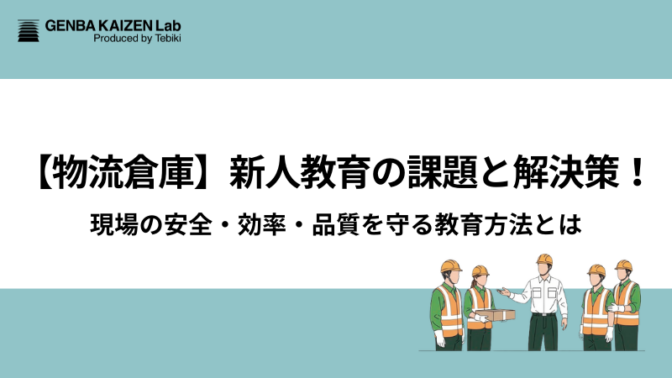かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
日本の製造現場で培った『カイゼン』や『品質管理』を展開すれば成功するはずだった海外工場が、思うような生産性と利益を生み出せないという課題をもつ企業は数多く存在しています。その1つの原因が、言葉の壁です。
指示が正しく伝わらない、教育に時間がかかる、安全に対する注意喚起が伝わっているか不安だ、などの課題感があると思います。
この伝わらないという問題は、単なる語学力の問題でも、現地スタッフの問題でもありません。もっと構造的に根が深いコミュニケーションの壁であり、工場の生産性を低下させる要因のひとつです。
本記事では、この言語の壁がどのような問題を引き起こすのかを深く掘り下げ、新しいコミュニケーションの仕組みを構築するための具体的な方法と成功事例を詳しく解説します。
また、まずは海外マネジメントの全体像と課題解決のポイントを体系的に知りたいという方向けに、以下の資料もご用意しました。ぜひ、併せてご活用ください。
目次
生産性が低下する「言語の壁」の具体的な問題とは
海外工場の生産性を低下させる要因のひとつである「言語の壁」は、単に「言葉が通じない」という表面的な問題ではありません。それはもっと根が深い構造的な課題で、品質の低下、ムダ業務の発生、安全リスクの増大といった様々な問題を引き起こします。
ここでは、多くの海外拠点が抱える5つの課題を掘り下げましょう。
課題①「カン・コツ」が伝わらない – 翻訳で抜け落ちる暗黙知の問題
日本の製造業の強みの一つに、マニュアルには書ききれない熟練者の技があります。それは長期雇用によって体得できる「カン」や「コツ」といった暗黙知なのですが、これは海外ではより大きな弱点となり得ます。
作業標準書をどんなに正確に現地の言葉に翻訳しても、数値や言葉で表現しきれない力加減や道具の持ち方、設備の異音を聞き分ける感覚といった部分は、どうしても伝えきれません。
例えば、ある設備の部品を締め付ける時に、マニュアルに書いてある締め付けトルクの中心値ではなく、季節や使われる場所、設備の状態を考えて少し緩め、あるいは少しきつめに微調整を行っている場合があります。この「少し」という感覚こそが、設備の安定稼働や耐久性を左右する重要なノウハウです。
通訳を介して「いい塩梅に」と翻訳して伝えても、現地スタッフはどの程度なのか分かりません。その結果、作業者や設備ごとに品質に大きなバラつきが生まれ、不良品の山を築いてしまうのです。日本の「見て覚える」「背中を見て育つ」という技術の伝承が、言語の壁によって完全に断絶されてしまうのです。
課題②英語だけでは解決しない – 現場の多言語が混在する現実
海外工場では多国籍な人材が所属していることが多く、そこで働く作業者が、その地域の出身者であるとは限らない場合がよくあります。
たとえば、台湾にあるEMS(委託を受けて加工する会社)で働く従業員は台湾人だけでなく、フィリピン、タイ、ミャンマーなどASEAN全域から集まってきています。あるいは、北米の工場では南米からの移民や出稼ぎ労働者も多数働いています。
これらの作業者は日常会話はできても、細かい指示になると正確に意図や作業内容を伝達するのは困難です。
課題③「言ったはず」が歪んで伝わる – 伝言ゲームによる情報の不確実性
本社や現地のマネジメントからの指示が、現場の末端まで正確に届かないという問題もあります。多くの場合、指示は日本人管理職からローカルのマネージャーへ、そしてチームリーダー、 現場作業員という順に伝達されます。まさに、伝言ゲームです。
皆さんも経験があると思いますが、次の人に情報が渡るたびに発信者の意図とは異なる内容に変わり、解釈の違いや思い込みによって少しずつ歪んでいくケースが多いのです。
たとえば、「製品Aを優先し、製品Bは後から急ぎで作って追いつくようにする」という指示をしたのに、「製品Bを急ぎで」だけが伝わり、結果的に、先に優先したかった製品Aが生産されていなかった、というような状況です。
言ったはず、伝えたはずという管理者の思い込みと、現場で起きている現実との間には、大きな乖離が生まれてしまうのです。
課題④教育が振り出しに戻る – 人材の流動性が生む非効率の繰り返し
海外では、日本では考えられないほど転職が多く、人材の流動性が高いという現実があります。ある程度スキルを身に着けたらより良い給与や労働条件を求めて、あるいは自分のさらなるスキルアップのために転職するのはごく当たり前のことです。
自己実現のために切磋琢磨し、人間として成長しようとするのは素晴らしいことなのですが、一方で時間をかけて育ててきたスタッフ、あるいは作業者が出て行ってしまうのは大きなロスです。特に、ローカルリーダーとして育てた幹部候補が会社を去ってしまうのは、痛手どころではありません。
人が抜けたところに求人を出してスタッフを補充できたとしても、またゼロから教育のやり直しです。これは、教育担当者の時間と労力を消費し、教育コストを浪費します。何より、せっかく伝承したカンやコツを再び伝承するために時間をかけて教えなければなりません。
結果、工場はいつまでも非効率的な生産を続けなければならなくなるのです。
課題⑤安全指示の浸透不足 – 文化や価値観の違い
製造現場は安全第一。すべてにおいて安全が優先です。しかし、海外では必ずしもその意識づけができているとは限りません。時として、生産性優先、あるいは利益優先になってしまっている海外拠点もあるのが現実です。
なぜ面倒な手順を守らなければならないのか、なぜ保護具を着用しなければならないのか、その理由や背景がわからないままルールだからで押し付けられても、作業者は腹落ちせず定着しません。既存のルールは面倒だ、暑いから保護具を着用したくない、と、勝手な行動をして労働災害を起こしてしまう場合があります。
特に、危険な作業に対するリスク認識に、日本と海外のギャップが存在することもあります。危険を知らせるサインを軽くとらえたり、自分だけは大丈夫というという根拠のない自信を持っていたり、日本よりも安全に対する意識は低い傾向があります。
安全指示が伝わらないことで重大な労働災害が発生すれば、従業員の命が危険に晒されるだけでなく、工場の稼働停止や罰金などの処罰、さらに企業のブランドイメージ低下など、計り知れないダメージを与えることになります。
解決の鍵は「言語への依存」からの脱却
ここまで見てきた5つの課題の根本原因は、言語に頼ったコミュニケーションを取ろうとしていることにあります。どの言語でどのように説明するか、そしてどう翻訳するかといった言語中心の発想ではなく、いかに言葉に頼らずに伝えるかという、違う視点を持つ必要があります。
言語は、その国の文化や価値観、思考様式が凝縮されたOS(オペレーティングシステム)のようなものです。日本のOSの上で完璧に動いていた「カイゼン」や「安全管理」といったアプリケーションが、異なるOSである海外の文化の上では、文字化けしたり、フリーズしたりするのは当然のことなのです。
目指すべきは、国の違いに関わらず同じようにアプリケーションが動くようにすることです。そのためには、見て真似ることで誰もが同じように理解できる仕組みを構築するのです。その仕組みには、3つの重要な要素が必要です。
視覚性 (Visual)
百聞は一見に如かず。言葉で長々と説明するよりも映像や動きで示す方が、はるかに早く正確に意図を伝えることができます。特にカンやコツのような非言語情報は、視覚に訴えることで初めて伝達可能になります。
再現性 (Repeatable)
いつでも誰でも何度でも、同じ情報にアクセスできて、繰り返し確認できることです。新人が入ってきたとき、作業を忘れてしまったとき、トラブルが発生したときなど、必要な時に必要な情報をすぐに確認できる仕組みは、人材の流動性が高い環境では不可欠です。
正確性 (Accurate)
伝言ゲームによる情報の劣化や、翻訳による意図の欠落が起こらない、お手本となる動きや手順といったオリジナルの情報がそのまま100%の形で末端まで伝わることです。情報の正確性は、品質と安全の生命線です。
この3つの要素を満たすコミュニケーションの仕組みこそが、言語や文化の壁を乗り越え、海外工場の生産性を飛躍的に向上させる鍵となるのです。
「言語の壁」を乗り越える3つのアプローチと、その比較
では、具体的にどのようなアプローチをすればよいでしょうか。海外工場での言語の壁を乗り越える方法は、1つではありません。現地語を習ったり、リアルタイム翻訳機を導入したりなど様々な方法がありますが、これらの方法は特定の個人の能力に依存したり、導入・運用お金がかかったり、全ての現場で適用できるわけではありません。
そこで、より多くの製造現場で現実的な選択肢として検討できる方法として、何を使って情報を伝達するかという観点から3つに分類し、比較検討してみます。
アプローチ1:人的リソース強化型
人を介してコミュニケーションの質を高めようとする、最も伝統的なアプローチです。たとえば、日本人駐在員に現地語を学ばせる、優秀な通訳を雇う、ローカルリーダーのコミュニケーション能力を開発する、などです。
メリットは、複雑でイレギュラーな事態にも柔軟に対応できることや、対話を通じて相手の理解度を確認しながら進められることです。
一方でデメリットは、極めて高い言語スキルを身に着けるまでに相当の努力と時間が必要なのと、その人が帰任したら仕組みが崩壊することです。また、伝言ゲームになるため、情報の正確性が保証されにくくなります。
このアプローチは、特定のキーパーソンに依存する脆弱な構造であり、持続可能な解決策とは言い難いのが実情です。
アプローチ2:テキスト・ドキュメント型
紙やテキストを介するアプローチです。たとえば、作業標準書の多言語翻訳、写真やイラストを多用したマニュアル、掲示板やチャットツールでのテキストによる指示などです。
メリットは、比較的低コストで始められることと、情報を体系的に整理し、記録として残すことができることです。
デメリットは、文字や静止画像ではカンやコツが伝えきれない、情報の更新・管理が煩雑、あるいは、そもそも読んでもらえないというリスクもあります。
このテキスト・ドキュメントによるアプローチは標準化の第一歩として重要ですが、それだけで言語の壁を解決するには不十分です。
では、このアプローチの限界を乗り越えるにはどうすればよいのでしょうか。本稿で触れた言語の壁だけでなく、海外拠点におけるマネジメント全般の課題解決に役立つ資料をご用意しましたので、ぜひご覧ください。
アプローチ3:ビジュアル・システム型
映像(動画)によりコミュニケーションするアプローチです。たとえば、動画マニュアルの作成と共有、現場へのタブレットやモニターの設置による情報へのアクセス環境整備、AR(拡張現実)を用いた疑似体験型の作業支援などです。
メリットは、お手本となる作業者の動きをそのまま映像で見ることができて、カンやコツがつかみやすい、スマートフォンやタブレットがあれば、自分のタイミングでわからない部分を繰り返し確認できること、そして、伝言や翻訳による誤変換が起きないことです。
デメリットはシステム構築や機材の導入に初期投資が必要なこと、動画の撮影や編集にはある程度の工数がかかることです。
このビジュアル・システム型は、情報を劣化させず、見てまねることができる情報伝達手段であり、誰にでもわかりやすいということが最大の特徴です。
3つのアプローチ比較まとめ
これら3つのアプローチを、「言語の壁」を乗り越えるための3要素(視覚性・再現性・正確性)と、その他の観点から比較してみましょう。
| アプローチ | 手法 | 視覚性 | 再現性 | 正確性 | 評価・課題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人的リソース 強化型 | 優秀な通訳の雇用バイリンガル社員育成 | △ | × | 〇 | 特定の個人に依存するため、属人性が高く持続的でない。 |
| テキスト・ ドキュメント型 | 多言語マニュアル図解イラスト | 〇 | 〇 | × | 細かい動きや感覚的な指示の伝達には限界がある。 |
| ビジュアル・ システム型 | 動画マニュアルの導入 | 〇 | 〇 | 〇 | 3要素を高いレベルで満たす、有効な手段となりうる。 |
この比較から分かるように、ビジュアル・システム型の動画マニュアルは、言語の壁を乗り越えるための3つの要素(視覚性・再現性・正確性)を最もバランス良く満たし、人材の流動性が高い海外工場において、もっとも有力な選択肢であると言えます。
海外工場や外国人労働者が多い製造現場では、動画マニュアル導入による現場教育・品質改善ケースは珍しくありません。動画マニュアルがグローバル課題に対してどのように寄与し、どのような事例が存在するのかについてまとめられた資料「外国人労働者に「伝わらない」を解決した動画マニュアル活用事例集」も参考になると思います。
【海外工場の事例】言語の壁を乗り越え生産性向上を実現した製造業
では、ビジュアル・システム型を通じた、海外工場の言語の壁を打ち破った実際の企業事例についてご紹介します。
株式会社Archem様:離職率の高いアメリカ工場で、言語の壁を越え品質と生産性を両立
自動車部品のグローバルサプライヤーである株式会社Archemは、アメリカ工場での高い離職率と、人が変わるたびに必要になる教育コストの増大、仕事の質の不安定さに課題がありました。多国籍の従業員が働く現場ならではの、言語の壁によるコミュニケーション不足が悩みの種でした。
そこで、動画マニュアル作成ツール(tebiki現場教育)を導入。取り組んだのは、動画マニュアルを使っていつでも、誰でも、何度でも学べる環境の整備です。現場にモニターを設置し、各工程の正しい作業手順を常時再生しておきました。人の入れ替わりや作業ローテーションがあっても、いつでも正しい作業をモニターで確認して学習できるようにしたのです。
また、多言語対応なので、国籍に関係なく母国語で説明を聞くことができるため、理解度が格段に上がりました。設備ごとにQRコードを貼り付けて、スキャンすれば関係する作業手順を確認できるようにしたことで、必要な作業マニュアルを探しに行く必要もなくなりました。
この活動の結果、作業のバラつきがなくなり、不良率が低減しました。新人の習熟期間も短くなり、工場全体の効率が向上しました。「見て学ぶ」環境を整備したことで従業員の自律的な学習が促進し、従業員満足度を向上させることにも成功したのです。
※同社の詳しい事例はこちらのインタビュー記事をご覧ください
事例2:HOEI THAILAND:タイ工場でダウンタイムを短縮し、新人教育を5か月から1か月へ
工業用洗浄機などを製造するHOEI THAILANDは、新人オペレーターが一人前になるまでに約5ヶ月もの教育期間を要していました。また、設備トラブルに対応できる人材も限られているため、その間設備が止まり、生産性が低いという課題がありました。
そこで、動画マニュアル(tebiki現場教育)を利用して、この状況の改善をすることに成功しました。まず、100ページ超の紙マニュアルによる新人教育をやめて、動画による作業説明とトラブルシューティングの学習を導入しました。
動画は通常の作業手順書に加え、不具合の「原因と対策」を1〜2分の短い動画にまとめるようにしました。また、不具合対策会議で決定した内容を動画化し、全社でナレッジとして共有しました。動画マニュアルは現場のリーダーが自ら撮影、編集、更新する体制も構築しました。
その結果、新人教育期間が最短1か月に短縮できたのです。また、不具合発生時の対処も誰もができるようにしたことで、設備の止まっている時間(ダウンタイム)も短くなり、効率的な生産ができるようになりました。また、属人化していたトラブルシューティングのノウハウが組織の資産として標準化されました。
※同社の詳しい事例はこちらのインタビュー記事をご覧ください
まとめ
本記事では、海外工場における「言語の壁」が引き起こす問題と、それを乗り越えるための3つのアプローチについて解説しました。
海外工場において生産性を阻害するのは単なる語学力不足ではなく、カンやコツが伝わらない、多言語が混在すること、伝言ゲームによる情報の劣化、人材流動性による技術伝承の断絶、そして安全意識の欠如という構造的なコミュニケーション課題です。
これを解決するためには言語での伝達から、言葉に頼らずに意図を伝える仕組みを構築することが不可欠です。言語の壁は個人の能力や努力で解決するのではなく、仕組みで解決できる課題とすることで道は開けます。
今回ご紹介した動画マニュアルというアプローチは、言葉の壁というやっかいな課題を解決するために有効な手段の一つです。生産効率の悪い、あるいは不良率の高い工程に導入して、生産性の改善につなげてください。