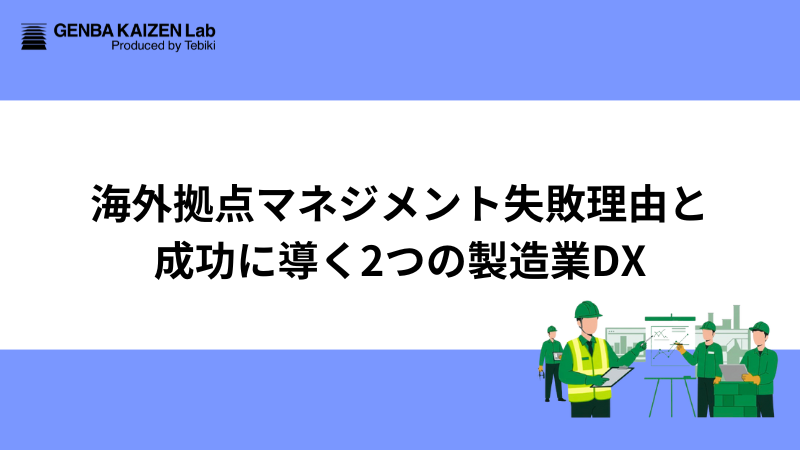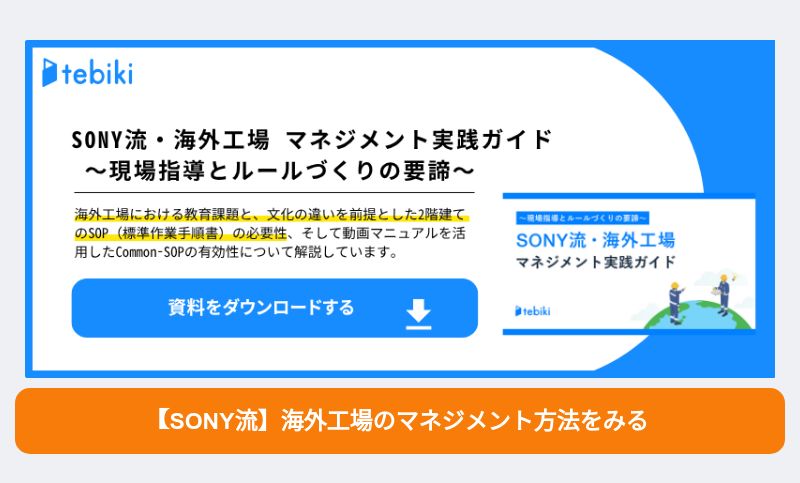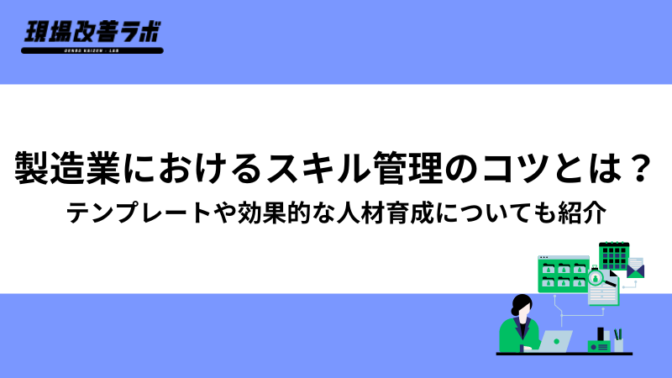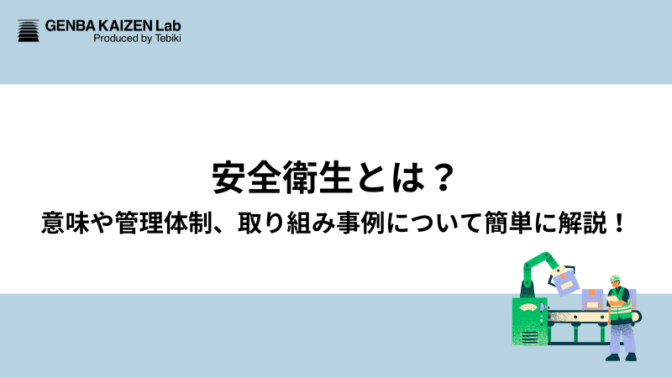かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」や、かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
大きな期待を背負って進出した海外工場が思ったより効率が悪く、利益が出せていないという課題をお持ちのグローバル企業がたくさん存在しています。時差や距離、言語、文化などの壁はもちろんのこと、現場の実態を把握して適切な対策を講じることの難しさに、多くの企業が悩んでいます。
しかし、これらの課題は「仕方がない」と諦めるべきものではありません。
海外拠点のマネジメントに失敗する企業には、共通した「5つの落とし穴」が存在します。そして、その落とし穴を埋め、利益を生み出す工場へと変貌させる鍵は、「現場のDX」にあります。
この記事では、海外拠点マネジメントが陥りがちな失敗の構造を解き明かし、「可視化」と「標準化」という2つの軸に基づいた具体的な解決策と成功事例を解説します。
「海外工場におけるマネジメントは、現場の状況や環境によって多種多様になりがちなので、改善指針がうまくまとまらず難易度が高い領域です。そこで1つの参考として「SONY流・海外工場マネジメント実践ガイド(pdf)」を紹介します。 特に文化の違いを前提とした教育課題と改善策についてまとめられているので、あわせて参考にしてみてください。
目次
海外工場のマネジメントが失敗に陥りやすい5つの落とし穴
海外拠点の利益が計画通りに上がらない。これは、海外進出した多くの企業が直面している課題です。念入りに準備したはずの海外工場が、なぜ思ったような成果を出せないのでしょうか。そこには、5つの要因があります。
1. 【現場の実態が見えない】各拠点の情報のブラックボックス化
海外拠点マネジメントにおける最大の課題は、「不透明性」にあると言っても過言ではありません。毎月報告される月報には生産数や不良率などの数字が並んでいますが、それがなぜ目標に対して未達になったのか、その原因とリカバリのために何に取り組んでいるのかがレポートに書かれていません。
設備故障、作業者不足など理由は書かれていても、なぜそういう状況になったのか、それが再発しないように何をしているのか、ということが本社から見えなくなっています。
また、詳細を問い合わせても、「現場に頑張らせて挽回します」「作業者に指導します」という精神論や場当たり的な対策が報告されてしまい、本社から支援が必要なのか、必要なら何をすれば改善されるのかが分かりません。
正直に報告するとかえって面倒なことになるからと、ネガティブな情報を海外拠点が出したがらない場合もあります。
このように、海外工場の情報がブラックボックス化して、的確な経営判断が下せなくなってしまうのです。
2. 【利益が出ない】コストのムダや非効率なプロセスが特定できない
次に深刻な問題となるのが「利益が出ない」です。
予算に対して受注は大きく下がっていないのに、利益は予算を大きく下回ってしまう。材料費の高騰や労務レートの上昇という理由もありますが、それ以上に想定外の間接コストがかかっていることがあります。
本社からコストを下げるように指示をしても、スタッフを減らしたらトラブル対応ができなくなる、操業のために必要な経費でコストカットはできない、などの答えが返ってきてしまいます。
この原因は、「現場が現場の問題に気づいていない」ことにあります。歩留まりが悪いならそれはどこの工程不良率が高いのか、想定した時間内に生産数が完了しないならどのプロセスに時間がかかっているのか。滞留しているロット、段取り変えのために設備が止まっている時間などを現場が分析できておらず、どこに非可動時間や作業効率のロスがあるのかを把握できていないのです。
現場がこのような状況なので、本社が原因を把握できないのは当然です。現場も本社も有効な対策を打てず、利益が出ない状況が継続してしまいます。
3. 【標準化されない】拠点ごとに品質や生産性がばらばらで属人化が進み、標準化が進まない
ベテラン作業者が退職したら品質が下がった、あの人がいなくなったら生産管理プログラムのどこをいじればいいのかわからない。このような問題は仕事の属人化と標準化の欠落が原因です。とくに、カンやコツといった長年の経験で培われた「暗黙知」は他の人へ伝授するのがむずかしく、属人化しやすい作業です。
また、同じ製品を作っているのにA工場とB工場で手順が違っていると、できあがった製品の特性や外観が微妙に違うというモノのばらつきが発生し、どちらかの工場の製品から市場クレームが多く発生するということも起こります。
作業の標準化ができておらず、手順書も共通になっていないとこのようなことになり、拠点ごとの品質や生産性にばらつきが生まれてしまうのです。
この状態を放置するとモノの品質が安定しないだけでなく、人の教育にも影響します。教育に使用する作業手順書の内容が異なることで新人の理解力が不足し、独り立ちするまでの時間に個人差が生じてしまい、組織としての成長が進まないという事態を招きます。
4. 【人材が育たない】OJTにバラつきがあるし、人材の流動性も高く定着しない
仕事の属人化と標準化の不足は、作業者だけでなく、現場を監督するスタッフの人材育成にも影響します。
標準化されたマニュアルがない現場では、OJTは指導者のスキルや経験に大きく依存します。教える内容が人によって違ったり、説明の分かりやすさが異なると、教わる側の理解度やスキルに差が出てしまうのは当然のことです。場合によっては、間違ったやり方が受け継がれてしまうことさえあります。
また、海外工場では日本のような長期雇用が当たり前ではありません。離職率が高く、頻繁に新人教育が必要になります。教育に時間とお金をかけてもすぐにいなくなってしまう場合があるので、仕事を細分化して教育し、少しずつできることを増やしていくようなやり方をしないと、非効率になってしまいます。
さらに、ローカルマネージャーの育成も課題です。ビジネス判断をするために出向させた日本人がスタッフの教育に長い時間を割くわけにはいきません。日本人との懸け橋になり、現地スタッフをまとめてくれるローカルリーダーを育てることが、海外工場の運営では重要です。
このように、海外工場における人材育成や組織づくりは一筋縄ではいきません。本稿で挙げたような課題を解決し、強い現場を作るためのヒントを以下の資料にまとめましたので、ぜひご活用ください。
5. 【不正が怖い】不正やコンプライアンスに問題が起きないか不安だが、それを監視するための仕組みがない
異なる国にある海外拠点では、ガバナンスの欠如が重大なリスクに繋がることがあります。
日本の本社からは、経費が適切に使われているか、仕入先と不適切な関係はないか、在庫管理は出し入れの記録がしっかり残り、不自然な材料持ち出しがないか、といった細かい監視をすることは困難です。内部統制をしっかりしておかないと、不正が発生するリスクを排除できません。
また、国ごとに法律や商習慣、労働や安全衛生に関するルールが異なります。現地のルールを逸脱して海外工場を運営すると、労務問題が発生したり、法令違反として罰金、最悪の場合、経営者の逮捕という事態になる可能性があります。
これらの内部統制や遵法についての教育をしっかり行い、不正が起きにくい、あるいは起こしにくい環境の構築と、監視の仕組みが必要になります。
成功の鍵は「現場のDX」にあり。課題解決の2つの軸
先に挙げた5つの落とし穴は複雑に影響しあい、海外拠点のマネジメントを失敗へと導きます。しかし、これらの課題は、「現場のDX」によって解決することができます。
「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と聞くと、多くの経営者は莫大なコストがかかる大規模なシステムの導入をイメージしてしまうかもしれませんが、ここで提唱する現場のDXは、低コストで迅速に導入できるデジタルツールです。
その成功の鍵は、「徹底的な可視化」と「徹底的な標準化」という2つの軸です。
軸1:徹底的な『可視化』現場で今、何が起きているかを客観的なデータでリアルタイムに把握する
海外拠点マネジメント失敗の要因が「ブラックボックス化」であるならば、その対策は「徹底的な可視化」です。感覚での報告や、勘や経験に基づく対応ではなく、客観的なデータに基づいた分析と判断、対策の実行をすることで解決できます。
これ以上のコストダウンは難しい、これ以上の生産性向上は困難だという報告の多くが、勘や思い込みで無理だと判断をしています。
各工程の作業時間をストップウォッチで計測して、どこで時間のロスが生じているのか、どこで付加価値を生まない停滞をしているのかを客観的なデータで分析すれば、改善すべき課題はすぐに見つかります。
課題がわかれば解決策を立案し、実行し、効果確認ができます。このように、可視化する仕組みがないため、現場のリアルな状況がわからず、非効率な経営が続いてしまうのです。
可視化するのは作業時間だけとは限りません。以下のような現場の状況をグラフにしたり、画像で認識することで、課題の抽出ができます。
| 種別 | 可視化(グラフ化、画像化)できる情報 |
|---|---|
| 生産状況 | 各ラインの生産数、稼働率、プロセス毎の停止時間、 不良品の発生状況など |
| 作業状況 | 各プロセスの作業時間、作業手順、 作業者ごとの作業スピードなど |
| 設備稼働状況 | 稼働効率(MTBF、MTTF、OEE)、エラー頻度(パレート)、 メンテナンス時間など |
| 品質状況 | クレーム数、不良内容と頻度(パレート)、 検査データ(傾向プロット)不具合の写真など |
| 安全状況 | 労災発生頻度、危険個所の写真、5Sパトロールでの指摘数など |
これらの情報をグラフ化し、電子掲示板での配信をすることで、誰もがアクセスして状況把握できるようにします。パソコンを使えない現場では、定期的に最新情報を掲示板に貼り出すことで、現場の作業者も状況を理解できるようにします。
このような徹底的な可視化によって海外工場の生の姿を把握し、データに基づいた分析と対策、そして意思決定を下すことができるようにします。
軸2:徹底的な『標準化』言語や文化、個人のスキルに依存せず、誰がやっても同じ成果を出せる仕組みを作る
もう1つの軸が、属人化を解消し、組織としての競争力を高める「徹底的な標準化」です。これは、単に標準類を発行したり、マニュアルを作って書庫に入れておくのではなく、誰もがいつでも見ることができて、正しく理解し、実行できる仕組みにする必要があります。
標準化する情報には、以下のようなモノがあります。
| 種別 | 標準化する情報 |
|---|---|
| ルール | 就業規則、出張規則、報告ルート、決裁者、 組織の責任と権限など |
| 作業手順 | 組み立て、メンテナンス、検査、出荷、事務処理、 書類保管など |
| 教育 | 階層教育(新人、中堅、マネジメント)、 スキル教育(品質知識、設計知識、CAD)など |
特に海外工場においては言語の違いが大きな壁になり、誤解や理解不足、情報伝達不足などが起きやすくなります。また、カンやコツが必要な作業を言葉で伝えきれるものではありません。
そこで有効なのが、画像や動画を活用した「ビジュアルマニュアル」です。
ベテラン作業者の手の動かし方、道具の持ち方などを動画で見ることにより、それを真似しやすくします。そして、何度も説明しなくても、理解できるまで繰り返し動画を見ることで、教わる側のスキル習得スピードが速まります。色や形、大きさがわかることで、現場での実作業を事前に頭の中にイメージしやすくもなります。
このような徹底的な標準化によって、個人の経験やスキルに依存しなくなり、組織の仕事の質のバラつきが小さくなります。さらに、新人教育が効率化されて独り立ちまでの時間が短くなるとともに、従業員のやる気向上にもつながるため、離職率の引き下げにも効果があります。
海外工場マネジメントを成功に導く2つの実践ポイント
「可視化」と「標準化」をどのように進めていけばよいのか、実践的な3つのポイントを具体的にご紹介します。
ポイント1. 現場の今をデータで捉え、徹底的に可視化する
まずは、ブラックボックスへの対応です。全社的に 統一したKPI(指標)を設定し、すべての海外拠点で同じ項目をモニタします。
生産性、不良率、設備稼働率などです。重要な指標を3〜5個決め、定期的にデータをとって集計し、これをグラフなどで可視化します。共通の指標を同じ周期で監視することにより、海外工場間の比較や異常値の発見が可能になります。
また、数字だけでは見えない現場のリアルな状況を把握するために、写真や動画の活用をルール化します。始業時の5Sチェック、改善活動前後の比較、初めて見つかった重大な不良品の写真などを撮影し、これも全社で統一したフォーマットに貼り付けて、電子掲示板などで共有します。別の場所にある工場のいい事例や、突発的な不良情報をリアルタイムで把握できるようにします。
作業時間をストップウォッチで計測したり、設備の稼働状況をセンサでモニタしてボトルネックを特定することも、生産性向上のための課題抽出に役立ちます。もう改善はやりつくしてこれ以上できることがない、という決めつけをなくし、現場の作業者自身に次の改善のチャンスを気づかせて、継続的な改善を行います。
最近では安価なIoTツールでデータを自動収集、集計できるシステムも増えています。大がかりなシステムを導入する必要はなく、パソコンとExcelとアンドン(パトライトなど)があれば生産状況の表示や停滞か所の表示ができます。
いきなり完璧を目指すのではなく、できるところから始めることが重要です。
ポイント2. 匠のワザを仕組みに変え、徹底的に標準化する
次に、可視化されたデータを元に、仕事の質を安定させるための「標準化」に取り組みます。
すべての業務にルールと手順を決めて、これを守れるようにマニュアル化します。その際、文字だけのマニュアルは読むだけでうんざりしてしまい、せっかく作っても定着しません。見てわかる動画マニュアルであれば飽きることがなく、理解できるまで繰り返し見ることもできるので、定着しやすくなります。
また、長い動画よりも、1~2分単位で作業を分割し、一つ一つのステップをしっかり理解させることも有効です。
とくに、熟練工の手順や道具の使い方は、言語で伝えられるものではありません。実際にやっているところを見て覚えるしかないのですが、動きが早くてよくわからないこともあります。そのような作業の伝承のためにも、再生速度を変えたり、多言語対応できる動画マニュアルを使えば、後世に残る仕組みを構築することができます。
最近は、工程にノートパソコンやタブレットを配置する工場も増えています。各工程の作業や設備の使い方はフォルダを探さなくても、貼り付けた QRコードを読み取ればいつでもマニュアルを見ることができるように教育の仕組みを作ることができます。
そして、一度作成したマニュアルはそれっきりにせず、絶えず見直しと更新をすることが重要です。作業改善した結果を必ずマニュアルに反映させて、現場で行っている作業と作業手順書に書いてあることが一致しているようにします。
同じものを生産する全ての工場が共通でマニュアルを使用することで、作業者の差だけでなく、工場間の品質のばらつきも抑えることができます。これを実現できるように、共通のネットワーク上に最新版のマニュアルが配備されていることが成功のカギになります。
「標準化」で海外工場のマネジメントに成功している企業事例
株式会社Archem|離職率の高いアメリカ工場で、言語の壁を越え品質と生産性を両立
自動車部品のグローバルサプライヤーである株式会社Archemは、アメリカ工場での高い離職率と、人が変わるたびに必要になる教育コストの増大、仕事の質の不安定さに課題がありました。多国籍の従業員が働く現場ならではの、言語の壁によるコミュニケーション不足が悩みの種でした。
そこで、動画マニュアル作成ツール(tebiki現場教育)を導入して解決を図りました。取り組んだのは、動画マニュアルを使っていつでも、誰でも、何度でも学べる環境の整備です。現場にモニターを設置し、各工程の正しい作業手順を常時再生しておきました。人の入れ替わりや作業ローテーションがあっても、いつでも正しい作業をモニターで確認して学習できるようにしたのです。
また、多言語対応なので、国籍に関係なく母国語で説明を聞くことができるため、理解度が格段に上がりました。設備ごとにQRコードを貼り付けて、スキャンすれば関係する作業手順を確認できるようにしたことで、必要な作業マニュアルを探しに行く必要もなくなりました。
この活動の結果、作業のバラつきがなくなり、不良率が低減しました。新人の習熟期間も短くなり、工場全体の効率が向上しました。「見て学ぶ」環境を整備したことで従業員の自律的な学習が促進し、従業員満足度を向上させることにも成功したのです。
※同社の詳しい事例はこちらのインタビュー記事をご覧ください
HOEI THAILAND|タイ工場でダウンタイムを短縮し、新人教育を5か月から1か月へ
工業用洗浄機などを製造するHOEI THAILANDは、新人オペレーターが一人前になるまでに約5ヶ月もの教育期間を要していました。また、設備トラブルに対応できる人材も限られているため、その間設備が止まり、生産性が低いという課題がありました。
そこで、動画マニュアル(tebiki現場教育)を利用して、この状況の改善をすることに成功しました。まず、100ページ超の紙マニュアルによる新人教育をやめて、動画による作業説明とトラブルシューティングの学習を導入しました。
動画は通常の作業手順書に加え、不具合の「原因と対策」を1〜2分の短い動画にまとめるようにしました。また、不具合対策会議で決定した内容を動画化し、全社でナレッジとして共有しました。動画マニュアルは現場のリーダーが自ら撮影、編集、更新する体制も構築しました。
その結果、新人教育期間が最短1か月に短縮できたのです。また、不具合発生時の対処も誰もができるようにしたことで、設備の止まっている時間(ダウンタイム)も短くなり、効率的な生産ができるようになりました。また、属人化していたトラブルシューティングのノウハウが組織の資産として標準化されました。
※同社の詳しい事例はこちらのインタビュー記事をご覧ください
まとめ
本記事では、多くの製造業が直面する海外拠点マネジメントの失敗要因5つと、その解決策について詳しく解説してきました。そして、その根源にあるのは、現場の「ブラックボックス化」と、「属人化した作業」です。この2つの課題を解決するためには、徹底的な可視化と標準化が重要です。
成功の鍵はDXなのですが、消して大規模な投資をする必要はありません。現場の問題解決に特化した現場DXで十分な成果を上げることができます。そして、その一つの方策が動画マニュアルであることを解説しました。
もし、毎月の月報を読んでも海外工場の実態が見えず、効率的な生産をするために何をすればいいのかが分からないのであれば、ぜひ今日の記事でご紹介した「現場のDX」で自社の課題を見つめ直してみてください。可視化と標準化によって、管理不能なブラックボックスから脱出し、利益を生み出す工場に変えることができます。