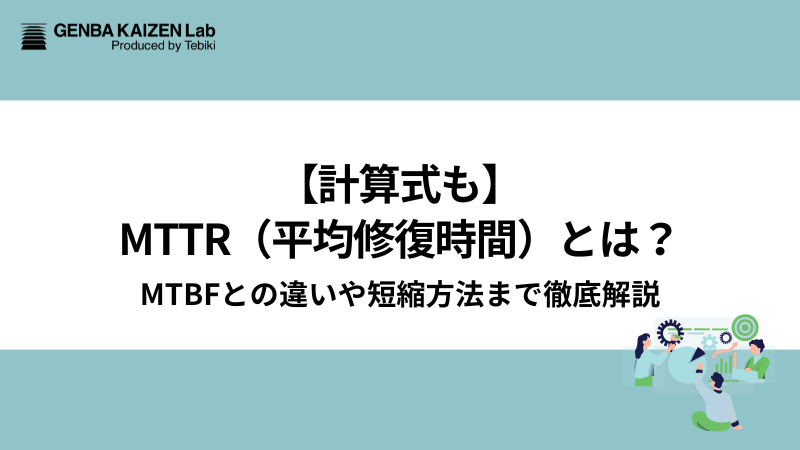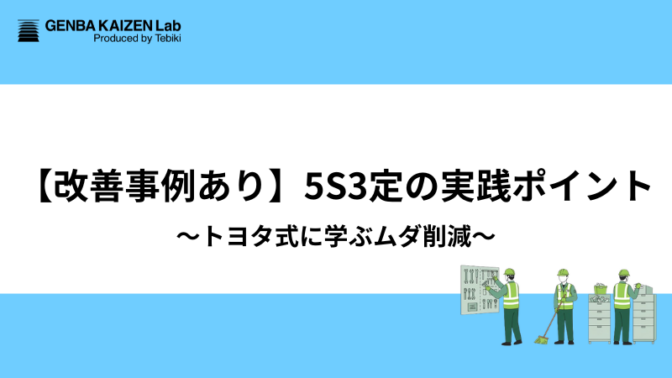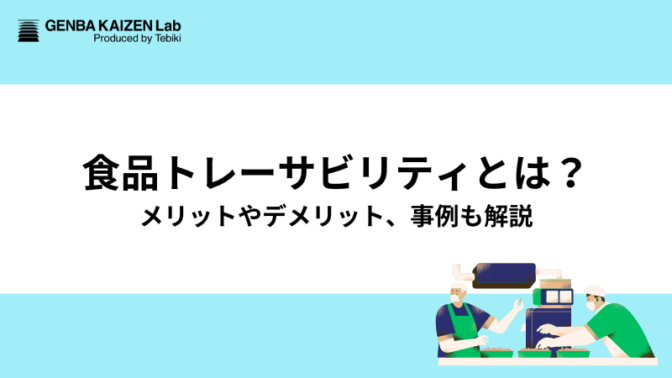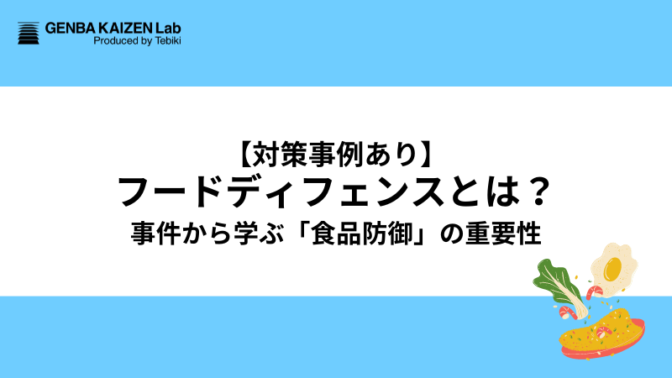かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」とかんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」を展開する現場改善ラボ編集部です。
システムや設備の安定稼働はビジネスの根幹を支える大切な要素ですが、予期せぬトラブルはいつ発生するかわかりません。そのような時、迅速な復旧を可能にする指標が「MTTR(平均修復時間)」です。MTTRの短縮は事業継続性を高め、損失を最小限に抑えるために欠かせません。
本記事では、MTTRの定義から計算方法、MTBFとの違い、そしてMTTRを効果的に短縮するための具体的な方法までを解説します。さらに、MTTR改善に役立つツールの活用方法もご紹介しますので、システム運用の効率化や信頼性向上を目指す方は、是非最後までご覧ください。
目次
MTTRとは?MTBFとの違いも解説
MTTRはシステムの可用性を判断する上で重要な指標であり、MTBFと合わせて理解することで設備の稼働率を正確に把握しやすくなります。
ここでは、MTTRとMTBFの違いを理解し、MTTRを短縮する方法について検討できるよう解説します。
MTTRの定義と役割
MTTRとは、日本語で「平均修復時間」を意味します。 障害が発生した時点を起点として、診断や修復、テストなどを行い、再びシステムや設備が利用できるようになるまでの時間です。
値が小さいほど、設備の復旧にかかる時間が短いことを意味します。 つまり、MTTRが短いほどシステムや設備のダウンタイムが短く、迅速な復旧が実現できていることになります。
MTTRはシステムの可用性を判断するための重要な指標であり、測定・分析することで、システムの信頼性や障害発生時の対応力を把握し、改善につなげられます。製造業では生産ラインの停止時間を最小限に抑え生産効率を高めるため、IT業界であればサービス停止による機会損失や顧客満足度の低下を防ぐための短縮が求められます。
MTTRとMTBFの違い
MTTRとよく関連して用いられる言葉に、MTBF(Mean Time Between Failures、平均故障間隔) があります。MTBFは、システムや設備が稼働を開始してから次に故障するまでの平均時間です。値が大きいほど、故障の頻度が低いことを示しています。
MTTRとMTBFはどちらも設備やシステムの稼働率を算出するために用いられる重要な指標であり、組み合わせて分析することで、システムや設備の信頼性や可用性を総合的に評価できます。
例えば、MTBFの値が大きくMTTRが長い場合、一度故障が発生すると復旧までに多くの時間を要し、結果的に稼働率が低下する可能性が予想できます。逆に、MTTRが短くMTBFの値が小さい場合、頻繁に故障や復旧作業が発生していることが予想され、稼働率の低下が推測できます。
このようにMTTRとMTBFは密接に関係しており、どちらか一方ではなく両方の指標をバランスよく改善していくことが重要です。
MTTRの短縮が重要な理由
MTTRはシステムや設備が故障や障害から復旧するまでにかかる平均時間です。この指標を短縮することには、以下のようなメリットがあります。
- ダウンタイムの最小化
- トラブル時の被害抑制
- 設備の安定稼働
- 作業者の負担軽減
ダウンタイムの最小化
MTTRを短縮すると設備が故障した際の復旧時間が短くなり、ダウンタイム(生産ラインの停止期間)を最小限に抑えらます。生産ラインが停止するとその間の生産量がゼロになり、計画通りの出荷ができなくなるため、ダウンタイムの削減は非常に重要です。
ダウンタイムの最小化には、以下のような効果が期待できます。
- 生産ロスの減少
- 納期遅延の防止
- 修理コストの削減
- 生産性の向上
トラブル時の被害抑制
平常時からMTTRの短縮に努めることで、設備やシステムにトラブルが発生した際の被害や影響を減少させることが期待できます。具体的には、事前の予防保全や故障時の迅速な対応体制の構築が重要です。これにより、トラブル発生時でも早期に復旧し、ダウンタイムやシステム停止時間を最小限に抑えることができます。
例えば、製造業においては、定期的なメンテナンスや予知保全によって設備の故障リスクを減少させ、万一の故障時には迅速な修理が可能となります。これにより、作業者や設備にかかる負担が軽減され、トラブルが発生してもその影響を広げることなく、迅速に生産を再開することができます。
また、MTTRはIT業界におけるセキュリティインシデントの管理や改善にも活用されています。例として、システム監視ツールを活用してリアルタイムで異常を検知し、トラブル発生の兆候を早期に把握することができます。このような対策を講じることでシステムのダウンタイムを最小限に抑え、顧客への影響を軽減し、ビジネスの継続性を確保できます。
平常時からMTTR短縮に向けた取り組みを行うことで、急なトラブルにも冷静かつ迅速に対応でき、最終的には企業の生産性向上や顧客満足度の向上にも寄与するでしょう。
MTTRの計算方法と適用事例
ここでは、MTTRの具体的な計算方法と、実際の現場での活用方法について解説します。計算式を理解し、事例を通して活用イメージを持つことで、MTTRが自社の課題解決にどのように役立つかが見えてきます。
MTTRの計算方法
MTTRは、以下の計算式で算出されます。
MTTR = 総修理時間 ÷ 総故障回数
- 総修理時間:ある期間内に発生したすべての故障や障害に対する修理時間の合計
- 総故障回数:同じ期間内に発生した故障や障害の回数
具体例を用いて計算してみましょう。
例えば、ある製造ラインで1ヶ月(30日間)のデータを確認した結果、以下のデータが得られたとします。
故障回数:5回
各故障に対する修理時間:3時間、2時間、4時間、1時間、5時間
この場合、総修理時間は 3 + 2 + 4 + 1 + 5 = 15時間 です。
したがって、MTTRは以下のように計算されます。
MTTR = 15時間 ÷ 5回 = 3時間
この製造ラインにおけるMTTRは3時間と算出されます。つまり、平均して1回の故障につき、復旧までにおおよそ3時間かかっていることがわかります。
MTTRの活用方法
MTTRは、MTBFと組み合わせることで、設備やシステムの稼働率を算出する際に役立ちます。稼働率は、設備やシステムが正常に稼働している時間の割合を示す指標であり、生産性やサービスレベルを評価する上で重要な指標です。
稼働率 = MTBF ÷ (MTBF + MTTR)
具体例を用いて稼働率を計算してみましょう。
先ほどの製造ラインの例で、MTBFが60時間だったとします。
この場合、稼働率は以下のように計算されます。
稼働率 = 60時間 ÷ (60時間 + 3時間) = 約0.952
この製造ラインの稼働率は約95.2%となります。つまり、この製造ラインは、95.2%の時間、正常に稼働していることがわかります。
MTTRを短縮することで、分母が小さくなるため、稼働率は向上します。このように、MTTRとMTBFは、設備やシステムの稼働状況を把握し、改善活動を進める上で非常に重要な指標となります。
MTTRを短縮するための具体的な方法
MTTRを短縮することは様々なメリットをもたらします。ここでは、MTTRを短縮するための具体的な方法を以下4つのポイントに絞って解説します。
- 予防保全を行う
- 初期対応のポイントを整備する
- 修復作業を効率化するツールやプロセスを構築する
- 故障の内容によって変動があることを認識する
初期対応のポイントを整備する
故障や障害が発生した際、迅速に復旧作業を開始するためには、初動対応が非常に重要です。特に、速やかにメンテナンス担当者に連絡を取れる体制を整えることが大切です。早朝や深夜、休日のトラブルでも速やかに対応できる体制づくりが、MTTR短縮の鍵を握ります。そのためには、異常発生時の連絡フローや対応手順を明確に定めたマニュアルを作成し、関係者全員に周知徹底しておくことが必要です。マニュアルには、誰が、いつ、どこに、どのように連絡するのか、具体的な手順を記載しておきましょう。
修復作業を効率化するツールやプロセスを構築する
復旧作業を迅速かつ確実に行うためには、作業手順の標準化と、それをサポートするツールの活用が有効です。例えば、作業手順書やトラブルシューティングガイドを整備し、作業者がすぐに確認できる状態にしておきます。
「動画マニュアルtebiki」のようなツールを活用すれば、作業内容をスマートフォンなどですぐに確認できるため、作業の効率化と品質向上に貢献します。動画マニュアルは、文字や写真だけでは伝わりにくい作業のコツや注意点を、視覚的に理解しやすくする効果があります。特に、複雑な作業や、経験の浅い作業者にとっては、非常に有効なツールとなるでしょう。
故障の内容によって変動があることを認識する
MTTRを向上させるためには、MTTRが「平均値」であることを意識することが重要です。故障の内容によって、復旧にかかる時間は大きく変動します。
例えば、簡単な部品交換で済む場合もあれば、大規模な修理が必要となる場合もあります。MTTRは、これらの異なる故障内容に対する修理時間を平均化した数値です。したがって、故障の内容によっては、平均よりも時間がかかる場合があることを認識しておく必要があります。この点を理解しておくことで、MTTRの数値だけに捉われず、個々の故障に対して適切な対応を取れるようになります。
MTTRを改善し生産性向上につなげる2つのポイント
MTTRを短縮することは単にシステムの復旧時間を速めるだけでなく、企業の生産性全体を向上させることにもつながります。
初期対応の標準化とノウハウ共有
MTTR短縮のためには、障害発生時の初期対応が非常に重要です。問題を迅速に特定し、適切な対応を即座に行うことが、復旧時間を大きく左右します。しかし、トラブル対応は経験や知識が必要とされるため、担当者によって対応スピードや質に差が出てしまうことも少なくありません。
そこで有効なのが「動画マニュアル」の活用です。動画マニュアルは、文字や写真だけでは伝わりにくい作業手順や注意点を、視覚的に、そして誰でも理解しやすい形で伝えられます。例えば、システムのエラーメッセージに応じた対処法や、機器のトラブルシューティング手順などを動画で確認できるため、経験の浅い担当者でも迅速かつ正確な対応が可能となります。
また、チーム全体で定期的に動画マニュアルを用いたトレーニングを実施することも重要です。これにより、対応手順の属人化を防ぎ、チーム全体のスキルを底上げできます。さらに、トレーニングを通じて、マニュアルの改善点を発見し、より実践的な内容へとブラッシュアップしていくこともできます。
リアルタイムなデータの観測と分析
MTTRの短縮には、初期対応の迅速化だけでなく、中長期的な視点での改善活動も欠かせません。そのためには、現場で発生する様々なデータを収集・分析し、故障や障害の予兆を早期に発見することが重要です。
例えば、設備の稼働データやエラーログ、作業者の報告などを一元管理し、分析することで、故障につながるかもしれない「ヒヤリハット」事例や、特定の条件下で発生しやすいトラブルの傾向などを把握できます。こうした「気づき」をチーム内で共有し、対策を講じることで、将来的なトラブル発生を未然に防ぐことができるのです。
ここで役立つのが、現場のデータ共有や分析を支援するツール「tebiki現場分析」です。「tebiki現場分析」を活用することで、現場で起こっている「いつもと違う」をデータで捉え、トラブルの予兆をいち早く察知できます。これは、MTTRの短縮だけでなく、予防保全の強化にもつながり、結果として生産性向上に大きく寄与します。
MTTR短縮に役立つツール
ここからは、MTTR短縮を強力にサポートする具体的なツールを2つ紹介します。これらのツールを活用することで、これまで解説してきた「動画マニュアルによる教育」や「データ共有と分析」を効果的に実現し、MTTR短縮をより現実的なものにすることが可能です。
設備保全のノウハウが伝わる「動画マニュアルtebiki」
「動画マニュアルtebiki」は、現場のノウハウを簡単に動画化し、共有・教育に活用できるツールです。
スマートフォンで撮影した動画をアップロードするだけで、自動的に字幕や目次が生成され、誰でも簡単に動画マニュアルを作成できます。
「動画マニュアルtebiki」がMTTR短縮に効果的な理由
- 直感的な理解を促進:文字や写真だけでは伝わりにくい作業手順や注意点を、動画で視覚的に理解できるため、作業の習熟が早まります。
- 属人化の解消: ベテランのノウハウを動画で記録・共有することで、特定の個人に依存しない、標準化された作業手順を確立できます。
- 教育の効率化: いつでもどこでも、スマートフォンやタブレットで動画マニュアルを閲覧できるため、教育にかかる時間やコストを削減できます。
- 多言語対応: 外国人労働者の方への教育もスムーズに。
【導入事例:アスクル株式会社】
”トラブル時の復旧、メンテナンス作業中にスマートフォンで該当の作業方法を検索する「辞書」のような活用方法をしています。これにより、作業頻度の低いメンテナンス手順の正しいやり方を効率的に都度確認しながら作業ができるので属人化の解消、そしてベテラン技術の伝承につながりました。”
アスクル株式会社では、「動画マニュアルtebiki」を導入することで、トラブル対応やメンテナンス作業の効率化を実現しています。特に、作業頻度の低いメンテナンス手順を動画で確認できるようになったことで、属人化の解消とベテラン技術の継承に成功しています。
動画マニュアルがかんたんに作れる「tebiki」の概要を見る
データ共有や分析に役立つ「tebiki現場分析」
「tebiki現場分析」は、現場のデータを収集・分析し、トラブルの予兆を早期に発見するためのツールです。設備の稼働データや作業者の報告などを一元管理し、異常の傾向を可視化することで、予防保全や改善活動に役立てられます。
「tebiki現場分析」がMTTR短縮に効果的な理由
- データの可視化: 現場の様々なデータをグラフやチャートで可視化することで、問題点を一目で把握できます。
- 異常の早期発見: データの傾向から、トラブルの予兆を早期に発見し、事前に対策を講じられます。
- 分析の効率化: データの収集・分析を自動化することで、分析にかかる時間やコストを削減できます。
【導入事例:NACL社】
NACL社では、「tebiki現場分析」を活用して、データ観測から異常に気づく仕組みを構築しています。設備や作業のデータを「tebiki現場分析」に取り込むことで、「いつもと違う」状態をデータで捉え、トラブルの未然予防につなげています。
デジタル帳票がかんたんに作れる「tebiki現場分析」の概要を見る
MTTRを理解してシステムや設備の信頼性を向上させよう
本記事では、MTTRを軸に、その定義や重要性、計算方法、短縮のための具体的な方法、さらにはセキュリティインシデントへの応用まで、幅広く解説してきました。
MTTRを理解し、効果的に活用することは、システムや設備の信頼性を向上させ、ビジネスの競争力を高めるために欠かせません。特に、トラブル発生時の迅速な対応は、顧客満足度の維持・向上に直結します。
そして、MTTRを短縮し、信頼性を向上させるために、まず実践していただきたいのが、「トレーニングによる対応力の強化と属人化の防止」です。
「動画マニュアルtebiki」を活用すれば、トラブル対応の手順を視覚的に、そして誰もが理解しやすい形で共有できます。さらに、「tebiki現場分析」を組み合わせることで、現場のデータを活用した、より高度なトラブルシューティングや予防保全が可能になります。
MTTRを短縮するための取り組みを強化したいと考えている方は、tebikiの活用が非常におすすめです。それぞれのツールの機能詳細や導入事例について知りたい方は、以下のフォームから資料をダウンロードしてご覧ください。