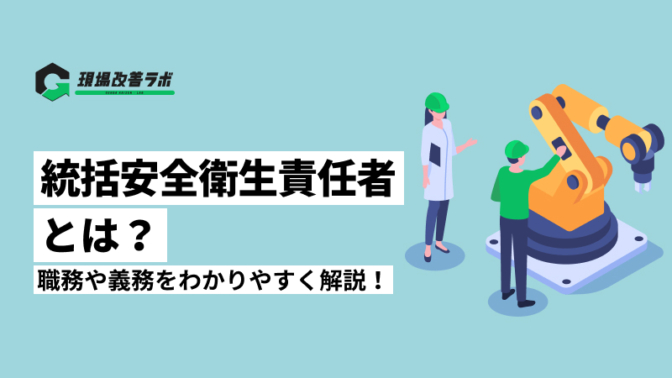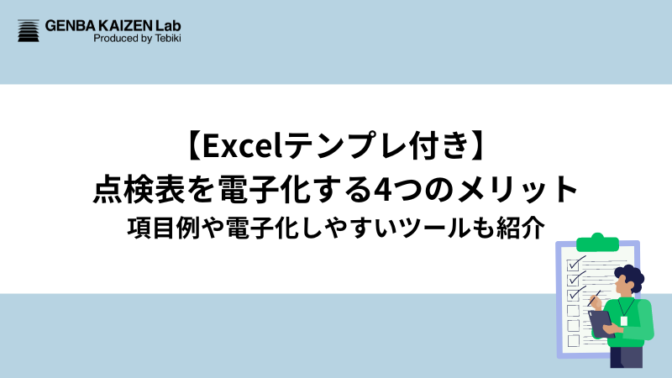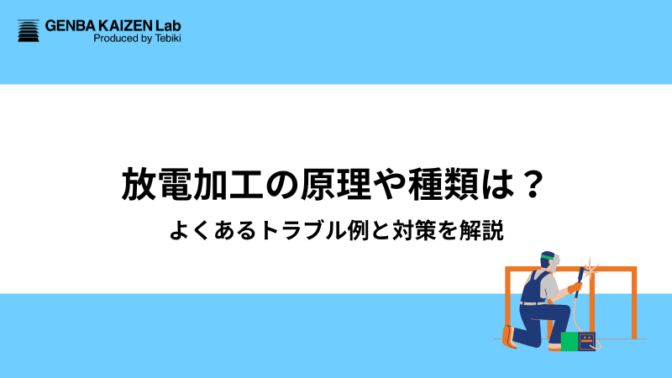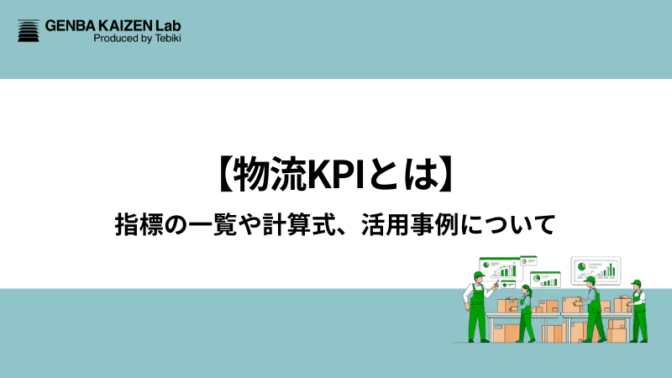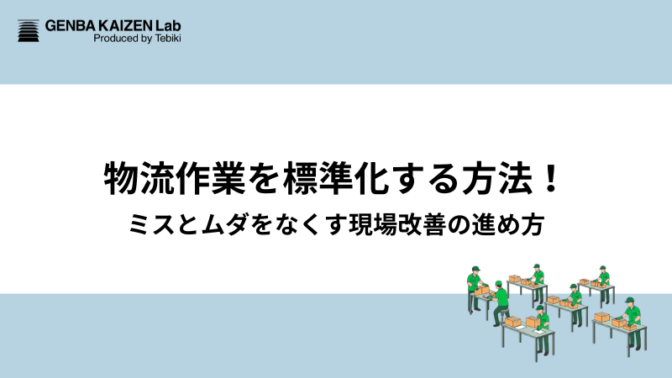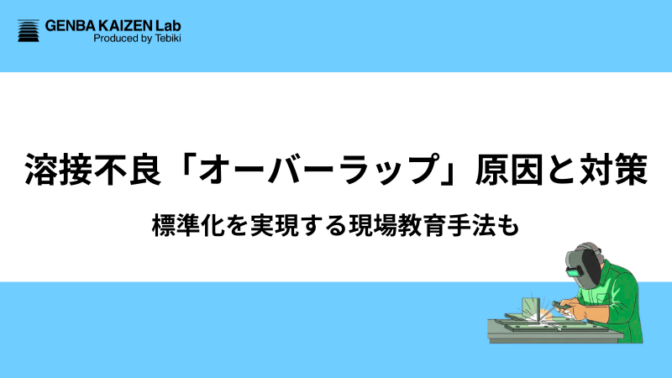かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」と、かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」を展開する現場改善ラボ編集部です。
MTBF(Mean Time Between Failures)とは、設備やシステムの平均故障間隔のことです。MTBFの値によって、故障するまでの平均値がわかります。
本記事では、MTBFの基本的な定義から計算方法、関連する指標との違いなどについて解説します。MTBFを高め、生産性を向上につなげるポイントについてもご紹介しますので、是非最後までご覧ください。
目次
MTBFとは? 定義や似た指標との違いを解説
MTBFという言葉は聞いたことあるけど、詳しくはわからないという人もいるのではないでしょうか?ここでは、MTBFの基本的な定義から似た指標との違いについて解説します。
MTBFとは「製造業からITまで幅広く活用される信頼性指標」
MTBFとは、「Mean Time Between Failures」の略で、日本語では「平均故障間隔」を意味します。この指標は、設備やシステムが稼働し始めてからもしくは修理完了からの平均値を表します。
例えば、ある機械が故障から復旧し再び稼働し始めてから、次に故障するまでの時間を計測し、それらを平均化したものがMTBFです。
MTBFの値が高いほど、その設備やシステムは信頼性が高く、故障が少ないと判断されます。MTBFは製造業をはじめ、ITシステム、通信インフラ、航空機の運用など幅広い分野で活用されており、設備の保守計画やダウンタイムの削減において重要な役割を果たしています。
MTBFとMTTFの違い
MTTF(Mean Time To Failure、平均故障時間)とMTBFは混同されやすいですが、それぞれ異なる意味を持つ指標です。MTTFは「使用を開始してから最初に故障するまでの時間」です。主に修理が不可能な設備や製品の信頼性を評価する際に使用されます。
一方、MTBFは修理可能な設備に用いられる指標であり、稼働開始もしくは修理完了から次の故障までの平均時間を測ります。この違いを理解して適切な指標を選べば、メンテナンス計画を最適化することが可能です。
MTBFとMTTRの違い
MTBFと混同されやすいもう1つの指標がMTTR(Mean Time To Repair、平均修理時間)です。MTBFが「正常に作動する時間の平均」を示すのに対し、MTTRは「故障から修理完了までの平均時間」を表します。
例えば、MTTRが短い設備は故障が発生しても迅速に復旧できるため、ダウンタイムを最小限に抑えることが可能です。MTBFとMTTRは相互に補完的な指標として扱われることが多く、総合的な設備の効率や信頼性を判断する材料となります。
MTBFとMTTFの違い
MTTA(Mean Time To Acknowledge、平均確認時間)は、システムや運用において障害やインシデントが発生した際に、その問題を認識するまでにかかる平均時間を意味します。MTBFが「故障までの平均時間」を示す一方で、MTTAは故障の発生から対応を開始するまでの期間を評価する指標です。
この指標は特に、リアルタイムでのシステム監視や問題解決が重要な分野で利用されます。ダウンタイムを短縮するには、MTBFやMTTRとともにMTTAを低減する取り組みが欠かせません。例えば、迅速なアラート通知と対応プロセスの整備は、全体の生産性向上に繋がります。
【例題付き】MTBFの具体的な計算方法
ここでは、実際にMTBFを計算する方法について解説します。
MTBFの計算方法
MTBFの基本計算式は「総稼働時間を総故障回数で割る」と算出されます。計算式は以下の通りです。
MTBF=総稼働時間 ÷ 総故障回数
この指標を用いることで、設備やシステムがどれだけ信頼性が高いかを定量的に評価できます。
【例題】
実際に、ある工場の機械が以下のように稼働した場合を考えます。
- 300時間稼働後に故障
- 修理後250時間稼働後に再度故障
- 再度修理し、200時間稼働後に故障
この場合、MTBFは以下のとおりです。
MTBF=(300+250+200)÷3=250
結果、MTBF=250となります。この計算結果から、設備が平均して250時間稼働するごとに故障する可能性があることがわかります。
MTBFと故障率の計算方法
故障率とは、設備やシステムがどれくらいの頻度で故障するかを示す指標です。計算式は以下の通りです。
故障率=故障回数 ÷ 稼働時間
【例題】
ある機械が1000時間稼働して5回故障した場合、故障率の計算は以下の通りです。
故障率(%)=5÷1000×100=0.5%
つまり、この機械の故障率は1時間あたり0.5%の確率となります。
MTBFと稼働率の計算方法
稼働率は、設備やシステムが実際に稼働している割合を示す指標です。計算式は以下の通りです。
稼働率=MTBF ÷(MTBF+MTTR)×100
ここで、MTTR(Mean Time To Repair)は「故障から復旧までの平均時間」です。
【例題】
例えば、ある機械のMTBFが250時間、MTTRが10時間の場合、稼働率は次のように計算されます。
稼働率(%)=250÷(250+10)×100=96.15%
つまり、設備の稼働率が96.15%であることを意味します。稼働率が高いほどダウンタイムが少なく、生産性が高いといえますが、過剰な負荷が設備にかかっている場合やメンテナンスが十分に行われていない場合には、設備故障や生産ロスのリスクが高まる可能性があります。
MTBFは設備やシステムの信頼性を測る基本的な指標であり、故障率や稼働率と組み合わせて活用することで、より効率的な設備管理が可能です。次に、業界別に見るMTBFの具体的な活用方法について解説します。
業界別に見るMTBFの活用方法
MTBFは製造業をはじめ、ITシステム、通信インフラ、航空機の運用など幅広い分野で活用されています。
ここでは、以下の2つの分野での活用方法をご紹介します。
- 製造業でのMTBFの活用方法
- IT業界でのMTBF活用方法
製造業でのMTBFの活用方法
製造業でダウンタイムを減らすには、生産ラインの中断を避けることが重要です。そのため、MTBF(平均故障間隔)は生産性を維持し、安定した稼働を実現するために欠かせない信頼性指標となっています。
製造設備が故障するとダウンタイムが発生し、以下のような問題を引き起こします。
- 生産性の低下
- 納期遅れのリスク
- 追加の修理コストの発生
これらの課題を最小限に抑えるために、MTBFが高い機器の選定が推奨されます。さらに、MTBFを活用すれば、適切なメンテナンスのタイミングを見極められ、突発的な故障のリスクを軽減できます。
また、製造業で広く採用されている管理手法がTPM(Total Productive Maintenance:全員参加の保全活動)です。TPMでは、設備総合効率を最大化するために「7大ロス」と呼ばれる要因を特定し、改善活動を行います。その中でも故障によるロスは特に重要で、MTBFのデータを活用することで、ロスを効果的に削減することが可能です。
例えば、MTBFを分析することで故障頻度の高い部品を特定し、予防的な部品交換や保全計画を立てられます。このように、MTBFのデータは企業の利益を向上させるための意思決定に大きく貢献します。
7大ロスから紐解く設備総合効率の改善ポイントについては、以下の専門家による講演動画でも詳しくご紹介しています。
IT業界でのMTBF活用方法
IT業界では、MTBFはシステムの信頼性や耐久性を評価する指標として利用され、主に以下のような場面で役立ちます。
- サーバーの安定稼働の評価
- ネットワーク機器の耐久性確認
- システム全体の信頼性設計
例えば、データセンターの運用では、サーバーの故障が発生すると業務が停止し、企業の損失や信頼低下に繋がります。このリスクを最小化するために、MTBFの高い製品を選定することが一般的です。
さらに、MTBFは新規システム導入時だけでなく、運用中の保守計画にも役立ちます。例としてITインフラの管理者はMTBFのデータを基に、故障が予想されるタイミングで計画的なハードウェア交換やシステムアップグレードを実施できます。このアプローチによりダウンタイムを防ぎ、サービスの継続性の維持が可能です。
また、クラウドサービスやSaaSプロバイダーにとっても、MTBFは顧客への信頼性をアピールする重要な指標です。例えば、「当社のシステムはMTBFが1,000時間以上」というデータは、顧客の安心感を高め、契約更新や新規導入の後押しとなるでしょう。
MTBFを活用するメリット
ここからは、MTBFを活用する以下3つのメリットについてご紹介します。
- 信頼性の向上
- 顧客満足度の向上
- コスト削減
信頼性の向上
MTBF(平均故障間隔)の改善は、設備やシステムの信頼性を高める上で非常に重要です。故障間隔が長くなることでダウンタイムを減らし、結果として生産性を向上させる効果があります。
例えば、製造業では生産ラインが停止することによる納期遅延や顧客の信頼低下といったリスクがつきものです。しかし、MTBFが高い設備を導入し、定期的なメンテナンスで稼働時間を維持すれば、製品供給の安定性が確保されます。これにより、設備やシステムの信頼性が向上し、顧客や取引先からの評価も高まります。
顧客満足度の向上
MTBFの向上によって故障やダウンタイムを減らせた場合、製品やサービスの品質を保ちながら低コストでの供給が可能です。結果的に、顧客満足度の向上に繋がります。
例えば、IT業界では、安定したネットワークやサーバー稼働を提供することで、エンドユーザーがトラブルに見舞われる頻度を減らします。また、製造業では、品質の高い製品を予定通り納品することで、顧客の信頼を勝ち取れるでしょう。顧客満足度の向上は、リピート注文や新規顧客獲得にも繋がります。
コスト削減
MTBFを活用した適切なメンテナンス計画は、コスト削減に直結します。予防保全を行うことで、突発的な故障による修理費用やダウンタイムによる損失を未然に防ぐことが可能です。
例えば、MTBFのデータを基に定期的な点検や部品交換を実施すれば、事後保全に比べて費用を大幅に抑えられます。また、メンテナンスを適切に行うことで機械や設備の耐用年数を延ばせるため、設備投資の頻度を減らし、長期的なコスト削減に繋がります。
MTBFを活用するときの注意点
故障のタイミングを予測するための重要な指標であるMTBFですが、活用時には注意すべきポイントもあります。以下の2つのポイントに気をつけましょう。
MTBFは正確な予測ではない
MTBF(平均故障間隔)は、設備やシステムの信頼性を評価するための重要な指標です。しかし、あくまでも平均値であるため、故障の発生時期を正確に予測はできません。特に、故障する間隔にばらつきが大きい場合、MTBFの値だけでは詳細な情報を得るのが難しくなります。
さらに、故障の程度や影響も一様ではありません。ある機器が軽微な不具合を頻繁に起こす場合と、まれに致命的な故障を起こす場合では、同じMTBF値でも受ける影響は違います。そのため、実際の運用環境や使用状況を考慮しながら、MTBFを参考値として活用することが重要です。
また、MTBFが高いとされている場合でも、その機器の耐用年数が優れているわけではありません。「MTBFは目安である」という前提を念頭に置き、他のデータと組み合わせて使用する必要があります。
MTBF以外の分析手法も活用する
MTBFは設備などの平均的な稼働期間を示す指標ですが、故障の具体的な原因までは明らかにしません。そのため、より精度の高い分析や予防策を講じるには、MTBFと組み合わせて他の手法を活用することが推奨されます。
代表的な手法として、FTA(Fault Tree Analysis)があります。FTAは、故障の原因を構造的に分析し、発生の可能性や因果関係を明らかにする方法です。この手法を用いることで、以下のようなメリットが得られます。
- 故障原因の可視化:故障に至るまでの要因をツリー状に整理し、全体像を把握できる
- 予防策の立案:特定の要因を排除するための対策を明確化できる
- リスク管理の強化:故障の可能性を減らすための具体的なアプローチを実施可能
例えば、製造業で頻発する機械の停止トラブルに対し、FTAを用いて根本原因を究明することで、メンテナンス計画を最適化し、MTBFの改善につなげられます。さらに、分析を通じて得られる知見は、次世代の設計や運用プロセスの改善にも役立ちます。
MTBFとFTAを組み合わせることで、信頼性評価と故障予測の精度が向上し、設備運用の効率化に繋がります。
MTBFを高め、生産性向上につなげるポイント
MTBFを高めて生産性向上につなげるには、以下の4つのポイントを押さえておく必要があります。
設計段階での対策
MTBFを高めるには、製品や設備の設計段階における品質の作りこみが重要です。設計段階で潜在的な故障原因を洗い出し、部品の品質や構造の最適化を行うことで、その後の故障リスクを大幅に減らせます。例えば、耐久性の高い部品を採用したり、冗長性のある設計を導入することで、システム全体の信頼性を向上させることが可能です。
製造業では、設計フェーズでの失敗が後のコスト増大に繋がりやすいため、設計段階でのリスク管理が特に重要視されます。
このとき、重要視されるのが「源流管理」です。品質問題を後工程に流さないように事前に特定し、将来的な再発を防止する源流管理の手法や事例について知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。
関連記事:【品質管理】源流管理とは?なぜ重要?具体的な手法や例を紹介
予防保全
予防保全は、MTBFを高める効果的な方法の1つです。定期的なメンテナンスと検査を行い潜在的な問題を早期に発見すれば、重大な故障を未然に防げます。
例えば、摩耗した部品を交換するタイミングを計画的に設定すれば、故障が発生するリスクを最小限に抑えられます。また、設備や機器の稼働データを分析することで、故障に繋がる傾向やパターンを特定することも可能です。このようなデータ駆動型のアプローチにより、計画的で効率的な保全作業が実現します。
予防保全の効果を最大化するには、保全業務のノウハウを「形式知化」することが重要です。設備の異常を早期に捉え、ドカ停を未然に防ぐコツや役立つツールについてまとめた資料を以下にご用意しましたので、本記事と併せてご覧ください。
社員教育
社員教育も、MTBF向上の重要なポイントです。適切な教育を通じて現場の社員が潜在的な問題に気づけるようになると、迅速に対処できる体制を整えられます。特に、メンテナンス作業を特定の社員に依存する状態(属人化)を避けるには、複数の社員が対応できるように教育を進めることが必要です。
また、メンテナンス作業に限らず、日々の設備操作を適切に行うためのトレーニングを実施することで設備の負荷を軽減し、故障リスクを下げられます。
このように社員教育は長期的な設備の信頼性向上に直結する一方、熟練の技術者にノウハウや技能が集中し、設備保全が属人化しやすいことにお悩みではないでしょうか?
そのような現場の方に向け、属人化を解消する3つのポイントや、「ヒト」と「機械」の作業分析の進め方について解説した動画を以下にご用意いたしました。MTBF改善に役立つ情報が満載ですので、是非ご覧ください。
>>>属人化を解消する「3つの秘訣」を動画で学ぶ(視聴無料)
適切なデータや記録の活用
MTBFの改善には、現場のデータを通して課題を発見し対策することが欠かせません。特に、日々の点検票や不具合報告書は、MTBFを高めるための貴重な情報源です。データを分析することで故障の原因や予兆を特定し、早期に対応することが可能になるでしょう。
例えば、過去の点検記録から特定の部品が一定期間で摩耗することがわかれば、その部品の交換スケジュールを最適化できます。また、不具合報告を詳細に記録することで、同じようなトラブルを防止するための具体的な改善策の立案も可能です。記録の蓄積と分析を習慣化することで、MTBFの向上に貢献する効率的な運用が実現します。
ここまで、MTBFを改善し設備のパフォーマンスを最大化させるポイントについて解説しました。次章からは、MTBF改善に向けた実践的な2つのツールについて解説します。
MTBF改善に役立つ「動画マニュアル」と「デジタル帳票」
故障発生頻度を減らし、安定した稼働を実現するためには、設備の適切な保守・管理が欠かせません。その手段として、「動画マニュアル」と「デジタル帳票」の活用が有効です。
動画マニュアルで保全業務の「標準化」を実現
設備の適切な運用・保守には、作業者の知識とスキルの均一化=保全業務の標準化が必要不可欠です。しかし、紙のマニュアルでは理解しづらかったり、作業者によって解釈が異なることがあります。
このような課題解決に役立つのが「動画マニュアル」です。動画マニュアルは視覚的にわかりやすく、実際の作業手順やノウハウを正確に伝えられるため、教育効果が高まります。
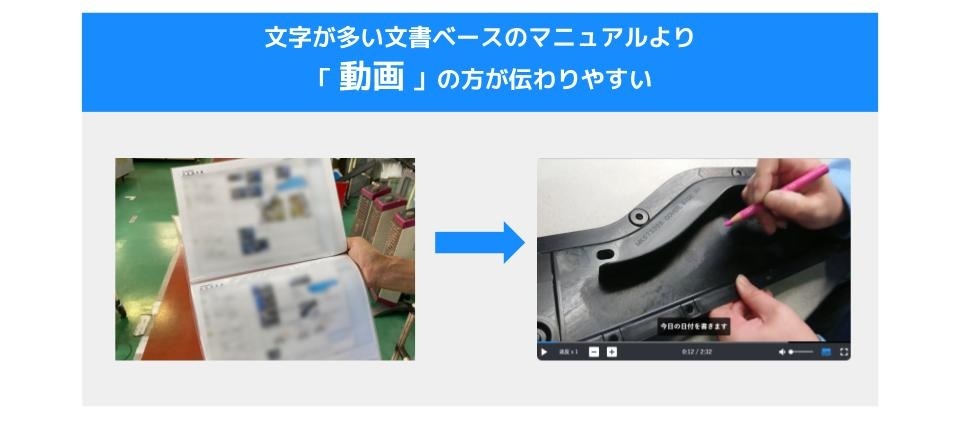
例えば、設備の定期点検や部品交換の手順を動画化することで、経験の浅い作業者でも適切な方法で保守を実施できるようになります。これにより、点検漏れや誤ったメンテナンスによる故障の発生を防ぎ、結果としてMTBFの向上につながります。また、動画マニュアルは何度でも視聴できるため、OJTの負担軽減や、新入社員の早期戦力化にも貢献します。
動画マニュアルが保全業務の標準化に貢献する仕組みや実際の動画サンプルについては、以下のPDF資料内で詳しくご紹介しています。作業手順が守られず、適切な予防保全につながっていないとお悩みの方は是非ご覧ください。
>>>保全業務の標準化を動画で「かんたん」にする方法をみる
デジタル帳票で現場記録をリアルタイムで確認
設備の状態を適切に把握し、計画的なメンテナンスを実施するためには、点検記録や故障履歴の管理が欠かせません。しかし、紙の帳票では記録漏れやデータの集計に時間がかかり、適切な判断が遅れるリスクがあります。
そこで、デジタル帳票を活用することで、現場の記録精度と管理効率を向上させることが可能です。
デジタル帳票を導入すれば、設備の点検データや異常の発生履歴をリアルタイムで記録し、即座に分析できるようになります。例えば、センサーと連携したデジタル帳票を利用することで、特定の設備がどのタイミングで故障しやすいのかを可視化し、予防保全の精度を高められます。これにより、突発的な故障を減らし、MTBFを向上させることができます。
「そうはいっても、いきなりデジタル帳票を導入するのは不安…」「帳票のデジタル化はどう進めるの?」とお思いの方に向け、帳票のデジタル化に向けたガイドブックをご用意いたしました。導入の具体的な手順や費用対効果、ありがちな失敗パターンも網羅されているため、デジタル帳票を検討されている方は是非ご覧ください。
>>>現場帳票をデジタル化する効果や費用対効果について知る
かんたんに使える「動画マニュアル」と「デジタル帳票」ならtebiki
tebiki現場教育で高品質な動画マニュアルを簡単に作成!
動画マニュアルの中では、現場に嬉しい機能が多数搭載された「tebiki現場教育」がおすすめです。
▼「tebiki現場教育」紹介動画▼

tebiki現場教育の最大の特長は、誰でも簡単に動画マニュアルを作れる点です。シンプルな操作画面だからこそ、動画編集経験がない方でも直感的に操作することができます。
編集に時間がかかる字幕生成を自動で行う機能も搭載されているため、1つの動画をサッと15分程度で作成している企業の方も多いです。tebiki現場教育を使えば、スマホで撮影、動画を保存、字幕を確認のたった3STEPで動画マニュアルを作成できます。
他にも、マニュアルの視聴状況がわかる組織レポート機能や、マニュアルの内容をテストとして出題できる「テスト機能」が備わっています。

ユーザーごとのマニュアル視聴状況が可視化されるため、標準化の習熟度や浸透具合を把握しやすくなります。たとえば、作業員がどの程度マニュアルを視聴し理解しているかを確認することで教育の効果を定量的に評価し、必要に応じて追加の指導を行うことが可能です。
実際に、複雑な作業工程もこのツールを使うことで効果的に標準化し、現場の効率を向上させた事例があります。
tebiki現場教育の機能詳細や導入の費用対効果、実際の導入事例については、以下のハンドブックでも詳しく解説しています。標準化や現場教育を効果的に改善したい方は、是非ご覧ください。
tebiki現場分析のデジタル帳票でデータ収集と分析が実現!
帳票のデジタル化には、「tebiki現場分析」がおすすめです。
tebiki現場分析とは、現場帳票の作成・記録・承認・分析が簡単に行えるシステムです。本サービスを活用することで、IEに必要な現場データを効率的に収集・分析することができます。

tebiki現場分析はスマートフォンやタブレットでの入力に特化したわかりやすい操作画面を採用しており、難解な研修を受けずとも誰でも簡単に帳票を記入し、編集できます。また紙では難しかった画像記録もデジタルで簡単に行えるため、現場の状況を視覚的に把握することが可能です。
他にも、「帳票のピンどめ」により使用頻度が高い帳票を優先して表示させる機能や、毎回の記録で共通する内容の入力を省略できる「定時記録」の機能を使うことで、日常的に発生する進捗管理業務をよりスムーズに記録することも可能です。これにより、現場の状況をリアルタイムでデジタルデータとして記録し、分析に役立てることが可能です。
実際に、1日あたり2時間を要していた集計作業が1分に短縮され、記録データをもとに設備トラブルの予防措置が実行できるようになった事例もあります。
さらにtebiki現場分析には収集したデータを簡単にグラフ化する機能を備えており、視覚的に進捗状況を分析できます。分析機能を活用することで、現場に潜むボトルネックや異常、ムダを定量的なデータをもとに簡単に特定し、MTBF改善につなげることが期待できるでしょう。
tebiki現場分析の機能詳細や導入サポート体制については、以下のハンドブックでも詳しくご紹介しています。デジタル帳票で現場データを可視化し、分析や改善につなげたい方は是非ご覧ください。
tebikiのツールを活用してMTBFを高めよう【まとめ】
ここまで解説してきたように、MTBFは設備やシステムの信頼性を向上させ、生産性を高めるために欠かせない指標です。MTBFを向上させるには、設計段階での対策や予防保全、社員教育、適切なデータの活用が重要なポイントとなります。これらの取り組みを効果的に進めるには、tebiki現場分析やtebiki現場教育のようなツールの活用が非常に有効です。
tebikiのツールを導入することで、以下のようなメリットを得られます。
- データの一元管理と活用
- 動画マニュアルとスキルマップの活用
- 属人化の防止と教育の効率化
MTBFを高めるための取り組みを強化したいと考えている方は、是非tebikiの活用を検討してみてください。それぞれのツールの機能詳細や導入事例について知りたい方は、以下のフォームから資料をダウンロードしてご覧ください。