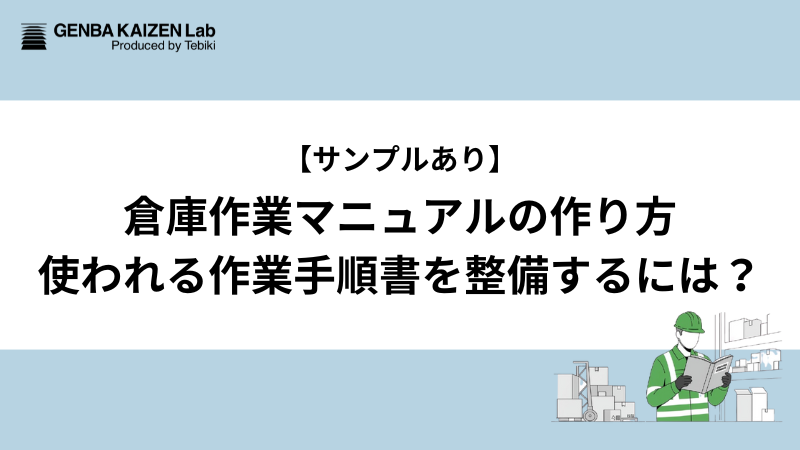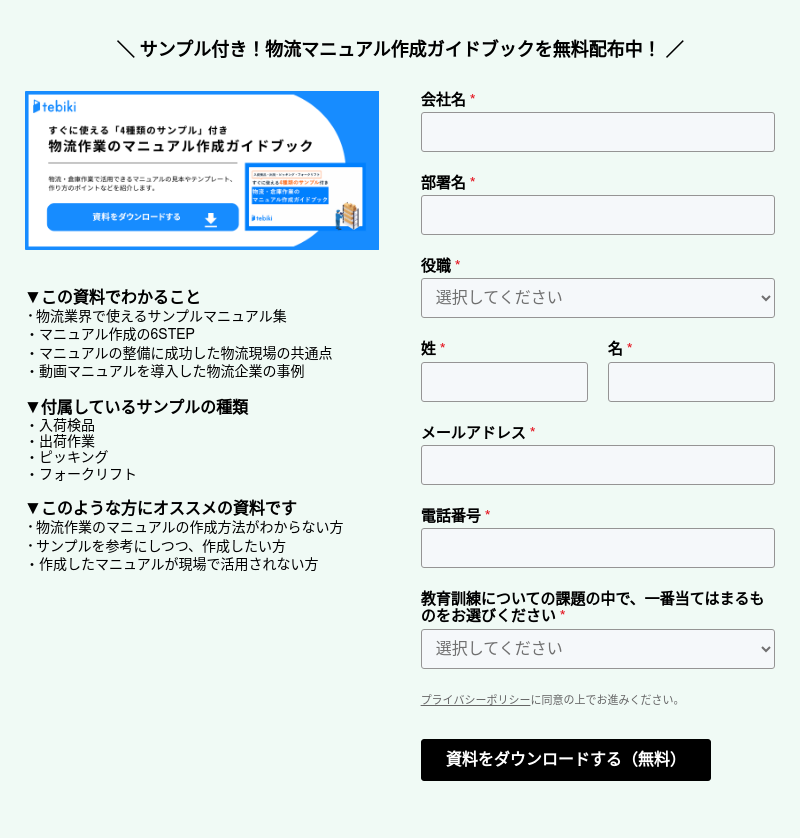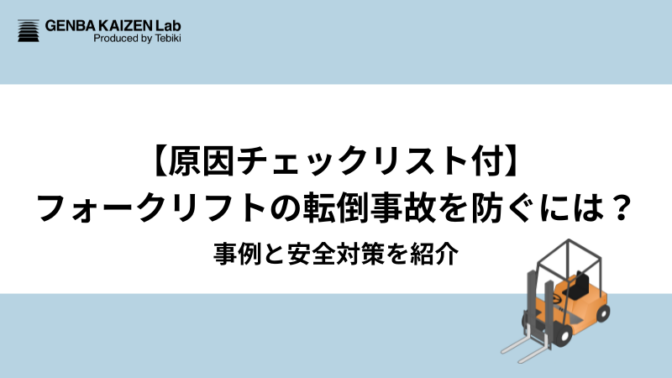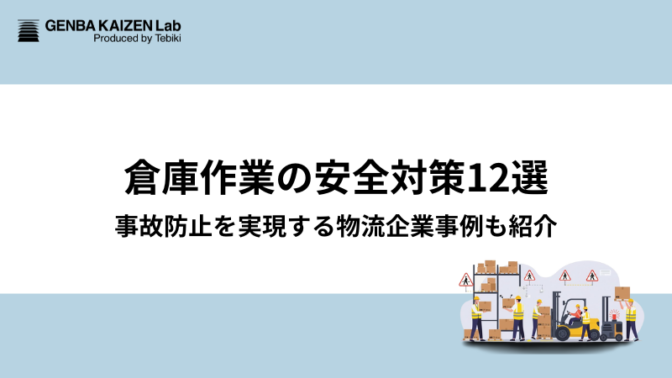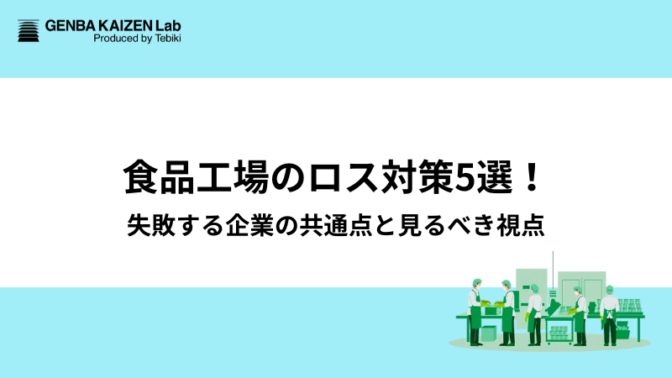かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
物流業における倉庫内の作業は、役割や業務の目的に応じて多岐に渡ります。正社員だけではなく、派遣社員やスポットアルバイトなどの習熟度や経験年数が異なる従業員が作業をするため、作業内容のばらつきが発生しやすい特徴もあります。結果的に、ミスやトラブルに発展しやすいのが現状です。
そのため、業務の標準化に向けた倉庫マニュアルの整備が欠かせません。この記事では、わかりやすい倉庫マニュアルの作り方や手順、マニュアルの整備によって現場改善を実現した事例を紹介していきます。
目次
倉庫作業マニュアルのサンプル【無料ダウンロード可】
倉庫内で発生する作業のマニュアルのレイアウトや内容などをゼロから考えると非常に時間がかかるため、サンプルを見ながらテンプレートに沿って作成するのが効率的に作成するうえでおすすめです。
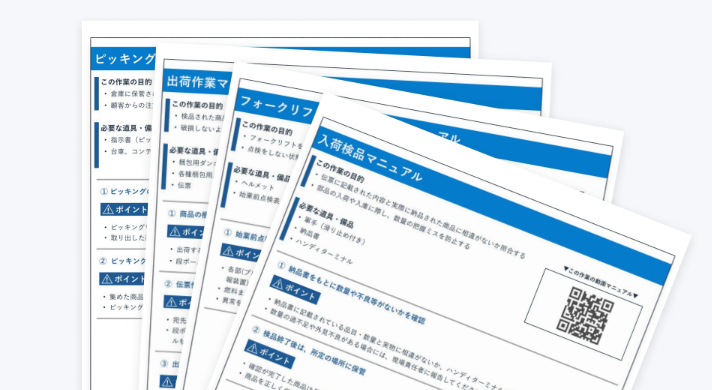
入荷検品・出荷・ピッキング・フォークリフトなど、すぐに活用できる4種類のサンプルとマニュアルのテンプレートをご用意しております。
4種類のサンプルとマニュアルのテンプレートは、以下のフォームをご入力頂くとダウンロードできます。効率的にマニュアルを作成するためにもぜひご活用ください。
倉庫マニュアルとは?重要性について
倉庫マニュアルは、倉庫内で発生する作業の効率化や標準化、安全意識の向上などに関与する非常に重要な文書です。ピッキングや入出庫管理、梱包・発送などの様々な業務が発生するため、作業ルールや手順を整備しなければ、発送の遅延や荷物の破損などが発生するリスクもあります。
また、他の職種と比較して短期やスポットアルバイトなど、入れ替わりも激しいため、マニュアルが整備されていないとミスやトラブルの発生率も高くなるでしょう。
倉庫マニュアルを整備することにより、適切な手順やルールを理解でき、作業の標準化が見込めます。新人教育にも効果的であり、口頭説明やOJTなどの教育担当者の工数削減にも役立つでしょう。
倉庫マニュアルで整備すべき作業の種類
倉庫内では様々な作業があるため、どの作業に対してのマニュアルを作成すれば良いのか悩むケースもあるはずです。ここでは、倉庫内の作業別にどのようなマニュアルが必要なのか種類について紹介していきます。
倉庫マニュアルを整備する際は、主に以下6つの業務に関する手順書を用意できると良いでしょう。
検品作業
対象商品の数量や状態を確認する検品作業では、扱う商品によって異なるため、マニュアルによって基準や作業ルールを定めておくと良いでしょう。
商品に傷や汚れ、へこみなどがないか不良品検品であったり、数量に誤りが無いかであったりなど、チェックする項目は多岐に渡ります。不良品や外装の状態が悪い状態で消費者のもとに届いてしまうと、クレームや顧客満足度の低下にもつながるでしょう。
チェック時の基準や作業手順などはもちろん、チェックシートを用意するなど、経験年数やスキルに依存せずに誰でも同じ品質で作業ができるようにマニュアルの整備が重要です。
入荷・入庫作業
仕入先や物流拠点などから商品が入ってくる「入荷」、入荷した商品を倉庫内の保管場所に入れる「入庫作業」、そしてそれぞれの作業後には商品を探し出す「ピッキング作業」が存在します。
これらの作業は高い正確性が求められます。入荷・入庫作業にミスが発生すると在庫数が把握できなくなり、不足や配送の遅延などにつながるなど物流の工程に大きな影響を及ぼしてしまうためです。
どのタイミングで誰が行っても作業品質にばらつきが発生しないようにするためにも、マニュアルを整備する必要があるでしょう。
流通加工
流通の過程で商品に施す加工作業の流通加工。包装やタグ付けなどの軽作業から、組み立てやカッティング、プレス加工などの専門性が必要な作業など、作業内容が非常に幅広いのが特徴です。
流通加工は複数拠点で実施されるため、作業の標準化を進めるうえでもマニュアルの存在は非常に重要と言えるでしょう。
ピッキング
倉庫内でリストや注文書をもとに指定の商品を集める(ピックアップ)するピッキングでは、多くの商品が保管されている倉庫内でどこに商品があるのかを理解し、ミスなく商品を見つける正確性が求められます。
倉庫規模に応じて保有している商品の数や種類も膨大になるため、マニュアルを整備してピッキング作業の品質を担保することが重要です。
ピッキングミスは人に由来する場合が多くあります。ミスの発生理由や減らすための対策を知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。
関連記事:ピッキングミスや数量間違いが多い人の特徴と9つの対策!改善事例もあわせて紹介
仕分け・出荷
サイズや宛先、種類などの定められている基準に沿って、商品や荷物を分類する仕分け作業でミスが発生すると、出荷作業の際に配送ミスや誤出荷につながる可能性があります。
単純作業・繰り返し作業と認識されていることもありますが、人の手で行う手仕分けについてはカンコツを要する職人技です。作業品質のばらつきを防ぐためにもマニュアルによって、作業を標準化する必要があるでしょう。
一方、機械による自動仕分けについても、機械の不具合や整備・点検などを誰でもできるようにマニュアルに落とし込んでおくのが賢明です。属人化してしまうと、不具合が発生した際に対応ができず、倉庫内の作業がストップしてしまうリスクがあります。
出荷作業に関するマニュアルの重要性や作成方法などについては、以下の関連記事もご覧ください。
関連記事:出荷作業マニュアル作成のポイント!見られる手順書を整備した企業事例も紹介
フォークリフト作業
フォークリフトは、人力では運搬できない重量物を倉庫内のラックに収納したり、積み下ろしや積み込みを行ったりするなど倉庫内の作業に欠かせない重機です。
しかし、操作ミスや不注意などによる事故の発生率も高いため、操作する従業員の安全意識を高めるためにも作業マニュアルの整備が重要です。フォークリフトの安全対策は特に重要なので、マニュアル整備の重要性も必然的に高まります。
イベント物流や梱包作業などの物流事業をはじめ、多角的な事業を展開している株式会社近鉄コスモスでは、フォークリフトの操作方法や安全教育に動画マニュアルを活用しています。
▼フォークリフトの禁止事項を解説する動画マニュアル▼
※「tebiki」で作成されています
フォークの爪でパレットを押したり、急発進や急旋回したりすることをNG行為として字幕とともに分かりやすく解説しているのが特徴です。
株式会社近鉄コスモスを含め、物流業界では、安全教育などに動画マニュアルを活用している企業が多くあります。下の画像をクリックすると、「安全教育に動画が適している理由」や「物流業における動画マニュアルの重要性」などが解説された資料がダウンロードできるので、あわせて参考にしてみてください。
倉庫マニュアルの正しい作成手順
わかりやすい倉庫マニュアルを作成するためには、作成する前の段階で準備をするのが大切です。ここでは、作成手順を紹介していきます。作成手順は以下のとおりです。
それぞれ詳しく解説します。
倉庫マニュアルを作成する目的を明確にする
なぜ倉庫マニュアルを作成するのか、目的を明確にするところからはじめましょう。目的を明確にしていない状態で進めてしまうと、誰が・いつ・何のためにマニュアルを利用するのかが曖昧になり、形骸化してしまう原因になります。
また、目的の明確化とあわせてどの作業のマニュアルを作成するのかも判断しましょう。ピッキングや検品、梱包など倉庫内では様々な作業があるため、どの作業でどのようなマニュアルが必要なのかを整理しておくのが大切です。
マニュアルのフォーマット/ツールを決める
マニュアルを作成する際、どのようなフォーマットを採用するのか、何のツールを使うのかなどもマニュアル作成のしやすさや利用者の利便性などに関わる重要な要素です。
マニュアルの主なフォーマットやツールは以下のようなものがあげられます。
| フォーマット | ・動画 ・文書 ・フローチャート |
| ツール | ・マニュアル作成ツール ・Excel/Googleスプレッドシート ・Word/Googleドキュメント ・PowerPoint/Googleスライド |
なお、ExcelやWord、PowerPointなどで作成する場合、リアルタイムでの更新・共有ができないため、マニュアルの改定が発生した場合に管理が煩雑になるので注意が必要です。一方、オンラインの共有ドライブ等で管理・更新ができるマニュアルであれば、大元のマニュアルを一度更新すれば、最新状態のマニュアルが他の拠点でもリアルタイムで反映・更新されるようになります。
実際に動画マニュアルを活用しているアスクル株式会社では、マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」の活用によって、紙で一元管理できなかったものの、動画マニュアルの活用で体系的にドキュメントを管理できていると効果を実感しています。
作成スケジュールを決める
マニュアルのフォーマットやルールが決まったら、作成を進める前にスケジュールを決めておきましょう。どの作業のマニュアルを、いつまでに、誰が作成するのかなどを締切日から逆算して計画することによって、マニュアル作成がスムーズ進行します。
なお、実際に活用する部門や上司などのチェックが入ることもあるので、スケジュール進行にはある程度余裕を持たせて置くのが大切です。
骨子を作成する
わかりやすいマニュアルを作成するためにも、全体の設計・骨組みとなる骨子が非常に重要です。骨子を作成することによって、情報の抜け漏れがなくわかりやすいマニュアルを作成しやすくなります。また、方向性が整っているので、次のステップの内容の肉付けがスムーズに進むので、時間をかけて取り組みましょう。
骨子を作成する際には、作業内容や手順、注意点など作業全体を俯瞰して細分化するのが大切です。作業内容を理解せずに局所的な視点で作成すると、現場とマニュアルに乖離が発生して、使われないマニュアルになってしまうので注意しましょう。
骨子をもとにして内容を肉付けする
マニュアルの骨子を作成できたら、内容の肉付けを進めていきましょう。骨子作成の段階で肉付けする内容や方向性は定まっているので、詳細を記入するのみで完了します。必要な作業手順が抜けていたり、誤りがあった場合には必要に応じて内容の補填や変更を実施しましょう。
なお、肉付けする際に新たな情報の追加などが多い場合、骨子の作り込みが不完全なので改めて骨子の見直しをしてみることをおすすめします。
「現場で使われる」倉庫マニュアルを作成する際のポイント
倉庫マニュアルを作成しても実際の現場で本当に活用されるのかは、マニュアルの完成度によって左右されます。ここでは、「現場で活用される」倉庫マニュアルを作成するポイントについて紹介していきます。
なお、倉庫マニュアルの作成方法を体系的に理解したい場合は、本記事を読み進めるよりも、マニュアルをはじめて作成する方に向けて「作成のコツ」や「導入時のポイント」がまとめられた資料「マニュアル作成ガイド」がおすすめです。以下のリンクをクリックすると資料がダウンロードできます。
>>『「わかりやすいコツ」つき!はじめてのマニュアル作成ガイド』を読んでみる
「紙のマニュアル」はなるべく使用しない
マニュアル=紙のイメージを持っている方も多いかもしれませんが、紙の活用はあまりおすすめできません。紙マニュアルの場合、手順やルールの説明を文章で行う必要があり、高度な文章技術が求められます。また、図解やイラストで説明しようとすると、使用する枚数が多くなってしまいます。結果的にわかりにくいマニュアルになってしまい、形骸化してしまうことに…。
このようなリスクを防ぐためにも、パソコンやタブレットなどの端末で閲覧できる電子マニュアルがおすすめです。マニュアルを電子化することで、印刷する必要がなく、閲覧したい情報にすぐアクセスすることができます。
なお、電子マニュアルの中でも特に「動画」を活用したマニュアルには、以下のように様々なメリットがあるため、従業員の作業理解度向上につながります。
- 人の動きや微妙なニュアンスを動きと音声で分かりやすく学べる
- 認識のばらつきを防止でき、標準化が実現する
- クラウド上で管理できるため、共有や更新がしやすい
- 紙と比べて管理工数を削減できる
実際に紙のマニュアルを活用していたサッポログループ物流株式会社では、業務の属人化や業務品質のバラつきが発生していましたが、動画にすることで業務の標準化やOJTの負担削減を実現しています。
資料「物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラ(pdf)」では、物流業界における「動画マニュアルを導入する効果」「生産性向上になぜ動画マニュアルが役立つのか」などが詳しく解説されています。現場で活用される倉庫マニュアルに役立つ内容が盛り込まれているので、下をクリックしてご覧ください。
>>「物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラ」を見てみる
作業者・現場の目線で作成する
過度にレイアウトや写真、文章表現などにこだわると、マニュアル作成者が見やすかったとしても現場では、逆に見にくい・使いづらいなどが考えられます。
実際にマニュアルを活用するのは、倉庫内で作業する従業員なので、現場で使いやすい・見やすいという点を重視したうえで作成するようにしましょう。
はじめから完璧を目指さない
マニュアルは最初に作成したものを使い続けるのではなく、作業やルールの変更、修正点などがあれば随時更新し、改善を繰り返しながら活用します。そのため、初めから完璧を目指さないのも大切な判断です。
できるだけ修正する必要がないマニュアルを作成する意識が強すぎると時間がかかりすぎてしまい、当初の想定時間よりも大幅に遅延してしまう可能性もあります。現場からのフィードバックをもらいつつ、段階的にクオリティを向上させるのがポイントです。
専門用語使わずに平易な表現を活用する
倉庫内作業では、専門的な用語が数多くあり、マニュアルを作成する際にも何気なくその用語を使ってしまうかもしれません。
しかし、マニュアルは経験年数が浅い従業員や短期・スポットのアルバイト/派遣社員など、様々な人が活用します。専門用語が多いと、意味が十分に伝わりきらずに認識の相違につながる可能性が考えられます。
そのため、なるべく平易な表現を心がけて、専門用語を用いる場合には、吹き出しで用語の意味を解説するなどの工夫が大切です。
倉庫マニュアルの整備によって現場改善を実現した物流企業の事例
ここでは、マニュアルを整備して、倉庫内作業の効率化や標準化などの現場改善を実現した物流企業の好事例を紹介していきます。
アスクル株式会社
事業所向けECサイト「ASKUL」・個人向けECサイト「LOHACO」を運営するアスクル株式会社。同社では、教育者の経験則によるOJTや紙の手順書によって教育を実施していましたが、教育担当者の属人化や作業のばらつきが発生してしまい、非効率な作業が多くなるなどの課題を抱えていました。
また、紙の手順書については、内容が重複していたり、似たような手順書が存在していたりなどの課題も抱えていたそうです。
属人化の解消やOJTや紙の手順書では伝わりにくい作業を伝えるために、動画マニュアルを導入しました。紙と比べて繰り返し反復して視聴ができ、業務の定着スピードの向上を実現し、独り立ちまでの期間が半年から3ヶ月までに短縮することができています。
「動画マニュアルによって最短距離で一人前になるための体制の構築ができている」と語る同社のインタビュー記事は以下からご覧ください。
ソニテック株式会社
新築戸建て住宅に使用される建築副資材を提供する事業を展開するソニテック株式会社。同社では、作業内容の正確な伝達が難しく、ミスが頻発する/従業員の増加によって、指導者への負担が増えるなどの課題を抱えていました。また、マニュアルはエクセルで作成しており、一度作成してもその後更新されないことが多かったそうです。
そこで、直感的に理解できる伝達手段として、動画マニュアルを導入。従来のマンツーマン教育から動画を活用した教育に移行し、教育にかかる時間削減や教育の均一化を実現しています。
結果的に、3か月かかっていた新人教育は実質ゼロにすることができ、教育内容の一定化によって、教える側・教えられる側それぞれのストレスが緩和されるなど、全体を効率化させることに成功しました。
「今後は、倉庫や事務所での安全衛生教育や情報セキュリティ教育にも活用していく予定」と語る同社のインタビュー記事は以下からご覧ください。
ここまで紹介した事例を含めて、物流倉庫では動画マニュアルが幅広く活用されています。資料「物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラ(pdf)」では、動画マニュアルで物流の教育現場が改善される理由、活用業務の例などを詳しく紹介していますので、以下の画像をクリックして資料をご覧ください。
>>「物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラ」を見てみる
わかりやすい倉庫マニュアルの作成には「動画」がおすすめ
「倉庫マニュアルの整備によって現場改善を実現した物流企業の事例」で紹介した企業では、倉庫マニュアルを動画で作成していることからも、動画の有効性が伺えます。ここでは、倉庫マニュアルの作成に動画がおすすめの理由について紹介していきます。
伝わりやすい倉庫マニュアルをかんたんに作成できる
紙の場合には文章で手順や動き、ルールなどを伝える必要があり、経験年数やスキルなどが異なる全ての従業員に均一な教育をするのは困難です。
一方、動画を活用することによって、動きや手順などを映像で伝えることができ、紙よりも情報を伝えやすくなります。認識の相違も生まれにくいので教育の均一化にもつながるでしょう。
なお、改善事例で紹介した企業では動画マニュアルの作成に「tebiki現場教育」が活用されており、動画編集機能は知識がなくても直感的に操作ができており、200本以上ものマニュアルを作成しています。
tebiki現場教育について、特徴や機能、メリットなどをより詳しく知りたい方には、サービス資料がおすすめです。3分で理解できる内容になっておりますので、ぜひ以下の画像をクリックしてご覧ください。
担当者の教育工数を大幅に削減できる
紙マニュアルだけで倉庫内の作業を伝えるのは困難なため、基本的にOJTと組み合わせて教育が実施されます。そのため、教育担当者の時間を奪ってしまい、通常業務を圧迫してしまうなどが発生しています。
一方、動画マニュアルでは、映像にあわせて作業を説明する音声も付属しているため、OJT担当者による説明を最小限に抑えられるのが特徴です。また、繰り返し学習ができるので、自発的な学習も促進できます。
作業の標準化が実現する
紙マニュアルの場合、読み手によって解釈が異なってしまうこともあり、理解度や作業内容がばらついてしまう可能性があります。OJTで補ったとしても、担当者ごとに伝える内容が異なることもあるので、標準化するのは困難です。
しかし、動画であれば文書よりもリアルな情報を伝えられるので、認識や理解度のばらつきを防止できます。結果として、作業の標準化につながるでしょう。
倉庫マニュアルを動画で作成することも検討したい方に向けて、動画のメリットや導入ステップを詳しく紹介しているガイドブックを用意しています。以下のリンクをクリックして、ガイドブックをご覧ください。
まとめ:わかりやすい倉庫マニュアルは動画で作成しよう
倉庫内での作業は多岐に渡るので、従業員ごとの理解度の一致や標準化に向けては、マニュアルの整備は欠かせません。なお、マニュアルの作成は紙ではなく、動画の活用がおすすめです。
動画マニュアルを活用することで、紙では伝えにくい動きやニュアンスを鮮明に表現でき、理解度を深めることができます。倉庫マニュアルの作成に動画の活用を検討したい方は、紙と動画の比較や動画マニュアルを導入するステップなどをまとめているガイドブックもご覧ください。画像をクリックすると、ガイドブックをダウンロードできます。