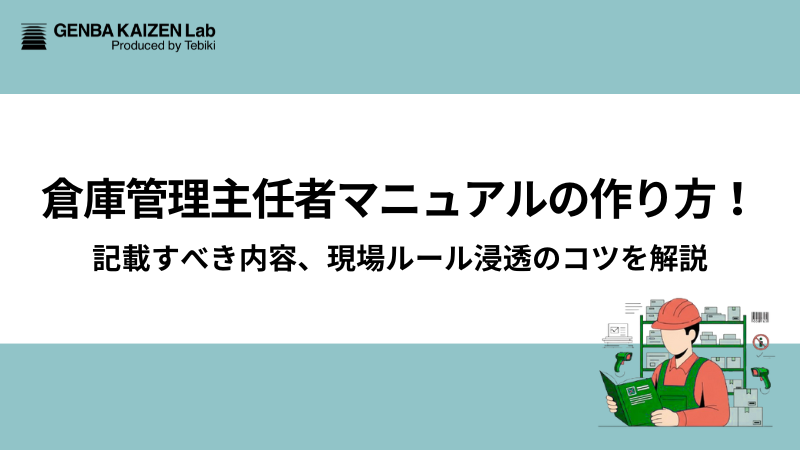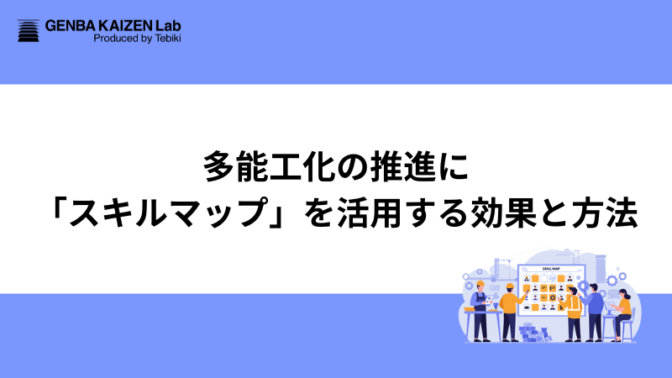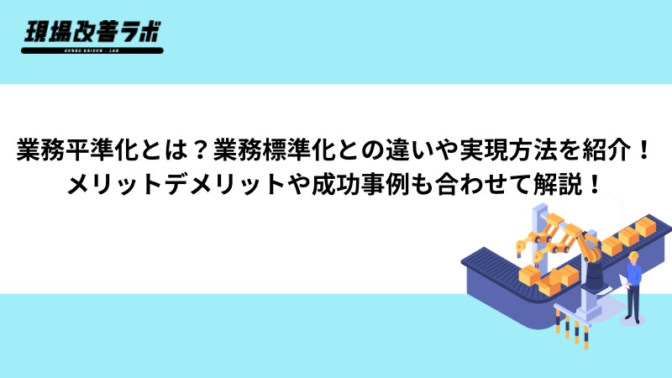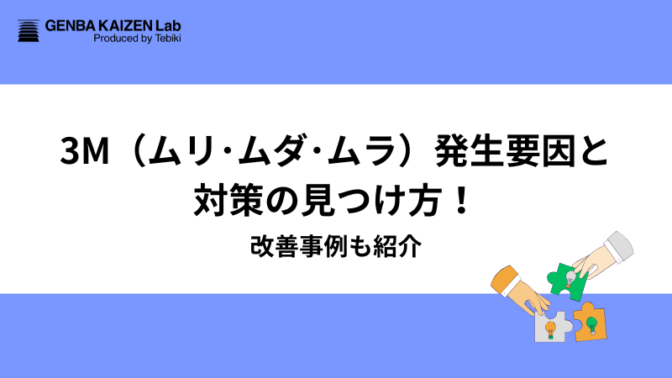わかりやすい倉庫管理主任者マニュアルの作成に役立つかんたん動画マニュアル「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
「倉庫管理主任者とは?必ず選任が必要?」「マニュアルを作成し、属人化を解消したい」そう思う倉庫を運営する物流企業の管理者も多いのではないでしょうか。
本記事では倉庫の現場作業を18年経験した筆者が、倉庫管理主任者の基礎知識から、属人化を解消するわかりやすいマニュアル作りの方法を解説します。是非最後までお読みいただき、健全な倉庫管理と従業員が働きやすい環境づくりの参考にしてください。
なお、本記事の他以下の「物流・倉庫作業のマニュアル作成ガイドブック」内で、マニュアル作成の流れや実際のサンプルマニュアルを展開しております。わかりやすく役立つマニュアル作成に是非お役立てください。
>>【すぐに使える4種類のサンプル付き】 物流・倉庫作業のマニュアル作成ガイドブックを見る
目次
倉庫管理主任者とは?法令に基づく役割と選任要件
まずは倉庫管理主任者の基本情報として、以下の3つを解説します。
- 倉庫管理主任者の選任は倉庫業者の「義務」
- 倉庫管理主任者の選任要件
- 倉庫管理主任者の設置には講習の受講もおすすめ
倉庫管理主任者の選任は倉庫業者の「義務」
「倉庫業法」により、倉庫を運営する企業は倉庫管理主任者を設置し、火災防止や管理業務をさせなければならないことが法令により定められています。
第十一条
倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。
基本は1倉庫につき1人の倉庫管理主任者が必要です。 ただし倉庫業施行規則により、以下の条件を満たしていれば複数の倉庫でも1人の倉庫管理主任者を設置すればいいとされています。
第八条
倉庫業者は、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置かなければならない。ただし、次に掲げる倉庫にあつては、同一の者をもつて当該倉庫に係る倉庫管理主任者とすることができる。
一 同一の敷地内に設けられている倉庫その他の機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫
二 同一の営業所その他の事業所が直接管理又は監督している複数の倉庫(同一都道府県の区域内に存在するものに限る。)であつて、それらの有効面積(国土交通大臣の定める倉庫にあつては、その有効面積又は有効容積を国土交通大臣の定めるところにより換算した値)の合計(認定トランクルームが当該複数の倉庫に含まれる場合には、当該認定トランクルームに係る床面積の合計を除く。)が国土交通大臣の定める値以下であるもの
正しく理解し、必要に応じた人数の倉庫管理主任者を設置しましょう。
倉庫管理主任者の選任要件
倉庫管理主任者は誰でもいいわけではなく、倉庫業施行規則第9条で定められた以下の要件を満たしたものでなければなりません。
- 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
- 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
- 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
- 国土交通大臣が第1号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
「倉庫の管理の業務」とは、次章で紹介する「火災・労災防止のための管理」や「適切な荷役業務の管理」を指します。すでに運用している倉庫であれば、該当者がいるか確認しておきましょう。
倉庫管理主任者の設置には講習の受講もおすすめ
新しい倉庫を立ち上げる際に、実務経験を持つ従業員がいないこともあると思います。 そんな時は先ほど解説した選任要件にもあるように、倉庫に関する講習を受講し、修了しましょう。
ちなみにこちらは国家資格ではなく、あくまでも倉庫管理主任者の要件を満たすためのものです。 講習の詳細や開催日時については、一般社団法人日本倉庫協会「倉庫管理主任者講習について」を参考にしてください。
次章では「倉庫管理主任者は具体的に何を行う?」という疑問にお答えします。
倉庫管理主任者が担うべき4つの仕事内容
倉庫管理主任者が具体的に何をすべきか、その業務内容は倉庫業法施行規則の第9条の2で明確に定められています。国土交通省「倉庫管理主任者マニュアル」に基づき、その4つの主要な業務を解説します。
倉庫管理主任者が担う業務領域は広く、項目も複雑なものが多いため「わかりやすいマニュアルをいかに作成できるか?」が円滑な業務を大きく左右します。
以下の「物流・倉庫作業のマニュアル作成ガイドブック」内では、マニュアル作成の流れや実際のサンプルマニュアルを展開しております。わかりやすく役立つマニュアル作成に是非お役立てください。
>>【すぐに使える4種類のサンプル付き】 物流・倉庫作業のマニュアル作成ガイドブックを見る
①倉庫の火災防止のため施設を管理する
主に倉庫の建物や設備(ハード面)のメンテナンスや、火災などによる事故を予防するための管理業務全般です。 例として以下のような点検や管理を行います。
- 屋根や壁、床などの破損状況の確認
- 防火シャッターや防火扉の動作確認、および閉鎖障害となる物品が置かれていないかの点検
- 消火設備(消火器、屋内消火栓など)や火災報知器が正常に機能するか、適切に配置されているかの確認 など
このように倉庫という「ハコ」そのものと、防火・防災設備の管理が第一の業務です。
②適切な保管や荷役業務を管理する
倉庫内の保管業務や、荷役に使用する設備(ソフト・運用面)の管理です。 以下のような点を確認します。
- 保管場所が適切か(定位・定品・定量=3定管理の徹底、危険物の隔離など)
- 保管ラックの歪みや破損、最大積載荷重が遵守されているか
- 保管されている貨物(寄託物)に損傷や変質、水濡れなどがないかの確認 など
また、フォークリフトやコンベアといった荷役機器の日常点検や、適切な運用がなされているかの管理も含まれます。 ここに料金の設定や営業活動といった経営に関することは含まれません。
効果的なフォークリフトの安全教育への取り組みにご興味がある方は、以下のリンクから資料をダウンロードし、詳細をご覧ください。
>>資料「動画マニュアルを活用したフォークリフトの安全教育・対策事例」をダウンロードする
③労働災害の防止のため安全体制を構築する
倉庫内で働く人々の安全を守り、労働災害を防止するための体制構築も倉庫管理主任者の重要な業務といえます。 たとえば、以下のような安全管理活動を行います。
- 作業員の健康状態や疲労度の把握
- フォークリフトの走行速度制限や、歩行者通路との交差ルールの遵守
- クレーン作業時など、吊り荷の下に作業員が立ち入っていないかの監視 など
安全管理も倉庫管理主任者の大切な業務です。近ごろ、安全管理に「動画」を採用し、職場の環境改善に成功する企業が増えています。その理由が気になる方や実際のサンプル動画を見たい方は以下のリンクから資料をダウンロードし、ご確認ください。
>>資料「~製造業・物流業の事例から学ぶ~動画マニュアルを使った安全教育の取り組みと成果」をダウンロードする
④現場従業員への研修を企画し実施する
正社員やパート、派遣・スポット作業員といった雇用形態にかかわらず、現場で働くすべての従業員に対し、安全かつ効率的に働くための教育訓練を企画し、実施するのも業務の1つです。 例として以下のような内容が挙げられるでしょう。
- 正しい荷物の取り扱い方法や保管ルール
- 5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の徹底、特に清掃による安全確保の重要性
- 倉庫内外の巡視点検の方法や、ヒヤリハット報告の重要性
このように、倉庫で働く上での基本的なルールやノウハウを伝え、現場全体の安全意識と作業品質を高めます。なお、訓練は過去の事故やヒヤリハット事例を利用すると効果的です。「使ってみたい」という方は、以下の資料を是非ご活用ください。
>>資料「イラストでわかりやすい!報告から教育まで行えるヒヤリハット事例・対策集」をダウンロードする
次は属人化を防ぐため、これらの業務をマニュアル化する際に記載しておくべき内容を解説します。
【チェックリストに】倉庫管理主任者マニュアルに記載すべき内容
前章で倉庫管理主任者の4つの主要業務を解説しましたが、それらを確実に実行するには一つひとつの行動を細かく記したマニュアルの作成がおすすめです。 マニュアルがあれば誰が点検しても確認漏れがなくなり、人によるバラつきを防げるため結果として属人化を解消できるでしょう。
ここでは、国土交通省「倉庫管理主任者マニュアル」を参照し、マニュアルに記載すべき具体的な項目を大きく以下の4つに分けてご紹介します。そのままチェックリストとしても活用できますので、是非お役立てください。
また、マニュアルの作り方に悩む方には、「そのまま真似できる『見本』付き!業務マニュアルの作り方完全ガイド」がおすすめです。わかりやすいマニュアルの見本やテンプレート、高い教育効果を出すための6STEPなどを掲載しており、「どのように作ればよいかわからない」「作っても現場で使われない」といった課題を持つ方に最適な資料です。
>>そのまま真似できる『見本』付き!業務マニュアルの作り方完全ガイドを見る
①倉庫の建物や設備の管理に関する項目
まずは施設の維持管理に関する内容です。記載したような課題がないか、くまなくチェックしましょう。
関連記事:倉庫管理とは?作業の効率と品質を高める改善方法を解説
①-1:屋根
| 勾配屋根 | ・屋根の棟や軒先の波打ち、小屋組のたわみ ・屋根材(瓦や金属板等)の割れ、破損、ズレ、飛散、塗料落ち、膨れ、変形、錆 ・ 屋根の上の異物・庫内野地板等の雨漏りシミや腐食 |
| 陸屋根 | ・庫内天井(コンクリート)の亀裂や雨漏りシミ ・屋上手すり壁や塔屋基部等の亀裂 ・屋上排水口の詰まり ・屋上の雑草や異物 ・伸縮目地充填材の劣化や破損 |
| 雨樋 | ・たて樋や軒樋のズレ、脱落、破損、塗装落ち、錆 ・樋や溜マスの落ち葉やゴミ詰まり ・壁等の雨水あふれによる濡れ跡 ・樋(庫内露出部)の防露被覆の有無 |
①-2:壁
| 鉄筋コンクリート 補強コンクリート ブロックレンガ 石等の壁 | ・壁面の亀裂(特に開口部四隅) ・仕上げ材の剥離や剥落 ・コンクリートの脱落、鉄筋の露出 ・庫内壁面や床基部の雨漏り跡(シミ) |
| 鉄網モルタル塗りの壁 | ・貨物横圧による壁面の湾曲 ・壁面の亀裂や破損 ・仕上げ材の剥離や剥落 ・内壁や庫内下地の床基部の雨漏り跡(シミ) |
| PC板 ALC板 セメント成型板の壁 | ・壁面の亀裂 ・目地シーリング材の劣化(亀裂や剥離) ・パネル接合目地のズレや隙間 ・庫内壁面や床基部の雨漏り跡(シミ) |
| 金属複合板 石綿複合板の壁 | ・壁面の塗装落ち、錆、亀裂 ・貨物横圧による壁面の湾曲 ・目地シーリング材の劣化(亀裂や剥離) ・パネル接合目地のズレや隙間 ・取付金具やビスの錆による腐食 ・庫内壁面や床基部の雨漏り跡(シミ) |
| スレート板 金属板の壁 | ・壁面の亀裂、割れ、脱落・壁面の塗装落ちや錆 ・フックボルトの錆による腐食 ・パッキングの劣化(やせ縮み) ・庫内下地や床基部の雨漏り跡(シミ) ・床の沈下、波打ち、傾斜(荷の傾き) ・床や梁のたわみ |
①-3:床
- 床や梁の亀裂
- フォークリフト荷役などによる床の振動
- 床仕上げ材の浮き上がり、はく離、鉄筋の露出、発錆
- 落下物等による床の損傷
- 床の磨耗
- 荷重制限表示の有無や位置
①-4:基礎
- 建物全体の傾斜や沈下
- 屋根の棟や軒先の波打ち
- 周辺地盤の亀裂、段差、陥没
- 壁や腰壁内外の亀裂
- 床の亀裂、波打ち、陥没(1階)
- 荷(はい)の異常な傾き
- 骨組みや筋かいの異常変形、はずれ
- 扉やシャッター、窓の建付不良や開閉不良
①-5:出入り口、窓、防潮板
| 出入り口 | ・シャッターや戸の円滑な開閉 ・押ボタンやスイッチ蓋の破損 ・閉鎖時の異常な隙間やがたつき ・円滑な施錠 ・シャッターや戸、枠の損傷や変形(フォークリフト等) ・シャッター降下位置の障害物 |
| 窓 | ・円滑な開閉 ・閉鎖時の異常な隙間 ・円滑な施錠 ・ガラスの破損 ・盗難防止用鉄格子の異常 ・隣接窓の防火戸の異常 ・地窓の防鼠用金網の異常 ・低位置より低い地窓のような防潮設備の異常 ・窓付近の雨漏り跡(シミ) |
| 防潮板 | ・指定設置場所の明記、適切な保管 ・ゆがみのない保管状態 ・付属金物の紛失 ・防潮板や枠の歪み、亀裂 ・ゴムパッキングの劣化、損傷、脱落 ・砂袋等の使用可能な状態での保管 |
①-6:設備
| 換気設備(強制換気) | ・換気の障害物 ・貨物の通風を考慮した積付 ・燻蒸用目張りの除去 ・換気扇の円滑な回転、異常音、振動 ・ルーバーやダンパーの異常 ・換気扇の発錆やほこり付着 ・換気装置起因の雨漏り |
| 排水設備 | ・排水設備からの雨水あふれ ・点検蓋上の障害物 ・排水溝の清掃状況 ・溜ます底の清掃状況 ・排水溝や溜ますの蓋、格子の損傷 ・庫内排水口の防鼠金網の異常 |
| 消火器 | ・規定本数の設置 ・設置間隔(歩行距離20m毎) ・用途適性 ・容器の損傷、ホースの劣化 ・消火剤の有効期限 ・転倒防止措置 ・消火器前の障害物 ・設置位置の適正 ・標識の有無 |
| 消火栓 | ・ホースの損傷や劣化 ・ノズルとホースの接続 ・バルブの水漏れ ・周囲の障害物 ・扉の容易な開閉 ・ホースの整頓状況 ・表示灯の点灯 ・ポンプ室の私物化 ・貯水槽の適量な水量 ・凍結のおそれ |
| 連結送水管 | ・送水口周囲の障害物(使用、消防車接近) ・放水口周囲の障害物 ・収納箱の変形や損傷、扉の開閉 |
| スプリンクラー | ・制御弁前の障害物 ・ヘッド周囲の空間(60cm以上) ・間仕切りや棚等による散水障害 ・凍結のおそれ |
| 不活性ガス消火設備 | ・注意事項の表示 ・避難誘導や立入禁止表示の掲示 ・選択弁や復帰ボタンの定位置 ・操作箱表示灯の点灯 ・避難口の確保 |
| 火災報知設備 | ・電源スイッチ (ON) ・発信器前の障害物 ・定期点検の実施 |
| 誘導灯 | ・ランプ切れ ・カバーの破損 ・誘導灯の見通し ・非常用電源の機能 |
| 避難通路 | ・防火戸の機能 ・避難通路上の障害物(貨物) ・非常灯の機能 ・防火戸閉鎖の障害物 |
| 受変電室の施錠 | ・屋内受変電室の施錠 ・屋外開放型受変電設備の施錠 ・屋外キュービクル扉の施錠 ・盤内への小動物や雑草等の侵入防止措置 |
| 電線 | ・電柱(本柱、支柱、支線)の異常、電線のたるみ ・電線管の損傷や取付部のはずれ ・電線接続部被覆の焼けこげ |
| 分電盤 | ・外部の損傷、腐食、汚損、扉の閉鎖 ・計器類の指示・パイロットランプの点灯 ・異音の発生 |
| 照明設備 | ・不点やちらつき・器具の損傷 ・器具やランプの汚れ ・器具の異常高温や異音 ・照度の確保 |
| 通報、警報、 表示設備 | ・非常ベルや通報器等の異常 |
| その他の設備 | ・避雷装置の損傷や取付ゆるみ ・タコ足配線の有無 |
①-7:定温倉庫
| 出入り口 | ・扉の通常時閉鎖 ・扉の円滑な開閉 ・閉扉時の異常な隙間やがたつき ・開扉時のエアカーテン効果 |
| 床、壁、天井 | ・床や壁、天井のシミ ・壁や天井の断熱材の損傷、剥離 ・断熱材被覆(耐火コート等)の損傷や剥離 |
| 空調・給排水等設備 | ・空調機フィルターの目詰まり ・温湿度記録計の誤差 ・設定温湿度の維持 ・ドレンパンの滞水 ・ドレン管の水漏れ ・異常音や振動 ・空調機電気使用量の変化 ・庫内消火栓配管の結露対策 |
| 電気設備 | ・壁貫通ケーブル周りや配電盤等の結露 |
| 貨物のはい付け | ・貨物と空調機、ダクト、給排水管の接触 ・空調機を塞ぐ高さの荷積み ・貨物と壁面の空間確保 |
①-8:構内
| 野積み倉庫 | ・強固な塀(1.5m以上)での囲い、または白線等での明示 ・照明装置の異常 ・非常ベルや通報器等の異常 |
| 擁壁 | ・亀裂 ・ふくらみ ・石組等のゆるみ ・擁壁上部地表面の亀裂 |
| コンクリート塀など | ・亀裂や破損 ・傾斜 |
| 鉄柵など | ・曲がり、折れ ・塗装落ち、発錆 |
| 舗装 | ・部分的沈下による水はけ不良 ・亀裂、割れ |
| その他 | ・構内の整理整頓、清掃状況 |
②安全衛生に関する項目
続いて、労働災害の防止や安全な作業環境の維持に関する項目です。
関連記事:【安全衛生教育とは?】具体例や種類・特別教育との違い
②-1労災防止
| 作業員の 健康状態チェック | ・準備体操や柔軟体操の実施 ・バランスのとれた食事 ・十分な睡眠 |
| 服装の点検 | ・清潔な作業衣の着用 ・安全帽の正しい着用(あご紐) ・安全靴の靴ひも結束 ・手袋、安全めがね等の着用 ・蛍光チョッキの着用(暗所) ・作業しやすい配置の配慮 ・使用後の原状復帰 |
| はい付け作業 | ・作業前の整地(小石、木片除去)、清掃(水や油) ・荷に応じた、はい付け方法や底長、重ね数や高さの決定 ・荷、方法、器具に応じた通路確保 ・危険時の作業者以外立入禁止 ・荷崩れ防止の固定(ロープ等) ・丸い荷への転がり止め使用 |
| はい崩し作業 | ・中抜きせず上から順に実施 ・受取作業者との声掛けによる受取ミス防止 ・作業後の整理整頓 |
| フォークリフト作業 | ・作業場の歩行通路明示(線引き) ・関係者以外の立入禁止 ・爪やカウンターウエイトへの人乗せ禁止 ・前方見通し不良時の安全注意と対策(誘導者による誘導など) ・制限速度の定め、表示、遵守・安全確実な積付(荷崩れ防止処置) ・道路走行時の表示(パレット装着または先端表示) ・停止4原則の遵守(平地停止、フォークの床面降下、エンジン停止/キー抜き取り、サイドブレーキ/歯止め) ・資格者証所持者による運転(安全衛生法) |
| コンベヤー作業 | ・服装の点検(袖口、裾)・事前点検(スイッチ、コード損傷) ・貨物をコンベヤー中心に積載・運転中のコンベヤーへの人乗り禁止 ・コンベヤーの安全確保・運転開始時の周囲への声掛け ・非常停止装置の場所、操作方法の事前確認 ・漏電防止(枕木使用、湿気回避) |
| クレーン作業 | ・合図は1名で実施(複数人禁止) ・倒壊防止(強固な地盤、アウトリガー) ・関係作業員以外の立入禁止 ・試し吊りの実施 ・合図による巻上げ(玉掛者等の退避確認) ・横引きの絶対禁止 |
| 堕落、転落 | ・適切な保護帽(あご紐方式)の着用 ・積荷やはい上での足下、重心への留意 ・積荷上作業時の安全な位置、姿勢の保持 ・高所作業(2m以上)での防護具、装置の確保 ・トラック作業時の補助ステップ使用 ・作業に必要な照度の確保 ・屋根上作業時の踏み抜き防止措置 |
| 飛来、落下 | ・無理なはい付け、積荷の禁止 ・定められた方法での作業徹底 ・荷崩れ、落下等の危険防止措置と作業中止 ・正しい玉掛け ・吊り荷下への立入禁止 ・コンベヤーの安定確保 ・共同作業時の声掛け確認 ・作業に適した服装(保護帽、安全靴) |
| 転倒 | ・作業場所の整理整頓、環境整備 ・凹凸、軟弱な床での作業方法工夫 ・乗降時の手摺りやステップ利用、足下確認 ・階段昇降時の足下確認、ゆっくり行動 ・共同運搬時の事前打合せ、声掛け |
②-2:火災防止
倉庫は大量の可燃物を保管しており、かつ一般的な建物より開口部が少なく、大きな建物の割に人が少ないのが特徴です。そのため、庫内火災には以下のようなリスクがあることを認識する必要があります。
- 発見が遅れがちである。
- 火災で停電になると庫内が真っ暗になる。
- 初期消火活動や通報が遅れがちである。
- 十分な排煙設備がないと庫内に煙が充満する。
- 熱がこもり庫内が高温化し、フラッシュオーバーやバックドラフトが起こりやすい。
- スプリンクラーや屋内消火栓で太刀打ちできない程度の激しい燃焼、発熱になることがある。
そのうえで下記の項目について確認を行い、安全を確保しましょう。
| たばこによる 火災予防対策 | ・倉庫や周辺の禁煙徹底 ・喫煙の指定場所遵守 ・喫煙所の安全で見やすい場所への設置 ・喫煙所の見やすく明確な表示 ・喫煙所の整理、整頓、清潔の維持 |
| 自然発火による 火災予防対策 | ・危険物(消防法第2条第7項)の危険品倉庫保管 ・商品知識に基づく最適な保管管理 ・商品名や物性の確認・荷姿、性質、数量、倉庫構造を考慮した保管 ・庫内の換気、温度、湿度への注意 ・積付指定(「転倒無用」等)の遵守 |
| 粉塵による 爆発事故予防 | ・粉塵発生の抑制 ・発火源対策(火気使用の厳重取締り) ・人的対策体制の確立 |
| 漏電による火災事故 | ・電気系統設備の定期チェックや計器測定による安全保持 ・分電盤の適正ヒューズ使用 ・簡易ビニールコード等の不使用 ・コードやソケット取付部の熱劣化注意(ショート防止) ・ソケット取付、端子、ハンダ付けのゆるみ注意 ・埋込白熱灯への耐熱電線使用(熱伝導の恐れ時) ・器具内への害虫や害獣の巣防止 |
| 指定可燃物の爆発による火災事故対策 | ・不明な化学製品、薬品の荷主への問合せ ・危険物や指定可燃物の性質熟知と最適な取扱い |
| 自動倉庫の 火災防止対策 | ・火種持込防止(監視カメラやセンサーによる温度、炎チェック) ・スプリンクラー配置や数の再検討、新システム導入 ・内部消火のためのスプリンクラー機能強化 |
| 放火による 火災事故対策 | ・整理整頓による倉庫周囲への可燃物放置禁止 ・軒下パレット等への防災シート被覆(やむを得ない場合) ・無人時の警備体制の万全化 ・ゴミの収集日当日出し(前日出し禁止) ・夜間の倉庫周囲の照明確保 ・塀や門扉等の破損箇所の早期修理 ・夜間駐車車両や荷役機械の燃料管理徹底 |
| その他 | ・不明な化学製品、薬品等の荷主への事前問合せ ・防火戸開閉障害となる物、近辺への物品放置禁止 ・通路、避難路、階段への物品放置禁止 ・入庫時の投げ捨てタバコ火種注意 ・電気器具、配線への接近はい付け禁止 ・自然発火性貨物の温湿度測定、十分な換気 ・粉塵爆燃性貨物の換気注意、十分な清掃 ・危険物、高圧ガスの危険品倉庫保管(数量不問) ・指定可燃物、毒物、劇物の法令適合保管 ・定期的な絶縁点検、ブレーカー点検の実施 ・裸電球の使用禁止(やむを得ない場合は防御設備) ・建物への電線接触注意・庫内火気使用施設の法令適合点検 ・防火戸、防火シャッターの作動点検 ・フォークリフトへの火花防止装置装着 ・消火用水の清潔保持、満水維持 ・業務終了時の倉庫扉完全閉鎖確認 |
③倉庫管理業務の適正な運営に関する項目
営業倉庫として貨物を適正に管理・運営するための項目です。 特に以下の2つは倉庫運営の品質を担保する基礎となります。
- 貨物の守秘義務:貨物について知り得た情報は他へは漏らしてはいけない。
- 善管義務: 保管貨物に対して、その品質や用途に応じて以下について最善の注意を払い、有効適切な保管上の管理を行う。(温度、換気、光線、電気、臭気、ゴミ、塵、汚れ、火、水、風、油、雷電、台風、高波、地震、虫、鼠、爆発物、引火性、浸食性、毒性、その他)
上記を踏まえたうえで、以下の項目を確認しましょう。
| 倉庫内外の巡視 | ・保管貨物特性の作業員全員の理解 ・貨物の変質(濡損、汚損、におい) ・荷造りのいたみ ・保管貨物へのほこり付着 ・換気状況 ・鼠害、虫害のおそれ ・混蔵忌避貨物の同時保管 ・危険物等注意事項の全員への周知 ・屋外(軒下等)への寄託貨物保管 ・パレット積貨物の傾き ・フレコンバッグ積付の安定性 ・パレットサポーター等の安全な積載 ・保管貨物の火災保険付保 ・保管貨物の賠償責任保険付保 |
| 在庫数量管理 | ・荷票等による現物在庫管理 ・入庫伝票と現物の適切照合 ・出庫伝票と現物の適切照合 ・荷主不明貨物の放置 ・事務所内の整理整頓 ・各種帳票の適切ファイリング ・パレット、台木、スキッドの点検 ・パレット木屑、資材くずの片付け ・定期的な倉庫内清掃 ・不用パレットの庫内外放置 ・倉庫周辺の清掃実施 |
| トランクルーム 保管管理 | ・顧客窓口の明確化 ・寄託荷主毎の個別管理 ・寄託貨物の変質 ・施設性能(定温定湿等)の適切維持 ・性能維持設備(空調機等)の定期点検 ・所在不明貨物対策 ・高額品の万全な保管管理 |
| 定温定湿倉庫 保管管理 | ・遮熱装置、防湿装置等の設置 ・湿度計の設置 ・空調機等の適切作動 ・空調機等の定期点検 ・日々の温湿度チェック ・温湿度管理表の記録、保存 |
| 在庫証明の発行 | ・在庫証明発行ルールの整備 ・発行責任者設置と業務全体の監理監督 ・在庫証明書の法的性格等の社内周知 ・作成者、確認者設置による複数チェック ・モデル様式、証明印鑑の制定 ・発行記録簿作成と証明書控え保存 |
| その他 | ・倉庫約款、料金表の店頭掲示 ・倉庫約款、料金表の最新化 |
④従業員教育に関する項目
常駐する作業員だけでなく、臨時の作業員に対しても行うべき教育・訓練の項目です。
④-1:倉庫作業に就く上での心得
前提として、以下の2点に基づいた業務が求められることを理解させることが重要です。
- 入庫時の荷姿、形のまま保管するのは倉庫の務めであり責任。これを承知し日々の作業を行う。
- 満庫時の貨物は高額(何億円)になる。取扱いミスは膨大な損害に繋がるため、寄託者の気持ちで丁寧に保管管理する。
④-2:従業員が徹底すべき項目
| 出勤したら まず行うこと | ・受持倉庫巡回(屋根、壁、庫前、錠鍵、電線等の異常確認) ・庫内巡回(荷崩れ、鼠、虫害、変質、腐敗、漏失、発散等の貨物異常確認) |
| 入出庫作業は 入出庫伝票に従って行うこと | ・伝票無き貨物の入出庫禁止 ・伝票と現物の照合(品名、銘柄、記号、等級、寸法、個数) ・出庫時、引取者からの変更申出は窓口担当者へ連絡(現場での直接交渉禁止) ・貨物異常(破れ、濡れ、汚れ、減量)確認、窓口連絡、入出庫立会い ・荷主、運送業者に関わらず立会い、双方での受渡確認 ・倉荷証券発行貨物への表示札取付け(窓口連絡) ・荷票への都度記入(日付、入出庫数量)、残高明確化、定期的確認 ・はい付け票の紛失防止 |
| 一日の入出庫作業を 終了したら | ・業務日誌等の所定場所保管、窓口担当者への作業内容報告 |
| 保管管理面で 遵守すること | ・貨物特性、倉庫構造、通風等を考慮した最適場所保管 ・はい付け時の乾燥した台木、パレット、スキット使用 ・積付マーク(天地無用、下積無用、転倒無用等)の遵守 ・荷摺無き倉庫での壁もたせ積付禁止(はい崩れ、壁損傷防止) ・熱気を嫌う貨物のはい付け(南側、西側壁から離す) |
| 倉庫内外の整理整頓、清掃に心がけること | ・庫内の入念な整理、整頓、清掃 ・通路清掃に加え、長期保管貨物の塵払い ・破損パレット、荷役機器の放置確認と片付け ・清掃用具の所定場所保管 |
| 倉庫内外の 巡視の励行 | ・倉庫内外の定期的、くまない巡視と下記注意 ・庫内の換気、温度の異常 ・庫内外の整理整頓、清掃状況・建物の損傷 ・貨物の変質、損傷・鼠害、虫害の有無 |
これらの項目を遵守させるにあたり、マニュアルや手順書を作成しても「読まれない」「活用されない」といった背景からルールが形骸化しては元も子もありません。
現場ルールを守らせる作業手順書やマニュアル整備のコツ、ルールを守らせる効果的な方法については以下の資料で詳しく展開しています。
>>“手順書通りにできない”から卒業!現場ルールを守らせる効果的な方法を見る
次の章ではこれらのマニュアルを活用し、法令を遵守しつつ安全な労働環境を実現する具体的な手順をご紹介します。
【4ステップ】倉庫管理で法令遵守・安全な労働環境を実現するための手順
倉庫管理主任者の設置は、法令順守(コンプライアンス)のためだけではありません。 主任者が法令に基づく業務を正しく遂行することは、現場の労働災害を防止し貨物を適切に管理することに直結します。これは従業員が安全で働きやすい環境を実現し、倉庫運営の品質を高めるための重要な取り組みです。
ここでは、法令を遵守しつつ安全な労働環境を実現するための手順を以下の4つのステップでご紹介します。
ステップ①:倉庫管理主任者を選任する
まずは【倉庫管理主任者の選任要件】で解説したように、法令の要件を満たす者を倉庫管理主任者として選任します。 要件を満たす者が自社にいない場合は、国土交通大臣の定める講習を受講させることで要件を満たすことが可能です。
選任後は、主任者がその業務を適切に遂行できるよう、社内での権限や役割を明確にしましょう。また、倉庫業法に基づき、選任(または変更)した際は、地方運輸局長への届出が必要な場合があるため注意が必要です。
ステップ②:倉庫管理のためのマニュアルを作成する
主任者が行うべき管理業務をスムーズかつ漏れなく実施できるよう、前の章でご紹介したチェックリスト項目が網羅されたマニュアルを作成します。国土交通省「倉庫管理主任者マニュアル」を参考にしてもよいですが、最も重要なのは自社の倉庫の実態に合ったマニュアルを作成することです。
ポイントは、主任者だけでなく現場の作業員が見ても理解できるよう「誰でもわかりやすい」マニュアルにすること。これにより、業務の標準化が実現します。
たとえば、総合物流企業である「株式会社近鉄コスモス」は、フォークリフトの始業前点検の方法を動画でマニュアル化しています。
※「tebiki現場教育」で作成
動画なら、実際の動きや確認すべき場所を直感的に理解できます。また、動きを真似するだけでいいため、誰がやっても同じような品質となる「標準化」を実現しています。この動画はかんたん動画作成ツール「tebiki現場教育」で作成されました。
tebiki現場教育についてもっと詳しく知りたい方は、以下のリンクから資料をダウンロードし、詳細をチェックしてください。
ステップ③:定期的に管理監督業務を実施する
マニュアルに基づいた倉庫管理主任者による監督業務(巡視・点検)は、定期的におこなうべきです。一度実施して終わりでは、環境の変化や新たなリスクに対応できず、改善にはつながりません。
国土交通省「倉庫管理主任者マニュアル」では「少なくとも半年ないし1年に1回」の定期的な自己点検が推奨されています。 形骸化させないためにも、「毎月第1月曜日は主任者点検日」「1月と7月は倉庫点検強化月間」といった形で、業務プロセスに組み込み、仕組み化しておくのがおすすめです。
ステップ④:課題を洗い出し、環境を改善し続ける
管理監督業務を実施しても、問題や課題を発見するだけでは、誰もが安心して働ける職場環境はつくれません。原因を特定し、改善を続けることで、はたらきやすい職場を作り上げていきます。
たとえば、点検で「通路に物がはみ出している」という課題を見つけたとします。「なぜはみ出すのか」を分析し、「保管場所のルールの見直し」を行います。
とはいえ、こうした手順がわかっていても、なかなか現場でうまくいかないものです。 次章では、「なぜマニュアルが機能しないのか」その理由を解説します。
倉庫管理主任者用マニュアルが機能しない現場の共通点
倉庫管理主任者マニュアルを作成したものの、うまく活用できていない現場もあります。 そんな現場には、多くの場合以下の3つの共通点が存在します。
- 「作成すること」が目的化し、形骸化している
- 教育者が忙しく、管理主任者への周知にリソースが割けない
- 分厚くわかりづらいマニュアルで、使いづらい
「作成すること」が目的化し、形骸化している
マニュアルを作成すること自体が目的になってしまっているケースです。 行政への提出や監査対応のために「作っただけ」の状態になり、現場では一切使用されません。
倉庫管理の本来の目的は法令を遵守し、従業員が安全に働ける環境を維持することのはずです。マニュアルが現場で使われなければ、その目的は達成できません。
教育者が忙しく、倉庫管理主任者への周知にリソースが割けない
新しく選任された倉庫管理主任者に対し、マニュアルの内容や自社の倉庫管理方針を十分に教育できないケースです。
多くの場合、教育担当者(センター長や物流部門の管理者など)が他の業務に追われて多忙であり、主任者への教育に十分な時間を割けないことが原因となっています。このOJT教育の課題や解決方法について、以下の記事で詳しく解説しています。ご興味がある方は、是非ダウンロードしご覧になってください。
>>関連資料「OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識とは?」をダウンロードする
倉庫管理は職場の安全を守るために不可欠です。重要度が高い業務と捉え直し、優先して倉庫管理主任者と情報を共有する体制を整えるべきでしょう。
分厚くわかりづらいマニュアルで、使いづらい
マニュアルが「分かりづらい」ために、現場から参考にされないケースです。 法令や規則を網羅しようとした結果、辞書のように分厚い文字ばかりのマニュアルになっていませんか。
これでは読もうという意欲が湧かないものです。 結果として、せっかく作成しても現場からは敬遠され、事務所の棚でホコリを被ってしまいます。
これらの「形骸化」「教育リソース不足」「分かりづらさ」といった課題の解決には、「動画」の活用がおすすめです。 次の章でその理由を詳しく解説します。
わかりやすい倉庫管理主任者用マニュアルには「動画」が有効
前章で挙げた「マニュアルが機能しない」という悩みは、以下の3つのメリットを持つ「動画」の活用で解決できます。
- いつでもどこでも見られて形骸化しづらい
- 動画の視聴だけで教育ができるので、本来の業務に集中できる
- 動画データの共有で周知が完了するので、管理しやすく扱いやすい
いつでもどこでも見られて形骸化しづらい
動画マニュアルは、スマートフォンやタブレットさえあれば、見る場所や時間を選びません。 通勤の電車の中や休憩時間中に、各自のスマートフォンで確認するよう共有しておけばよいためです。
辞書のように分厚い紙のマニュアルだと、わざわざ事務所に戻ってページを開こうとは思えず、ついつい後回しになりがちです。 しかし、動画であれば普段テレビや動画配信サービスを見るのと同じ感覚で、必要な箇所をピンポイントで確認できます。この手軽さが、マニュアルの形骸化を防止します。
動画の視聴だけで教育ができるので、本来の業務に集中できる
教育にかかる時間を大幅に削減できるのも、動画マニュアルの大きな利点です。
一度、正しい点検方法や管理手順を動画で作成しておけば、次回以降は「この動画を視聴してください」と指示するだけで、講義やOJTに時間を割かずに済みます。 これにより、教育担当者や倉庫長は本来の管理業務や改善活動に集中できます。
また、教える人によって内容がバラつくこともなくなり、倉庫管理主任者への教育の質を標準化できるため、結果として生産性の向上にもつながります。
動画データの共有で周知が完了するので、管理しやすく扱いやすい
動画データなら、倉庫管理主任者へのマニュアル周知もかんたんです。 作成した動画をクラウドシステムなどを通じて共有するだけで完了します。
たとえば、本社で作成した最新の安全ルールを、離れた場所にある複数の倉庫管理者へ一斉に共有する際も即時に対応可能です。
紙のマニュアルのように「印刷して配布し、古いページと差し替える」といった物理的な管理の手間も発生しません。PCやスマートフォン内で常に最新版が管理されるため、非常に扱いやすいといえます。
「tebiki現場教育」なら誰でもかんたんに動画が作成できる!
「tebiki現場教育」は、動画マニュアルをスマートフォンひとつで誰でもかんたんに作成できるサービスです。
動画作成の機能だけでなく、現場教育で役立つ豊富な機能を備えている点を高く評価されています。
| タスク指示機能 | …閲覧してほしい動画の指示を出せる! 閲覧してほしい動画を指示でき、教育の抜け漏れを防ぎます。目標達成の進捗状況のレポートや早急な対応が求められる動画の閲覧指示を効率的に行えます。 |
| レポート機能 | …教育の進捗状況を見える化! 誰が・いつ・どのマニュアルを閲覧したかをダッシュボードで確認できます。タスク指示を出した動画の進捗状況も可視化され、部署による教育の遅れを防ぎ、目標の進捗の確認を効率化します。 |
| 自動翻訳機能 | …100か国語以上の言語に翻訳可能! 100か国語以上へ翻訳可能なため、各言語ごとマニュアルを個別作成する必要なし。ボタンひとつで、各言語に対応したマニュアルを自動生成できます。外国人を雇用する現場でも目標や行動の水準を安定できます。 |
| テスト機能 | …「理解したつもり」を防ぐ! オリジナルの確認テストを作成し、合格基準の設定も可能。設定したルールや手順の自己流解釈や認識のズレを予防できます。 |
これらの機能を活用すれば、倉庫管理主任者マニュアルはもちろん、その他安全教育や作業手順の教育を効率化できます。「tebiki現場教育」について詳しく知りたい方は、下の画像をクリックしてサービス資料をダウンロードしてみてください。
>>わかりやすい倉庫管理主任者マニュアルが簡単に作れる!「tebiki現場教育」の便利な機能や導入事例を見る
倉庫の安全管理に動画を活用している企業事例
動画を倉庫の安全管理や現場教育に活用し、安全で効率の良い倉庫運営に役立てている企業事例を2つご紹介します。
他にも事例を詳しく見てみたい方は、以下のリンクから別紙の資料をご覧ください。
>>【物流業】動画マニュアルを使った安全・現場教育の取り組みと成果について詳しく見る
アスクル株式会社
まずご紹介するのは、ECサイト「ASKUL」「LOHACO」を運営するアスクル株式会社の事例です。
| 課題 | tebiki現場教育導入後の効果 |
|---|---|
| ・高度に自動化された物流設備(マテハン)のメンテナンス教育がOJTや紙マニュアルでは属人化していた ・教育者によって正確性や習熟度にバラつきがあり、教育漏れが発生していた ・発生頻度の低いトラブル復旧はベテランに依存し、安定稼働(=安全確保)上の課題となっていた | ・新人が正確なメンテナンス業務を習得し、独り立ちまでの期間が半減(半年→3ヶ月) ・動画によりメンテナンス業務が標準化され、属人化を解消 ・スマホで手順を「辞書的」に確認でき、作業頻度の低い業務も正確に実施可能に |
同社では、EC物流を支える高度に自動化された物流設備(マテハン)のメンテナンス業務において、教育の属人化が課題でした。従来のOJTや紙マニュアルでは教育者による正確性にバラつきがあり、特に発生頻度の低いトラブル対応はベテランに依存し、センターの安定稼働(=安全確保)を脅かすリスクとなっていました。
そこで動画マニュアル(tebiki現場教育)を導入し、複雑なメンテナンス手順やトラブル復旧方法を「見える化」。新入社員でもスマートフォンで作業手順を「辞書」のように検索・確認しながら、正確な業務を習得できる体制を整えました。
これにより教育の標準化と効率化が実現し、独り立ちまでの期間が半減。属人的な技術に依存せず、物流センターの安定稼働と安全性を確保する体制構築に成功しています。
>>同社が活用した動画マニュアル「tebiki現場教育」の機能詳細や事例をもっと見たい方はこちらをクリック!
株式会社ロジパルエクスプレス
次にご紹介するのは、倉庫や車両などの自社資産を活用した物流サービスを提供する株式会社ロジパルエクスプレスの事例です。
| 課題 | tebiki現場教育導入後の効果 |
|---|---|
| ・拠点ごとに紙マニュアルやルールが異なり、業務品質や安全手順にバラツキがあった ・ベテランのノウハウが属人化し、安全技術が蓄積・継承されていなかった ・紙マニュアルは検索性やアクセス性が悪く、現場で必要な時に安全手順を確認できなかった | ・動画による安全品質教材を全拠点に配信し、全従業員の安全品質意識を向上 ・現場教育が平準化され、顧客からも品質向上と評価・現場での検索性 ・アクセス性が向上し、トレーナーの負荷軽減と教育コスト圧縮を実現 |
同社では拠点ごとに紙マニュアルの基準が異なり、安全手順や業務品質にバラツキが生じていることが課題でした。例として紙マニュアルでは「台車の荷積みは胸の高さまで」といった安全基準の認識が曖昧になり、荷物落下事故に繋がるケースもありました。またベテランのノウハウが属人化し、安全技術が継承されない点も問題視されていました。
そこで動画マニュアル(tebiki)を導入し、安全管理部が中心となって全社共通の安全品質教材を作成。事故防止強化月間に合わせ、フォークリフトの危険予知トレーニング動画などを全拠点に配信し、全従業員の安全品質意識の向上に取り組みました。
導入後は現場作業員が必要な時に安全手順を動画で確認できるようになり、教育が平準化されました。また、トレーナーの業務負荷を圧迫することなく安全教育を実施できる体制が整い、教育コストの圧縮と安全性の両立を実現しています。
>>同社が活用した動画マニュアル「tebiki現場教育」の機能詳細や事例をもっと見たい方はこちらをクリック!
まとめ
倉庫管理主任者の設置は、法令で定められた倉庫業者の義務です。倉庫設備、火災や労災などの災害予防、従業員への教育などを通じて、安全で働きやすい倉庫をつくります。
そのうえで用意しておくべきなのが「マニュアル」です。詳細な管理方法を解説するマニュアルを作成しておけば、倉庫管理の標準化を実現します。
そのマニュアルをわかりやすくし、安全教育の効果を高めるのに有効な方法として「動画」を紹介しました。中でもおすすめなのが、かんたん動画作成ツール「tebiki現場教育」です。誰でもかんたんに動画の作成ができるため、効果の高い職場の安全衛生活動を実現します。
tebiki現場教育についてさらに詳しく知りたい方は、是非以下の資料をダウンロードいただき、詳細をご確認ください。
引用元/参照元
・e-Gov法令検索「倉庫業法」
・e-Gov法令検索「倉庫業法施行規則」
・一般社団法人日本倉庫協会「倉庫管理主任者講習について」
・国土交通省「倉庫管理主任者マニュアル」