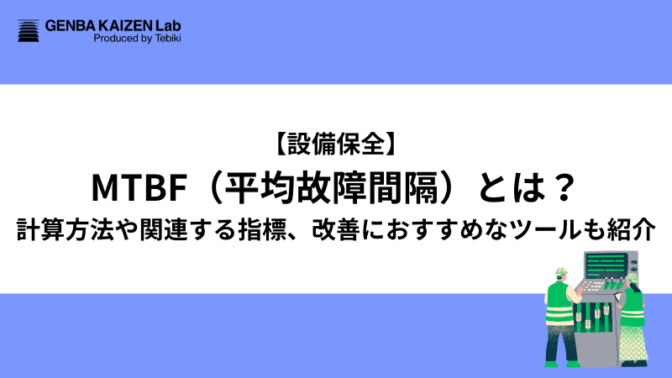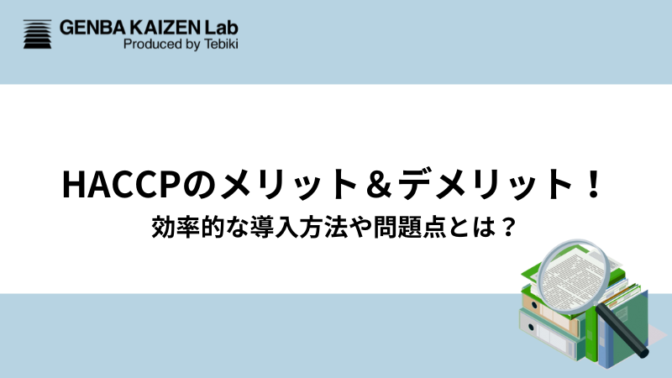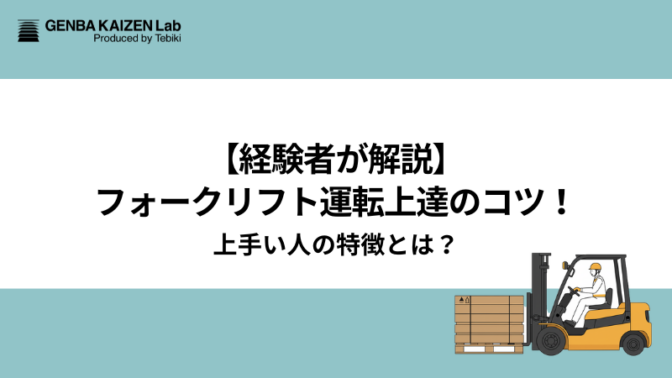かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
物流現場における出荷作業は、顧客満足度や企業経営に直結する重要なプロセスです。しかし、「具体的な手順がよく分からない」「ミスが多くて困っている」などの悩みや疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では出荷作業の基本的な意味や一連の流れ、よくある課題、そして安全かつ正確に作業を進めるための注意点について網羅的に解説します。
加えて、出荷時に課題視されやすいピッキングミスの原因や、現場で成果を上げた改善策を体系的にまとめた資料「誤出荷ゼロへ!ヒューマンエラーによるピッキング作業ミスをなくす具体的な対策と改善事例」もご用意しています。出荷作業の精度向上や現場改善のヒントをさらに知りたい方は、こちらも是非ご覧ください。
>>誤出荷ゼロへ!ヒューマンエラーによるピッキング作業ミスをなくす具体的な対策と改善事例を見る
目次
出荷作業とは?
出荷作業とは、顧客からの注文に基づき、倉庫や物流センターなどに保管されている商品を、ピッキング(選び出し)、検品、梱包し、顧客や指定された配送先へ送り出すまでの一連の作業のことです。
良い商品を作り、効果的なマーケティングを行っても、出荷作業でミスが発生したり、遅延したりすれば、顧客からの信頼を失いかねません。正確かつ迅速な出荷は、リピート購入や企業のブランドイメージ向上にも繋がるため、品質と効率の改善は常に求められます。
物流における出荷作業の役割と目的
物流プロセスは、大きく「入荷」「保管」「ピッキング」「出荷」といった流れで構成されます。出荷作業は、このサプライチェーンにおける最終工程であり、商品をお客様の手元に届けるための重要なバトンタッチの役割を担います。
出荷作業の主な目的は、以下の要素を確実に満たすことです。
- 正確性: 注文された商品を品番・数量ともに間違いなく届ける。
- 品質保持: 商品を適切な状態で、破損なく届ける。
- 納期遵守: 指定された期日までに確実に届ける。
- 安全性: 作業者と商品の安全を確保しながら作業を行う。
これらの目的を達成することが、顧客満足度向上に不可欠です。
「出荷」と混同しやすい物流作業との違い
物流現場では、「出荷」と似たような意味合いで使われたり、混同されたりしやすい用語がいくつかあります。ここで主な用語との違いを明確にしておきましょう。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 出荷作業 | ピッキング、検品、梱包、配送業者への引き渡しまでの一連の倉庫内作業プロセスのこと |
| 発送 | 荷物を送り出す行為、またはその手続きのこと |
| 配送 | 荷物を目的地まで運ぶプロセスのこと |
| 集荷 | 配送業者が荷物を引き取りに来る行為のこと |
| 出庫 | 倉庫から物(商品以外も含む)を出す行為全般のこと |
| 入荷 | 倉庫に商品などを受け入れるプロセスのこと |
出荷作業の基本的なフロー
出荷作業の流れは、扱う商品や企業の業態によって多少異なりますが、一般的には以下のようなステップで進められます。
受注情報の確認
まずは出荷作業のはじめである受注情報の確認です。どの商品を、いくつ、どこへ、いつまでに届ける必要があるのか、といった情報を正確に把握します。多くの場合、基幹システムやWMSに注文データが蓄積されますが、情報に誤りがあると後続のすべての工程に影響するため、データの正確性を担保するのが重要です。
在庫引当
受注情報に基づいて、倉庫内にある在庫から出荷する商品を確保する「在庫引当」を行います。なお、在庫が不足している場合は、欠品処理や顧客への連絡などの対応が必要です。正確な在庫引当は、過剰な出荷や欠品による機会損失を防ぐために不可欠なプロセスといえるでしょう。
ピッキング
ピッキングとは、倉庫内の保管場所を回って指定された商品を集める作業です。
注文ごとに集める「オーダーピッキング」や複数注文分をまとめて集めた後で仕分ける、「トータルピッキング」など様々な方式があります。出荷作業全体の効率を大きく左右する工程であり、移動距離の長さや商品を探す時間が課題となりやすい部分です。商品間違い、数量間違い)が発生しやすい工程でもあるため、正確性とスピードの両立が求められます。
ピッキングミスが発生する原因や改善した事例を読みたい方は、以下のテキストをクリックしてご覧ください。
関連記事:ピッキングミスや数量間違いが多い人の特徴と9つの対策!改善事例もあわせて紹介
検品
ピッキングされた商品が、注文内容と完全に一致しているかを確認する重要な工程が検品です。品番、商品名、数量、外観(傷や汚れがないか)、有効期限などを、ピッキングリストや納品書と照合します。
検品でミスが発生すると誤出荷に直結してしまうため、WMS、ハンディターミナルを導入や作業をマニュアルに落とし込むなどの対策を講じる必要があるでしょう。
梱包
検品を終えた商品を、配送中の衝撃や汚損から守るために箱や袋に詰める作業が梱包です。梱包方法を標準化し、資材の無駄をなくすこともコスト管理の観点から重要と言えるでしょう。
なお、商品のサイズや形状、壊れやすさに合わせて適切なサイズの段ボール箱や袋を選定したり、納品書や請求書、お礼状、販促用チラシを同梱するなどのも重要です。
仕分け・積み込み
出荷する荷物を、配送先や輸送ルート、利用する運送会社ごとに分類する作業が仕分けです。仕分けられた荷物は、トラックなどの輸送車両へ積み込まれます。
積み込み作業では、荷物の形状や重さを考慮し、荷崩れが起きないように安定した状態で積む必要があります。重いものを下に、軽いものを上に積むのが基本です。また、フォークリフトなどの荷役機器を使用する場合は、周囲の安全確認を徹底し、事故防止に努めなければなりません。
出荷確定・完了報告
荷物を配送業者へ引き渡し、トラックが出発したら、WMSなどのシステム上で出荷実績を登録(出荷確定処理)します。これにより、在庫データが更新され、売上計上や請求処理に必要な情報が関連部署に連携されます。
正確な実績登録は、適切な在庫管理と円滑なバックオフィス業務のために不可欠です。必要に応じて、出荷完了の報告を関係者に行います。
ここまでに紹介した一連の倉庫内出荷作業を改善し、効率化したい方は、効率化に向けた12のアイデアを紹介している以下のテキストをクリックしてご覧ください。
関連記事:倉庫作業の効率化!15の改善アイデアと成功事例を紹介
出荷作業に必要とされる主なスキル
出荷作業の一連の流れと業務内容に触れたところで、ここからは出荷作業に求められるスキルや能力について解説します。向いている人の特徴にもなりうる内容だと思いますので、参考にしてみてください。
ただ、こうしたスキルは個人の資質や経験に頼りがちで、「注意してもピッキングミスが減らない」「属人化で品質が安定しない」といった課題も少なくありません。
実は今、物流現場では個人の努力に頼るのではなく、業務手順そのものを“仕組み化”して再発を防ぐ取り組みが注目されています。
ピッキングミスの原因分析から標準化の進め方、そして現場教育の成功事例までを詳しくまとめた資料を以下で紹介しています。現場のミスを根本から改善したい方は、是非ご覧ください。
>>誤出荷ゼロへ!ヒューマンエラーによるピッキング作業ミスをなくす具体的な対策と改善事例を見る
正確なピッキングスキル
出荷作業の核となるのが、指示された商品を正確に選び出すピッキング作業です。膨大な商品の中から、品番や数量を間違いなく特定し、集めるためには、注意力と確認を怠らない姿勢が不可欠です。
類似した品番やパッケージの商品も多いため、細部まで注意深く確認する能力が求められます。また、ハンディターミナルなどの機器を正確に操作するスキルも、ミスなく作業を進める上で重要です。
ピッキングミスを減らす対策やミスの解消を実現した企業事例などを詳しく知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。
関連記事:ピッキングミスや数量間違いが多い人の特徴と9つの対策!改善事例もあわせて紹介
豊富な商品をさばける作業スピードの速さ
多くの場合、出荷作業には納期があり、限られた時間内に多くの商品を処理する必要があるため、ひとつひとつの作業を効率的かつ迅速に進行・処理するスキルが求められます。単に急ぐだけでなく、正確性を保ちながら作業をスピーディに進める工夫やコツも自発的に学んでいかなければなりません。
危険を感知する安全意識
倉庫内にはフォークリフトが走行していたり、高所に商品が積まれていたり、重量物を扱ったりと、様々な危険が潜んでいます。そのため、周囲の状況に気を配り、危険な箇所や状況を事前に察知する安全意識の高さが不可欠です。定められた安全ルールを遵守することはもちろん、5S活動を心がけ、危険な行動を避ける意識が求められます。
なお、安全教育はKYT(危険予知訓練)や危険な状況の模擬体験など、様々な方法があります。安全教育の実施方法や教育方法などについて詳しく知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。
関連記事:職場の「安全教育」とは?意識向上の具体例や資料集も
商品の保管場所を把握する空間認識能力
広大な倉庫の中から目的の商品を迅速に見つけ出すためには、倉庫内のどこに何が保管されているかを把握するロケーション管理のスキルが役立ちます。
棚番やエリア区分などを理解し、効率的なルートでピッキング場所へ向かうための空間認識能力があると、作業時間を大幅に短縮できます。これは経験によっても向上するスキルです。
立ち仕事や重い荷物の運搬に対応できる体力
出荷作業は、倉庫内を歩き回ったり、長時間立ちっぱなしで作業したりすることが多い仕事です。また、扱う商品によっては、ある程度の重量物を持ち上げたり運んだりする場面もあります。
そのため、これらの作業に耐えうる基本的な体力が必要となります。もちろん、無理は禁物であり、適切な休憩や補助具の活用も重要です。
単純な反復作業を継続できる集中力
ピッキング、検品、梱包といった一連の作業は、反復的な動作が多く含まれます。
同じような作業が続く中でも、注意力を維持し、集中力を切らさずに正確さを保ち続ける能力が重要です。特に、作業終盤の疲れてきた時間帯でも、ミスなく丁寧に作業をやり遂げるための持続力が求められます。
出荷作業で発生しがちな課題とその根本原因
多くの現場で日々行われている出荷作業ですが、その裏では様々な課題が発生しています。ここでは、よく聞かれる代表的な課題と、その背景にある根本原因を探ってみましょう。
誤出荷や数量間違い、商品破損などのミスが多い
出荷作業におけるミスは、顧客満足度とコストに直結する深刻な問題です。誤出荷や商品破損が発生すると、クレーム対応や返品・再発送の手間とコストを発生させ、企業の信頼を大きく損ないます。特にピッキング段階では、類似品の取り違えや数量の数え間違いが起こりやすく、検品での見落としもミスに繋がります。
これらのミスは、在庫差異の原因ともなり、正確な在庫管理を妨げる要因にもなります。品質に関わるミスの削減は、出荷業務における最優先課題の一つと言えるでしょう。誤出荷が発生する原因や出荷ミス対策などを詳しく理解したい方は、下をクリックして記事をご覧ください。
出荷作業に時間がかかる
出荷作業全体のリードタイムが長く、生産性が上がらないという悩みも現場では根深い課題です。特にピッキング工程では、商品のロケーションが不明確で探す時間が長引いたり、倉庫内の動線が悪く移動距離が過大になったりすることで、多くの時間が浪費されがちです。
また、検品や梱包といった工程においても、手順が標準化されていなかったり、手作業が多くシステム化が進んでいなかったりすると、作業に時間がかかり、ボトルネックとなることがあります。こうした非効率な作業の積み重ねは、納期遅延による顧客満足度の低下や、残業時間の増加による人件費の圧迫といった問題を引き起こします。
出荷作業に潜んでいる課題や改善・効率化する流れを理解したい方は、下のテキストをクリックして関連記事をご覧ください。
労働災害が発生しやすい
重量物の取り扱いやフォークリフトなどの車両が行き交う物流現場では、常に労働災害のリスクが存在します。通路に置かれた障害物による転倒、高所からの墜落、荷崩れ、車両との接触事故などは、実際に起こりうる重大な事故です。
これらのリスクは、5Sの不徹底、安全ルールの不徹底や教育不足など、様々な要因によって高まります。ひとたび事故が発生すれば、従業員の負傷や生命に関わる事態に至るだけでなく、生産活動の停止、企業の社会的信用の失墜、損害賠償など、計り知れない損失をもたらします。
出荷作業の生産性を向上させる方法
ミスの削減と同時に追求したいのが、出荷作業の効率化による生産性向上です。ここでは、現場の生産性を高めるための具体的な改善アプローチを5つ紹介します。
出荷作業のマニュアルを整備する
出荷作業マニュアルを整備すれば、作業方法やルールなどの基準を統一でき、従業員によって理解度や作業内容のばらつきを抑えることができます。また、新人社員でも一定レベルの出荷作業が行える夜になるので、教育コストの削減にもつながるでしょう。
「マニュアル=紙」のイメージが強いかもしれませんが、電子化してパソコンやタブレットなどの端末で閲覧している企業も多くあります。電子化することで、検索性や更新性が高く、何よりもかさばらないので管理コストも抑えられます。
なお、電子マニュアルの1つとして、動画マニュアルを活用している企業も物流業界では多い傾向です。下の資料では、物流業界での活用事例や動画マニュアルのメリットなどを紹介しています。下のテキストをクリックしてご覧ください。
>>「物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラ」を見てみる
作業手順の見直しと標準化
現状の作業を分析し、最適な手順を定め、それを全員が守れるように標準化することが改善の基本です。
まずは、現状の作業分析を実施して、各工程にかかる時間や作業員の動きを客観的に把握しましょう。ストップウォッチで時間を計測する、作業風景を動画で撮影して分析するなどの方法があります。これにより、どこに無駄な動きやボトルネックがあるかが見えてきます。
分析した情報を基にして、作業手順書の新規作成や見直しなどを実施することで、標準化や安全意識の向上にもつながるでしょう。出荷作業マニュアル作成ポイントはこちらの記事を参考にしてください。
なお、熟練者の持つ出荷作業における「カン・コツ」を効果的に伝え、形骸化させない手順書の作成ノウハウをまとめた資料をご用意しています。 下の画像をクリックして、ダウンロードしてみてください。
倉庫レイアウトと動線の最適化
倉庫内のレイアウトや作業員の動線は、作業効率、特にピッキング時間に大きく影響します。ABC分析などを活用し、出荷頻度の高い商品を取り出しやすい場所に配置するなど、ロケーション管理を最適化しましょう。
また、商品特性や物量に合わせてピッキング方式(シングル、マルチオーダー等)を選定し、移動距離が最短になるようなルートを設定することも重要です。
システム導入による効率化・精度向上
WMS(倉庫管理システム)や各種デバイスを導入することで、作業の自動化、ペーパーレス化、情報管理の精度向上を図り、大幅な効率化を実現できます。
WMS(倉庫管理システム)は、在庫管理から作業指示、実績管理までを一元化し、業務全体の最適化を支援します。ハンディターミナルやスマートデバイスは、バーコード活用によるペーパーレス化とリアルタイムな情報連携を実現し、入力ミスを削減します。
出荷作業の改善に「動画マニュアル」が効果的な理由
「出荷作業の生産性を向上させる方法」でも紹介したように、出荷作業の標準化や教育において、動画マニュアルは多くのメリットがあります。ここでは、動画マニュアルが出荷作業の改善に効果的な具体的な理由を紹介していきます。
教育担当者の負担を軽減できる
動画マニュアルを活用することで、新人教育や手順変更時の説明にかかる教育担当者の負担を大幅に軽減できます。一度質の高い動画を作成すれば、同じ説明を何度も繰り返す必要がなくなります。新人は自分のペースで動画を見て予習・復習できるため、OJTではより実践的な指導や質疑応答に時間を割くことが可能になるでしょう。
これにより、指導時間の短縮と教育品質の均一化が実現し、教育担当者は本来の管理業務や改善活動により多くの時間を充てられるようになります。
1つ事例を紹介します。マンツーマンでの新人教育に負担を抱え、指導者の日常業務に影響を及ぼしていたソニテック株式会社では、課題を解決すべく動画マニュアルを導入。マンツーマン教育から動画を活用した教育へシフトし、3か月かかっていた教育時間が実質ゼロになったと動画マニュアルの効果を実感しています。
同社の事例を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:3ヶ月間の直接指導を動画マニュアルで完全に置き換え、業務の効率化を実現
外国人労働者・派遣社員の即戦力化が実現する
言語や文化の異なる外国人労働者や、短期間で作業を覚える必要のある派遣社員にとって、動画マニュアルは非常に有効です。視覚的に作業の流れや注意点を伝えられるため、言葉だけでは理解が難しい内容も直感的に把握できます。
字幕機能や自動翻訳機能を活用すれば、言語の壁をさらに低減できます。自分のスマートフォンなどで時間や場所を選ばずに繰り返し学習できるため、短期間でのスキル習得を促し、多様な人材の早期戦力化を実現します。
物流企業ではありませんが、外国人教育が動画マニュアルを通じてうまくいっている事例として、株式会社Archemの取り組みが挙げられます。同社はアメリカのテネシー工場で動画マニュアル「tebiki現場教育」を活用し、モニターで繰り返し再生できる体制を構築し、いつでも誰でも閲覧できる環境を整備。常時作業内容が確認できる動画再生によって品質向上を実感しています。
以下の資料では、外国人労働者を抱える現場の課題や課題を解消する方法など、外国人労働者への「伝わらない」に動画マニュアルを活用した事例を紹介しています。以下の画像をクリックして資料をご覧ください。
紙よりも効率的に作成・更新できる
従来の紙マニュアル作成に比べ、動画マニュアルは効率的に作成・更新できる点も大きなメリットです。スマートフォンのカメラで作業風景を撮影し、専用ツールやアプリを使えば、専門知識がなくても容易にテロップ挿入や簡単な編集が行えます。
一度作成した動画はテンプレートとして活用したり、部分的に修正したりすることも簡単です。現場で手順変更があった際も、該当箇所を再撮影して差し替えるだけで迅速に更新でき、常に最新の正しい情報を現場に共有することが可能になります。
動画マニュアルを活用して出荷作業の改善につなげたい場合には、動画マニュアルのメリットや期待される教育効果などを詳しくまとめた資料「動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法」をご覧ください。以下の画像をクリックするとダウンロードできます。
まとめ:出荷作業は物流工程における重要なプロセス
出荷作業は、顧客との最終接点であり、企業の信頼性を左右する重要な業務です。その精度と効率を高めることは、顧客満足度の向上だけでなく、コスト削減や現場の生産性向上にも直結します。
一連の流れやポイントを踏まえ、最適な出荷作業ができるような環境の構築を進めていきましょう。なお、出荷作業に課題感を抱えている方、生産性を向上させたい方には、教育担当者の負担軽減・新人の即戦力化につながる動画マニュアルの活用がおすすめです。以下の資料では、物流工程の生産性を向上に動画マニュアルが役立つ理由や参考事例を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。