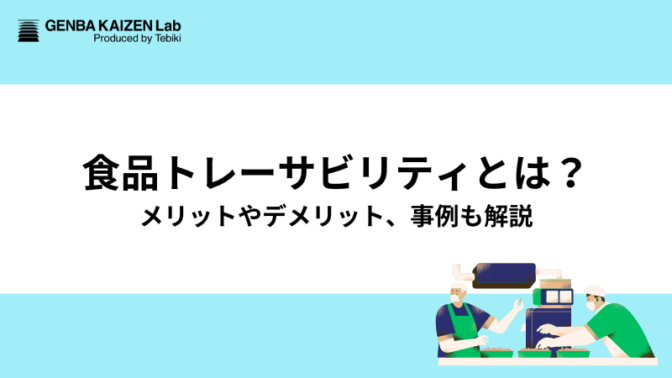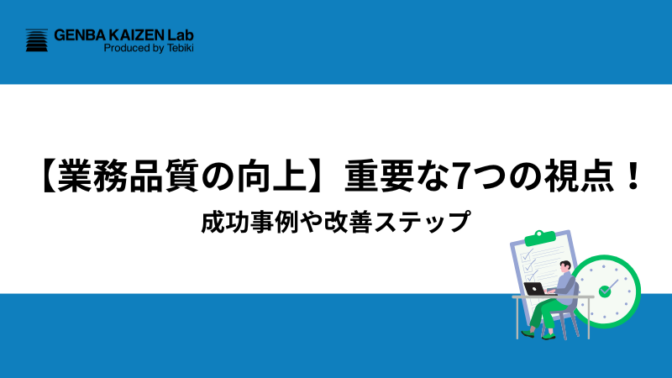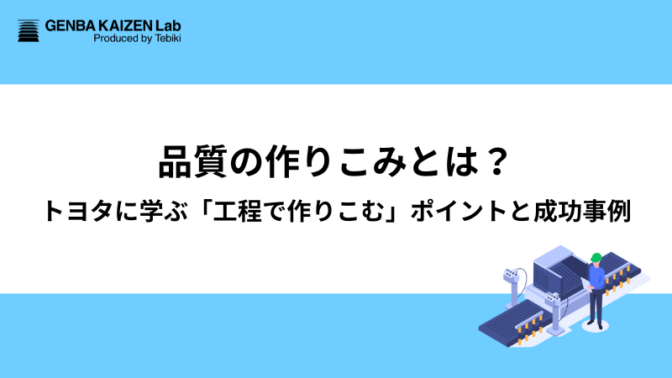かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
物流現場における「ピッキング作業」は、倉庫全体の生産性や正確性を左右する重要な工程です。しかし実際には、作業ミスや移動のムダ、属人化による教育の非効率など、さまざまな課題に悩まされている現場も少なくありません。
そこで本記事では、実際にピッキング作業を改善した企業の事例をもとに、課題の乗り越え方をわかりやすく解説します。「作業手順の見直し」「教育体制の整備」「システム導入」「レイアウト最適化」など、現場ですぐに活かせる改善手法を具体的に紹介しています。
しかし、特に「作業ミス」や「属人化」といった課題は個人の「注意」や「再教育」に頼るだけでは、根本的な解決が難しいものです。重要なのは手順や基準そのものを“仕組み化”し、誰が作業しても同じ品質を再現できる状態を整えることです。
ピッキングミスの原因分析から標準化の要点、そして実際の改善事例までをまとめた資料を以下で紹介しています。現場改善のヒントを求める方は是非ご覧ください。
>>誤出荷ゼロへ!ヒューマンエラーによるピッキング作業ミスをなくす具体的な対策と改善事例を見る
なぜピッキング改善が必要なのか?よくある課題とは
ピッキング改善は倉庫の生産性・正確性・コスト効率を大きく左右する重要なテーマです。近年、EC市場の急拡大や消費者ニーズの多様化により、物流現場には「多品種・少量・短納期」への対応が求められています。その中でもピッキング作業は全工程の中で特に人手がかかりやすく、業務全体のボトルネックになりがちな部分です。
しかし現場では、以下のような具体的な課題が立ちはだかっています。
- 作業効率の低さ(生産性の問題)
- ミスの多発(品質の問題)
- コストの高さ(費用の問題)
- 作業の属人化
- 教育・研修の負担
こうした課題、特に「ミスの多発」や「属人化」は、根が深い問題です。 「何度注意しても同じミスが起きる」「ベテランが辞めると品質が保てず、新人の教育コストばかりかさむ」…そんな悩みを抱えていませんか?
ヒューマンエラーを個人の資質の問題にせず、誰もが正しい手順で作業できる「標準の型」を作ることが、誤出荷ゼロへの近道です。
「なぜミスは起きるのか?」という原因の深掘りから、現場にルールを浸透させる具体的なステップ、そして実際に品質改善に成功した企業の事例までを下記の資料に凝縮しました。 品質と教育の課題を本気で解決したい方は是非ご一読ください。
>>誤出荷ゼロへ!ヒューマンエラーによるピッキング作業ミスをなくす具体的な対策と改善事例を見る
作業効率の低さ(生産性の問題)
倉庫内の動線が最適化されていない、商品ロケーションがわかりにくいといった理由で、作業員が必要な商品を探すのに時間がかかってしまうケースがあります。結果的に、移動距離が長くなり、1件あたりのピッキングに必要な時間が増加し、生産性が低下してしまいます。
ミスの多発(品質の問題)
品番や数量の取り違え、破損などによるピッキングミスが発生すると、誤出荷によって顧客からの信頼を失うリスクがあります。特に新人や経験の浅い作業員に多く見られる傾向があり、再発防止には作業手順の明確化や教育体制の整備が欠かせません。
ピッキングミスや数量間違い・誤出荷の対策や改善事例については、以下の記事でも紹介しています。あわせてご覧ください。
▼関連記事▼
ピッキングミスや数量間違いが多い人の特徴と9つの対策!改善事例もあわせて紹介
誤出荷ゼロを目指す!出荷ミスの原因と6つの対策例
コストの高さ(費用の問題)
人手に依存したピッキング作業は、人件費がかさむうえにミスによる返品・再配送コストも発生しやすく、全体として物流コストの増加を招きます。繁忙期などには短期雇用の増加により、さらなる教育コストも必要になります。
作業の属人化
現場でよくあるのが、ベテラン社員に業務が集中し、新人はなかなか戦力化できないという構造です。結果として、作業品質にばらつきが生じたり、特定の人に頼らざるを得ない体制が確立されてしまいます。これでは業務を標準化できず、長期的な改善にもつながりません。
教育・研修の負担
せっかく整備したマニュアルが読まれない、理解されにくいといった声は物流現場で多く聞かれます。結果的にOJTやマンツーマン指導に過剰依存した現場教育にならざるを得ず、教育指導者の教育品質にバラつきが生じるケースがあります。
このように現場では、教育品質の安定と効率化が大きな課題となっています。
こうした課題に共通しているのは、「業務の属人化」と「標準ルールの不在」です。それら2つの課題解消として重要な打ち手が「業務の標準化」です。業務手順を可視化・明文化し、誰が作業しても同じ結果が出せる状態をつくることが、ピッキング改善の第一歩となります。標準化の重要性や具体的な推進方法については、以下の資料で詳しく解説しているので、わせてご覧ください。
>>>「企業が業務標準化に着手するべき理由(pdf)」を見てみる
難しい外国人教育
外国人労働者の割合が増えてきている物流現場では、外国人教育も課題に上がることが多いです。母国語マニュアルを1から整備するわけにはいかないものの、とはいえコミュニケーションも難しいので直接指導ではなかなか教育が行き届かず、外国人教育の効率的なやり方を模索している現場担当者は少なくありません。
そこで昨今、外国人教育に取り入れられているのが「非言語マニュアル」の導入です。日本語を扱わずとも作業手順を教育するには、「一目見ればある程度の作業手順が分かるマニュアル」が必要になります。例えば「動画」や「映像」を用いたマニュアルです。
外国人教育に動画マニュアルを導入する物流現場は珍しくなく、多くの導入事例が存在しています。以下の資料「外国人労働者に「伝わらない」を解決した動画マニュアル活用事例集(pdf)」では動画の導入イメージや事例を紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。
【事例で紹介】ピッキング改善の具体的な方法
ここからは、ピッキング改善の具体的な方法を改善事例を交えながら解説します。
なお倉庫や物流現場では、ピッキングミス対策や改善を「注意」や「再教育」ではなく、手順や基準を“仕組み化”して再発を防ぐ取り組みが広がっています。作業ルールを明確にし誰が行っても同じ品質を再現できる状態を整えることが、ヒューマンエラーの抑止に直結します。
ピッキングミスの原因から標準化の要点、改善事例までをまとめた資料を以下で紹介しています。現場改善のヒントを求める方は是非ご覧ください。
>>誤出荷ゼロへ!ヒューマンエラーによるピッキング作業ミスをなくす具体的な対策と改善事例を見る
作業手順の見直し・標準化
ピッキング改善において、最初に見直すべきは「作業手順の標準化」です。
マニュアルやルールが統一できていないと、作業の内容にバラつきが出てしまいます。作業のバラつきはミスの原因となり、結果的に生産性や信頼性の低下を招きます。
例えば、株式会社ロジパルエクスプレスでは、拠点ごとのマニュアルやルールが統一されておらず、業務品質や作業手順にバラつきがあることが課題でした。また、統一化されていないことでやるべき作業が抜けてしまうこともありました。
そこで、各拠点で苦労して作成したマニュアルの活用を進めるためにツールやアイデアを検討し、動画マニュアルの導入に辿り着いたそうです。動画マニュアルでは、紙のマニュアルよりも情報が伝わりやすく、人によって理解にバラつきができることも少なくなりました。さらに、承認にかかる時間も短縮できたことで、拠点ごとのマニュアルではなく、統一したマニュアル作成も可能になっています。
つまり、誰が作業しても同じ成果が出せるように「作業手順の標準化」を進めることが、改善の第一歩となります。
同社の詳細な改善事例は、以下のインタビュー記事からご確認いただけます。
インタビュー記事:動画で全拠点の安全品質意識の向上と業務ノウハウの可視化を達成
人材育成と作業の標準化による改善
ピッキング改善は「仕組み」だけでなく、「人」の育成も欠かせません。
どれだけ優れたシステムやマテハンを導入しても、それを使いこなすのは作業者自身です。しかし実際には、OJTによる教育に限界がある現場も多く、教える側の負担や教え方のばらつきに課題を感じる声がよく聞かれます。
例えばソニテック株式会社では、荷主や便によって異なるピッキング作業手順の教育に大きな課題を感じていました。異なるピッキング作業を覚えてもらうことは非常に難易度が高く、効率的な教育を模索していたのです。
荷主や便によってピッキング作業が異なるため、その内容を教え、覚えることは大きな負担です。多様なピッキング方法を正確に理解し、迅速に作業できるようにするには、教育と実践的な経験が不可欠です。マンツーマン指導を行っているものの、作業内容の正確な伝達が難しく、ミスが発生することもしばしばあります。例えば、「商材の表面にシールを貼る」という指示が、誤って「横面にシールを貼る」という行動になるなど、指示の不明瞭さが課題となっています。
そこで直接指導やマンツーマン指導を主軸としたOJT教育を展開しましたが、教育担当者ごとの教え方のバラつきが生じ、なかなか新人作業員のスキルが向上しない状況に陥っていたのです。そこで同社は、「誰が教えても同じ教育内容」や「誰が見ても同じ解釈になるマニュアル」の整備が必要であることを考え、「動画マニュアル(tebiki)」を導入しました。
結果的に、3ヶ月のOJTが必須だった教育体制が改善され、現在はOJT教育工数が実質ゼロになったのです。また、手軽に動画マニュアルが作れるのが強みであるtebikiを活用していることで、動画マニュアル1本あたり5分~10分で作成ができているとのこと。
tebikiを活用して新人向けにピッキング作業を動画化しており、これが業務の効率化に大きく貢献しています。
同社の具体的な改善事例は以下のインタビュー記事よりご覧いただけます。
インタビュー記事:3ヶ月間の直接指導を動画マニュアルで完全に置き換え、業務の効率化を実現
※動画マニュアル「tebiki」の詳細な機能や活用イメージがわかるサービス資料はこちら。
システム導入による改善
ピッキング作業の効率と精度を改善するには、「システム導入」が効果的です。
特に、作業の見える化や作業指示の最適化が実現できるシステムは、属人化の解消やミス削減に直結します。ここでは代表的な4つのシステムと、導入によって得られた改善効果を紹介します。
1. WMS(倉庫管理システム)の導入で作業の全体最適を実現
WMSは、在庫管理やロケーション管理、作業指示などを一元的に管理できるシステムです。
例えば、紙のピッキングリストによる手作業でミスが多発し、再出荷にかかるコストが増えていた場合です。そこにWMSを導入し、ピッキングリストをタブレットで表示、ロケーションも自動ナビゲーション化します。このようにシステムを導入すれば誤出荷を減らし、スタッフも迷わず作業できるようになります。
2. DPS/DASの導入でピッキング精度をアップ
デジタルピッキングシステム(DPS)やデジタルアソートシステム(DAS)は、間口にランプやデジタル表示で作業内容を案内するシステムです。新人でも迷わず作業ができるようになり、教育時間を短縮できます。
例えば、小売向けの商品を扱うある倉庫でも、DPS導入により探す時間を削減し、1時間あたりのピッキング件数を増加させることも可能です。マニュアル操作と比較しても、効率アップやミス削減を期待できます。
3. 音声ピッキングでハンズフリー&アイズフリー作業
音声ピッキング(ボイスピッキング)は、作業指示を音声で伝え、作業員が音声で応答する仕組み。ハンズフリーで作業できるため、冷凍倉庫などの特殊環境でも活躍します。
食品メーカーの物流センターなどでも、音声ピッキング導入により、冷凍庫内のピッキング作業時間を短縮可能です。また、ゴーグルが曇るといった課題もなくなり、作業者のストレス軽減にもつながります。
4. AGV/AMRによる省人化・自動化
無人搬送車(AGV)や自律走行搬送ロボット(AMR)は、ピッキング後の商品を自動で搬送したり、作業者のもとへ棚ごと運んだりする仕組みです。
某物流企業では、磁気テープやQRコード無しで指定した時間に、指示したルートで自動で荷物を運ぶためにAGVやAMRを導入しています。搬入された荷物を倉庫内の指定の場所に移動するなどの作業も可能です。
ピッキングにかかる時間も短縮でき、作業人数の削減も期待できます。
マテハン機器の活用による改善
ピッキング作業の効率化には、人の作業を補完する「マテハン機器(マテリアルハンドリング機器)」の導入も有効な手段です。
ピッキング対象の商品の移動や仕分けを自動化することで、作業員の負担を軽減し、スピードと精度を両立できます。ここではマテハン活用例をご紹介します。
某製造工場では、マテハン機器の活用によって入出庫・保管業務に関する課題を解決しました。
コンテナ搬送のAMRと連動し、生産ラインから要求があった部品の出庫から搬送までを自動で実行できるようにしました。これにより、搬送業務の無人化や部品の取り間違いといったヒューマンエラー(人為的ミス)を低減できます。ジャストインタイムでの部品供給を実現しています。
また、在庫管理システムと連携させることで、在庫品を効率よく保管することもできています。
倉庫レイアウト・ロケーション管理の最適化
倉庫レイアウトやロケーション管理の最適化をすることも、ピッキング作業の改善につながります。レイアウトを見直すだけでも、移動距離の短縮や作業効率の向上につながるためです。さらに、WMSとの連携を含めロケーション管理をすることで探す時間の短縮やヒューマンエラーの削減につながります。
某企業の倉庫では、在庫置き場が煩雑になりやすいといった課題がありました。取り扱う商品が増えると、慣れている作業員しかロケーションを把握できないなどの属人化にもつながってしまいます。
そこで、VMSを導入してロケーション管理を徹底したところ、新人でもロケーションがわかるようになりました。さらに倉庫全体のレイアウトを見直すことで動きやすい動線にしたことが作業効率の向上にもつながっています。
ピッキング改善を成功させるためのポイント
ピッキング作業の改善を真に成功させるには、単なる方法論の導入にとどまらず、「現状分析」「目標設定」「費用対効果の検討」「スモールスタートによる効果測定」といったプロセスを丁寧に踏むことが欠かせません。
現状分析と課題特定:まず“どこに問題があるのか”を見極める
最初に取り組むべきは、ピッキング作業の現状を可視化することです。例えば、作業者ごとのピッキング時間やミスの発生件数をデータで把握し、どの工程にボトルネックがあるのかを分析します。
ある物流企業では、ピッキング作業の動画を撮影・分析することで、「移動距離が長く、取り出しに手間取るゾーン」が特定されました。その結果、レイアウト変更と作業手順の見直しによって、処理時間を短縮できた事例があります。
明確な目標設定:改善の方向性を数値で描く
ピッキング改善を成功させるためには、あいまいなゴールではなく、「ピッキング効率を20%向上させる」「誤出荷率を1%以下に抑える」など、具体的で測定可能な目標を掲げることが重要です。
目標を明確にすることで、関係者間の認識を揃えることができ、改善策の選定や進捗管理もしやすくなります。
費用対効果の検討:投資額に見合ったリターンが得られるかを見極める
改善施策を導入する際には、「どれだけのコストがかかり、どれだけの効果が得られるか」をあらかじめ試算しておく必要があります。
例えば、音声ピッキングシステムを導入する場合、機器の購入費用や初期設定費だけでなく、教育時間やメンテナンスコストまで含めて算出し、それによって得られる作業時間の短縮効果やミスの削減数と比較検討することで、判断に納得感を持たせることができます。
スモールスタートと効果測定:小さく試して、成果を確認してから広げる
一気に全体へ展開するのではなく、まずは一部エリアや商品カテゴリで試行的に導入する「スモールスタート」が推奨されます。これにより、リスクを抑えつつ、効果を定量的に測定することが可能です。
実際に、ある倉庫では、人気商品のゾーンだけにデジタルピッキングシステムを導入。作業スピードが向上したことを受けて、他エリアにも順次展開したという流れがありました。
ピッキング改善は、単なる設備や手法の導入ではなく、「考え方」と「プロセス設計」そのものが鍵を握ります。現場の実情をしっかり捉え、段階的に改善を積み重ねることで、効率化・省人化・品質向上を同時に実現できます。
まとめ
本記事では、物流現場の重要工程であるピッキング作業の効率化とミス削減に向けた課題と、その具体的な改善方法を事例と共に解説しました。生産性向上には、作業手順の標準化、WMSやマテハン等のシステム・機器導入、倉庫レイアウトやロケーション管理の最適化、そして人材育成といった多角的なアプローチが有効です。
成功の鍵は、現状分析から目標設定、費用対効果の検討、スモールスタートという段階的なプロセスを踏むことです。特に、作業の属人化解消や多様な人材への教育標準化においては、視覚的に分かりやすく「カンコツ」まで伝わる「動画マニュアル」の活用が1つの有効手段です。
現場改善を支援する教育ツールとして、本記事でも紹介した動画マニュアル「tebiki」の導入に少しでも興味がある方は、以下の画像をクリックしてサービス資料をご覧になってみてください。