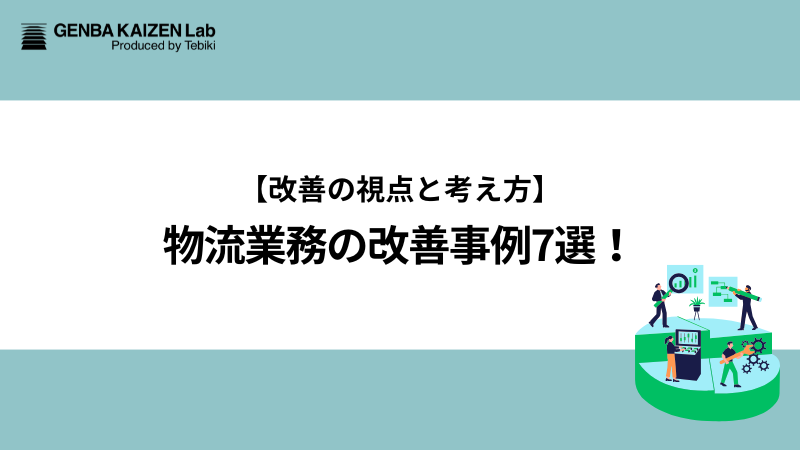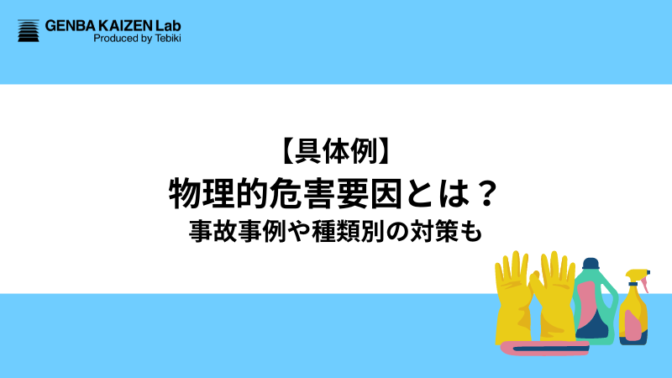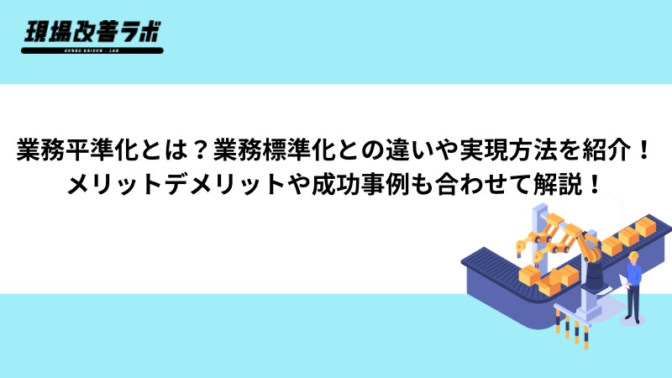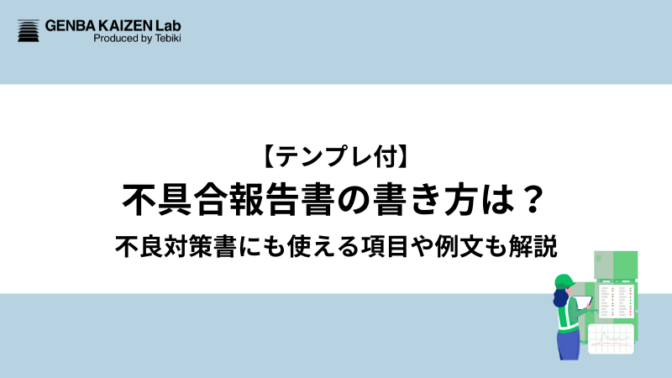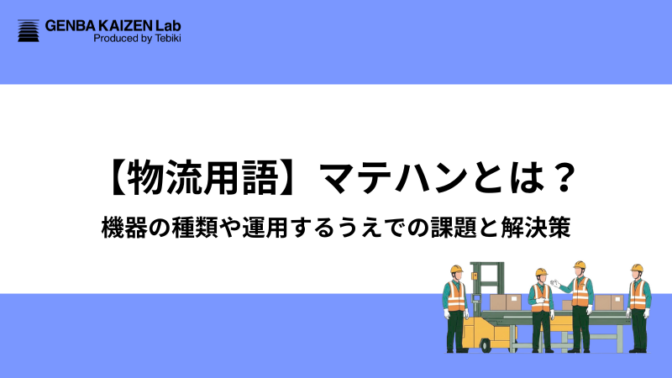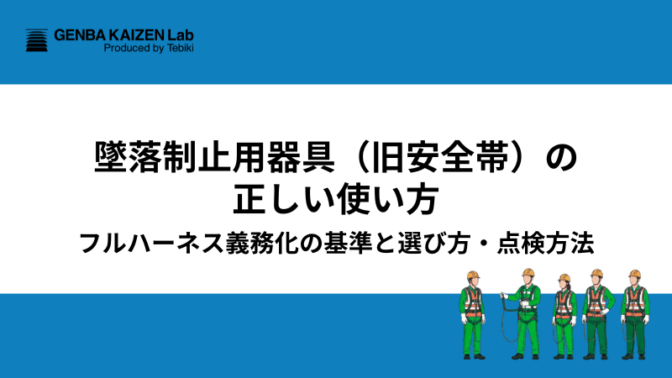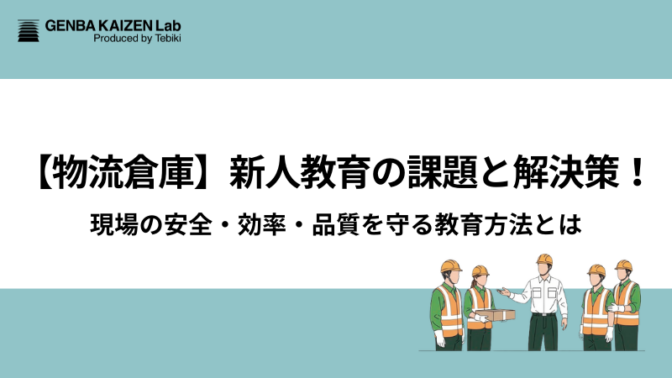かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
物流業務には、出荷ミスや作業効率の低下、人材育成の難しさなど、多くの課題が存在します。こうした現場の課題に対して、どのような改善を行うのかが多くの企業にとって重要なテーマです。
本記事では物流業務の改善に役立つ視点や考え方や、実際に成果を上げた7つの改善事例を詳しくご紹介します。
なお、物流現場の作業品質が安定しない現場にはいくつかの「共通項」があります。この共通項の招待や作業品質のばらつき・低下を改善する具体的な方法については、以下の資料で詳しく解説しているため、本記事と併せてご覧ください。
>>「物流現場の作業品質が安定しない理由と品質のばらつきを無くす対策」をみてみる
目次
物流業務の改善点を見つける視点と考え方
物流業務を改善するには、「どこに問題があるのか」を正確に見極める視点が欠かせません。
漫然と作業をしていても改善点は見えてきませんが、いくつかの視点を持つことで、現場のムダや事故リスク、教育上の課題が浮き彫りになります。ここでは、物流業務の改善点を見つけるために押さえておきたい5つの着眼点を紹介します。
- 労働災害やヒヤリハットなどの安全トラブルに着目する
- 業務上の3M(ムリ・ムダ・ムラ)に着目する
- ヒューマンエラーが起きている業務に着目する
- 作業環境や輸送環境などのハード面に着目する
- スタッフの採用や育成などのソフト面に着目する
これらの課題があることで作業品質にばらつきが生じ、最終的には生産性の低下といった重大な課題を招く可能性は高いといえます。作業品質のムラが発生する仕組みや標準化に向けた対策や好事例について解説した資料を以下にご用意しておりますので、本記事と併せてご覧ください。
>>作業品質が安定しない理由はどこにある?物流現場の品質ばらつきを改善する具体的な手法や事例をみる
労働災害やヒヤリハットなどの安全トラブルに着目する
物流現場に限らず職場で優先すべきは「安全」です。労働災害など、重大な事故につながりかねないヒヤリハットの記録は、現場改善の重要なヒントになります。
たとえば、「フォークリフトのすれ違い時にヒヤッとした」「棚の角に手をぶつけた」など、一見小さな出来事でも放置すると大きな事故を招くかもしれません。このような事象を見逃さず、なぜ起きたのかを深掘りすることで、危険箇所の把握や作業動線の見直しにつなげられます。
また「5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)」を徹底することで、安全と効率の両立を目指すことも有効です。見た目の美しさだけでなく、危険を未然に防ぐ仕組みとして5Sを捉える視点が大切です。
関連記事:フォークリフトのヒヤリハット事例集と対策まとめ!危険予知の事例もあわせて解説
業務上の3M(ムリ・ムダ・ムラ)に着目する
物流業務では、作業の3M(ムリ・ムダ・ムラ)を見つけて取り除くことが、改善の基本です。
- ムリ:人員配置や長時間におよぶ作業時間の負荷
- ムダ:動作や移動距離の無駄
- ムラ:従業員ごとの業務品質バラつき
たとえば、あるスタッフだけに業務が偏っていたり、毎回決まった場所まで資材を取りに行かなければならないレイアウトなどは、明らかに非効率です。
現場にカメラを設置して動線を確認したり、作業時間を可視化して比較することで、3Mの要因が見つかるケースは多くあります。日々の業務の中で「なぜそれをしているのか?」を問い直すことが、改善の第一歩になります。
無料セミナー動画「3M(ムリムダムラ)の視点と改善 製造業の品質向上と生産性向上への鍵」では、3Mに基づいた改善活動のヒントが解説されています。製造業向けの動画ではありますが、物流業務に通ずる知見や実践のヒントも得られますので、あわせて参考にしてみてください。
>>>無料セミナー動画「3M(ムリムダムラ)の視点と改善 製造業の品質向上と生産性向上への鍵」を見てみる
ヒューマンエラーが起きている業務に着目する
ピッキングミスや誤出荷といった、ヒューマンエラー(人為的ミス)が頻発している業務は、改善余地が大きいポイントです。ヒューマンエラーは、経験不足や集中力の低下、マニュアルの不備など、さまざまな原因で発生します。
重要なのは、「どうしてヒューマンエラーは起きるのか」「どうしたら有効な対策がなされるのか」と真因を究明し、再発防止策を練ることです。
「なぜミスが起きるのか?」という問いの真因は、人の「不安全行動」を促す心理にあります。行動科学に基づき、その心理的な連鎖を断ち切る決定的な防止網の作り方がこちらです。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
作業環境や輸送環境などのハード面に着目する
改善というと「人」に注目しがちですが、「設備」や「環境」に原因があることも少なくありません。
倉庫内の照明が暗かったり、温度や湿度が作業に適していなかったりすると、集中力の低下や体調不良を招き、ミスやトラブルの原因となります。また、輸送における温度管理の不備や車両トラブルなど、サプライチェーン全体を見渡す視点も求められます。
こうしたハード面の課題には、システム導入やレイアウト変更、定期的なメンテナンスの実施といった対策が効果的です。また、フェイルセーフやフールプルーフといった仕組みに着目し、ヒューマンエラーを防ぐ方法もあります。
現場従業員の採用や育成などのソフト面に着目する
物流業務の改善には「人」の成長が欠かせません。特に物流現場では、人材不足や離職率の高さが業務の不安定化を招いています。
そのため、採用だけでなく、入社後の教育やキャリア支援も含めた「育成」が大切です。新人スタッフが早期に現場に馴染めるよう、即戦力につながる教育体制の整備や、外国人スタッフ向けの多言語対応なども進めるべき課題です。
例えば、ソニテック株式会社のように、作業標準ルールが定義された「一目見ればわかるマニュアル」を整備し、従業員の作業品質がバラつきやすいOJT教育やマンツーマン指導から脱却した事例は、1つの改善成功事例と言えます。
▼物流業務の改善事例:ソニテック株式会社▼
同社の改善事例を詳しく知りたい方は、こちらをクリックしてインタビュー記事をご覧ください。次章からは、このような物流業務におけるさまざまな改善事例を7つご紹介します。
物流業務の改善・物流効率化に取り組んだ改善事例7選
物流現場の課題は多岐にわたりますが、他社の取り組み事例から学ぶことで、自社に活かせるヒントが見つかります。ここでは、実際に物流業務の改善や効率化に取り組み、成果を上げた7つの事例をご紹介します。
- 倉庫内業務の安全・品質向上に取り組んだ事例
- 5S活動の徹底に取り組んだ事例
- 出荷業務・ピッキング作業のミスを半減した事例
- 物流システム導入で業務効率化に取り組んだ事例
- 新人スタッフ受入時の教育改善に取り組んだ事例
- 輸送環境などサプライチェーンマネジメントの改善に取り組んだ事例
- 外国人従業員の受入体制を改善した事例
業務の安全性向上から教育体制の強化まで、幅広いアプローチをぜひ参考にしてください。
倉庫内業務の安全・品質向上に取り組んだ事例
ASKUL LOGIST株式会社では、安全教育がなかなか伝わらない、教育にかかる工数やバラツキに課題を抱えていました。そこで、「一目見れば作業内容や安全ルールが分かるマニュアル(動画マニュアル)」を整備し、安全と品質を両立させる現場改善に成功しました。
具体的には、動画化されたマニュアルの電子データを、オンライン共有ドライブに格納し、全ての物流拠点で動画が見られるように体制を構築したのです。導入時教育、定期的な安全教育などのシーンで動画マニュアルを活用しています。
動画は繰り返し確認できるため、同社は新人教育の時間が1回あたり「2時間から30分に短縮」できるなどの効果がありました。また、文章だけでは伝わりにくいポイントを動画で「見える化」することで、理解度が向上し、作業のバラつきやミスが減少しています。
| 動画マニュアル導入前の課題 | 動画マニュアル導入後の効果 |
|---|---|
| ・安全教育を行ってもなかなか伝わらない ・導入時教育、倉庫内の繰り返し教育の工数が膨大 ・従来の教育だと受け手側の解釈で理解がバラついてしまう | ・導入時教育、倉庫内の繰り返し教育の工数が大幅に削減 ・均質化された同じ教育を受けるので業務の標準化につながった |
物流業における動画マニュアルの活用事例やユースケースについては、資料「物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラ(pdf)」で解説されているので、あわせてご覧ください。
5S活動の徹底に取り組んだ事例
物流業界に限らず、よく使われる現場改善で行われるのが「5S活動の徹底」です。5Sによって倉庫内のムダを排除します。
ある物流企業では、倉庫現場のレイアウトやロケーションの最適化、従業員の最適動線などがうまくいっておらず、どこから手を付けるべきか悩んでいました。そこで5Sの視点を取り入れ、生産性向上と効率化を実現したのです。
整理・整頓・清掃・清潔・しつけの5Sを基盤にして、レイアウトの最適化や作業導線の見直しを行うことで、作業効率と安全性が大きく向上します。さらに、改善提案制度を導入すれば、現場からの気づきを仕組みとして活かす風土づくりも進められます。
5S活動の具体的な理解や実践方法は、無料セミナー動画「生産性を高める5S活動 正しい運用に欠かせない「重要なS」とは」で詳しく解説されています。5Sを自社の現場にどう応用するのか、イメージが湧くようになっているので、お時間がある際に視聴してみてください。以下をクリックすると視聴申込ページに遷移します。
>>>無料セミナー動画「生産性を高める5S活動 正しい運用に欠かせない「重要なS」とは」を見てみる
出荷業務・ピッキング作業のミスを半減した事例
株式会社ジェイ・メイトでは、仕分けミスが多いことが課題でした。そこで、「誰が見ても同じ作業」ができるよう、「動画によるマニュアル」を整備し、ピッキング作業におけるヒューマンエラー削減に成功しました。
具体的には、ピッキングリストの読み間違いや、手順の誤解による出荷ミスを減らすために、動画マニュアルを使用しました。動画マニュアルにすることで、新人スタッフでもすぐに理解できる「視覚的な教育」ができるようになり、教育時間の短縮と品質の安定化を同時に実現しています。
| 動画マニュアル導入前の課題 | 動画マニュアル導入後の効果 |
|---|---|
| 仕分けミスが多い | 仕分けミスの半減新人訓練期間の短縮 |
同社は、物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を活用して現場改善を実現しました。tebikiの詳細機能や活用事例は資料「3分で分かる『tebikiサービス資料』(pdf)」にまとめられています。下の画像をクリックするとダウンロードできるので、あわせてご覧ください。
物流システム導入で業務効率化に取り組んだ事例
ある物流企業では、アナログな管理によって目視による間違いが発生しやすい状況でした。人の手による作業領域が広く、結果的に人的ミスが増えていたのです。
そこで在庫管理システムを導入した結果、適切な在庫管理ができるようになりました。また、これまで目視で確認していた項目もデジタル化されたことで間違って発送してしまうなどのミスも軽減できています。在庫管理自体がデジタル化されたことによって、一元管理が可能になり業務負担の軽減にも貢献しています。
人的ミスが目立つ作業領域に関しては、物流システムの導入を検討し、システム化できる余地がないかどうかをリサーチしてみましょう。
新人スタッフ受入時の教育改善に取り組んだ事例
ソニテック株式会社では、「マニュアルをエクセルで整備したものの、見られない」「マニュアルは作って終わり」という課題に直面し、結局OJT教育やマンツーマン指導に頼らざるを得ない状況が続いていました。その結果、新人スタッフの指導工数は最低3ヶ月が必要であったことに加え、教育担当者によって教え方にバラつきがあるため、新人スタッフの作業品質もバラつきが生じていたのです。
そこで、動画マニュアルを内製で作成・整備し始めました。新人スタッフは動画マニュアルを見て、分からないところを後ほど補足してもらうというような教育体制を整備し、3ヶ月かかっていた教育工数は実質ゼロになったのです。
これにより、業務の標準化と教育の属人化解消を実現しました。
| 動画マニュアル導入前の課題 | 動画マニュアル導入後の効果 |
|---|---|
| マンツーマン指導の工数が膨大作業品質にバラつきが生じる | マンツーマン指導の工数が大幅に削減均質化された同じ教育を受けるので業務の標準化につながった |
動画マニュアル作成ツール導入前後の様子や詳細については、以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:3ヶ月間の直接指導を動画マニュアルで完全に置き換え、業務の効率化を実現
輸送環境などサプライチェーンマネジメントの改善に取り組んだ事例
国内の大手企業ではSCM(サプライチェーンマネジメント)施策を行い成功した実績があります。共通しているポイントは、以下の4つです。
- ジャスト・イン・タイム(JIT)&リーン生産
- 需要予測&AI・データ活用
- 物流の効率化(ラストワンマイル&拠点戦略)
- 環境配慮型サプライチェーン(グリーンSCM)
SCMでは、必要なものを必要な量だけ、必要なタイミングで供給する必要があります。そのためには、需要予測や物流の効率化などが欠かせません。
SCMの具体的な改善手法については、SCMコンサルタントが専門的に解説している以下の記事でご覧いただけるので、あわせて参考にしてみてください。
関連記事:【専門家解説】サプライチェーンマネジメント成功事例から分かる、SCM最適化に不可欠な要素とは?
外国人従業員の受入体制を改善した事例
ASKUL LOGIST株式会社では、外国人スタッフが働きやすい職場づくりにも注力しています。同社では「安全教育や作業手順が外国人スタッフにどうしても伝わらない」という問題に直面し、外国人教育に課題を感じていました。言語の問題や文化の違いは、現場改善の大きな壁として立ちはだかっていたのです。
そこで同社は、言語を問わず理解しやすい「動画マニュアル」を導入。視覚的に作業内容を伝えることで、言葉の壁を越えた教育が可能となり、定着率・理解度ともに大幅に向上しました。
▼物流業務の改善事例:ASKUL LOGISTICS株式会社▼
同社が導入した動画マニュアル作成ツールは、物流現場に特化した「tebiki現場教育」だったということもあり、tebiki特有の機能である「1クリックで、字幕が100か国以上の外国語に自動翻訳される機能」を活用し、スピーディな外国人教育を可能としたのです。
tebiki現場教育の詳細機能や活用事例がまとめられたサービス資料は、以下のリンクをクリックしてご覧ください。次章では、ASKUL LOGISTICS株式会社をはじめとする様々な物流企業で活用されている、動画マニュアルの有効性をご紹介します。
>>>かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」の機能やプラン、改善事例を見てみる
物流現場の業務改善に活用される「動画マニュアル」の有効性
物流業務の改善において、「作業の標準化」や「教育の効率化」は欠かせないテーマです。特に新人や外国人スタッフの教育に課題を感じている現場では、動画マニュアルの導入が有効な手段として注目されています。
物流改善に対する動画マニュアルの有効性は?
作業品質を安定させ、教育コストを削減するなら、動画マニュアルの導入が効果的です。
理由は、構内作業のような動作を伴う業務は、文章だけで伝えるよりも、動画のほうがはるかにわかりやすいからです。物流現場では、商品のピッキング、検品、出荷といった作業が連続して発生しますが、それら一連の流れを映像で見せることで、スタッフの理解度が飛躍的に向上します。
▼物流業務に関する動画マニュアルのサンプル▼
※「tebiki現場教育」で作成
前述したように、ソニテック株式会社では新人スタッフの教育を「動画」に置き換え、3ヶ月は必須だったマンツーマン指導の教育工数をゼロにしています。
さらに、外国人スタッフの受け入れが増えている物流現場では、動画は言語の壁を超える教育手段としても有効です。こちらも前述したとおり、ASKUL LOGIST株式会社では、外国人従業員への教育に動画を活用しています。視覚的に理解できる内容にすることで、母国語を介さずに作業の基本を習得させることができました。
実際、物流業界では年々外国人労働者の比率が高まっており、厚生労働省の統計(「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)」)でもその傾向が顕著です。そうした背景からも、伝わりやすさと教育のスピードが両立できる動画マニュアルの活用は、今後さらに広がっていくと考えられます。
多くの物流現場で活用されている動画マニュアルツール
物流現場での動画マニュアル活用は、すでに多くの企業で実績があります。中でも、物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」は導入しやすさと運用のしやすさから、多くの現場で選ばれています。
たとえば、スマートフォンで撮影した動画に字幕や音声を追加し、ワンクリックでマニュアル化できるシンプルな操作性が特徴です。日本語が不得意な外国人スタッフ向けに多言語対応も進んでおり、教育のスピードと均一化が両立できる環境が整えられます。
また、動画ごとに視聴ログを確認できるため、「誰がどこまで学習したか」が一目でわかり、指導の抜け漏れを防ぐ効果もあります。このようなツールを活用することで、物流現場は「属人的なOJTから脱却し、再現性のある教育体制」へと進化しているのです。
tebiki現場教育は、動画マニュアルの撮影から編集・公開まで、10分程度で完了するケースも多く、稼働時間を圧迫することなく教育をスムーズに進められるのが大きな特徴です。
詳しい機能やプラン、活用事例がまとめられた資料は以下のリンクをクリックしてご覧ください。
>>>かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」の詳細を見てみる
物流業務の改善策は実施して終わりではない
物流業務の改善は、一度やって終わりではありません。現場の状況は日々変わるため、改善策の「実施後」がむしろ本番です。継続的に見直す姿勢は欠かせません。
たとえば、新しい仕組みを導入しても、使い方が現場に定着していなければ、時間が経つにつれて元の状態に戻ってしまいます。このような改善の形骸化を防ぐには、PDCA(計画・実行・評価・改善)のサイクルを回し続けることが重要です。
tebiki現場教育は動画マニュアルの作成支援だけでなく、作成後のサポートや運用も支援しているので、現場改善が継続的になされているのかどうかを常に可視化します。また、動画の視聴履歴や習熟度が可視化されるため、改善策が本当に現場に根付いているかも確認が可能です。
物流改善は、続けることが成果につながるカギです。改善の定着とPDCAを回す仕組みを整えておきましょう。
【補足】物流業務の改善に関するQ&A
ここからは、物流業務の改善に関するQ&Aをご紹介します。
物流現場、倉庫作業の改善提案ネタはどう探せばいい?
物流業務の改善は、現場の「気づき」から始まります。そのため、改善提案のヒントは日々の作業の中に多く隠れています。
たとえば、荷物の置き場がわかりにくい、移動距離が無駄に長い、同じミスが繰り返されているなど。このような些細な違和感が、業務改善の重要な糸口です。
改善提案ネタを探すには、現場で働くスタッフの声を拾い上げ、ヒヤリハットや使いづらさを記録することが効果的です。
以下の記事では、実際の改善提案事例やネタの探し方をわかりやすく解説しています。ぜひご活用ください。
トヨタ流の物流改善に取り組む事例は?
物流改善の代表的な手法といえば、やはり「トヨタ流改善」です。トヨタでは「カイゼン」を基本とし、現場でのムダ・ムリ・ムラ(3M)を徹底的に排除しながら、現場の声を起点にした改善文化を根づかせています。
特に注目すべきは、サプライヤーとの連携や現場主導のPDCAサイクルの実践です。現場の従業員自らが改善提案を行い、それが経営レベルにまで反映される仕組みは、他業界でも応用可能です。
下記の記事では、トヨタのサプライヤー企業では出荷ヤードには「かんばんポスト」を設置し、出荷スケジュールが一目でわかるようになった事例も紹介されています。
参考記事:「改善は楽しい」 仕入先との共存共栄は共に汗かき、話を聞いて
トヨタ流改善の基本である「ムダ」の削減と、それによって生まれる「良い流れづくり」について、トヨタ生産方式の観点から詳しく解説します。
>>トヨタ生産方式を通じた”ムダ”の削減と「良い流れづくり」を見てみる
物流改善に関係する「物流効率化法」とは?
物流業務を抜本的に見直すなら、「物流効率化法」の活用も視野に入れるべきです。
この法律は、複数企業間での共同配送や拠点の集約、モーダルシフト(鉄道・船舶への転換)などを推進し、物流の効率化を支援する制度です。
この制度を活用すれば、税制優遇や補助金の対象になる場合もあります。特に、中小企業にとっては導入コストを抑えながら、現代的な物流体制への移行が可能です。
法の概要や、支援内容の詳細については、国土交通省のホームページで確認できます。
まとめ
物流業務の改善は、単なる効率化ではなく、「安全性・品質・教育・仕組み」など複数の要素をバランスよく見直すことが大切です。
特に近年、人手不足や多様な働き手の受入といった課題があり、ハード面だけでなくソフト面の改善も欠かせません。動画マニュアルやPDCAサイクルの活用、トヨタ流の改善文化などを取り入れることで、現場の実行力が高まり、継続的な改善へとつながります。
本記事で紹介した事例や取り組みは、いずれも小さな一歩から始まっています。自社に合った改善策を選び、一度きりで終わらせず、現場の声を活かしながら継続することが、物流業務の本質的な改善への近道です。
物流業務の改善を推進するための有効手段の1つに「動画マニュアル」を本記事では推奨しました。動画マニュアルの作り方や導入推進方法については、以下の資料が役立ちますので、参考にしてみてください。