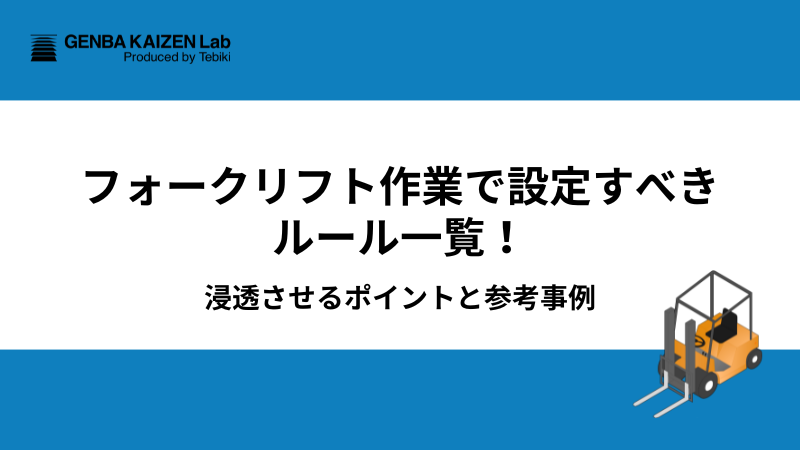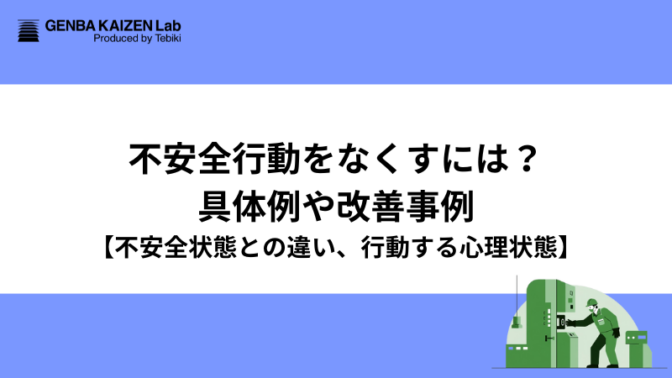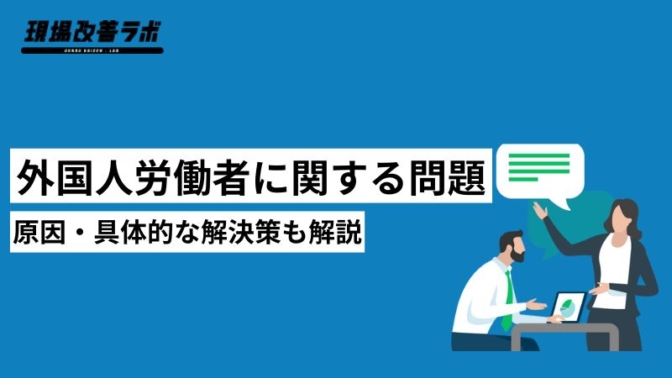物流業で役立つかんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」を展開する現場改善ラボ編集部です。
フォークリフトを使用する現場の責任者や安全管理者の中には、次のような疑問をお持ちの方もいるでしょう。
- 「自社の運用ルールは十分だろうか」
- 「事故を防ぐにはどんなルールが必要か」
フォークリフトは業務効率化に欠かせませんが、操作を誤れば物損や重大な労働災害につながる危険もあります。事故を防ぐには、資格の有無など基本項目から構内の速度制限まで具体的な運用ルールを明確に定め、全作業員に徹底させることが重要です。
本記事ではフォークリフト作業に15年以上従事する筆者が、法律で定められた基本ルールから事業所ごとの具体的運用ルールまでを解説します。最後まで読むことで事故を未然に防ぎ、安全な職場環境を作るヒントを得られます。
▼ゼロ災を目指す!安全意識を高めるフォークリフトの安全教育・対策事例集はこちらをクリック!▼
目次
フォークリフトのルールを設定しないとどうなる?考えられるリスク
フォークリフトを使用する現場では、その環境に応じた明確な社内ルールを策定することが安全管理の第一歩です。
ルールが設定されていない状態は安全意識の低下や不安全行動を招き、ヒヤリハットや重大な労働災害に直結する危険性をはらんでいます。フォークリフトは業務効率を飛躍的に向上させる便利なマテハン機器ですが、その裏には常に危険が潜んでいることを忘れてはなりません。
事実、一般社団法人日本産業車両協会が厚生労働省「労働災害統計」を基に取りまとめた「フォークリフトに起因する労働災害の発生状況―厚生労働省労働災害統計より―」によると、毎年約2,000件の労働災害が発生し、そのうち20~30件が死亡災害につながっています。
▼フォークリフトに起因する労働災害発生状況▼
| 年 | 死傷災害(件) | 死亡災害(件) |
|---|---|---|
| 2023 | 1,989 | 22 |
| 2022 | 2,092 | 34 |
| 2021 | 2,028 | 21 |
| 2020 | 1,989 | 31 |
| 2019 | 2,145 | 20 |
出典:フォークリフトに起因する労働災害の発生状況―厚生労働省労働災害統計より―|一般社団法人日本産業車両協会
このような悲しい事故を自社の現場で決して起こさないためにも、ルールの設定と全作業員への周知徹底が不可欠です。
関連記事:【最新】フォークリフト事故の実態!事例や発生件数・原因について
フォークリフト作業で設定すべき社内ルール
フォークリフト作業の安全を確保するには、労働安全衛生法に準拠した明確かつ実践的な社内ルールを策定し、全作業員に徹底させることが不可欠です。
ここでは、事業者が設定すべきルールを以下3つのカテゴリに分けて具体的に解説します。
- 基本ルール
- 構内走行時のルール
- 駐車時のルール
フォークリフトのルールを守らせるには、日頃から安全教育を実施し、従業員の安全意識を高めることが不可欠です。従業員の安全意識を高めるフォークリフト安全教育の方法・事例については、以下のガイドブックをご覧ください。
>>目指せゼロ災!安全意識を高めるフォークリフトの安全教育・対策事例集をみてみる
フォークリフトの基本ルール
まず、作業の開始から終了まで常に遵守すべき最も基本的なルールから解説します。これらは、安全なフォークリフト作業の土台を形成します。
フォークリフトの資格の有無
フォークリフトの運転は、法令で定められた資格(技能講習または特別教育)を持つ者だけが行えます。
| 対象フォークリフト | 必要な資格 |
|---|---|
| 最大荷重1トン未満 | 特別教育 |
| 最大荷重1トン以上(上限なし) | 技能講習 |
自動車の運転免許とは全く別の資格であり、無資格運転は事業者にも重い罰則が科せられます。有資格者名簿の作成や、キーの厳格な管理体制を構築しましょう。
関連記事:【フォークリフトの特別教育】社内実施の方法・技能講習との違い
定期的な点検の実施
安全衛生規則 により、「作業開始前点検」「月次点検」「年次点検」の3つが義務付けられています。これらは機械の故障に起因する事故を未然に防ぐための重要なプロセスです。全ての点検を確実に実施し、その記録を規定期間(3年間)保管する体制を整備しなければなりません。
関連記事:フォークリフト点検は義務?点検の種類や項目、やり方について
作業計画書の作成
フォークリフト作業を行う際はあらかじめ作業計画書を作成し、関係者へ周知することが法律で定められています。
第151条の3
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業 (不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第151条の7までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
計画書は安全な作業を遂行するための、いわば「設計図」の役割を果たします。
作業指揮者の配置
作業の指揮者を定め、その者に作業計画に基づいた指揮を行わせる必要があります。指揮者は、計画通りに作業が進んでいるかを監督し、変化する現場状況に応じて的確な指示を出す「現場の管制塔」です。特に複数人での作業や非定常作業では、その役割が極めて重要になります。
安全装備の着用
運転者および周囲の作業員は、指定された保護具を正しく着用しなければなりません。特にヘルメットは、転倒・転落時の衝撃から頭部を守るため極めて重要です。
フォークリフトの構内走行時のルール
構内での走行は、人や物との交錯が頻繁に発生する最も危険な局面の一つです。ここでは厳格な走行ルールを定め、遵守することが求められます。
制限速度の遵守
事業所ごとに構内の制限速度を定め、全運転者はこれを厳守します。一般的に推奨される速度は時速10km以下です。速度を抑えることで危険を察知してから停止するまでの制動距離を大幅に短縮し、衝突のリスクを低減できます。
歩行者や作業員とエリアを分ける
フォークリフトの走行通路と歩行者通路は、ガードレールや床の色分けラインなどで明確に区分・分離します。これは「人車分離」と呼ばれ、個人の注意喚起に頼るよりもはるかに効果的な、接触事故防止の根本対策です。
関連記事:フォークリフト事故・労災の実態:事例や発生件数・原因について
用途以外の使用禁止
フォークリフトを、荷物の昇降・運搬という主たる用途以外に使用してはいけません。特に、パレットの上に人を乗せて高所作業をさせる行為や、フォークに直接ロープを掛けて荷を吊り上げる行為は重大災害に直結するため厳禁です。
関連記事:事例で学ぶ!フォークリフトの危険行為をなくす安全教育の実践法
走行ルールの確保
荷物で前方の視界が確保できない場合は、必ず後進で走行します。また、急発進・急ハンドル・急ブレーキといった「急」の付く操作は、荷崩れや車両転倒の最大の原因となるため禁止です。運転席以外の場所に人を乗せることも、もちろん許されません。
停止表示の遵守
通路の交差点や見通しの悪い場所に設置された「止まれ」の標識では、必ず完全に車両を停止させ、左右の安全を十分に確認してから発進します。出会い頭の衝突事故を防ぐための、最も重要な基本ルールの一つです。
資格の把握
作業指揮者は、どの運転者がどのフォークリフトの運転資格を持っているかを把握し、運転者は作業中に資格証を携帯します。さらに資格者は腕章をつける、ヘルメットにステッカーを貼るなどして、資格の有無を誰もが一目で把握できる「仕組み」を構築することが、より確実な安全管理につながります。
フォークリフト駐車時のルール
作業を終えてフォークリフトから離れる際の駐車措置も、厳格な手順の遵守が求められます。不備は「逸走」と呼ばれる、無人での暴走事故を引き起こす原因となります。
逸走防止措置の活用
運転席を離れる際は、以下のような方法で逸走防止措置を徹底します。
- フォーク(ツメ)を完全に地面まで下ろす。
- マストを前傾させ、フォークの先端を接地させる。
- 駐車ブレーキを確実にかける。
- エンジンを停止し、キーを抜いて携行する。
特に、乗用車と違い「パーキング」ギアはないため、駐車ブレーキと車輪止めが最後の安全装置です。
斜面での駐車の禁止
駐車は、必ず指定された「平坦」な場所で行います。プラットホームへの登り通路やドッグレベラー上など、わずかでも傾斜のある場所での駐車は逸走のリスクが非常に高いため、厳禁です。
特にトルコン車や電気式のフォークリフトはギアロック機構がないため、駐車ブレーキが甘いと簡単に動き出してしまいます。二次的な安全措置として、車輪止めを必ず使用する習慣をつけましょう。
フォークリフトのルールを浸透させるためには「動画」が有効
前項で具体的なルールを紹介しましたが、最も重要なのは、これらのルールを作業員1人ひとりに確実に浸透させることです。そのための有効な手段として、本記事では「動画」を活用した教育をおすすめします。
以下の動画のように、実際の作業風景を見ながら学ぶことで、口頭や紙媒体に比べはるかに理解度の高い教育が実現できます。
▼フォークリフト操作の禁止事項を解説する動画マニュアル▼
(tebiki現場教育で作成)
動画を使用した教育で得られる主な効果として、以下の2つをご紹介します。
- 危険作業・NG例を動画で学ぶことで、安全意識が高まる
- 正しい作業手順やルールを一目で理解できる
危険作業・NG例を動画で学ぶことで、安全意識が高まる
文字や口頭での説明だけでは、危険行為の深刻さや具体的な状況をリアルにイメージすることは困難です。しかし、実際の危険作業やNG例を収めた動画を視聴することで危険性を直感的に理解でき、それが危険作業の強力な抑止力となります。
正しい作業手順やルールを一目で理解できる
正しい作業手順や構内のルールを周知する上でも、動画は非常に効果的です。紙のマニュアルでは伝わりにくい現場のリアルな状況も、映像であれば一目で理解できます。特に新人教育において、実際の現場映像を用いることで、ルールの背景や意味がより深く伝わります。
ここまで、フォークリフトのルール周知に動画が有効であることを解説してきました。しかし、「動画制作は専門知識が必要で大変そうだ」と感じる方も多いかもしれません。
そこでおすすめしたいのが、物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」です。
「tebiki現場教育」なら、スマートフォン1つで専門知識がなくても簡単に高品質な教育動画を作成できます。現場の安全意識を効率的に高め、安全な職場づくりを実現するために、ぜひ本サービスにご興味をお持ちいただけましたら、以下のリンクから詳しい資料をダウンロードしてご覧ください。
>>安全意識を高める動画マニュアル「tebiki現場教育」のサービス資料はこちら
フォークリフトのルールの周知に動画を活用している企業事例
前項では、フォークリフトのルールを周知する上で動画が有効であることを解説しました。
ここでは、実際に動画マニュアルを活用している企業として、以下の2社をご紹介します。
- 株式会社近鉄コスモス
- 株式会社フジトランスコーポレーション
より多くの事例や実際の動画マニュアルをご覧になりたい方は、以下のリンクをクリックし別紙の資料をご参照ください。
>>動画マニュアルを使ったフォークリフト安全教育・対策事例をもっとみる
株式会社近鉄コスモス
事業BPO・作業BPO・梱包作業などの事業を展開している物流企業の「株式会社近鉄コスモス」では、フォークリフトのルールを周知するため、動画マニュアルを活用しています。
例えば、以下の動画のように実際の禁止行為を映像で見せることで、経験の浅い作業員でも危険性を直感的に理解できるよう工夫されています。
(tebiki現場教育で作成)
tebiki現場教育について、より詳しい機能や事例を知りたい方は、以下の資料をご覧ください。
>>物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料を見てみる
株式会社フジトランスコーポレーション
港湾運送事業や倉庫業などを展開する総合物流企業「株式会社フジトランスコーポレーション」では、「tebiki現場教育」を導入することで、フォークリフトの安全基準を効率的に標準化することに成功しています。
同社では、1,000人を超える従業員を抱え、外国人労働者を含む派遣労働者が定期的に入れ替わる環境において、教育担当者の工数の多さが課題でした。そんな中、従業員が先輩の作業をスマートフォンで撮影していたことに着目し、動画マニュアルの導入を決定しました。
「誰でも簡単に動画マニュアルが作れる」という特長を活かし、現在では倉庫内でのフォークリフト作業をはじめ、船舶での貨物の積み卸しや梱包作業、安全教育に「tebiki現場教育」を活用し、現場作業の安全性を確保しています。
株式会社フジトランスコーポレーションの「tebiki現場教育」活用法についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をご一読ください。
>>物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料を見てみる
【補足】フォークリフトの事故を防止する上で有効な対策
これまで解説してきたルールの設定に加えて、事故を防止するためには以下のような対策も有効です。具体的な方法として3つご紹介します。
- 危険予知(KY)活動の実施
- 5S活動の実施
- 安全対策グッズの導入
危険予知(KY)活動の実施
作業に潜む死角などの危険要因を事前に予測し、対策を話し合う「KY活動(危険予知活動)」を習慣化することが重要です。
例えば朝礼の場で、その日の作業における危険なポイントをメンバーで挙げ合い、具体的な対策を共有します。チームで実践することで個人では気づけない危険を発見でき、現場全体の安全意識を効果的に高めることができます。
▼形骸化しない次世代の「KY活動」の進め方や事例をご覧になりたい方はこちらをクリック!▼
5S活動の実施
5S活動、特に「整理・整頓」の徹底は、不要な死角をなくし現場の見通しを改善します。物流現場では、具体的に以下のようなルールを定めることが有効です。
- フォークリフトの作業スペースやカウンタウエイト上に、工具などの物を置かない
- 歩行帯に荷物やパレットを置かない
- カゴ台車など、搬送機器の定位置管理を徹底する
安全な職場環境の土台として、これらの活動を継続的に実践することが求められます。
▼ただの整理整頓ではない!現場に潜むキケンを排除する「5S活動の進め方」について知りたい方はこちらをクリック!▼
安全対策グッズの導入
人間の注意力だけで事故を防ぐには限界があるため、ルールや教育を補完する安全対策グッズの導入も有効です。
例えば、フォークリフトの接近を床に投影された光で知らせる「ブルーライト」や、見通しの悪い角に設置する「広角ミラー」などが挙げられます。近年では、人を検知して警報を発するAIカメラも普及してきました。
これらの物理的な対策を組み合わせることで、ヒューマンエラーをカバーするより強固な安全体制を構築できます。物理的な対策に加え安全教育の実施により、設備や仕組みなど「ハード面」と人的ミスの防止という「ソフト面」の二重対策が行われるため、事故の未然防止により効果を発揮するでしょう。
▼ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育の進め方や企業事例について知りたい方はこちらをクリック!▼
まとめ
本記事では、フォークリフトを安全に運用するために設定すべきルールを、「基本ルール」「構内走行時のルール」「駐車時のルール」の3つのカテゴリに分けて解説しました。
記事で紹介した具体的なルールは以下の通りです。
| 基本ルール | ・フォークリフトの資格の有無 ・定期的な点検の実施 ・作業計画書の作成 ・作業指揮者の配置 ・安全装備の着用 |
| 構内走行時のルール | ・制限速度の遵守 ・歩行者や作業員とエリアを分ける ・用途以外の使用禁止 ・走行ルールの確保 ・停止表示の遵守 ・資格の把握 |
| 駐車時のルール | ・逸走防止措置の活用 ・斜面での駐車の禁止 |
これらのルールは、設定するだけでなく、現場の作業員一人ひとりに確実に周知し、浸透させることが何よりも重要です。しかし、日々の多忙な業務の中で、質の高い教育を現場全体に行き渡らせるのは、決して簡単なことではありません。
そこでおすすめしたいのが、物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」です。
ルールを周知するための動画を誰でも簡単に作成でき、教育の効率化と人的リソースの大幅な削減を実現します。
「tebiki現場教育」の具体的な機能や導入事例、導入後のサポート体制などについては、以下の資料で詳しく紹介しています。是非ダウンロードしてご覧ください。