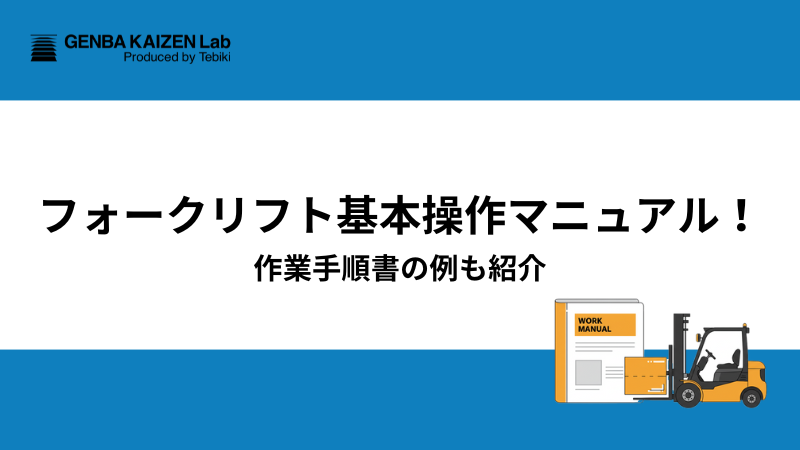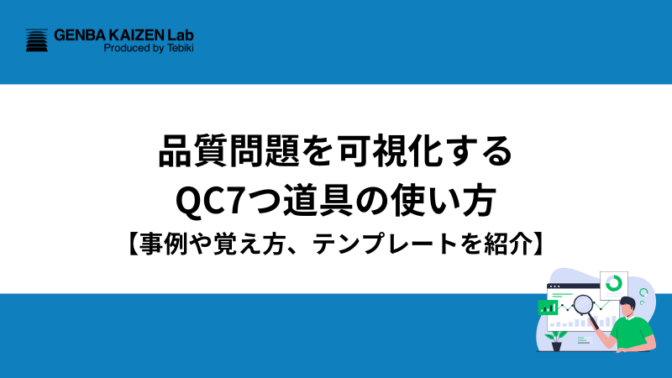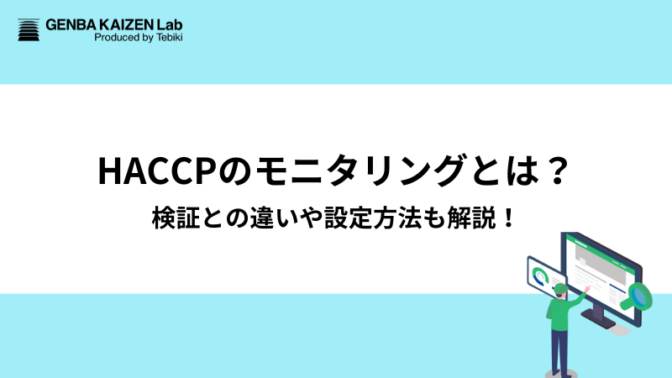物流や倉庫に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
本記事は、フォークリフトの運転や基本操作がまとめられたマニュアルです。内容はすべて、フォークリフト運転技能講習修了証を所持する現役物流スタッフによって執筆されているため、新人スタッフの基本操作理解はもちろん、実用的なマニュアル作りの参考にもなるはずです。
フォークリフトに関連したマニュアルを作成する際、内容や構成をはじめ、レイアウトやデザインなども考える必要があるため、かなりの工数が発生します。そこで、スムーズにマニュアルが作成できるように、フォークリフトのサンプルマニュアル、そのまま使えるテンプレートが付いた資料をご用意しています。
資料内では、マニュアル作成の流れや企業事例なども紹介していますので、下のリンクをクリックして本記事とあわせてぜひご覧ください。
>>「フォークリフトマニュアルのサンプル/テンプレートが付いたガイドブック(pdf)」を見てみる
目次
フォークリフト作業におけるマニュアルや手順書整備の重要性
そもそも、なぜフォークリフト作業にマニュアルが必要なのか、その理由として以下の4つが挙げられます。
- 安全確保
- 作業効率の向上
- 教育・訓練の標準化
- 法的要求・コンプライアンス
それぞれの観点から理由を紹介していきます。
安全確保・物損事故の防止
労働災害事故や、物損事故による経済的損失を防ぐために、作業マニュアルの整備が重要となります。特に安全確保は重要です。なぜなら、小さなフォークリフトでも1トンを超える重量物であるため、接触すれば重大な事故につながる可能性が高いからです。
その証拠に、厚生労働省の調査では、2019年~2023年の5年間で毎年、平均25.6人が「フォークリフトが起因する労働災害事故で命を落としている」という報告が上がっています。
▼フォークリフトによる死亡災害件数の推移▼
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フォークリフトによる死亡災害(件) | 20 | 31 | 21 | 34 | 22 |
さらに注意したいこととして、万が一、人身事故が発生した場合には労働安全衛生法に基づく罰則が科されたり、被害者やそのご家族から多額の損害賠償を請求されたりするケースがあるということ。したがって、フォークリフトのマニュアル整備は非常に大切であり、事故の撲滅に努めることが極めて重要です。
しかし、「分かっているはずなのにルールを守らない」「つい危険な近道をしてしまう」といった作業員の不安全行動に頭を悩ませる現場は少なくありません。
なぜ人は、危険だと理解していながら不安全な行動を繰り返してしまうのでしょうか。その答えは、人間の行動原理を探る「行動科学」の中にあります。
この行動科学の観点から、繰り返される不安全行動の根本原因にアプローチし、決定的な防止策を講じるための考え方を、以下の資料で詳しく解説しています。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
作業効率の向上
フォークリフトの作業マニュアルを作成すれば「誰が操作しても、最も効率的で安全な作業手順」を示すツールになります。作業者ごとのやり方の違いや自己流による無駄な動きがなくなることで、結果として、現場全体の作業スピードが安定して向上します。
また、正しい手順は荷物の積み直しといった二度手間、あるいはヒヤリハット・事故による作業中断のリスクの低減が可能です。
簡単なトラブルであれば、フォークリフトの作業マニュアルを見てすぐ解決できることもあり、作業が止まっている時間を短縮できることもメリットと言えるでしょう。
ただし、これらのメリットは、作成したマニュアルが現場で「実際に使われ」、その内容が確実に守られてこそ得られるものです。
文字ばかりで分かりにくかったり、熟練者の持つ「カンコツ」が伝わらなかったりする形骸化したマニュアルでは、誰も活用できず、宝の持ち腐れとなってしまいます。
フォークリフト作業の安全性と効率を本当に向上させる、現場で活きる手順書作成のポイントについては、以下の資料で詳しく解説しています。
>>カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイントを見てみる
教育・訓練の標準化
新入社員や経験の浅い作業員への均質な教育ができることも、作業マニュアルを整備するメリットと言えます。特にフォークリフトの操作方法において、OJTでは指導者や環境によってバラつきが生じやすいものです。
例えば、「走行時の右手の位置について、先輩社員のAさんには太ももの上と言われたが、ベテラン社員のBさんにはレバーに添えておくように言われた」など、どちらが正解か困惑してしまうことが多々あります。
しかし、フォークリフトの作業マニュアルを整備しておけば、指導者によってバラつきが生じるOJTのデメリットを最小化でき、教育・訓練の標準化を図れます。
「誰もが同じ教育を受け、同じように作業が実行できる」状態を作るには、正しい作業内容が一目で分かる状態を作ることが重要です。例えば「動画」や「映像」によるマニュアル整備は1つの有効手段です。動画によるマニュアル整備を進める物流企業は徐々に増えています。
「一目で分かるマニュアルの例」として、物流企業「株式会社近鉄コスモス」の現場従業員が実際に作成している、フォークリフトに関する動画マニュアルを、以下に掲載します。
※「tebiki」で作成されています
このような、物流業における動画マニュアルの活用事例やユースケースについては、資料「物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラ(pdf)」で解説されているので、あわせてご覧ください。
>>物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラを見てみる
法的要求・コンプライアンス遵守
労働安全衛生法など、関連法規遵守の観点からも、フォークリフトの作業マニュアル整備は重要です。マニュアル通りに運用することで、本来すべき項目を「知らなかった」や「忘れていた」などの理由で怠ってしまうことを防止します。
例えば、労働安全衛生規則における第151条の25では、フォークリフトの点検について以下のように明記されています。
事業者は、フオークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
一 制動装置及び操縦装置の機能
二 荷役装置及び油圧装置の機能
三 車輪の異常の有無
四 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能
このことをフォークリフトの作業マニュアルに組み込んでおくことで、コンプライアンス違反を防げます。
フォークリフトの始業点検や定期自主検査、特別教育など、現場には多くの法的要求事項が存在します。
これらの法令遵守の状況を確認・審議し、現場の安全レベルを継続的に高めていくことこそ、「安全衛生委員会」の重要な役割です。
しかし、毎月の「議題ネタ」がマンネリ化し、「今月は何を話そうか…」と悩むことも少なくありません。 その「議題ネタ探しの視点」と具体的な「年間カレンダー」を、元労基署長が解説します。
>>安全衛生委員会「議題ネタ探しの視点」と「2026年の議題ネタ年間カレンダー」を見てみる
【6ステップ】フォークリフトの基本操作マニュアル(作業手順書の例)
ここからは、実際にフォークリフトの基本操作マニュアルを紹介します。ここで紹介する内容はそのまま作業手順書の内容例になるため、自社でマニュアルを整備・作成する際の参考にしてみてください。
マニュアルの内容は、厚生労働省「フォークリフト」に基づいた作成を推奨します。基本的には以下の操作手順をマニュアルで網羅すると良いでしょう。
なお、ここで紹介している内容とあわせて、「物流・倉庫作業のマニュアル作成ガイドブック(pdf)」もご活用ください。ガイドブック内では、フォークリフトマニュアルのサンプル・そのまま使えるテンプレートが付属されているので、レイアウトやデザインなどを考慮する必要がなく、スムーズなマニュアル作成が実現します。下のリンクをクリックするとダウンロードが可能です。
>>「フォークリフトマニュアルのサンプル/テンプレートが付いたガイドブック(pdf)」を見てみる
1. 乗車前の点検(始業前点検)
労働安全衛生規則における第151条の25では点検の規定が定められているため、日々の始業前に必ずフォークリフトを点検しなければなりません。
具体的な点検箇所とタイミングは以下の通りです。
| 点検項目 | 具体的な点検箇所 | 点検のタイミング | |
|---|---|---|---|
| エンジン車 | バッテリー車 | ||
| 車輪の異常の有無 | ・タイヤの摩耗度合 ・異物がはさまっていないか ・ホイルナットの緩み | エンジン始動前/暖機運転時 | 始動スイッチ「切」時 |
| 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能 | ・ヘッドライト ・バックランプ ・方向指示器 ・クラクション | エンジン始動前/暖機運転時 | 始動スイッチ「切」時 |
| 制動装置及び操縦装置の機能 | ・アクセル ・ブレーキ ・ハンドル操作 | エンジン始動後 | 始動スイッチ「入」後 |
| 荷役装置及び油圧装置の機能 | ・リフト操作 ・ティルト操作 | エンジン始動後 | 始動スイッチ「入」後 |
車両トラブルによる事故発生を防ぐのはもちろん、故障の早期発見という観点からも始業前点検は重要です。
フォークリフトの点検作業は煩雑なので、動画や映像によるマニュアルを整備する手段も検討の余地があります。たとえば物流企業「株式会社近鉄コスモス」は、始業前点検を動画マニュアル化し、効率的な現場教育を推進しています。
▼点検手順を教育する動画マニュアルの例▼
※「tebiki」で作成されています
物流現場における動画マニュアルの具体的な活用方法や導入効果について、さらに詳しくまとめた資料をご用意しています。自社の課題解決のヒントとしてご活用ください。
>>>「物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラ(pdf)」を見てみる
2. 正しい乗車方法と運転姿勢
正しい乗車方法や運転姿勢をフォークリフトの作業マニュアルに明記しておけば、事故や怪我の防止、疲労の軽減につながります。
- 安全に乗降車するには
- 正しい運転姿勢
- 安定した操作と疲労軽減につながる姿勢のポイント
それぞれの観点から具体的に方法を解説します。
安全に乗車するには
安全に乗車するためのポイントは以下の通りです。
| 乗降車時のポイント | 要因 |
|---|---|
| 運転席の左側から乗車する (カウンタバランスフォークリフト) | 右側からも乗車できるが狭い右側に操作レバーがあり、誤動作による事故の防止 |
| 手すりを使用する | 落下防止 |
| 飛び乗らない | 落下防止、足をぶつけて怪我をする恐れがある |
上記を意識し乗車することで、怪我を防止できます。
正しい運転姿勢
続いて、着席時のシート周りの操作手順と、正しい運転姿勢を解説します。まず、深く座った状態でのシート操作の方法は以下の通りです。
- シートの前後の調整:アクセルペダルとブレーキペダル、クラッチペダル(インチングペダル)に無理なく脚が届く位置
- リクライニングの調整:真っすぐな姿勢でハンドルや各レバーに無理なく手が届く位置
- ミラーの調整:後方が視認できる位置
- シートベルトの着用
カウンターバランスフォークリフトの基本姿勢は以下の通りです。
| 項目 | 基本となる位置 |
|---|---|
| 右足 | アクセルペダル |
| 左足 | 床面に置く |
| 右手 | 右足太ももの上に軽く置き、必要に応じてレバー操作 |
| 左手 | ハンドル操作 |
リーチフォークリフトの基本姿勢は以下の通りです。
| 項目 | 基本となる位置 |
|---|---|
| 右足 | 床面に置く |
| 左足 | ブレーキペダル操作 |
| 右手 | 右足太ももの上に軽く置き、必要に応じてレバー操作 |
| 左手 | ハンドル操作 |
安定した操作と疲労軽減につながる姿勢のポイント
フォークリフトを正しい姿勢で操作することにより、操作が安定するメリットがあります。さらに、腰痛予防になったり疲労の軽減につながります。
具体的には、以下の方法がおすすめです。
- シートに深く座る
- 足が無理なくペダルに届く位置にシートの前後を調節する
- 手が無理なくハンドルやレバーに届く位置にシートのリクライニングを調節する
身体にストレスがかからない運転姿勢に設定することがポイントです。
3. エンジン始動と発進の手順
エンジン始動から発進の手順を、マニュアル化し徹底させることは、事故や故障の低減につながります。トルコン車とバッテリー車、クラッチ車、リーチフォークリフトで発進の手順が異なるのでそれぞれ見ていきましょう。
トルコン車とバッテリー車
- 前後進レバー、フォークの操作レバーが「中立」の位置にあることを確認する(目視、操作)
- 駐車ブレーキがかかっていることを確認(目視、操作)
- 左足でインチングペダル(バッテリー車はブレーキペダル)を踏み込む
- キーを回しエンジン始動(バッテリー車はスイッチ「入」)
- 前後進レバーを「前進」に入れる
- 周囲の安全確認(指差呼称)
- 駐車ブレーキの解除
- 左足をインチングペダル(バッテリー式はブレーキペダル)からゆっくりと離す
- 右足でアクセルペダルをゆっくりと踏み込み発進する
インチングペダルとは、主にトルコン式フォークリフトにある左足で操作するペダルです。クラッチとブレーキの機能を併せ持ち、軽く踏み込むとまず動力が切れ(半クラッチ状態)、さらに踏むとブレーキがかかります。
インチングペダルを上手く使えば、シフトレバーを中立に戻さなくても高回転で荷役作業することができます。
荷物の積み下ろしなど、荷役作業の効率を高める便利な機能です。
クラッチ式
- 前後進レバー、高低速レバー、フォークの操作レバーが「中立」の位置にあることを確認する(目視、操作)
- 駐車ブレーキがかかっていることを確認(目視、操作)
- 左足でクラッチを踏み込む
- キーを回しエンジンを始動する
- 前後進レバーを「前進」に、高低速レバーを「低速」に入れる
- 周囲の安全確認(指差呼称)
- 駐車ブレーキを解除する
- 左足をクラッチペダルからゆっくりと離す
- 右足でアクセルペダルをゆっくりと踏み込み発進する
リーチフォークリフト
- 前後進レバー、フォークの操作レバーが「中立」の位置にあることを確認する(目視、操作)
- 周囲の安全確認(指差呼称)
- 左足でブレーキペダルをゆっくりと踏み込む
- 進行方向へ走行レバーを操作し発進する
4. 基本的な走行操作
カウンターバランスフォークリフトの基本的な走行操作は車とほぼ同じです。真っすぐに前を向いた状態で椅子に座り、両足を使いアクセルとブレーキで速度を調整しながら走行します。
また、左手でハンドル操作、右手は必要に応じてレバー操作をおこないます。
旋回の特徴
車の走行操作と大きく違う点は、ハンドルを旋回すると後輪が左右に曲がることです。前輪が操向する自動車とは真逆となります。
これにより、自動車よりも小回りが利くため、狭い倉庫内でも軽快に走行できます。
旋回時には以下の点に注意しましょう。
- 右旋回時は左側、左旋回時は右側にカウンタウェイトが大きく振れるため、人や物への接触に注意する
- 高速走行からの急旋回、坂道での旋回は転倒のおそれがあるため絶対に行わない
前後進の切り替え
エンジン式フォークリフトの前進、後進の切り替えは、フォークリフトが完全に停止してからおこないます。一方で、バッテリー式フォークリフトは「プラギング操作」ができるため、フォークリフトが停止していなくても前後進レバーの切り替えが可能です。
プラギング操作とは、バッテリー式フォークリフト走行時、進行方向と反対のレバーを入れても電動モーターの制動力で負担をかけずにギアを変えられる機能です。完全停車を待たずにギアを入れ替えられるうえに制動力を得られるため、スムーズで効率的な作業をおこなえます。
リーチフォークリフトの特性
リーチフォークリフトも後輪操向である点はカウンターバランスフォークリフトと同じですが、大きく異なる点はフォークを前後に移動させられることです。フォークは、作業で使用した後必ずいっぱいまで引き込むようにしましょう。
また、カウンターバランス式よりもタイヤの切れ角が大きいため、小回りが利くのも大きな特徴です。その分、より一層旋回時の転倒に注意が必要となります。
前進走行時の注意点
前進走行時は、周囲の確認をしっかりと行いましょう。速度は、構内の安全表示に従いますが、なければ10kmを上限と考えておけば安全です。
また、見通しの悪い場所や、他車と交わる可能性がある箇所は一旦停止し、指差呼称で安全を確認してから走行します。
後進走行時の注意点
後進走行時は、左右の安全を指差呼称で確認してから発進します。前進に比べて死角が増えるため、ミラーだけでなく目視での確認作業も必須です。
旋回時は旋回方向の人や物の巻き込みに注意しましょう。
関連記事:フォークリフトバック走行時の後方確認の重要性と安全対策
5. 荷役操作の基本(荷降ろし・運搬・積み込み)
荷役操作では、フォークの操作が加わるためこれまでよりも詳細な手順が必要です。
- 荷降ろしの手順
- 運搬の際の注意点
- 積み込みの手順
それぞれ、安全に作業するための具体的な手順を解説します。
荷降ろし時
| 接近と停止 | 荷台の20~30cm手前で停止する |
| サイドブレーキをかけ、前後進レバーを「中立」にする | |
| フォークの位置調整 | マストを地面と垂直にする |
| フォークをパレット差込口の高さまで上げる | |
| フォークの差し込み | 前方の安全確認(指差呼称) |
| 前後進レバーを「前進」に入れ、サイドブレーキ解除 | |
| ゆっくり前進して(リーチフォークリフトはリーチを伸ばして)パレットにフォークを差し込む(この時点ではフォークをすべて挿入せず、根元10~20cm残しておく) | |
| 荷物の持ち上げ | サイドブレーキをかけ、前後進レバーを「中立」にする |
| パレットを約10cm程度上げる | |
| 積み荷の安定を確認(指差呼称) | |
| 荷物の移動 | 後方の安全確認(指差呼称) |
| 前後進レバーを「後進」に入れ、サイドブレーキを解除する | |
| 荷台の先端まで後進したら、一度荷台にパレットを置き、フォークを根元まで入れる | |
| パレットを10㎝程度上げ、静かに後進しパレットと荷台の隙間が20~30cm開いたら停止 | |
| 走行体勢への移行 | サイドブレーキをかけ、前後進レバーを「中立」にする |
| パレットを地面より5~10cmの高さまで下げる | |
| マストを最大後傾させる | |
| 移動準備 | 全周囲の安全確認(指差呼称) |
| 前後進レバーを「後進」に入れ、サイドブレーキを解除する | |
| 指定の速度を守り、指定場所へ移送する |
荷下ろしでは、作業手順が特に細かくなり、事故などが発生する可能性もあるため慎重な作業が大切です。参考にしたい事例として、物流企業の株式会社近鉄コスモスでは、フォークリフトの禁止事項を動画マニュアルにまとめています。
▼禁止事項を教育する動画マニュアルの例▼
※「tebiki」で作成されています
物流現場における動画マニュアルの活用事例や導入効果を詳しく知りたい方は、以下の資料もあわせてご覧ください。
>>「物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラ(pdf)」を見てみる
運搬時の注意点
フォークリフトを使用した荷物の運搬は、以下の点に注意してください。
- 前後進時には必ず周囲の安全を確認(指差呼称)
- 構内の制限速度を遵守する
- 運搬走行時はフォークを地面から5~10㎝上げた位置(低重心)にする
- 前方の視界が確保できない時は後進走行を基本とする
積み込み時
| 接近と停止 | 荷台の20~30cm手前で停止 |
| サイドブレーキをかけ、前後進レバーを「中立」にする | |
| フォークの位置調整 | マストを地面と垂直にする |
| パレットの下面を荷台より10~15cm高い位置まで上げる | |
| 荷物の運搬 | 前方の安全確認(指差呼称) |
| 前後進レバーを「前進」に入れ、サイドブレーキを解除する | |
| ゆっくり前進して荷台の指定場所まで移動する | |
| 荷物の設置 | サイドブレーキをかけ、前後進レバーを「中立」に |
| パレットを荷台の指定箇所に静かに降ろす | |
| フォークの引き抜き | 後方の安全確認(指差呼称) |
| 前後進レバーを「後進」に入れ、サイドブレーキを解除する | |
| 静かに後進し、フォークの先端と荷台の隙間が20~30cm開いたら停止 | |
| 走行体勢への移行 | サイドブレーキをかけ、前後進レバーを「中立」にする |
| フォークを地上5~10cmまで下げる | |
| マストを後傾させる(6度以上) | |
| 移動準備 | 全周囲の安全確認(指差呼称) |
| 前後進レバーを後進に入れ、サイドブレーキを解除する | |
| 次の作業場所へ移動する |
6. 駐車と降車の手順
最後に、作業完了後の駐車と降車の手順と注意点について解説します。
駐車と降車の手順
- 平坦な場所に駐車する
- サイドブレーキをかけ、前後進レバーを「中立」にする
- マストを少し前傾させ、フォークを完全に下げる
- エンジン停止(スイッチ「切」)、キーを抜く
- 周囲の安全を確認(指差呼称)
- 手すりを使用し左側から降車する
駐車と降車の注意点
駐車と降車時は以下の点に注意してください。
- 指定された場所がある場合は、その位置に駐車する
- 指定された場所がない場合は、他車の通行や作業の邪魔にならない場所に駐車する
- 降車時は絶対に飛び降りない
ここまでフォークリフトの操作手順を作業の一連の流れで解説しました。これらの手順をマニュアル化することは重要ですが、どれだけマニュアルを整備しても「現場で使われなければ意味がない」と言えます。
「現場で本当に使われる」作業手順書を作成するには、いくつかのポイントがあります。カンコツまで含めて効果的に伝える方法を知りたい方は、以下の資料が参考になります。
>>カンコツが伝わる!「現場で使われる」作業標準書のポイントを見てみる
フォークリフトの事故や労災を防ぐための安全運転とは
厚生労働省「労働災害統計」によると、2019年~2023年の5年間で、年平均25.6人がフォークリフトが起因する労働災害事故で命を落としています。このような事故を防ぐためにも、以下のような安全に関する基本的なルールや法律で定められている事項や現場での注意点をしっかりと守ることが重要です。
- 作業マニュアル
- 労働安全衛生法/労働安全衛生規則
- 各現場内のフォークリフト運用ルール
- ヒヤリハット事例の周知
しかし、ルールやマニュアルを整備し、危険性を周知しているにもかかわらず、なぜフォークリフトによる労働災害は後を絶たないのでしょうか。
その大きな原因の一つが、作業者の「うっかり」や「思い込み」「近道行動」といった「ヒューマンエラー」です。
ルールを一方的に提示するだけでは、ヒューマンエラーを防ぐことは困難です。なぜそのルールが必要なのか、どういった行動がエラーに繋がるのかを作業員一人ひとりが深く理解し、安全な行動を徹底するための安全教育が不可欠となります。
ヒューマンエラーに起因する労働災害を未然に防ぐための、効果的な安全教育の進め方については、以下の資料で詳しく解説しています。
>>ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育を見てみる
より具体的な安全対策や、現場での改善事例については、こちらの記事も参考になります。
▼関連記事▼
・フォークリフトの安全対策8例!事故を防止した改善事例や安全意識を高める方法も解説
・フォークリフト安全作業マニュアル!事故や労災を防ぐ操作方法
「現場で使われる」フォークリフト手順書の整備事例
フォークリフト操作は複雑で高度な技術が求められるため、文字や画像だけでのマニュアルでは教育難易度が高くなりがちです。「文字の羅列で内容が理解しにくく、現場で使われなくなった」というような、マニュアルが形骸化するケースは多く、いかに現場に浸透する手順書が作れるかが鍵を握ります。
そこで昨今、多くの物流企業で取り入れられているのが「動画」によるマニュアル整備です。
例えば物流企業「株式会社近鉄コスモス」は、フォークリフトの禁止事項やNG操作を動画におさめ、動画マニュアルとして展開することで、安全意識の向上に努めています。以下は実際に同社で活用されている動画マニュアルです。
▼安全意識の向上につながる動画マニュアルの例▼
※「tebiki」で作成されています
他にも同社は、始業前のフォークリフト点検手順も動画におさめ、マニュアル化しています。
▼点検手順を教育する動画マニュアルの例▼
※「tebiki」で作成されています
物流現場における動画マニュアルの具体的な活用方法や導入効果について、さらに詳しくまとめた資料をご用意しています。自社の課題解決のヒントとしてご活用ください。
>>>「物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラ(pdf)」を見てみる
動画によるマニュアル整備が少しでも気になる方は、物流や倉庫業務にも特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料をご覧ください。詳細な機能や活用事例等、動画マニュアルを導入するにあたって参考となる情報が詰め込まれています。下の画像をクリックするとダウンロードが可能です。
まとめ:安全なフォークリフト作業と効果的な教育体制のために
本記事では、フォークリフト作業におけるマニュアルの重要性から、手順書の例となる基本操作、そして安全運転の重要ポイントについて、現役オペレーター監修のもと解説しました。
フォークリフトマニュアルは、安全確保、作業効率化、教育標準化、コンプライアンス遵守に不可欠です。正しい基本操作を習得し、常に安全を意識することが、重大事故や労災を防ぐための基本となります。
しかし、文字や図だけでは伝えきれない操作のコツや危険箇所も存在します。本記事で紹介したように、動画マニュアルを活用すれば、実際の動きや注意すべき点を視覚的に、より深く理解させることが可能です。これは、効果的な教育や安全意識向上に大きく貢献するでしょう。
物流業に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」でであれば、安全で生産性の高いフォークリフト作業の浸透・実現をお手伝いできます。この記事で得た知識と、動画マニュアルのような新しい教育方法の活用を通じて、フォークリフトによる労働災害の未然防止と生産性向上を目指しましょう。