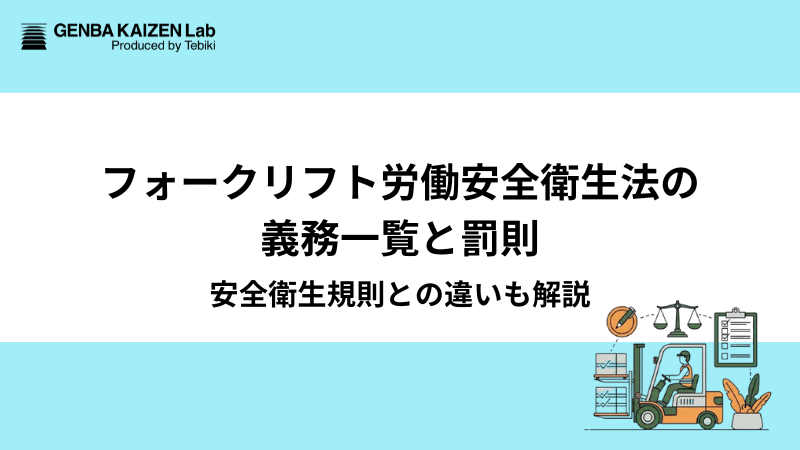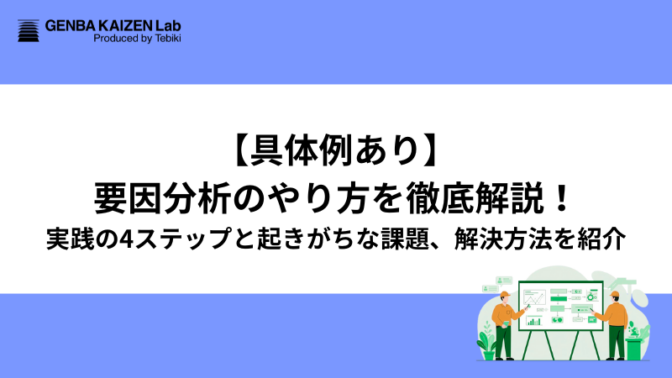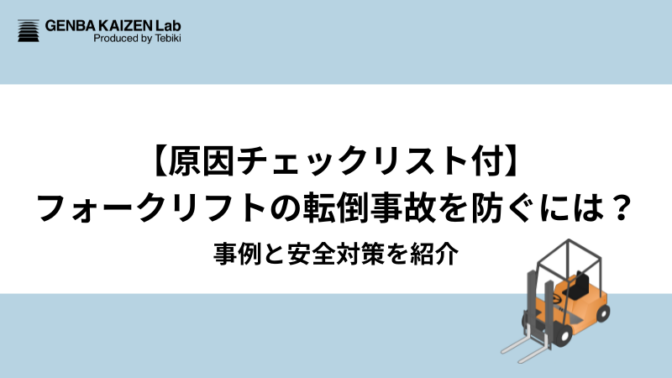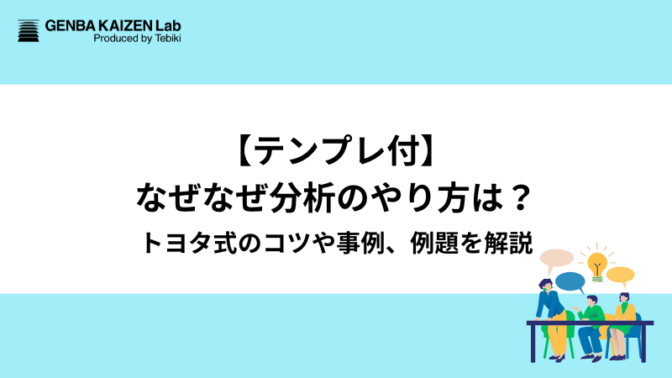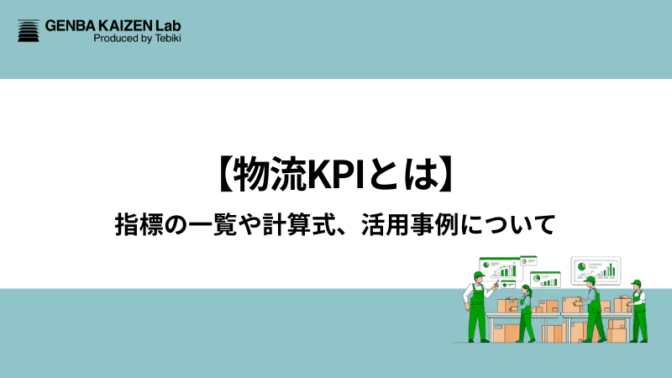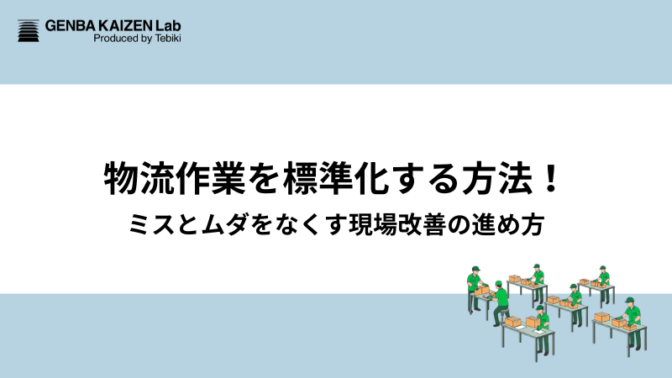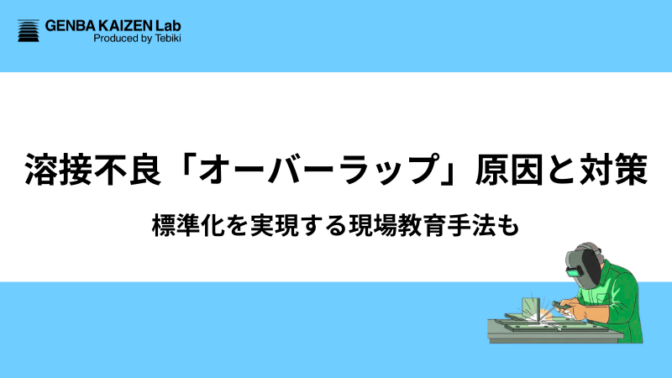労働安全衛生法の遵守に役立つかんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
業者は労働安全衛生法を遵守する義務がありますが、「労働安全衛生規則」との違いが曖昧だったり、法令遵守のために具体的に何をすべきか把握しきれていなかったりするケースも少なくありません。
そこで本記事では、物流現場で5年以上の安全衛生担当経験を持つ筆者が両者の違い、フォークリフト運用で事業者がすべきこと、さらに法令遵守と事故防止につながる効果的な安全教育の方法を解説します。コンプライアンスに則った安全で働きやすい職場づくりの参考として、是非最後までご覧ください。
なお物流現場では、フォークリフトにおける安全教育の手段として「動画マニュアル」の導入も増えています。正しい操作手順だけでなく、何をどうやったら危険やヒヤリハットにつながるのかも可視化(危険の見える化)するため、安全意識や危険意識が浸透する教育アプローチとして有効とされています。
動画マニュアルによるフォークリフト安全対策の具体的な効果や企業事例は、以下のリンクに記載した資料で詳しく展開しているので、併せてご参照ください。
>>「動画マニュアルを活用したフォークリフトの安全教育・対策事例」を見てみる
目次
労働安全衛生法とは?安全衛生規則との違い
労働安全衛生法は、事業者が職場で講じるべき安全対策や健康管理の具体的な基準を国が定めた法律です。倉庫管理者にとってはフォークリフトの運用ルール、荷役作業の安全基準、作業員の健康診断の実施といった現場の安全体制を維持するための具体的な措置が義務付けられています。
ここでは、まず基本となる以下の2点について解説します。
- 労働安全衛生法の目的:労働者の安全と健康を守るための基本法
- 労働安全衛生法と労働安全衛生規則の関係性
労働安全衛生法の目的:労働者の安全と健康を守るための基本法
労働安全衛生法の目的は、その第一条で以下のように明記されています。
第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
条文からわかるように、労働安全衛生法を遵守することは従業員が安心して働ける職場づくりそのものといえます。
関連記事:労働安全衛生法とは?義務一覧や罰則・安全対策の具体例
労働安全衛生法と労働安全衛生規則の関係性
労働安全衛生法を調べる際、必ずセットで「労働安全衛生規則」という言葉が出てきます。この二つは似て非なるものであり、その関係性を理解することが重要です。
| 労働安全衛生法(法律) | 「労働者の安全と健康を守りなさい」という国が定めた大きな方針・命令です。 憲法のような全体的なルールと考えると分かりやすいでしょう。 |
| 労働安全衛生規則(省令) | 法律(法)で定められた方針を実行するために、「具体的にはこうしなさい」という詳細なマニュアル・ルールを定めたものです。 |
フォークリフトの運用に関していえば、資格、点検、作業方法などの具体的なルールは、ほとんどがこの「労働安全衛生規則」に書かれています。
次の章では、「フォークリフトの運用で事業者がやるべきこと」とは具体的に何なのか、詳しく解説します。
事業者が果たすべきフォークリフトに関する4つの義務
労働安全衛生法および労働安全衛生規則に基づき、フォークリフトを運用する事業者は、主に以下の4つの義務を果たす必要があります。
- ①資格に関する義務:フォークリフトには2種類の資格がある
- ②定期自主検査に関する義務:3種類の点検を実施し保管する
- ③作業計画に関する義務:当日の作業方法を周知する
- ④安全な運転・作業方法に関する義務:雇い入れ時に安全衛生教育を施す
特に安全衛生教育の実施は、重大な事故に発展しがちなフォークリフトの労働災害を防ぐうえで非常に重要な要素です。フォークリフトの安全衛生教育で教えるべき内容や実際の対策事例について知りたい方は以下のリンクから詳しい資料をご覧ください。
>>フォークリフトの安全衛生教育・対策事例について詳しく知りたい方はこちらをクリック!
①資格に関する義務:フォークリフトには2種類の資格がある
まず、資格を有する者以外にフォークリフトを運転させてはなりません。「公道ではなく自社の敷地内(構内)だけだから大丈夫」といった解釈は間違いであり、明確な法令違反となります。
必要な資格は、フォークリフトの最大荷重によって以下の2種類に分けられます。
| 項目 | 対象 | 適用法令 |
|---|---|---|
| フォークリフト運転特別教育 | 最大荷重1トン未満 | 労働安全衛生規則 第36条の5 |
| フォークリフト運転技能講習 | 最大荷重1トン以上 (上限なし) | ・労働安全衛生法 第61条 ・労働安全衛生法施行令 第20条 |
どちらも法律で定められた内容と時間の講習を受講し、修了することが必須です。フォークリフトの資格や特別教育の社内実施方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:【フォークリフトの特別教育】社内実施の方法・技能講習との違い
②定期自主検査に関する義務:3種類の点検を実施し保管する
2つ目の義務は、フォークリフトの定期的な点検です。
点検の種類とは?
安全に運用するため、以下の3種類の点検が義務付けられています。
| 検査の種類 | 期間 | 点検項目 | 適用法令 |
|---|---|---|---|
| 始業前点検 | その日の作業を開始する前 | ・ブレーキ ・ハンドル ・タイヤ など | 労働安全衛生規則 第151条の25 |
| 月次点検 (定期自主検査) | 1か月を超えない期間ごとに1回 | ・始業前点検の項目 ・油脂関係の量 ・車体の異常 など | 労働安全衛生規則 第151条の22 |
| 年次点検 (特定自主検査) | 1年を超えない期間ごとに1回 | 走行装置、荷役装置全般 | 労働安全衛生規則 第151条の21 |
特に年次点検(特定自主検査)は専門的な知識・技能が必要なため、有資格者による実施、または専門業者への委託が必須です。また、これら定期自主検査(月次・年次)の結果は、3年間の記録保管(労働安全衛生規則 第151条の23)が義務付けられています。
点検項目や具体的な点検方法について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
関連記事:フォークリフト点検は義務?点検の種類や項目、やり方について
点検作業の属人化を防ぐ「動画マニュアル」
始業前点検や月次点検は、現場の作業員が実施するケースが多いです。しかし点検項目は多岐にわたり、紙の手順書だけでは「この項目はどういう意味か」「どこをどう見れば良いか」が分かりにくいことも少なくありません。筆者自身もはじめは点検項目を見ても判断に迷い、その度に先輩に質問していました。
特に月次点検は実施頻度が低いため、OJTの機会が限られます。さらに忙しくなると点検作業が特定の作業員頼み、いわゆる「属人化」に陥りがちです。
こうした課題の解決には、点検の手順を「動画」で共有する方法が有効です。 実際に、総合物流企業である「株式会社近鉄コスモス」では、フォークリフトの始業前点検の様子を動画化し、誰でも分かりやすいマニュアルを作成・活用しています。
※「tebiki現場教育」で作成
動画であれば、点検箇所や確認のポイントが視覚的に伝わり、教育の標準化と属人化の解消につながります。同社が動画の作成に使用した「tebiki現場教育」の詳細を知りたい方は、以下のリンクから資料をダウンロードしチェックしてください。
③作業計画に関する義務:当日の作業方法を周知する
3つ目の義務は、フォークリフト作業に関する「作業計画」を定め、従業員に周知することです。 労働安全衛生規則では、以下のように定められています。
第151条の3
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業 (不整地運搬車又は貨物自動車を 用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第151条の7ま でにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。
3 事業者は、第1項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
ここでいう「車両系荷役運搬機械」がフォークリフトに相当します。 具体的には「ここのトラックへの積み込み作業は、フォークリフトが場外と構内を出入りする箇所に近く接触の危険性があるため、誘導員を配置する」といった計画を立て、作業員全員に周知徹底することが求められます。
また、フォークリフトの乗り方自体を作業手順書として定め、標準化しておくことも有効です。フォークリフトの基本操作マニュアルについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
関連記事:フォークリフト基本操作マニュアル!作業手順書の例も紹介
④安全な運転・作業方法に関する義務:雇い入れ時に安全衛生教育を施す
4つ目の義務は、従業員の雇い入れ時には必ず安全衛生教育を受けさせることです。
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
法律上、具体的な教育方法までは明記されていません。しかし、労働安全衛生法の根本である「労働者の安全と健康を守る」目的を達成するには現場の実態に即した効果的な安全教育を実施すべきです。
その有効な方法の一つが「動画マニュアル」の活用です。マニュアルを動画化することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 文字では伝わりにくい危険箇所や正しい手順を、視覚的に分かりやすく伝えられる
- 指導者による教育内容のばらつきを防ぎ、教育の質を均一化できる
- 新人や外国人でも自分のペースで繰り返し視聴でき、知識の定着が図れる
このように動画マニュアルは「現場の実態に即した」安全教育を効率的かつ確実に実施し、法令遵守と事故防止を両立させるための強力なツールとなります。
動画マニュアルを活用したフォークリフトの安全教育や対策事例については、以下のリンクをクリックしチェックしてください。
>>「動画マニュアルを活用したフォークリフトの安全教育・対策事例」を見てみる
これら4つは法律で定められた事業者の義務ですが、「もし義務を果たさなければどうなるのか?」という疑問も生じるでしょう。そこで次の章では、法令違反時の罰則について解説します。
労働安全衛生法違反の罰則とは?
事業者が法律で定められた義務を果たさない場合、罰則が科されるだけでなく、企業の経営にも関わる重大なリスクを負うことになります。
無免許運転:6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
「①資格に関する義務:フォークリフトには2種類の資格がある」で解説したように、フォークリフトは有資格者しか運転できません。 万が一、無資格者に運転させた場合、労働安全衛生法 第119条(第61条違反)により、事業者(違反行為者および事業者)は「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されます。
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(労働安全衛生法61条が該当)
特定自主検査(年次点検)の未実施:50万円以下の罰金
特定自主検査は労働安全衛生法第45条の規定に基づき、労働安全衛生規則第151条の21および第151条の24において事業者への実施が義務付けられています。この義務を怠った場合、労働安全衛生法第120条の規定により「50万円以下の罰金」に処されます。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
法令違反は「知らなかった」では済まされません。事業者はこれらの義務を正確に理解し、遵守するための仕組みの構築が必要です。
次の章では、「違反を避けるためには具体的にどうすればいい?」という疑問にお答えします。
労働安全衛生法などの法令に違反しないために事業者がやるべきこと
法律違反は拘禁刑や罰金が科されるだけでなく、企業の存続にも関わる重大なリスクを伴います。 ここでは、罰則の影響と、義務を確実に果たすための具体的な行動について、以下の5つのポイントを解説します。
- 【重要】罰則の影響は単なる経済的なコストにとどまらない
- フォークリフト作業者を限定し、無免許運転をさせない
- 定期自主検査を毎日の業務に組み込み習慣化する
- 作業計画書を作成し、作業前に周知し徹底させる
- 安全教育は「努力義務」だが、事故防止のために実施する
【重要】罰則の影響は単なる経済的なコストにとどまらない
法令違反によるリスクは、罰金という経済的コストだけではありません。
「両罰規定」により当事者と責任者が共に罰せられる可能性あり
労働安全衛生法では、違反行為を行った作業員本人だけでなく、その事業者(法人)や現場の責任者(管理者)も罰せられる「両罰規定」が適用される場合があります。これにより、管理者が刑事罰(拘禁刑など)の対象となる可能性もゼロではありません。 企業にコンプライアンス違反のレッテルが貼られれば社会的信用を失い、経営基盤を揺るがしかねない事態に発展するという認識が不可欠です。
その他にも行政処分の可能性あり
万が一、点検未実施などが原因で労働災害が発生した場合、罰金に加えて操業停止命令、書類送検といったさらに重い行政処分が下される可能性があります。
このような事態を防ぐには、日頃からの安全教育の実施による従業員一人ひとりの安全意識の向上と、法令遵守のルールの徹底が不可欠です。
フォークリフトの安全教育を現場で実践する方法やコツ、事例については以下のリンクをクリックし別紙のガイドブックをご覧ください。
>>安全意識を高める!「フォークリフトの安全教育・対策事例」を見てみる
フォークリフト作業者を限定し、無免許運転をさせない
無資格運転を確実に防ぐには、社内の安全教育を受講した有資格者しか運転できない仕組みを構築することが重要です。
一方で、現場では「忙しいから」「手が空かないから」といった目先の効率を優先するあまり、資格を持たない外部のドライバーや他の作業員に運転を許してしまうケースが見受けられます。
しかしその者が無資格だった場合、重大な法令違反(労働安全衛生法違反)となるだけではありません。そもそも資格がないということは安全な操作知識や技術が不十分である可能性が高く、重大事故に直結する極めて危険な行為です。万が一事故が発生すれば、運転者本人だけでなく、それを許容した管理者や企業も重い責任(罰則や信用の失墜)を問われることになります。
このような「つい、うっかり」の無資格運転を根絶するには、例外を許さない厳格な管理体制が不可欠です。筆者が過去に在籍した物流現場でも、運転資格者を厳格に管理・限定する(=有資格者以外は物理的に運転できない状態にする)ようにした結果、無資格運転が根絶されました。
さらに、「安全意識と正しい操作技術を持つ有資格者」のみが運転するようになったことで、副次的な効果としてそれまで原因不明だった貨物の損傷やフォークリフト本体の傷・ヘコミも激減しました。
このような対策として、「フォークリフトの鍵は有資格者のみが管理・所持する」といった物理的なルールを設けることも有効です。
関連記事:フォークリフト作業で設定すべきルール一覧!浸透させるポイントと参考事例
定期自主検査を毎日の業務に組み込み習慣化する
年次検査(特定自主検査)は専門業者へ外注するのが基本ですが、「始業前点検」と「月次点検」は、教育を受けた現場の作業員が実施できます。
これを徹底するコツは、業務の一環として「習慣化」することです。 例えば朝礼やラジオ体操のように、業務開始前の必須タスクとして始業前点検を組み込んだり、月次点検も「毎月1日」や「第1月曜日」など実施日を固定し、全員が「やるのが当たり前」という環境を作ることが、抜け漏れや形骸化を防ぐ鍵となります。
そして、点検作業の教育には「動画」が有効です。紙のマニュアルでは伝わりにくい点検のポイントも、動画ならOJTのように正確に学べます。
実際に総合物流企業である「株式会社近鉄コスモス」ではフォークリフト始業前点検の手順の動画を作成しています。
※「tebiki現場教育」で作成
わからなければ何度でも見返せるため、点検作業の質を均一化し、安全レベルを維持できます。 この動画マニュアルは「tebiki現場教育」でかんたんに作成できます。ご興味のある方は、以下の資料をご覧ください。
作業計画書を作成し、作業前に周知し徹底させる
作業計画書の作成と周知は法令違反を防ぐだけでなく、作業環境の改善にも直結するため必ず実施すべきです。
作業計画書は、作業に潜む危険を洗い出す「リスクアセスメント」に基づいて作成されます。例えば、「ここは2台のフォークリフトが接近する危険があるため、指揮者を配置する」といった具体的な安全対策を計画に落とし込めます。
また、作業員全員がその日の作業全体の流れを把握できるため、作業効率の向上にも期待できます。
リスクアセスメントの進め方や例題について、元労働基準監督署署長が直々に解説した動画もご用意しております。以下のリンクをクリックし、本記事と併せてご覧ください。
>>現場のキケンを見極める『リスクアセスメント術』を動画で見る
従業員への継続的な安全教育は「努力義務」だが、事故防止のために実施する
労働安全衛生法では雇入れ時の教育(第59条第1項)に加え、労働者の作業内容を変更した際にも同様の安全衛生教育を実施することが法的に義務付けられています(第59条第2項)。これらは罰則を伴う法的義務です。
これとは別に、同じ作業に継続して従事している労働者に対し、事業場の安全衛生水準の向上を図る目的で定期的な教育を行うことは「努力義務」(第60条の2)とされています。しかし、事故を未然に防ぐという目的を達成するにはこの努力義務も積極的に果たすべきです。具体的には、定期的なKYT(危険予知訓練)の実施などが効果的でしょう。
次の章では「フォークリフトの事故防止に本当に効果のある安全教育とはどういったものがある?」という疑問に詳しくお答えします。
フォークリフトの事故防止に効果のある安全教育の方法
安全教育を実施するのであれば、法令遵守のためだけでなく、現場の事故防止に本当に効果のある「中身のある教育」を目指すべきです。 ここでは、事故防止に効果的な4つの方法をご紹介します。
- 行政の指針に基づき基礎を教える
- 作業を標準化し、慣れや自己流によるヒューマンエラーを防ぐ
- 危険予知活動(KYT)で危険への感受性を高める
- 安全教育に動画を取り入れ、職場の安全レベルを引き上げる
行政の指針に基づき基礎を教える
フォークリフトの安全教育は、国(厚生労働省)も実施を推奨しています。まずは、行政が示す指針に基づいた基礎的な教育を施すのが良いでしょう。
中央労働災害防止協会(中災防)は、フォークリフト運転業務従事者への安全衛生教育について、以下の内容と時間を例示しています。
| 科目 | 範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 最近のフォークリフトの特徴 | (1) フォークリフトの構造上の特徴 (2) 各種荷役運搬方法の特徴 | 2.0 |
| 2 フォークリフトの取扱いと保守 | (1) フォークリフトによる作業と安全 (2) フォークリフトの点検・整備 | 2.0 |
| 3 災害事例及び関係法令 | (1) 災害事例とその防止対策 (2) 労働安全衛生法令のうちフォークリフトに関する条項 | 2.0 |
| 計 | 6.0 |
引用:中災防「フォークリフト運転業務(労働安全衛生法施行令第20条第11号の業務)従事者安全衛生教育」
これらは基礎的な内容が多く、特にこれからフォークリフト作業に従事する従業員や、知識を再確認したい従業員には効果的です。講義内容は厚生労働省が公開している資料「フォークリフト」などを参考にするとよいでしょう。
作業を標準化し、慣れや自己流によるヒューマンエラーを防ぐ
作業に慣れてくると、「この方が早い」と安全よりも効率や生産性を重視した自己流の運転をしがちです。しかし、物流現場は時間に追われ煩雑になりがちだからこそ、安全を確保した上で効率や生産性を追求すべきであり、自己流の作業はヒューマンエラーや重大事故の温床となります。
例えば、「フォークリフトで荷物を運ぶ際は、荷物の高さに関わらず必ずバック走行を基本とする」というルールを定めて標準化します。 場合によっては方向転換が手間に感じるかもしれませんが、「運搬中の荷物で死角が生じ、地面に置かれた別の荷物が見えず接触した」といった事故は確実に防げます。
こうした物損事故は小さなミスに見えますが、「ハインリッヒの法則」によれば、1件の重大災害の背後には29件の軽微な事故と300件のヒヤリハットが存在するといわれています。小さな事故を見逃さず、標準化によって未然に防ぐことが重要です。
作業を標準化し、労働災害を未然に防止する安全教育の方法についてさらに詳しく知りたい方は、以下の資料も併せてご覧ください。
>>「ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育」をダウンロードする
危険予知訓練(KYT)で危険への感受性を高める
危険予知訓練(KYT)とは、作業に潜む危険を事前に洗い出し、対策を話し合うことで労働災害を未然に防ぐための安全活動です。 少人数のチームで取り組むことで、作業員一人ひとりの「危険への感受性」を高め、災害のない職場づくりを目指します。
KYTを定期的に行うことは、フォークリフトの事故防止においても非常に有効な手段です。筆者自身、同僚から「転倒」の危険性を指摘され、自分では思いもよらなかった危険に気づかされた経験があります。
とはいえ、KYTが「いつも同じ内容でマンネリ化している」「形骸化している」という現場も少なくありません。それらを回避する方法のひとつに「動画」があります。イラストシートよりもリアリティのある映像を用いることで、より多くの危険要因の発見や、議論の活発化が期待できます。
たとえば、ある物流企業ではロールボックスパレットの事故対策の具体的な方法を動画で共有しています。
※「tebiki現場教育」で作成
実際の作業映像であれば、経験の浅い作業員や短期アルバイトの方でも一目で状況を理解し、訓練に参加できます。また、訓練で決定した行動目標を動画で共有すれば、「いつでも見返せるおさらい教材」として知識の定着を促し、OJTのような教育負担も軽減できます。
動画を活用した次世代のKYTについて詳細や実際の動画を閲覧されたい方は、以下のリンクから別紙のガイドブックをご覧ください。
>>労災ゼロ!形骸化したKYTから脱却する「動画KYT」の詳細をみてみる
安全教育に動画を取り入れ、職場の安全レベルを引き上げる
安全教育の「質」を高めることは、職場の安全レベル向上に直結します。その最も効率的な手段が、動画の活用です。
なぜなら、紙のマニュアルや口頭でのOJTでは伝えきれない「動き」や「やってはいけない具体的な動作」を、動画なら誰でも視覚的に、かつ均一に理解できるからです。
例えば、総合物流企業である「株式会社近鉄コスモス」では、フォークリフトの基本動作に関する禁止事項を動画で共有し、教育の効率化と質の向上を実現しています。
※「tebiki現場教育」で作成
このように「やってはいけないこと」を明確に映像で見せることで、作業員の安全意識と理解度を効果的に高めることができます。 同社が動画の作成に使用した「tebiki現場教育」の詳細は、以下をクリックしてご確認ください。
>>フォークリフトの危険・作業ルールがわかりやすく伝わる動画マニュアル「tebiki現場教育」について詳しく見る
次の章では、「実際に動画活用で安全レベルを引き上げた企業の事例をもっと見たい」という方に向けて、物流企業の事例を2つご紹介します。
動画で効果的に安全教育を実施している物流企業の事例
動画を安全教育に活用し、従業員の安全意識を高めフォークリフトの事故防止に役立てている企業事例を2つご紹介します。
他にも事例を詳しく見てみたい方は、以下のリンクから別紙の資料をご覧ください。
>>【物流業】動画マニュアルを使った安全教育の取り組みと成果について詳しく見る
株式会社フジトランス コーポレーションの事例
最初にご紹介するのは、港湾運送や倉庫業などを手掛ける物流企業、株式会社フジトランス コーポレーションの事例です。
| 課題 | tebiki現場教育導入後の効果 |
|---|---|
| ・安全教育において教育者による指導内容や受講者の理解度にばらつきがあった ・特にフォークリフトなど「動き」を伴う作業の危険性を伝える教育が困難だった ・動画教材を内製したくても動画編集ソフトが複雑で現場で作成できなかった | ・動画によって安全教育の内容が標準化され、危険認識のズレが減少 ・現場担当者が質の高い安全教育コンテンツを簡単に作成可能に ・多言語翻訳機能で外国人労働者への安全ルール教育も円滑に |
同社では、特にフォークリフト作業など「動き」を伴う業務において、講師による指導のニュアンスの違いや受講者の受け取り方の差が安全教育上の課題でした。また、安全教育用の動画教材を内製しようとしても、従来の編集ソフトは操作が複雑で、現場担当者の大きな負担となっていました。
そこで動画マニュアル(tebiki現場教育)を導入し、安全衛生推進部が中心となって安全教育用の教材を作成。正しい作業の「動き」や危険なポイントを視覚的かつ具体的に示すことで、教える側と教わる側の危険認識のズレを大幅に減らすことに成功しました。
さらに多言語自動翻訳機能を活用し、増加する外国人労働者に対しても言語の壁を越えて安全ルールを正確に伝えることが可能となり、安全教育の質の向上と標準化を実現しています。
>>同社が活用した動画マニュアル「tebiki現場教育」の機能詳細や事例をもっと見たい方はこちらをクリック!
ASKUL LOGIST株式会社の事例
次にご紹介するのは、EC専門の総合物流企業であるASKUL LOGIST株式会社の事例です。
| 課題 | tebiki現場教育導入後の効果 |
|---|---|
| ・OJTや紙の安全マニュアルでは内容にばらつきがあり、教育が標準化できていなかった ・安全ルールが言語の壁などで多様な人材に伝わりにくかった ・安全教育を繰り返し教える工数が多く、教育担当者の負担が大きかった | ・動画と自動翻訳で、多様な人材が安全ルールを理解しやすい教育を実現 ・動画をKYT(危険予知訓練)に活用し、従業員の危険感受性と安全意識が向上 ・新人の安全教育時間が大幅短縮(2時間→30分)し、管理者の負担も激減 |
同社では短時間勤務者や外国籍スタッフ、障がいを持つスタッフなど多様な人材が活躍しており、誰にでも確実に安全ルールを伝え、理解してもらうことが課題でした。しかし従来のOJTや紙マニュアルによる教育では内容のばらつきや理解度の差が生じやすく、特に危険な動作や注意すべきポイント、言語の壁などが安全教育の障壁となっていました。
そこで動画マニュアル(tebiki現場教育)を全拠点で導入。労働安全衛生法に基づくリスクアセスメントを重視し、安全な作業標準を動画で整備しました。字幕の自動翻訳機能により、国籍や言語に関わらず全ての従業員が安全に関する情報を正確に理解できるよう工夫しています。
さらにヒヤリハット事例の共有やKYT(危険予知トレーニング)にも動画を活用し、現場の状況に近い臨場感で危険への感受性を高め、安全意識の向上を図っています。これにより導入教育の工数を大幅に削減しつつ、安全で標準化された作業を実現しています。
>>同社が活用した動画マニュアル「tebiki現場教育」の機能詳細や事例をもっと見たい方はこちらをクリック!
まとめ:法令遵守と安全教育の両立で、事故ゼロの職場を目指そう
フォークリフト運用において、労働安全衛生法および安全衛生規則の遵守は単なる義務ではなく「命を守るための最低限のルール」です。資格・点検・作業計画・安全教育といった4つの義務を確実に果たすことで、重大事故のリスクを大幅に減らすことができます。
さらに教育を「形だけ」で終わらせず現場で実効性をもたせるには、動画マニュアルのように“見て分かる仕組み”を導入することが効果的です。安全意識の浸透と教育の標準化を両立し法令遵守と事故防止を実現することが、これからの現場に求められる真の安全管理といえるでしょう。
本記事でご紹介した動画マニュアル「tebiki現場教育」は、多くの物流企業様にご活用いただいています。スマートフォン1つで誰でも簡単に教育動画を作成・共有でき、現場の安全レベル向上に貢献します。
ご興味をお持ちの方は、是非下記の資料をご覧ください。
引用元
・e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
・e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」
・e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
・厚生労働省「フォークリフト」