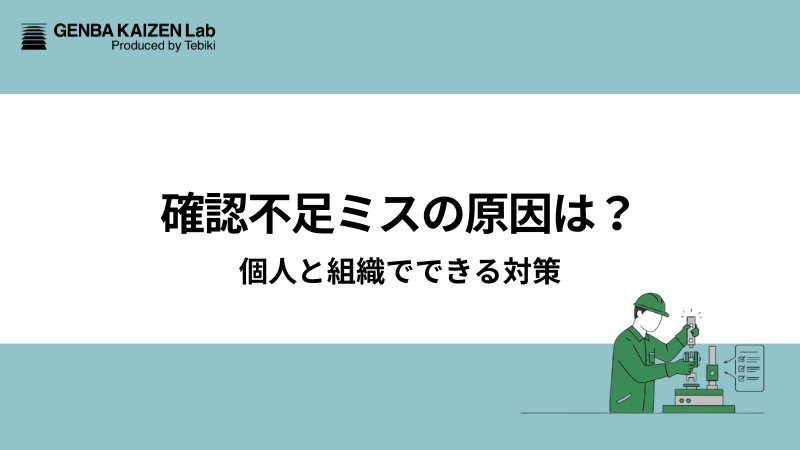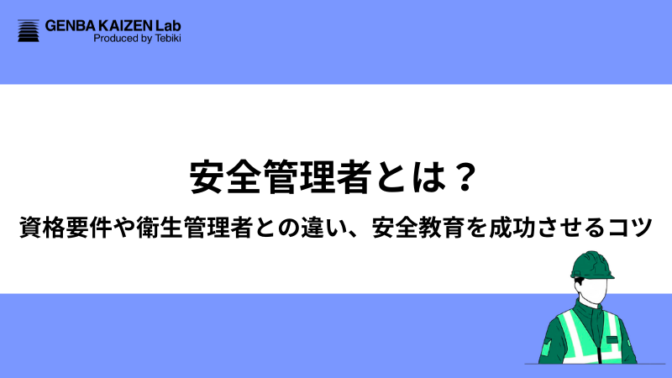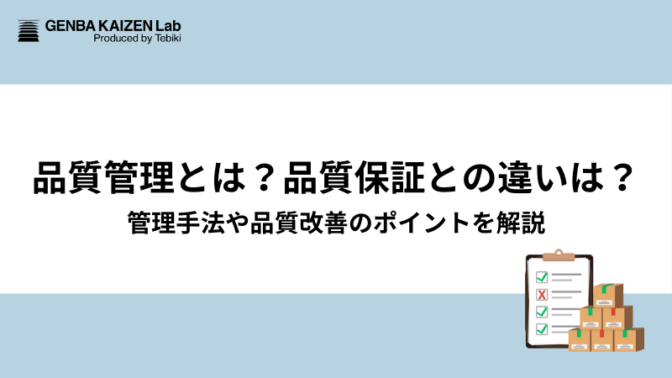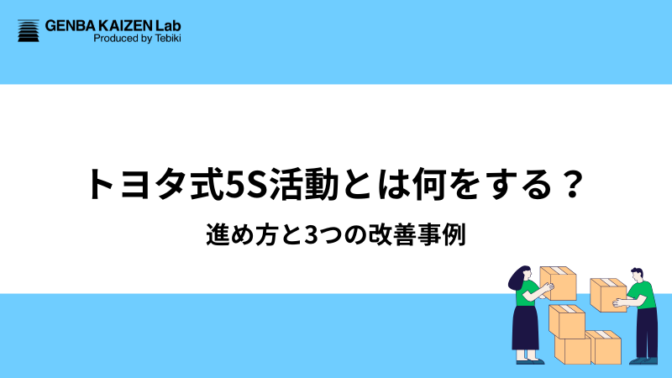かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
仕事での確認不足によるミスは、誰にでも起こり得る悩ましい問題です。しかし、その原因を正しく理解し、適切な対策を講じれば、必ず減らすことができます。
そこでこの記事では、多くの企業の教育現場を支援してきた弊社の実践的な経験と豊富な知見に基づき、確認不足ミスの根本原因から、個人でできる対策、そして組織全体で取り組むべき防止策までを網羅的に解説します。
確認不足によるミスは、個人の注意力だけに頼っていては防ぎきれません。
なぜ人は間違えるのか。ヒューマンエラーが起きるメカニズムを解明し、精神論ではなく「仕組み」として未然に防ぐための具体的な対策を以下の資料で解説します。
>>製造業におけるヒューマンエラーの未然防止と具体的な対策方法を見てみる
目次
確認不足によるミスが発生する根本的原因
仕事における確認不足は、単なる「うっかり」だけでは片付けられない、様々な要因が絡み合って発生します。ここでは、個人に起因するものと、環境や業務プロセスに起因するものに分けて、その主な原因を探っていきましょう。
自社やご自身の状況と照らし合わせながら、根本的な課題を見つけるヒントにしてください。
確認不足などのミスは、個人の注意不足や環境要因だけで語れるものではありません。なぜ人はわかっていても確認を怠るのか、その行動原理に踏み込む必要があります。
行動科学の視点からエラーのメカニズムを解明し、精神論に頼らずミスを未然に防ぐための具体的な手法を以下の資料で解説します。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
個人の意識・行動に起因する原因
個人の特性やその時の状態が、確認不足を引き起こすことがあります。
思い込みや慣れによる慢心
「いつもこうだから大丈夫だろう」「これは前にやったことがあるから」といった思い込みや慣れは、注意深い確認を怠らせる大きな原因です。
特に、経験を積んだ中堅社員ほど「これくらい確認しなくても分かる」と考えてしまいがちですが、その慢心が思わぬミスに繋がることがあります。常に初心を忘れず、基本に立ち返る姿勢が求められます。
「いつも通りで大丈夫」という慢心は、確認手順を省く「ルール無視」の始まりです。
この品質意識の低下が招くリスクへの考え方と、根本的な対策を以下の資料で解説します。
>>品質意識の低下が招く「ルール無視」に対する考え方と対策を見てみる
知識・経験不足
業務内容や手順に関する知識・経験が不足していると、どこを確認すべきか、何が重要なのかを判断できず、結果的に確認が不十分になります。
これは特に、新人や若手社員、あるいは新しい業務を担当し始めたばかりの人によく見られるケースです。「何を確認すれば良いか分からない」状態では、効果的な確認は行えません。
焦りやプレッシャー
納期が迫っていたり、複数のタスクを同時に抱えていたりすると、精神的な焦りから確認作業を急いでしまいがちです。「早く終わらせなければ」「次のタスクに移らなければ」というプレッシャーが、丁寧な確認プロセスを省略させ、ミスを誘発します。
時間的な制約がある中でも、冷静さを保つ工夫が必要です。
疲労や集中力の低下
睡眠不足や長時間労働による疲労は、集中力や注意力の低下を招きます。頭がボーっとしている状態では、普段なら容易に気づけるはずの数字の間違いや誤字脱字、手順の抜け漏れなどを見逃しやすくなります。
体調管理も、確認不足を防ぐための重要な要素と言えるでしょう。
情報のインプット不足・誤解
指示や情報の受け取り方に誤解があったり、必要な情報が十分に伝わっていなかったりする場合も、確認不足に繋がります。「多分こうだろう」という憶測で作業を進めてしまうと、後で大きな手戻りが発生する可能性があります。 特に、口頭での指示や複雑な内容の伝達では、認識のズレが生じやすいものです。
例えば物流業の「ソニテック株式会社」は以前、新人教育の際、作業内容の正確な伝達が難しく、誤った情報がインプットされてしまうことがしばしばありました。
マンツーマン指導を行っているものの、作業内容の正確な伝達が難しく、ミスが発生することもしばしばあります。例えば、「商材の表面にシールを貼る」という指示が、誤って「横面にシールを貼る」という行動になるなど、指示の不明瞭さが課題となっています。
このように、情報の受け手と送り手の間で認識が合っていないと、確認作業そのものが成り立たなくなる可能性があります。コミュニケーションの初期段階での認識合わせが重要です。
※同社の詳しい課題と改善に向かった事例は、以下の記事で詳しく紹介されています。
インタビュー記事:3ヶ月間の直接指導を動画マニュアルで 完全に置き換え、業務の効率化を実現
組織・環境・仕組みに起因する原因
個人の問題だけでなく、働く環境や組織の仕組みが確認不足を誘発しているケースも多々あります。リーダーやマネージャーの方は特に、これらの要因に目を向け、改善に取り組む必要があります。
業務プロセス・手順の不明確さ
作業の手順や確認すべき項目が明確に定められていない、あるいは人によってやり方が違う(属人化している)場合、何をどのように確認すれば良いのか分からず、確認漏れが発生しやすくなります。業務の標準化が進んでいない状態は、確認不足ミスの温床と言えます。
例えば製造業の「大同工業株式会社」でも以前、属人化による手順の違いが課題となっていました。
基本的な内容は文書マニュアルに記載されていますが、実際に実務をおこなう時のちょっとしたコツやポイントは言語化しにくく、動作を見せて伝え、その実務を通じて担当者が会得するしかなく、しかも担当者によってコツやポイントに差があり、それゆえ業務手順も異なるという”我流化”(業務品質のバラつき)が起こっていました。
このように、手順が標準化されていない状態は、確認の基準そのものが曖昧になりがちです。
※同社の詳細な課題と、そこから改善に向かった事例については以下の記事で紹介しています。
インタビュー記事:製造業の技術部門の業務を動画で標準化。品質評価に関わるヒヤリハットを8割削減して、多能工化を実現。
コミュニケーション不足・連携不足
チーム内や部署間での情報共有が不十分だったり、連携がうまくいっていなかったりすると、認識の齟齬が生じ、確認漏れやミスに繋がります。「言ったはず」「聞いたはず」という思い込みやすれ違いが、確認作業の精度を低下させます。
特に、拠点が多い企業や部門間の壁が高い組織では、この問題は顕著になりがちです。
例えば物流業の「ASKUL LOGIST株式会社」のように、全国に多数の物流拠点を展開する企業では、拠点間で業務の進め方やノウハウにばらつきが出やすく、情報共有の仕組みがなければ、ある拠点での改善事例や注意喚起が他の拠点に伝わらず、同じようなミスが繰り返される可能性があります。
部門間・拠点間のコミュニケーション不足は、確認すべき情報そのものが不足したり、誤った前提で確認作業を行ってしまったりするリスクを高めます。
※同社の詳細な課題と、そこから改善に向かった事例については以下の記事で紹介しています。
インタビュー記事:従業員数3,500名超・全国15拠点で 動画マニュアルtebikiを活用!
教育・研修体制の不備
業務に必要な知識やスキル、確認の重要性についての教育が不十分だと、従業員はどのように業務を進め、何を確認すべきかを体系的に理解できません。
特にOJT(On-the-Job Training)が指導担当者任せになっており、内容にばらつきがあったり、そもそも指導役が忙しくて十分な時間を確保できていなかったりすると、人材育成が進まず、確認不足を招く一因となります。 多くの企業が、このOJTに関する課題を抱えています。
例えば人材紹介業を展開する「株式会社GEEKLY」では、新人の入社時期がバラバラなため集合研修が難しく、OJTが中心となるものの、トレーナーの時間を大幅に奪ってしまうという問題がありました。
新人社員が1人入社すると1ヵ月で50時間程教育に時間をかけていました。また、新人教育を担当するトレーナーはエース社員が受け持つことが多かったのですが、教育の負担が大きく新人を請け負ったチームは目標が未達になってしまうという課題がありました。
※同社の詳細な課題と、そこから改善に向かった事例については以下の記事で紹介しています。
インタビュー記事:年間の新人教育時間を3,700時間削減。トレーナーの教育時間が大幅に減り営業成績も向上!
時間的プレッシャーが高い職場環境
常に納期に追われ、時間に余裕がない職場環境では、従業員は確認作業に十分な時間を割くことが物理的に難しくなります。「確認よりもスピード」という文化が根付いている場合、丁寧な確認は軽視されがちです。
組織全体として、効率化と品質担保のバランスを見直す必要があるかもしれません。
心理的安全性の低さ
ミスを過度に恐れるあまり、疑問点を確認できなかったり、問題を指摘しづらかったりする職場環境も、確認不足を助長します。「こんなことを聞いて怒られないだろうか」「指摘して関係が悪くならないか」といった不安が、必要な確認をためらわせるのです。
心理的安全性が低いと、潜在的なリスクが見過ごされやすくなります。
それらの心理メカニズムを行動科学で読み解き、根本から解決する方法を以下の資料で解説します。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
確認不足が引き起こすミスや事故の例
「たかが確認不足」と軽く考えていると、思わぬ事態を招くことがあります。
ここでは、様々な業界で見られる確認不足によるミスや事故の具体例をいくつかご紹介します。これらは決して他人事ではなく、あなたの職場でも起こりうることです。
▼製造業の労災対策を網羅的に知りたい方▼
製造業での労災ゼロを達成する従業員の安全意識を向上させる安全教育
▼ヒューマンエラーや作業ミスの対策を重点的に知りたい方▼
・繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網
・ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育
デスクワークにおける事例
オフィスワーク中心の業務でも、確認不足は様々な問題を引き起こします。
事務・経理での事例
請求書に記載する金額の桁を一つ間違えて入力し、気づかずに取引先に送付してしまうケースがあります。後日、取引先からの指摘で発覚し、謝罪と再発行の手間が発生します。また、締結する契約書の細かな免責条項を確認せずサインし、後にトラブルが発生した際に、自社に著しく不利な条件をのむことになった、という事例も少なくありません。
さらに、メールの宛先(To, Cc, Bcc)を確認せずに、機密情報を含むファイルを社外の無関係な人物に誤送信してしまい、情報漏洩インシデントに発展することもあります。
営業での事例
顧客への提案資料を作成する際、以前の類似案件の情報を流用した部分の確認を怠り、現在の顧客の要望と異なる内容を提示してしまうことがあります。商談中に「話が違う」と信頼を損ねる結果になりかねません。
また、開発部門に最新の生産状況を確認せずに、安易に納期を回答し、結果的に大幅な納期遅延となりクレームに繋がるケースもあります。見積書の計算根拠となる単価や数量の確認が漏れており、赤字になる金額で受注してしまい、後で大きな損失を出すこともあります。
開発・ITでの事例
クライアントからの要求仕様に関する質疑応答の記録を確認せず、「確かこう言っていたはず」という思い込みで開発を進めた結果、完成後に大規模な仕様変更(手戻り)が必要になることがあります。
また、テスト項目の網羅性を確認しないままテストを実施したため、特定の条件下で発生する重大なバグを見逃し、リリース後にシステムダウンを引き起こすケースもあります。サーバー構築後のセキュリティ設定リストの最終確認を省略したため、不要なポートが開放されたままとなり、不正アクセスの被害に遭うこともあります。
デスクレスワーク(現場作業)における事例
製造、物流、建設、小売、医療・介護など、現場での作業においては、確認不足が直接的に製品の品質や人命に関わる重大な事故に繋がるケースもあります。
製造現場での事例
製造業では、確認不足によるミスの未然防止は重要課題の1つです。製造業におけるミスは、工場全体の稼働率・生産性の低下につながるため、ミスの削減がなされる仕組みづくりはどの現場でも重要です。
例えば製造業の「クマガイ特殊鋼株式会社」では、同じ作業者が連日、同じミスをしてしまう場面が発生しました。これらのミスは、正しい手順とポイントを確認していれば防げるものとして、同社はミスが発生しないための教育体制を刷新し、改善に向かっています。
具体的には、正しい作業手順を動画マニュアルとして映像化し、従業員に視覚的に理解してもらう教育体制を整備しました。同社の詳しい事例は以下のインタビュー記事からご覧いただけます。
インタビュー記事:人材危機に立ち向かう創業100年以上の中小企業。tebikiの活用で教育体制の改革と多能工化を推進!
物流現場での事例
物流現場では「仕分けミス」が課題としてよく挙げられますが、作業手順の確認不足のためにミスが発生するケースは珍しくありません。
例えば物流業の「株式会社ジェイ・メイト」は、誤った手順がどうしても現場で発生してしまうことに課題を感じ、正しい手順を現場に浸透させるための方法を模索していました。
現状では、OJT教育をそのまま「動画」におさめ、スタッフ全員に見てもらうような教育体制を整備し、ミスの削減につなげています。同社の改善事例は以下のインタビュー記事からご覧いただけるので、あわせてご覧ください。
インタビュー記事:効率よく再教育することで、倉庫内作業の仕分けミスが半減!
建設現場での事例
設計変更があったにも関わらず、現場の職人が古い図面で作業を進めていることへの確認を現場監督が怠った結果、建物の基礎部分に構造的な欠陥が生じ、是正に多大な費用と時間を要することがあります。
また、高所作業前に、安全帯の使用状況や足場の固定状況に関するチェックリストの確認を形骸化した結果、作業員がバランスを崩して転落事故を起こすケースもあります。発注担当者が、発注する資材の数量や納入日について現場責任者との最終確認を行わなかったため、現場に不要な資材が大量に届き、作業スペースを圧迫してしまうこともあります。
小売・飲食現場での事例
特売商品の発注数を過去のデータのみで判断し、当日の天候や近隣イベントなどの特殊要因を確認せずに発注した結果、予想を大幅に下回る売上となり、大量の在庫(ロス)を抱えることがあります。
また、注文を受けた際に、顧客のアレルギーに関するヒアリングと、キッチンへの伝達内容の復唱確認を怠った結果、提供した料理にアレルゲンが含まれており、顧客がアナフィラキシーショックを起こし救急搬送されるという、極めて重大な事態を招くこともあります。
医療・介護現場での事例
患者へ薬剤を投与する直前の「氏名」「薬剤名」「用量」「用法」「時間」の5R確認を、思い込みで省略した結果、別の患者の薬剤を誤投与し、健康被害を引き起こすことがあります。
また、患者のカルテ情報(アレルギー歴、既往歴など)の最終確認を担当医と看護師の間で行わなかったため、禁忌とされている薬剤を投与してしまい、患者の容態が急変するケースもあります。夜勤から日勤への申し送り事項(患者の状態変化、注意点など)の確認が口頭のみで、記録によるダブルチェックがなされなかった結果、重要な情報が伝わらず、必要なケアが行われないといった事態も起こり得ます。
これらの事例はほんの一部です。確認不足は、あらゆる業務において、信用の失墜、経済的な損失、そして時には人命に関わる深刻な事態を引き起こす可能性があることを、改めて認識する必要があります。だからこそ、確認不足が生じないための仕組みを講じることが急務なのです。
確認不足ミスを防ぐための具体的な対策【個人編】
確認不足によるミスは、意識と行動を変えることで確実に減らすことができます。ここでは、個人で実践できる具体的な対策方法をご紹介します。少しの心がけで、ミスは着実に減らせるはずです。
「思い込み」を排除し、常に疑問を持つ姿勢を
「たぶん大丈夫だろう」「いつも通りで問題ないはず」といった安易な考えは捨て、「本当にこれで合っているか?」「見落としている点はないか?」「前提条件は変わっていないか?」と常に疑問を持つ癖をつけましょう。
マニュアルや指示書の内容を鵜呑みにせず、自分の頭で考え、納得した上で作業を進めることが重要です。疑う視点を持つことが、確認の質を高めます。
チェックリストを作成し、確認作業を「見える化」する
確認すべき項目をリスト化し、1つひとつチェックしていく方法は、シンプルながら非常に効果的です。特に、繰り返し行う定型作業や、手順が複雑で間違いやすい業務には有効と言えます。
作成したチェックリストは、壁に貼ったり、PCのデスクトップに置いたりして、常に目に入るようにしておくと良いでしょう。また、ミスが発生したり、業務内容が変わったりした際には、リストを更新し、常に最新の状態に保つことも大切です。
指差し確認・声出し確認で注意力を高める
重要な数字や、間違いやすい設定箇所、安全に関わる項目などは、指で差し示しながら「ヨシ!」、あるいは声に出して「〇〇(確認項目)、確認しました」と宣言することで、注意力を高め、見落としを防ぐことができます。
一見、原始的な方法に見えるかもしれませんが、人間の脳は、視覚だけでなく、触覚や聴覚など五感を活用することで、より確実に情報を認識すると言われています。特に、ルーティンワークで集中力が途切れがちな時に有効です。
時間に余裕を持ったスケジュール管理を徹底する
焦りは確認不足の大きな原因です。業務に取り掛かる前に、必要な作業時間だけでなく、確認作業に要する時間も予め見積もり、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。納期ギリギリになって慌てて確認するのではなく、計画的に確認時間を確保することがコツです。タスクを細分化し、各工程の完了時に確認ステップを入れるのも効果的です。
5W1Hを意識して情報整理・伝達を行う
指示を受ける際や、他の人に情報を伝える際には、「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」の5W1Hを明確にすることを意識しましょう。
これにより、情報の抜け漏れや曖昧さをなくし、関係者間の認識のズレを防ぐことができます。整理された情報は、確認作業そのものを容易にし、ミスの防止に繋がります。
5W1Hの意識は重要ですが、個人の注意力や記憶力に頼る対策には限界があります。「人」の努力だけでミスをゼロにすることはできません。
個人の能力に依存せず、誰でも確実に業務を遂行できる「標準化された仕組み」を作るには、マニュアルの整備が不可欠です。作成のコツとすぐに使える見本を以下の資料で紹介します。
>>そのまま真似できる「見本」付き 業務マニュアルの作り方完全ガイドを見てみる
【組織・チーム編】確認不足ミスを防ぐための仕組みづくりと環境整備
個人の努力だけでは、確認不足によるミスを完全になくすことは困難です。特に、ヒューマンエラーは一定の確率で発生しうるものです。だからこそ、チームや組織全体で、ミスが起こりにくい「仕組み」を作り、環境を整備していくことが不可欠です。ここでは、リーダーやマネージャーが中心となって取り組むべき対策をご紹介します。
業務手順の明確化と標準化(マニュアル整備)
「誰がやっても同じ成果を出せる」ように、業務の手順を明確にし、標準化することは、確認不足対策の根幹と言えます。分かりやすい業務マニュアルを整備することで、作業の品質が安定し、確認すべきポイント(チェック項目)も明確になります。
標準化の重要性については、多くの企業が課題として挙げています。例えば「理研ビタミン株式会社」では、紙マニュアルによる教育の限界を感じていました。
品質保証部門での分析手順書に「フラスコに試薬Aと試薬Bを入れて、よく振り混ぜる」というのがあります。この「よく振り混ぜる」という文字の情報だと、人によっては一方向だけに振る、縦方向に振る、小刻みに振る、といったバラツキが生まれてしまいます。
こうした課題に対し、全部門が共通認識を持てるようなマニュアル整備(動画マニュアルtebiki)を進めた結果、業務の標準化に成功しています。 同社の標準化に向けた具体的な取り組みは、以下の記事で詳しく紹介しています。
インタビュー記事:品質保証部門と製造部門がONEチームで取り組んだ業務標準化と技術伝承
業務の標準化を進める上でのマニュアル整備のポイントやコツについて、より詳しく知りたい方は、「カンコツが伝わる!「現場で使われる」作業手順書のポイント(pdf)」が参考になります。現場で確実に使われる標準書の作成ノウハウがまとめられているので、以下をクリックして、ダウンロードしてみてください。
>>カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイントを見てみる
ダブルチェック・トリプルチェックの仕組み化
重要な業務やミスが発生した場合の影響が大きい作業については、複数人で確認する体制(チェック体制)を構築しましょう。単に「ダブルチェックしてください」と指示するだけでなく、「誰が(担当者)」「いつ(タイミング)」「何を(確認項目)」「どのように(確認方法)」を確認するのかを明確にルール化し、形骸化しないように運用することが重要です。
責任の所在を明確にし、チェックリストなどを活用すると良いでしょう。ただし、過剰なチェックは業務効率を低下させる可能性もあるため、業務の重要度やリスクに応じて、最適なチェック体制を検討する必要があります。
ダブルチェック体制を整えても、人間の心理が引き起こす「確認したつもり」や「形骸化」までは防げません。
なぜ人はリスクある行動をとってしまうのか。行動科学の視点からそのメカニズムを解き明かし、精神論や回数重視のチェックに頼らない事故防止策を以下の資料で解説します。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
「分かりやすさ」を追求したマニュアルへのアップデート
マニュアルを整備しても、「内容が古くて使えない」「文字ばかりで読む気がしない」「読んでも具体的にどうすればいいか分からない」といった状態では、せっかくのマニュアルも形骸化してしまいます。特に、現場作業におけるコツや感覚的な要素、一連の流れで理解すべき複雑な手順などは、文字や静止画だけのマニュアルでは十分に伝わりにくいことがあります。
そこで有効なのが「動画マニュアル」です。実際の作業風景やPC画面の操作などを映像で見せることで、業務全体の流れ、細かい手順、注意すべきポイント、言葉では説明しにくい微妙な力加減やタイミングといった技術(カンコツ)まで、直感的かつ正確に理解できます。
実際にどのような動画マニュアルが業務で使われているのか、具体的なサンプルを見てみたい方は、「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集(pdf)」が役立ちます。様々な現場の動画サンプルがまとめられており、自社での活用イメージを膨らませるのに最適です。以下をクリックして、ダウンロードしてみてください。
>>実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集を見てみる
情報共有を円滑にするコミュニケーション環境の整備
チーム内での定例ミーティングの実施、情報共有ツール(チャット、プロジェクト管理ツールなど)の積極的な活用、相談しやすい雰囲気づくりなどを通じて、業務に必要な情報がスムーズに、かつ正確に伝わる環境を作りましょう。
特に、「報告・連絡・相談(報連相)」を徹底し、認識の齟齬や情報のブラックボックス化を防ぐことが重要です。誰が何を知っているのか、どこに情報があるのかが分かりやすい状態を目指しましょう。
定期的な教育・研修の実施と効果測定
マニュアルを整備するだけでなく、その内容を従業員が正しく理解し、実践できるようにするための教育・研修を定期的に実施することが重要です。新人研修だけでなく、既存従業員向けのフォローアップ研修や、業務変更に伴う研修なども計画的に行いましょう。
研修後は、理解度テストや実技チェックなどを行い、教育効果を測定し、必要に応じて追加のフォローアップを行うことで、知識とスキルの定着を図り、業務改善に繋げます。人材育成は、一過性のものではなく、継続的な取り組みが不可欠です。
ミスを報告・相談しやすい心理的安全性の高い環境づくり
万が一ミスが発生した場合でも、それを隠さずに速やかに報告・相談できるような、心理的安全性の高い職場環境を醸成することが極めて大切です。ミスを個人の責任として過度に追求するのではなく、「なぜそのミスが起こったのか」という原因分析(真因追求)に焦点を当て、組織として確認ミス防止策を考える文化を育むことが重要です。
誰もが安心して「分からない」「困っている」「間違えたかもしれない」と言える環境が、結果的に大きな事故や問題を未然に防ぐことに繋がります。
もし確認不足でミスをしてしまったら?適切な対処法
どれだけ注意していても、人間である以上、ミスを完全にゼロにすることは難しいかもしれません。大切なのは、ミスをしてしまった後に、どのように対応し、次に活かすかです。
速やかな報告と正確な情報伝達
ミスに気づいたら、あるいはミスかもしれないと感じたら、隠さずに、できる限り速やかに上司や関係者に報告しましょう。
その際、「いつ、どこで、誰が、何を、どのように」間違えたのか、そして現状どうなっているのか、事実を客観的かつ正確に伝えることが重要です。初期対応の遅れや不正確な情報が、問題をさらに大きくし、被害を拡大させてしまう可能性があります。
ミスの原因分析と具体的な対策の検討
なぜそのミスが起こったのか、根本的な原因を客観的に分析しましょう。単に「不注意だった」で終わらせるのではなく、「個人の思い込みがあったのか」「業務プロセスに問題はなかったか」「マニュアルは分かりやすかったか」「コミュニケーションは十分だったか」「教育は足りていたか」など、多角的な視点で掘り下げます。
そして、分析結果に基づいて、具体的で実行可能な対策を考え、チームや関係者と共有します。
確認不足ミスを防ぐ対策の例
- 確認漏れを防ぐために、チェックリストの項目を追加・修正する
- ミスが発生した箇所について、マニュアルの記述をより分かりやすく修正・追記する(必要であれば、動画マニュアル化して視覚的に分かりやすくすることも検討)
- ダブルチェックの担当者や確認タイミング、確認方法を見直す
- 関係者への情報共有方法やツールを改善する
- ヒューマンエラーが発生しやすい工程に、ツールを導入したり、作業手順を変更したりする
ミスの原因を「不注意」で片付けるのは、単なる「その場しのぎ」に過ぎません。
根本原因を突き止め、再発を確実に防ぐための「要因分析」の手法と、それを用いた現場改善の進め方を以下の資料で解説します。
>>その場しのぎを常態化させない要因分析による現場改善を見てみる
対策の実行と効果検証
決定した対策は、必ず実行に移し、関係者に周知徹底しましょう。「決めただけ」「周知しただけ」で終わらせず、その効果が出ているか、他に新たな問題が発生していないかを定期的に検証することが重要です。
もし効果が薄かったり、別の問題が出てきたりした場合は、再度原因を分析し、対策を修正します。このように、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回していくことが、継続的な品質向上とミスの削減に繋がります。
確認不足対策をサポートするツール活用という選択肢
個人の意識改革や組織的な仕組みづくりに加えて、テクノロジー(ツール)をうまく活用することも、確認不足によるミスを防ぎ、業務の効率化と品質向上を両立させるための有効な手段です。
ここでは、確認不足対策に役立つ一般的なツールと、特にマニュアルの作成・運用・活用を効果的にサポートするツールについて触れておきます。
動画マニュアル作成ツール
動画マニュアルは、確認不足によるミス対策に有効な手段です。基本的に、業務や作業のミスが発生する主な要因として「正しいやり方や順序が分からない」点が主に挙げられるため、視覚的な分かりやすさが特徴である動画マニュアルはミスの削減に寄与します。
特に、文字や静止画だけでは伝わりにくい複雑な手順や実際の操作、注意すべきポイントを映像で具体的に示すことで、直感的な理解を促進します。
例えば製造業の「児玉化学工業株式会社」は、動画マニュアルを内製で作成しており、正しい業務手順を動画におさめています。これにより、「従業員が正しい業務プロセスをいつでも確認できる体制」が整備され、現場全体のミス削減につながっています。
同社が実際に活用している動画マニュアルを以下に掲載するので、参考にしてみてください。
▼ヤスリでバリをとる動画マニュアル(音量にご注意ください)▼
※「tebiki」で作成
いずれの工程も文字では伝えにくく、通常であればOJTによる教育負担が大きい工程なので、何度も業務手順の確認が発生しやすい(つまり確認不足によるミスが発生しやすい)ですが、動画マニュアルによって作業イメージが明確に固まりやすくなります。
上記動画マニュアルは「tebiki現場教育」で作成されていますが、tebikiの詳細機能や活用事例について少しでも気になった方は、以下の画像をクリックしてtebikiのサービス資料もあわせてご覧ください。
マニュアル作成・管理ツール
業務手順の標準化と、分かりやすいマニュアルの作成・更新・共有・運用を効率化するためのツールです。確認不足によるミスは、多くの場合、「正しいマニュアル整備がなされていない」「マニュアルが読まれる文化が醸成されていない」ことが主な原因です。
したがって、わかりやすいマニュアルの作成・管理ツールは1つの有効手段と言えます。わかりやすいマニュアルの作成方法や手順、ポイントについては、「成功に導く「わかりやすいコツ」つき はじめてのマニュアル作成ガイド(pdf)」が参考になります。これからマニュアルを本格的に作成したい場合は、以下の画像をクリックして、資料をダウンロードしてみてください。
タスク管理ツール・プロジェクト管理ツール
「誰が」「何を」「いつまでに」行うべきかを可視化し、タスクの抜け漏れを防ぎます。多くのツールにはリマインダー機能がついており、確認作業の実施漏れ防止にも役立ちます。業務の進捗状況をチーム全体で共有できるため、連携ミスを防ぐ効果も期待できます。
コミュニケーションツール・情報共有ツール
ビジネスチャットツールや社内SNSなどを活用することで、迅速かつ手軽な情報共有や質疑応答が可能になり、認識の齟齬やすれ違いを減らすことができます。メールよりも気軽に確認し合えるため、コミュニケーションのハードルが下がり、結果的に確認不足を防ぐことに繋がります。
まとめ:確認不足は「仕組み」で防ぐ!継続的な改善でミスゼロを目指そう
確認不足によるミスは、個人の注意力の問題だけに帰結させるべきではありません。その背景には、業務プロセス、マニュアルの分かりやすさ、コミュニケーションのあり方、教育体制、そして組織文化など、様々な要因が絡み合っています。だからこそ、個人の意識改革や努力はもちろんのこと、組織全体でミスが起こりにくい「仕組み」を構築し、それを継続的に改善していくことが何よりも不可欠です。
特に、業務手順の明確化と標準化は、確認不足対策の根幹をなす重要な取り組みです。作業の手順や確認すべきポイントが誰にとっても明確であれば、ミスは起こりにくくなります。そして、その標準化された手順を、新人からベテランまで、誰もが分かりやすく理解し、確実に実践してもらうためには、質の高いマニュアルの整備と、それを活用する文化の醸成が欠かせません。
文字や図だけでは伝わりにくい現場のコツや一連の作業フローも、動画マニュアルを活用すれば、視覚的に分かりやすく、かつ正確に伝えることが可能です。これにより、教育効果は飛躍的に高まり、業務の品質向上と安定化に大きく貢献します。
弊社では、製造・物流・小売・介護といったデスクレスワーカーが多く働く現場の教育に特化した動画マニュアル作成・共有ツール「tebiki現場教育」を提供し、これまで数多くの企業の業務改善、人材育成、品質向上、そして安全確保を支援してまいりました。tebikiのような動画マニュアルが、具体的にどのように現場の課題解決に貢献できるのか、その機能や導入効果、実際の企業での活用事例などを詳しくまとめた資料をご用意しています。ご興味がある方は、下の画像をクリックしてダウンロードしてみてください。