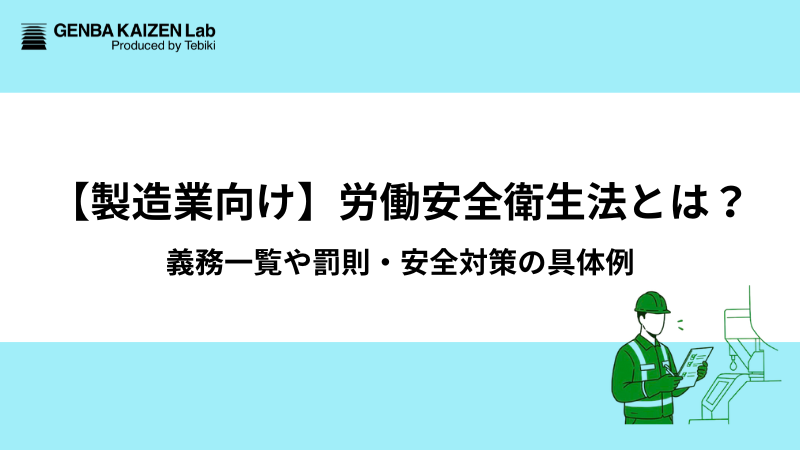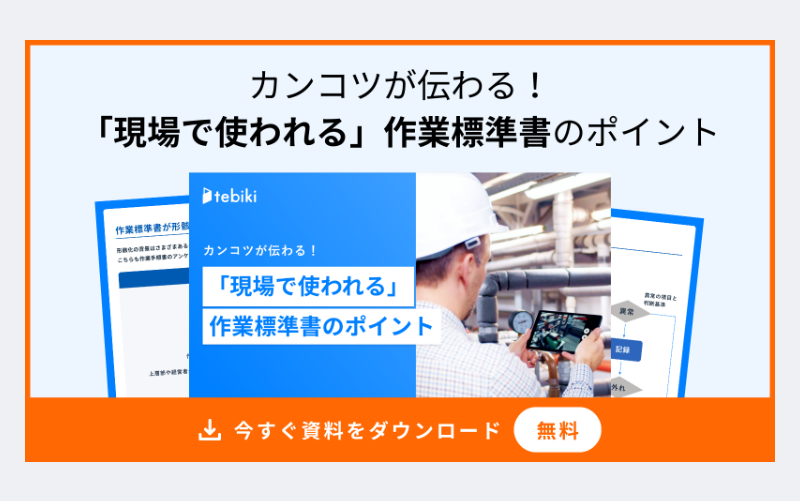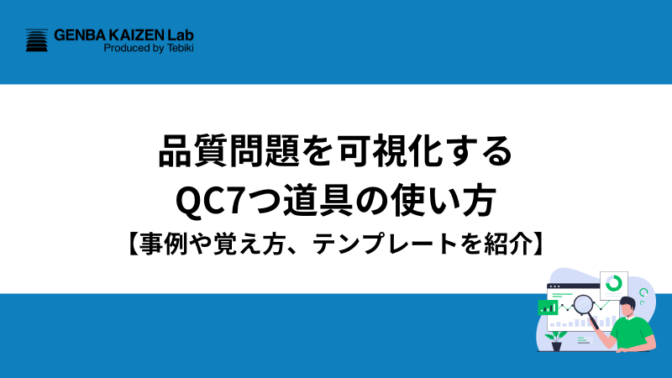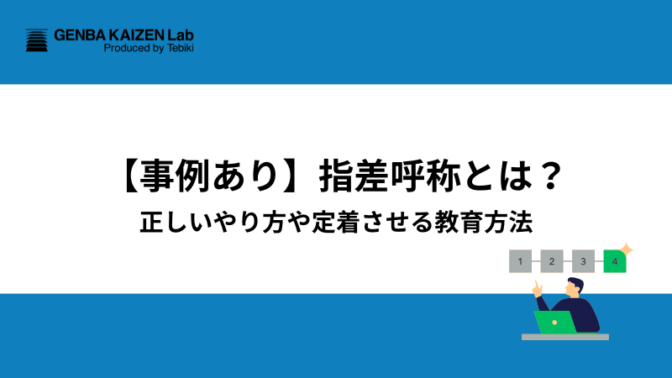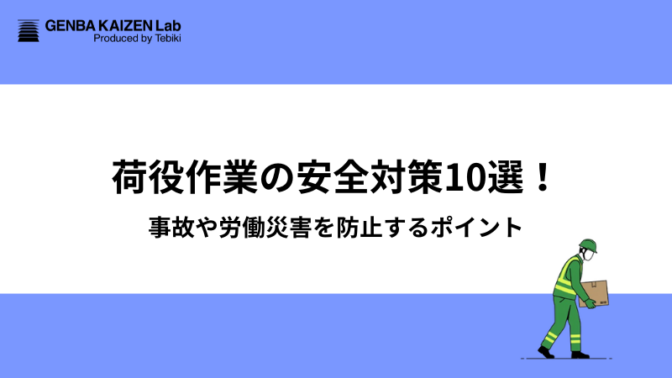かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
製造業における労働災害を防ぐには、法律に基づいた安全衛生対策、すなわち労働安全衛生法が極めて重要です。
そこで本記事では、労働安全衛生法の目的や基本方針から、製造現場で事業者が果たすべき義務、安全教育の実施、機械や化学物質に関する管理、違反時の罰則までを網羅的に解説します。
現場の安全を守る仕組み作りを模索している現場責任者は特に参考になると思います。
目次
労働安全衛生法とは?目的と3つの柱、労働基準法との違いをわかりやすく解説
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成することを目的として制定された法律です。製造業を含むすべての事業所で義務付けられており、単に労働災害や健康障害の予防にとどまらず、快適な環境整備にも力点を置いています。
労働安全衛生法の目的:労働者の安全と健康を守るための基本法
労働安全衛生法は、「労働者の安全と健康を守る」という目的に対する具体的な義務を定めています。
転倒や機械災害などの労働災害を未然に防ぐだけでなく、健康診断や作業環境の改善など従業員の心身の健康維持など多くの方策が必要です。単なる法的義務ではなく、安全で働きやすい環境づくりは、離職防止や生産性の向上にも直結する重要な取り組みの1つです。
関連記事:【事例あり】労働災害対策8選!職場で効果的な「安全意識向上の取り組み」とは
労働安全衛生法の3つの柱
労働安全衛生法が目指す安全衛生活動は、主に以下の3本柱で構成されています。
労働災害防止のための危害防止基準の確立
機械や化学物質などに起因する災害を未然に防ぐため、国が安全装置の設置基準や作業方法などを定め、事業者に遵守を義務付けています。技術的な基準整備が事故の予防につながります。
責任体制の明確化
総括安全衛生管理者や安全管理者などの選任を通じて、現場における安全衛生の責任体制を明確にします。組織として誰が何を担うかを定めることで、安全管理の実効性を高めます。
自主的活動の促進措置
リスクアセスメントや安全衛生委員会の設置など、企業自らが継続的に安全衛生活動を行うことを促しています。法律は最低基準を示しつつ、職場ごとの自主改善も重視しています。
リスクアセスメント、安全衛生委員会に関する解説は以下の記事でまとめられています。
▼関連記事▼
・リスクアセスメントの目的とは?実施に向けた進め方のポイントや企業事例も解説
・安全衛生委員会ネタ一覧!工場や建設業で使える「面白い」テーマは?
労働安全衛生法と労働基準法の違い
労働基準法が労働時間や賃金、休憩など「労働条件の最低基準」を定める法律であるのに対し、労働安全衛生法は「職場の安全と健康の確保」に特化した法律です。
| 項目 | 労働安全衛生法 | 労働基準法 |
|---|---|---|
| 目的 | 労働者の安全・健康を確保し、 快適な職場環境を形成すること | 労働条件の最低基準を定め、 労働者の権利を保護すること |
| 内容 | 職場の安全対策、健康管理、 作業環境の整備、安全教育など | 賃金、労働時間、休憩・休日、 有給休暇、解雇規制など |
| 管理項目 | 安全衛生体制(管理者・産業医・委員会)、 設備・化学物質の管理など | 労働契約、就業規則、労使協定、 労働時間制度、割増賃金など |
【一覧表あり】製造業の事業者が果たすべき主な義務
労働安全衛生法では労働者の安全衛生を守るため、事業者に多くの義務を課しています。
安全衛生管理体制の整備に関する義務
製造業における安全衛生管理体制の整備は、労働災害や健康障害を防ぐための土台となる重要な取り組みです。
安衛法では、事業場の規模に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任が義務付けられており、それぞれの専門性を活かして安全衛生活動を統括・推進します。
| 項目 | 主な役割 | 主な 根拠法令 | 選任義務のある事業場規模(製造業) | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|
| 総括安全衛生管理者 | 安全衛生活動の統括・指揮 | 安衛法 第10条 | 政令で定める一定規模以上の事業場 | 安全衛生方針の決定、管理体制の整備、教育の統括など |
| 安全管理者 | 安全に関する技術的事項の管理 | 安衛法 第11条 | 常時使用する労働者が50人以上の事業場 | 災害発生防止、設備点検、安全指導の実施など |
| 衛生管理者 | 衛生管理・作業環境の点検・健康障害予防 | 安衛法 第12条 | 同上 | 職場環境の衛生巡視、健康診断の管理、衛生教育など |
| 産業医 | 医学的観点から労働者の健康管理を行う | 安衛法 第13条 | 同上 | 健康診断結果の管理、長時間労働者への面談、職場巡視など |
また、安衛法第17条では、常時100人以上の事業場では、安全委員会の設置を義務付け、労働災害の防止策や再発防止など重要な安全対策について調査・審議し、事業者へ意見を述べる役割を定めています。
労働者への安全衛生教育に関する義務
労働者への安全衛生教育に関しては、安衛法で以下のように定められています。第59条(安全衛生教育)事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
具体的な労働者への安全衛生教育に関しては、大きく「雇入れ時教育」「特別教育」「職長等教育」という3つの義務があります。
| 教育の種類 | 概要 | 根拠 法令 | 対象者 | 実施の タイミング |
|---|---|---|---|---|
| 雇入れ時 教育 | 新たに雇用された労働者に対して、作業に関する危険や保護具の使用方法などを教育する。 | 安衛則 第35条 | すべての新入労働者 | 業務開始前に実施 |
| 特別教育 | 危険・有害業務(例:研削といしの取替え、アーク溶接)に従事する労働者に対して、専門的な教育を実施する。 | 安衛則 第36条 | 特定の危険・有害業務に従事する労働者 | 該当業務に就く前に実施 |
| 職長等教育 | 労働者を直接指導・監督する職長や班長に対して、安全管理や指導方法などを教育する。 | 安衛法 第60条 | 新たに職長や作業指導者に就く者 | 職務に就く前または直後に実施 |
より安全教育の効果を高めたい場合は以下の記事も参考にしてください。
関連記事:【製造業の安全教育】安全意識を高める教育手法やネタ例を解説!
機械や設備、危険物・有害物に関する義務
製造業における設備・物質管理では「リスクの高い対象に対して、事前対策・定期管理・責任者配置」が法的に定められており、違反した場合は重大な労働災害や法的責任を招く恐れがあります。実施漏れのないよう、定期的な確認と記録管理が重要です。
| 義務の種類 | 概要 | 根拠法令 | 対象の例 | 実施内容・タイミング |
|---|---|---|---|---|
| 危険な機械への規制(許可・検査・譲渡制限など) | プレス機械やクレーンなどによる災害防止のため、安全装置の設置や定期自主検査が義務付けられている。 | 安衛法 第37条〜 第44条 | プレス、クレーン、コンベヤーなど特定機械を設置・使用する事業場 | 設置時の構造規格適合、定期的な自主検査、安全装置の設置 |
| 化学物質のリスクアセスメント | 有害性のある化学物質の取り扱い時は、リスクアセスメントを実施し、必要な措置を講じる義務がある。 | 安衛法 第57条の3 安衛則 第34条の2 | SDS交付対象物質やリスク物質を使用・製造する事業場 | 化学物質ごとのリスク評価・結果記録・低減措置を継続的に実施 |
| 作業主任者の選任 | 特定の危険・有害作業に従事させる場合、免許を受けた者または技能講習を修了した者のなかから作業主任者を選任し、現場管理を行わせる義務がある。 | 安衛法 第14条 | 有機溶剤作業、特定機械作業、足場組立作業などを行う事業場 | 資格者を選任し、現場の指導・点検・指示を行わせる |
労働者の健康管理に関する義務
労働者の健康リスクは「身体的」だけでなく「心理的」側面からも管理することが義務付けられています。診断や指導は形式的にならないよう、記録管理・再検査・産業医の助言活用まで含めて運用することが重要です。
| 義務の種類 | 概要 | 根拠法令 | 対象 | 実施内容・ タイミング |
|---|---|---|---|---|
| 一般健康診断・特殊健康診断 | 労働者の健康状態を把握し、疾病の早期発見・予防を目的とした診断。特定の有害業務従事者には特殊健診が必要。 | 安衛法 第66〜68条 安衛則 第44〜47条など | 全労働者(一般健診)、有害業務従事者(特殊健診) | 一般:年1回以上、特殊:6か月ごとなど法定頻度で実施。結果は本人に通知し、記録を5年間保存。 |
| ストレスチェック制度 | 心理的な負担の程度を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防止するための制度。 | 安衛法 第66条の10 安衛則 第52条の9〜13 | 常時50人以上の労働者がいる事業場 | 年1回以上、医師や保健師等によるチェックを実施。高ストレス者には希望に応じて面接指導を行う。 |
| 長時間労働者への面接指導 | 長時間労働による過労・健康障害を防ぐため、医師による面接指導を行う制度。 | 安衛法 第66条の8〜9 安衛則 第52条の2〜7 | ・時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者 ・時間外・休日労働が月100時間を超える研究開発業務従事者など | 本人申出に基づき、医師による面接指導を速やかに実施。結果に基づき、就業上の措置を検討・実施。 |
快適な職場環境の形成に関する義務
快適な職場環境の形成は、「身体的負担の軽減」だけでなく、「有害因子からの防護」や「快適性の確保」という複数の観点から体系的に取り組む必要があります。単なる換気や温度管理にとどまらず、法令に準じた測定・記録・改善の継続実施が重要です。
| 義務の種類 | 概要 | 根拠法令 | 対象職場・物質例 | 実施内容・タイミング |
|---|---|---|---|---|
| 作業環境測定の実施 | 粉じん、騒音、有機溶剤などの有害因子を扱う作業場では、作業環境測定の実施が義務付けられています。 | 安衛法 第65条 | 粉じん、騒音、有機溶剤)などを扱う作業場 | 原則6か月以内ごとに1回以上の測定。管理区分に応じて改善措置(局所排気装置、耳栓、防じんマスクなど)を実施し、結果を法定期間(3年、7年、30年など)保存。 |
| 職場生活支援の施設 | 休憩室、更衣室などの生活支援施設を設置し、労働者が快適に職場で過ごせる環境を整備することが求められます。 | 安衛法 第71条の2 厚労省 「快適職場指針」など | 全業種対象 | 労働環境に応じた施設の整備(例:更衣室・洗面所の換気、冷暖房、遮音措置)を行い、衛生的・安全な職場生活を確保する。 |
| 受動喫煙の防止 | 労働者の健康を守るため、事業者には受動喫煙を防止する措置(喫煙室の設置や分煙の徹底)が義務付けられています。 | 安衛法 第68条の2 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン | 全業種対象 | 喫煙室の基準(換気・密閉構造・標識設置等)を満たす必要あり。屋内全面禁煙または分煙措置を実施し、掲示義務や利用ルールの明示も必要。自治体の条例もあわせて確認を推奨。 |
知らなかったでは済まされない!労働安全衛生法違反の罰則
懲役または罰金が科されるケース
労働安全衛生法では、安全衛生管理者の未選任や安全教育の未実施、事故発生時の報告義務違反などに対し、50万円以下の罰金が科される可能性があります(安衛法 第120条など)。
たとえ故意でなくても、「知らなかった」では済まされず、行政調査や是正勧告の対象となるため、日頃からの法令遵守が不可欠です。
罰則だけではない企業が受けるダメージ
罰則を受けることに加え、企業名の公表や書類送検、公共事業からの指名停止、信用失墜による取引停止や採用難など、経営に重大な影響を及ぼすリスクも存在します。SNSや口コミで「危ない職場」と認識されれば、優秀な人材確保が困難になり、離職率上昇にもつながりかねません。
製造業や現場における安全対策と教育の具体例5選
ここまで解説しました通り安全対策は非常に多岐にわたる一方で、事故防止には現場に密着した実践的教育が必要です。
危険予知活動(KYT)のマンネリ打破
KY活動が形骸化しがちな現場では、題材の工夫と進行方法の見直しが鍵となります。実際の作業写真や動画を使った「危険箇所の可視化」で当事者意識を高められます。また、参加者全員が発言する仕組みをつくることで、一方通行にならない対話型の活動へと転換でき、実効性のある危険予知につながります。
ヒヤリハット報告の活性化と活用
ヒヤリハットは重大災害の前兆とも言われ、日常的に情報を蓄積することが事故防止の第一歩です。報告のハードルを下げるには、報告用紙の簡素化や報酬制度の導入が効果的です。集まった事例を再発防止策として全社に展開することで、単なる報告に終わらない「活かす安全文化」が育まれます。
新人・外国人作業員への教育の徹底
経験の浅い新人や、言語や文化の違いがある外国人労働者は、災害リスクが特に高い層です。したがって安全教育は非常に重要です。
しかし、特に外国人労働者のような日本語が難しい作業者の教育は簡単ではありません。そこで安全教育では「見て覚える」から脱却し、視覚的に理解できる動画の活用が効果的です。
たとえば、日世株式会社では多言語対応の動画マニュアル(tebiki現場教育)を導入し、外国人スタッフの理解度を大幅に向上させました。教育の質と伝わりやすさの両立が、災害防止の鍵となります。
言葉の壁を越えて、安全ルールや標準作業を正確に伝える動画マニュアルの活用事例について知りたい方は、下の資料リンクをクリックしてご覧ください。
>>>「外国人労働者に「伝わらない」を解決した動画マニュアル活用事例集」を読んでみる
業務標準化で「誰がやっても安全」な状態を作る
ベテランの経験や“カン・コツ”に頼った作業は属人化のリスクが高く、ミスや事故の原因にもなります。そのため、作業手順を明文化し、誰が行っても同じ品質と安全性を確保できるよう「業務の標準化」が求められます。
文章だけでなく動画や図解を組み合わせた標準書を使えば、視覚的に理解しやすく定着率も向上します。教育の効率化にもつながり、現場力の底上げが図れます。
そこで、現場で本当に使われる作業標準書の作成ポイントを解説した資料もあわせてご覧ください(下の画像がおすすめです。
ヒューマンエラーを防止する仕組みづくり
ヒューマンエラーは「人間だから起こるもの」と捉え、その前提で防ぐ仕組みを構築することが重要です。チェックリストやダブルチェックに加え、「仕組みで守る」というヒューマンエラー対策を取り入れることで、エラーを根本から減らせます。
ヒューマンエラーは細かい各論による対策というよりも「仕組みづくり」が重要です。ヒューマンエラー対策が注意喚起やダブルチェックに留まり、再発していませんか?「人間はミスをする」という前提に立った、効果的な対策の考え方をまとめた資料で、本質的な改善を目指しましょう。
製造業におけるヒューマンエラーの具体的な未然防止方法については、以下の資料で解説しています。
>>>「製造業におけるヒューマンエラーの未然防止と具体的な対策方法」を見てみる
まとめ
本記事では、製造業における労働安全衛生法の目的から事業者の具体的な義務、罰則、そして実践的な安全対策までを網羅的に解説しました。
事業者は、安全衛生管理体制の整備や安全教育の実施、健康診断、作業環境測定など多岐にわたる法的義務を負います。これらを怠れば、罰則はもちろん、企業の信頼を損なう深刻な経営リスクにつながりかねません。
しかし、単なる法令遵守にとどまらず、KYT活動の活性化や業務標準化、ヒューマンエラーを防ぐ仕組みづくりといった現場主体の自主的な取り組みこそが、実効性のある災害防止の鍵となります。その1つの有効手段として「動画マニュアル(tebiki現場教育)」を本記事では推奨しました。
特に経験の浅い作業員や言葉が伝わりにくい外国人労働者には、視覚的な教材が不可欠です。製造業に特化した動画マニュアル作成ツールなら安全に寄与できるので、検討してみてください。