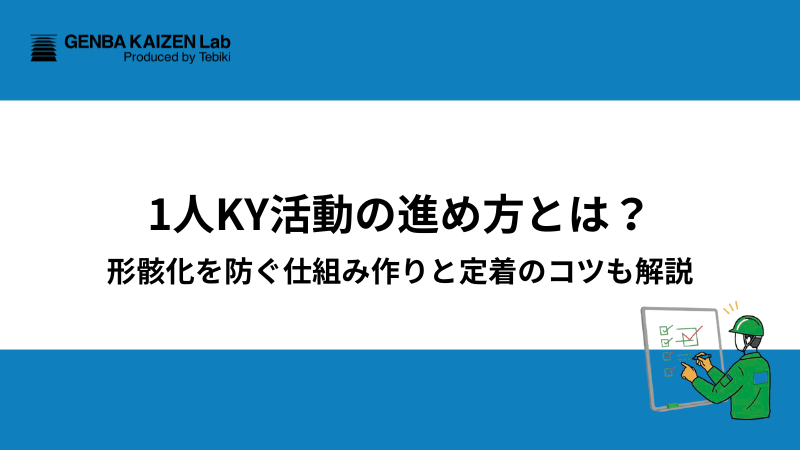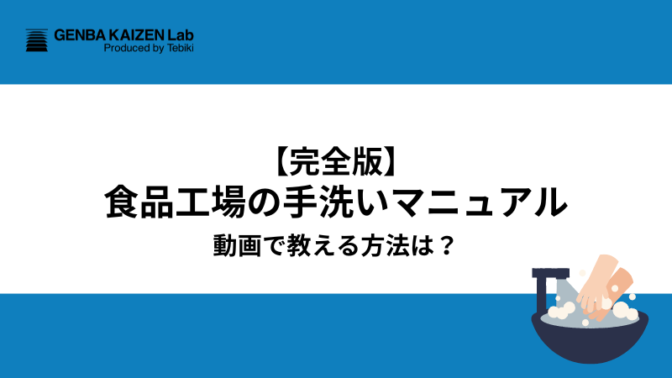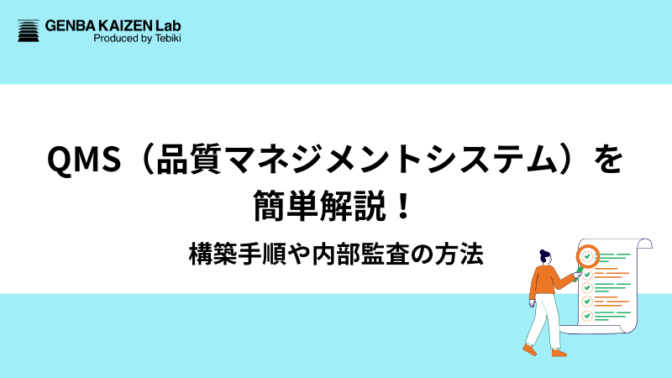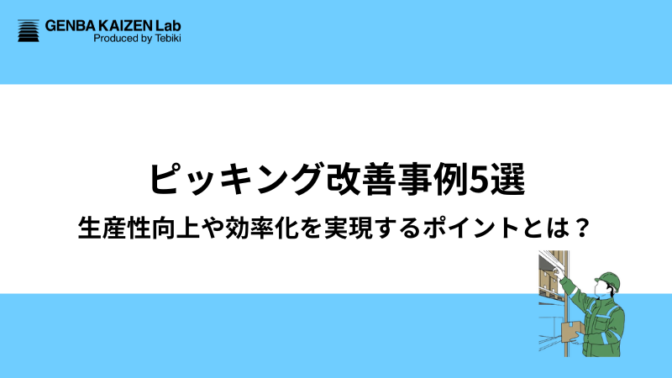かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
作業現場における安全管理は「気づき」が大切です。特に単独作業が増える昨今、他者の目が届かない場面で事故を防ぐには、自ら危険を察知し行動に移す力が必要になります。
そこで有効手段となるのが1人KY(危険予知)活動です。1人KY活動は作業前に1人でリスクを洗い出し、対策を考える実践的な安全習慣です。
この記事では、1人KYの定義や重要性、KY活動・KYTとの違いを解説します。具体的な進め方やマンネリ化を防ぐ工夫まで、現場で本当に使えるノウハウを体系的に紹介します。
ちなみに、「危ないから止めましょう」と注意しても不安全行動は繰り返されます。行動科学セーフティマネジメント=BBS(Behavior based safety)によると、ヒトが危険行動を繰り返してしまう理由は、たった2つしかないと言われています。
※BBS:行動に基づいたセーフティのことで、安全性に関わるすべての行動を管理できるようにするプロセスのことであり、過去30年以上の何千という実験・検証から成果を実証されている科学的手法。
このBBSに基づいて、不安全行動を止めさせるための方法を、資料「繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網」にまとめているので、あわせてチェックしてみてください。
また、具体的なKY活動に向けた訓練に「KYT(危険予知トレーニング)」がありますが、安全効果を高める教育手法として昨今「動画を用いたKYT」の導入が増えています。動画KYTの効果や改善事例は以下の資料からご覧いただけるので、こちらも参考にしてみてください。
1人KY(1人危険予知)活動とは?
1人KY活動とは、作業者が単独で作業に入る前に、自身の手で危険を予測・確認する取り組みのことです。特に単独作業や非定型作業の現場で、自ら危険を察知し、災害を未然に防ぐために重要な活動です。
複数人で行うグループKYとは異なり、単独作業や突発作業など、その場に他者がいない状況で特に有効です。
1人KYでは、作業環境や設備、自分の体調などを多角的に確認し、事故の要因となり得るリスクを洗い出します。そのうえで、危険を回避する具体的な行動目標を自分自身で設定するため、「自分の身は自分で守る」という意識が強く育まれます。
忙しい現場でもわずか数十秒で実施できるシンプルな手法ながら、安全第一の文化を支える活動です。
なぜ「1人」で行うことが重要なのか?
単独作業には、複数人作業では見落とされがちな重大なリスクが潜んでいます。
例えば「相談相手がいない」「異常の発見が遅れる」「自己流の判断で作業を進めてしまう」など周囲の目がないことによる油断や見落としが、事故や災害につながりやすく危険です。そのため、1人KYでは、他者に頼らず自分で気づき、自分で対処する力を養うことが目的となります。
1人KY活動は安全スキルの中でも実践的な力であり、突発的なトラブル時にも冷静に行動できる判断力と責任感を高める活動にもなります。
1人KYは、単なる手順確認ではなく、安全教育の一環と位置づけるべきでしょう。
KY活動(KYK)、危険予知訓練(KYT)との違い
混同されやすい「KY活動(KYK)」と「KYT(危険予知訓練)」ですが、2つには違いがあります。
まずKY活動とは、日常の作業前に行う危険の確認・予測行動全般を指し、指差し呼称や点検なども含まれます。一方、KYTは訓練要素が強く、4ラウンド法などの手法を用いて、グループで危険感受性や判断力を養う教育的な場とされています。
1人KYはKY活動の1つの形式であり、KYTの訓練を実作業えKYTで得た知識と感性を日々の現場で発揮するための実践的な手法と言えるでしょう。
▼関連記事▼
・KY活動(危険予知活動)の進め方は?記入例文やネタ切れ対策を紹介【エクセルシート付】
・危険予知訓練(KYT)の効果的な方法は?例題や解答、4ラウンド法の進め方を解説
単独作業に潜む特有の危険(Why)
例えば単独作業が多い林業現場では、発見の遅れや連携不足による災害リスクが常に存在します。
厚生労働省によると、作業員同士の接近に気づかず巻き込まれる災害は年間5.9件のペースで発生し、近接警報装置の導入が推奨されています。また、伐倒方向の誤認による死亡災害は年間4.3件、落下物による災害は3.5件、退避ミスによるものは2.6件と、いずれも単独で判断・行動する状況で起こりやすい事例です。
さらに、走行中の機械の転落(2.1件)巻き込まれ(2.1件)なども含め、単独行動時の視野不足や連携不全が原因となるケースは少なくありません。
こうした背景から、単独作業ではリスクの「見える化」と事前の危険予知(1人KY)の徹底が重要とされます。
1人KY活動がもたらす3つの効果(What)
1人KY活動の効果は自分で危険に気づき、行動できる力を高めることにあります。
第1の効果は「危険感受性の向上」です。繰り返し実践することで、普段は見過ごしてしまうような小さな異変や潜在リスクに気づける目が養われ、ヒヤリハットの未然防止につながります。
第2に「安全行動の習慣化」が進みます。作業前の指差し呼称や点検が当たり前になることで、不注意や省略といった不安全行動の発生を抑制することが可能です。
第3に「判断力・問題解決能力の向上」が挙げられます。1人で危険を予測し、「自分ならどう対処するか」と考える癖がつくことで、突発的なトラブルに冷静かつ的確に対応できる力が身につきます。
労働災害やヒューマンエラーの根本対策について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
▼関連記事▼
・【事例あり】労働災害対策8選!職場で効果的な「安全意識向上の取り組み」とは
・ヒューマンエラー対策13選!原因や製造業の対策例【種類や多い人、有名事故、トヨタの考え方】
1人KY活動の具体的なやり方・進め方
1人KY活動の具体的なやり方・進め方として、ここでは以下の3つにわけて解説します。
- 基本編:シートを使った1人KY 4ラウンド法
- 実践編:シート不要!手軽にできる1人KY
- 応用編:非定型・突発作業での1人KYのコツ
※安全効果を高める教育手法として昨今「動画を用いたKYT」の導入が増えています。動画KYTの効果や改善事例は以下の資料からご覧いただけるので、こちらも参考にしてみてください。
基本編:シートを使った1人KY 4ラウンド法
シートを使った1人KY 4ラウンド法は以下の4つに分けられます。
- 第1ラウンド(現状把握)
- 第2ラウンド(本質追究)
- 第3ラウンド(対策樹立)
- 第4ラウンド(目標設定)
文字ではなく動画による解説付きで理解を深めたい方は、元労基署長が登壇している無料セミナー動画「元労基署長が解説!事故を未然防止するKY活動と4ラウンド法の在り方とは?」をご覧ください(下の画像をクリック)。
第1ラウンド(現状把握)
作業に取りかかる前に、現場の状況や作業内容を丁寧に確認します。使用する設備・工具、明るさや足場、周囲の人の有無などの作業環境に潜む危険を具体的に書き出します。
例えば「放電加工機の電極交換時に、手袋が絡まる可能性あり」「切粉が床に落ちて滑る恐れ」など、実際のヒヤリハットにつながる要因を洗い出すことが大切です。現状把握では、質より量を意識し、思いつく限り危険を挙げていきます。
第2ラウンド(本質追究)
洗い出した危険の中から、最も重大なリスクを1つ選び出します。判断基準は「被害の大きさ」と「発生の可能性」の2つ。
例えば「放電加工機の高温部への接触による火傷」や「絶縁不良による感電リスク」など、作業者の命に関わるような本質的な危険を明確化します。
選定後は赤ペンで○をつけ、さらに最重要項目には◎をつけて強調。目と声で意識付けるために、「〇〇作業時には感電の危険あり!ヨシ」というふうに指差し呼称を行うことを推奨します。
第3ラウンド(対策樹立)
絞り込んだ本質的な危険に対して、どうすれば安全に作業が行えるかを自分で考えます。
例えば「絶縁手袋を着用」「設備の電源OFFを再確認」「床の油分を拭き取ってから作業」など、現実的で実行可能な対策を列挙します。対策樹立のポイントは、「自分が本当に実行できるか?」を軸に考えることです。
放電加工のような精密作業では、安全確認が後手になりがちですが、ここでの対策が命を守る行動につながります。
第4ラウンド(目標設定)
考えた対策の中から、特に重要な行動を1つ選び、明確な目標として言語化します。例えば「電源をOFFにしてから交換作業に入る」「作業前に手袋と靴の状態を確認する」など。目標は「○○を○○する」形式で簡潔にまとめ、指差し呼称と組み合わせて習慣化を図ります。
「手袋ヨシ!」「電源ヨシ!」など、声と動作を一致させることで、作業者の注意力が一段と高まります。
実践編:シート不要!手軽にできる1人KY
時間や環境に制限がある現場では、紙を使わずに行える1人KYが有効です。手軽にできる1人KYとして以下の3点を解説します。
- 自問自答KY
- 指差し呼称KY
- ワンポイントKY
自問自答KY
作業前に「いつもと違うところはないか?」「省略できる手順はないか?」「もし○○したらどうなるか?」と自問することで、潜在的な危険への感度が高まります。
重要なのは流れ作業に陥らず、毎回必ず立ち止まること。特に慣れた作業ほど油断しがちなので、こうした問いかけを通じて「見えないリスク」を浮き彫りにできます。
頭の中でKYを繰り返す習慣は、短時間で実行でき、忙しい現場でも即導入可能な効果的手法です。
指差し呼称KY
最も重要な確認ポイントだけに絞り「バルブ閉鎖、ヨシ!」「電源オフ、ヨシ!」など、対象を指差して声に出すことで、安全確認の精度が格段に向上します。
ポイントは「見る」「指す」「声に出す」という3ステップを省略しないこと。3ステップをルーチン化することで、曖昧な確認や見落としを減らし、ヒューマンエラーを未然に防げます。設備操作や切替作業など、ひとつのミスが事故につながる場面で特に有効です。
ワンポイントKY
全作業にKYを徹底するのが理想ですが、時間が限られる現場では「危険度の高い作業」に集中して、直前に1つのリスクとその対策だけを確認する「ワンポイントKY」が有効です。
例えば「高所作業での転落リスク」なら「安全帯の接続確認をする」など、重要なポイントに絞ることで、効果的に安全確認を継続できます。簡潔な分、意識の集中度が高まり、注意喚起としても強く作用します。
応用編:非定型・突発作業での1人KYのコツ
非定型・突発作業では、あらかじめ決まったKYT手順が通用しないケースが少なくありません。そんなときに頼りになるのが「着眼点」です。
事故を防ぐ鍵は、何を見るべきかを自分で判断できる目を養うこと。例えば【人】の観点では「体調は万全か?焦りや無理はないか?」で、【機械・設備】では「異音・異臭、安全装置の状態、工具の適正使用」などが挙げられます。
また、【環境】に目を向け「足場や照明、他作業者との距離」を確認し、【作業方法】では「無理な姿勢や手順省略がないか」をチェックしましょう。
マニュアルのない状況だからこそ、危険を見抜く力=KYの本質が試されます。日頃から「何を見て、どう判断するか」を意識することが、安全な即応力につながります。
1人KY活動を形骸化させず、組織に定着させるためのポイント
1人KYを一過性の取り組みで終わらせず、現場に根付かせるには「教育」と「習慣化」の両輪が不可欠です。ここでは、安全衛生担当者・管理職の方が押さえるべき定着のノウハウを以下の順で具体的に紹介します。
- 指導のコツ:「やらされ感」をなくし、自発性を引き出す
- 習慣化の仕組み:「短時間・見える化・共有」
- 動画の活用で、危険の感受性をさらに高める
指導のコツ:「やらされ感」をなくし、自発性を引き出す
KY活動が「やらされ仕事」になってしまうと、形だけのものになり、効果が薄れます。自発的に動ける現場をつくるには、以下の3点を押さえましょう。
- 「なぜ」を伝える
- 成功体験を積ませる
- 双方向のコミュニケーション
「なぜ」を伝える
1人KYを現場に浸透させるには「なぜこれをやるのか?」を明確に伝えることが大切です。単に「やりなさい」と指示するだけではなく、「単独作業にはどんなリスクがあるか?」「過去にどんな災害が起きたか?」といった背景を具体的に示すことが重要です。
実際の事故事例を交えて伝えると、現場の作業員にも自分ごととして受け止めやすくなります。また、1人KYが災害の未然防止にどれだけ効果があるかを示すことで、形式的ではない「意味ある活動」として捉えてもらえるようになります。
例えば物流業のASKUL LOGIST株式会社は、事故事例やヒヤリハットを動画で従業員に共有し、どこに危険が潜んでいるか、なぜ安全対策が重要なのかを伝えています。
安全教育を徹底するという観点では、ヒヤリハット事例の共有やKYTを行うなどがあります。ヒヤリハット事例の共有では、直近の拠点で起こった事故事例を動画マニュアルで共有すると禁止動作の確認や、感染病などその時々で挙げられるトピックスをと注意喚起を促しています。KYTを実施する際でもtebikiの動画マニュアルを活用しています。動画の方がより現場の状況に近いリアルな臨場感をつくれて「何が原因」で「どこに注意が必要」かが伝わりやすいというのを実感しています。
同社の安全対策に関する詳細な事例は、以下のインタビュー記事よりご覧いただけます。
インタビュー記事:従業員数3,500名超・全国15拠点で動画マニュアルtebikiを活用!
成功体験を積ませる
最初から高度な危険予知を求めるのではなく、簡単な作業で「自分の気づき」が役立ったという小さな成功体験を積ませましょう。
例えば「足元の段差に気づいてつまずかずに済んだ」「手袋の破れを見つけて交換した」など、日常にある気づきを承認することがポイントです。現場で得られる達成感が、活動継続の最大の動機になります。
小さな気づきが命を守るという意識を育てることで、自発的な行動につながっていきます。
双方向のコミュニケーション
指導時は「こうしなさい」と伝えるだけでなく「この作業でどんな危険がありそうか?」と問いかけることで、本人の思考を促すことが重要です。
作業者自身が考えたことを「なるほど、いい視点だね」「それは他の人にも役立つよ」とフィードバックし、承認・賞賛することで、学びの定着が格段に高まります。上司の評価があると、1人KYは「ただの義務」ではなく「自分が考える価値ある行為」へと昇華していきます。
習慣化の仕組み:「短時間・見える化・共有」
継続的に1人KYを行ってもらうには、日常業務に無理なく組み込む工夫が必要です。ここでは具体的に以下の3つの工夫を紹介します。
- 時間を区切る
- 活動の見える化
- 好事例の共有
時間を区切る
活動を定着させるには「時間を決める」ことが効果的です。例えば「作業前の1分間だけKYに使う」といったルールを明文化すれば、作業者の負担感を減らし、日常の一部として習慣化できます。
また、ルーチン化することで「忘れない」「バラつかない」といった効果も得られ、現場全体の安全意識の向上につながります。
活動の見える化
1人KYを「見える化」することで、実施率や活動の中身が把握しやすくなり、現場にも適度な緊張感が生まれます。
例えばチェックシートやデジタルアプリを活用し、「実施」「内容」「気づき」を簡単に記録する仕組みを整えると、日報にも活用しやすくなります。見える化された記録は上司からのフィードバックにも使え、マンネリ化防止にもつながります。
好事例の共有
1人KYで得られた気づきやヒヤリハットは、できる限り全体で共有しましょう。朝礼やミーティングで「○○さんの1人KYで作業前に○○に気づけた」といったエピソードを紹介することで、他の作業者にも具体的な参考となり、行動変容を促します。」
「自分たちのチーム内だけで終わっている」という課題を超えて、組織としての安全文化が醸成されていきます。
動画の活用で、危険の感受性をさらに高める
1人KY活動を形骸化させず、継続的に高い効果を発揮させるためには、単なる現場任せにせず、会社全体での取り組みとして位置づけることが不可欠です。特に効果的なのが、社内のイベントと連動させる方法です。物流業を営む株式会社ロジパルエクスプレスの事例は、その好例といえます。
同社では、拠点ごとにマニュアルや安全ルールにばらつきがあり、それが事故のリスクにつながっているという課題を抱えていました。そこで導入したのが、動画マニュアル「tebiki現場教育」です。
紙マニュアルでは伝えきれなかった作業のスピード感や危険性を、動画で直感的に共有できるようにし、さらに「事故防止強化月間」といった全社的な取り組みと連動して、フォークリフト操作時の危険予知トレーニング動画を全拠点に一斉配信しました。
このように、1人KYを含めた安全活動を社内イベントと組み合わせることで、「やらされ感」ではなく、「自分ごと」として捉え直すきっかけを作ることが可能です。動画はヒヤリハットや実際の事故映像をもとに構成することで、危険を疑似体験でき、現場作業者の危険感受性を飛躍的に高める効果があります。
また、手順の中で重要な動きや力のかけ方といった文章化しにくいポイントを明確に伝えることも可能です。さらに、外国人作業員への教育にも有効で、視覚的に理解できる動画なら、言語の壁を越えて正しい安全行動を浸透させられます。
動画マニュアルが安全対策に有効である理由の詳細や他事例は、以下の資料にまとめられています。あわせてご覧ください。
>>「安全意識が高い製造現場はやっている! 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例」を読んでみる
まとめ
1人KY(一人危険予知)活動は、単独作業時のリスクに備えるための重要な安全行動です。
定型・非定型を問わず、作業前に自ら危険を見つけ、対策を考えることで、事故を未然に防ぐ力が養われます。
シートを使った4ラウンド法から、自問自答・指差し呼称など手軽に実践できる方法まで多様な取り組みが可能です。
加えて、教育・習慣化・動画活用など、現場への定着を図る工夫も不可欠です。現場力向上のツールとして、本記事でも紹介した「動画マニュアル(tebiki現場教育)」もあわせて検討してみてください。