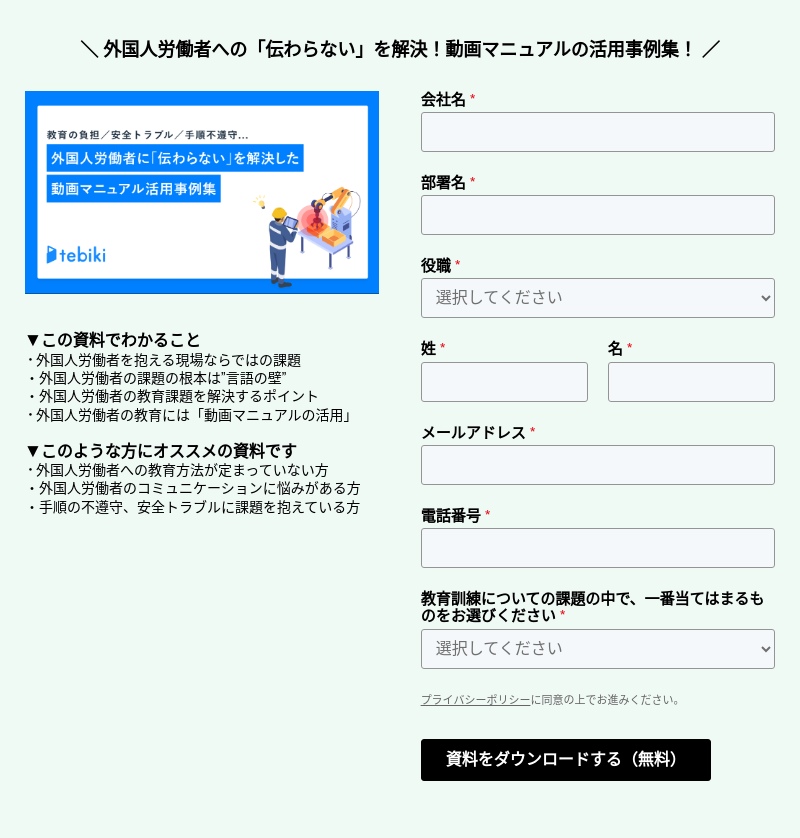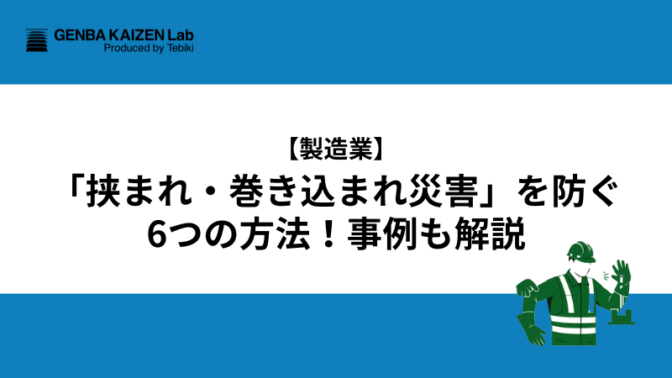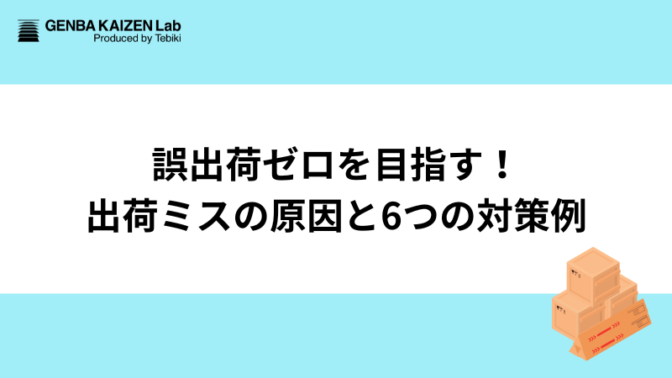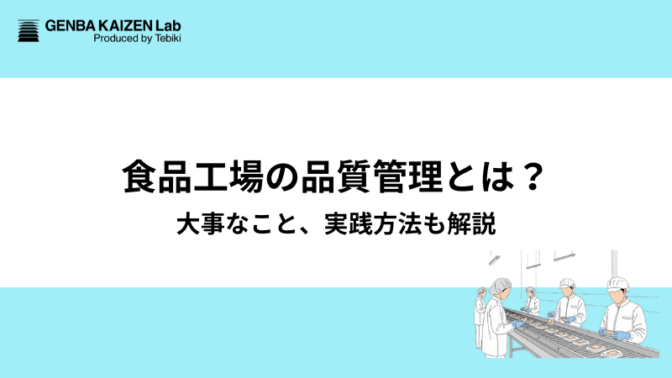かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
厚生労働省の調査では、令和6年10月末時点で外国人労働者数は前年比25万人増加しており、日本人労働者が不足している現状を鑑みると今後も増加すると予測できます。
外国人労働者を雇う場合に、問題となるのが言語の壁です。日本語の言語レベルにはバラつきがあるため、作業の理解度やコミュニケーションにも影響が生じる可能性も十分に考えられます。この記事では、言語問題が発生してしまう理由や影響、解消する方法や実際に言語問題を解消した好事例などを紹介していきます。
なお、以下の資料では、外国人労働者の言語問題を解消する具体的な方法や企業事例を紹介していますので、フォームを入力して資料をご覧ください。
外国人労働者の言語問題が発生する理由・影響
外国人労働者の言語問題は現場のミスコミュニケーションを引き起こし、作業の遅延や安全問題につながります。ここでは、外国人労働者の言語問題が発生する理由について、影響を交えて紹介していきます。
外国人労働者の言語問題が発生する理由
日本語の習得難易度が高い
外国人労働者の言語問題の根幹には、企業が求める日本語レベルの高さがあります。製造業やサービス業の現場では、正確なコミュニケーションやトラブルを防ぐための手順遵守が求められるため、外国人労働者に一定レベルの日本語レベルを求めるでしょう。
一方で、日本語を習得するにはかなりの勉強時間やトレーニングが必要です。実際に、FSI(アメリカ外交官養成局)では、日常会話や専門的な会話に支障がないレベルの日本語能力を習得するには88週間(2,200時間)の学習時間が必要とされ、同調査における取得難易度も最高レベルに位置づけられています。
また、外国人労働者の日本語力を示す指標の1つである日本語能力試験(JLPT)はN1からN4までのレベルに分かれていますが、多くの製造業では少なくともN2レベルの日本語力が求められることが一般的です。このように必要な言語レベルに対しての習得難易度の高さが壁になっている場合が多いのです。
内定後に日本語を勉強する人が多い
外国人労働者の多くが来日後に日本語学習を始めることも言語問題が起きる理由の1つです。
実際に、「にほんごの会企業組合」が地域の日本語教室に通う外国人を対象に行った統計によると、母国でも日本語を学んでいた人が27.5%であるのに対し、日本に来てから日本語の勉強を始めた外国人が55.3%と倍近い数値になっていることが明らかになっています。
外国人労働者が来日後に日本語学習を始める場合、日本語でスムーズにコミュニケーションを取れるようになるには、かなりの時間が必要です。学習を始めたばかりの日本語能力では、現場で必要とされる専門的な指示や安全規則の理解が不十分であり、労働者の安全が確保されないリスクや生産性の低下が引き起こされることがあります。
日本語を勉強中の外国人労働者に対してコミュニケーションが思うように取れず、意図を思うように伝えられないと悩む方に向けて、言語の壁を解決するポイントや、外国人教育に成功している現場の事例をまとめた資料を用意しておりますので、下の画像をクリックしてご覧ください。
外国と日本で文化が異なるため
外国人労働者と日本人との間にある文化的な違いは、コミュニケーションの障害となります。外国と日本の文化の違いを理解する上では、ハイテクスト・ローテクストがあることを理解しておきましょう。
| ハイコンテクスト | 言葉以外の意図も「察してもらう」文化のこと |
| ローコンテクスト | すべての意図を言語化する文化のこと |
日本は「空気を読む」「以心伝心」などが当然のように活用されており、典型的なハイコンテクスト圏の国です。例えば、上司が「この作業場散らかっているね」と指摘した場合、「散らかっているから片付けてね」という意味合いが含まれており、指摘された従業員は自然と片付けをする必要があると認識するはずです。
一方で、直接的な言語表現をするローコンテクストの国の方には、この意味合いは通じないことが多いです。そのため、日本的なコミュニケーションを求めても思うように意思疎通ができないこともあるため、まずはローコンテクストでのアプローチが無難と言えるでしょう。
実際に外国人労働者を抱えている総合物流企業、ASKUL LOGIST株式会社でも、言語の壁や文化の違いによって安全教育を実施しても言語問題によって伝わらない課題を抱えていましたが、教育に使っていたマニュアルを紙から動画にすることで外国人労働者の理解度向上を実現しています。
言語の問題を乗り越えた同社の事例を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:言語問題を解消したASKUL LOGIST株式会社の記事を読んでみる
外国人労働者の言語問題による影響
正しい手順やルールが伝わらずトラブルになる
正確なコミュニケーションが取れない場合、作業指示の誤解が生じやすく、正しい手順やルールが伝わらないことも考えられます。手順やルールの認識に齟齬があると、作業効率の低下はもちろん、誤った機械操作や危険物の取扱いにより、事故や怪我などの労働災害に発展するリスクも十分に考えられます。
外国人労働者の労働災害を防止するポイント、発生した場合の対処法などを詳しく知りたい方は、以下の記事もクリックしてご覧ください。
関連記事:外国人労働者の労働災害防止策5選!事故時の対応や適用保険も紹介
外国人労働者の早期退職につながる
言語問題を解消できずに適切なコミュニケーションが取れないことによって、外国人労働者の職場環境に対する不満を強め、孤立感を増大させる可能性があります。結果として早期退職することもあるでしょう。
特に同じ国の人が働いていない環境では孤独感が増してしまうため言語だけでなく、企業としてメンタル面でのサポートを施すことも重要です。
教育に時間がかかる
業務指導の際に言語が理解できないと、繰り返し説明が必要になるため、外国人労働者の教育には通常よりも多くの時間が必要とされます。たとえば一連の作業についてトレーニングを行う際、単純な操作説明でも正確に伝えるために言語を介して詳細な手順を伝える必要があるため、通常の教育時間以上の時間がかかることもあるでしょう。
外国人教育に時間がかかってしまうと、教育担当者が通常業務に割ける時間も減ってしまうため、会社全体の生産性に影響を及ぼす原因になります。外国人教育の課題を解決するためのポイントなどを詳しく知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。
関連記事:外国人労働者の教育課題はこう解決する!5つの指導ポイント
外国人労働者の言語問題を解消する方法
ここでは、外国人労働者の言語問題を解決する手段を紹介していきます。
作業内容を説明する表示物・マニュアルは母国語で整備する
多言語表示は言語問題を直接解決し、安全確保と作業効率の向上につながる対策です。標識や指示の内容を外国人労働者が即座に理解できることで、誤操作や事故リスクの削減が見込めます。
たとえば機械の操作に関する警告標識を日本語のみで表示している場合、意味を理解できずに誤操作をしてしまう可能性があるため、労働者の母国語にあわせて多言語で整備するのが大切です。また、作業手順やルールなどを周知するマニュアルについても、従業員に応じて母国語で作成するようにしましょう。
食品の開発製造を手掛けているタマムラデリカ株式会社では、外国人労働者の国籍に応じたマニュアルを動画で作成し、紙と比べて細かいニュアンスが伝わりやすくなった、マニュアル作成の時間を削減できたなどの効果を実感しています。
外国人労働者の教育を成功させた好事例となっておりますので、こちらのインタビュー記事をご覧ください。
会話や指示に「やさしい日本語」を取り入れる
外国人労働者との業務上の会話や作業の指示では、「やさしい日本語」を取り入れるのも重要です。やさしい日本語とは、日常的に何気なく使っている言葉を外国人にも分かるように配慮したかんたんな日本語のことです。製造現場におけるやさしい日本語の活用事例は以下のとおりです。
| 具体例① | |
|---|---|
| 普段の日本語 | この作業は指や腕を切断する危険性があるため、正規の手順を厳守したうえで作業を実施してください。 |
| やさしい日本語 | 危ない作業です。正しい流れで作業してください。 |
| 具体例② | |
|---|---|
| 普段の日本語 | 作業中に発生したゴミは、種類ごとに分別し、特定のゴミ箱に廃棄してください。 |
| やさしい日本語 | 作業中のゴミは、種類ごとにゴミ箱に入れてください。 |
語学力に応じて適切な日本語教育を実施する
言語レベルは外国人労働者ごとにバラつきがあるため、現状の語学力に合わせて適切な日本語教育を施すようにするのも大切です。日本語を学ぶ方法は様々ですが、以下が学習方法として一般的です。
- 社内研修
- 日本語学校
- オンライン学習(eラーニング)
- 独学
学習方法によって、金銭的なコストが発生するもの、従業員のリソースが発生するものなど様々です。自社の状況にあわせて最適な日本語教育を実施できるように整備を進めましょう。
自発的に繰り返し学習できる教育体制を整備する
言語を習得するうえでは、何度も繰り返し言語に触れるのが大切なので、一方的に強要するのではなく、外国人労働者が自発的に繰り返し学習できる体制を構築するのも重要です。
教材や作業マニュアルなどが分かりづらいと心理的なハードルが高くなってしまうので、わかりやすいマニュアルを整備する必要があります。わかりやすいマニュアルを整備する方法の1つとしては、マニュアルの電子化です。紙で作成していたマニュアルをPCやタブレット上で視聴できるようにすることであり、中には動画化している企業もあります。動画化している企業事例は次の見出しで紹介します。
外国人労働者の言語問題を解消した好事例3選
ここでは、外国人労働者の言語問題を解消した企業の好事例を3つ紹介します。
【日世株式会社】外国人労働者の理解度テスト正答率が100%に
ソフトクリームの総合メーカーである日世株式会社では、外国人労働者が増加する中で、紙ベースの日本語マニュアルだけでは伝えたいことが伝わらない課題を抱えていました。また、職人技な部分も多く、製造現場の技術伝承が進んでいなかったそうです。
これまでよりも深く学べる環境を構築すべく、現場教育ツール「tebiki」を導入し、動画で繰り返し学べる環境を構築しました。その結果、外国人の理解度テストの回答率は100%近くまで改善。日本語が読めない従業員に対しても、自動で字幕を生成する機能によって、より伝わるマニュアルの作成が実現しています。
「翻訳機能を活⽤して、外国⼈との⾔葉の壁も乗り越えた」と語る同社のインタビュー記事を読みたい方は、以下をクリックしてご覧ください。
【児玉化学工業株式会社】5か国以上の言語が飛び交う現場でルールを浸透
住宅設備・自動車向け合成樹脂加工や産業機器の製造などを行っている児玉化学工業株式会社。同社では、様々な国籍の外国人労働者を抱えており、紙のマニュアルだと理解されないずに伝えることに課題を抱えていました。
そこで、マニュアルをビジュアル的に見せるために、現場教育ツール「tebiki」を導入し、紙から動画に置き換えています。結果として、日本人はもちろん、外国人にも社内ルールや作業手順を浸透させることに成功し、マニュアルの作成工数についても紙と比べて1/3まで削減しています。
「かんたんに外国語へ翻訳できるので、現場で作業のポイントが伝えやすい」と語る同社のインタビュー記事を読みたい方は、以下をクリックしてご覧ください。
【ASKUL LOGIST株式会社】外国人スタッフの理解度が向上
事業所向け通販企業「アスクル株式会社」100%出資の物流企業であるASKUL LOGIST株式会社。同社では、外国人労働者向けに安全教育を実施しても言語や文化の違いによって、思うように伝わらない課題を抱えていました。また、紙のマニュアルでは動きや注意するポイントなどが伝わらずに導入教育で教えた内容をセンター内で繰り返し教える工数も発生していたそうです。
これらの課題を解決すべく、現場教育ツール「tebiki」を導入。従来の教育と比べて、動画の活用によって作業の標準化を効率的に進められているそうです。また、字幕の自動翻訳も行えるので外国籍スタッフの教育にも使いやすいと実感しています。
「母国の言語で学習できるようになり、定着度が上がり現場への入りがスムーズになった」と語る同社のインタビュー記事を読みたい方は、以下をクリックしてご覧ください。
ここまで紹介した企業と同じように、外国人労働者の言語問題に動画マニュアルを活用してみたいと考えている方は、教育事例をより詳しく紹介している以下の資料をご覧ください。画像をクリックするとダウンロードできます。
まとめ
外国人労働者を雇用する場合、大きな課題となる言語の壁は早急に対処するべきです。放置しておくと、生産性・品質の低下、労働災害などに発展する可能性もあります。
言語問題を解消する方法や事例を紹介してきましたが、重要なのは自社の現状に即した方法を採用することです。なお、好事例として紹介した企業では、言語問題を動画で解消する取り組みが行われており、再現性の高い方法として動画の活用もおすすめします。
以下の資料では、はじめて動画マニュアルを作成する方に向けたノウハウを詰め込んでおりますので、動画活用を検討してみたい方は以下の画像をクリックして資料をご覧ください。